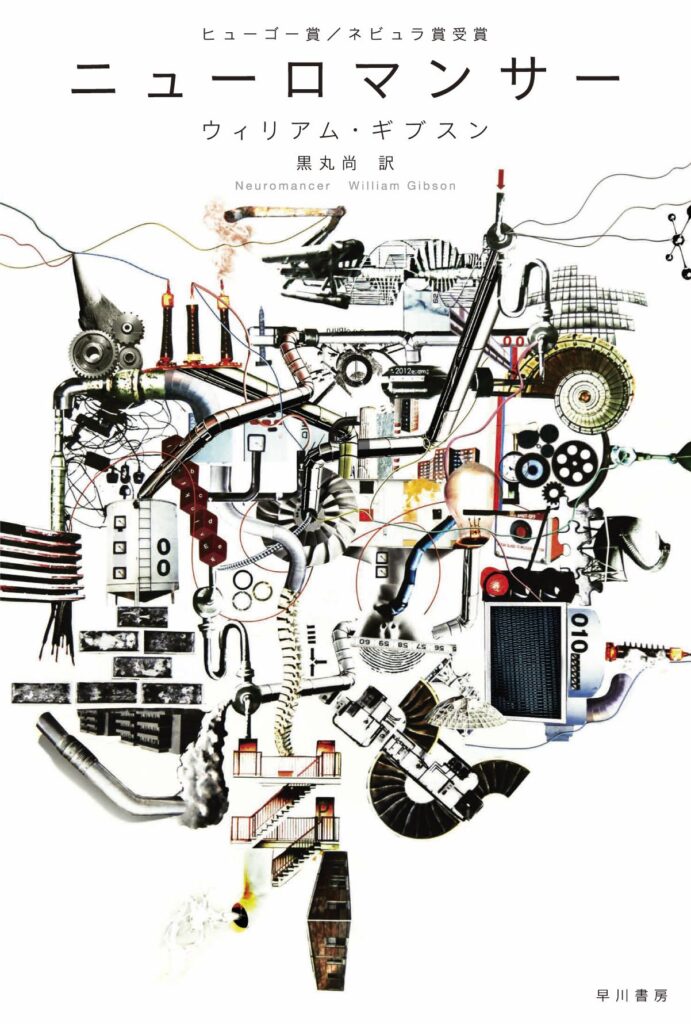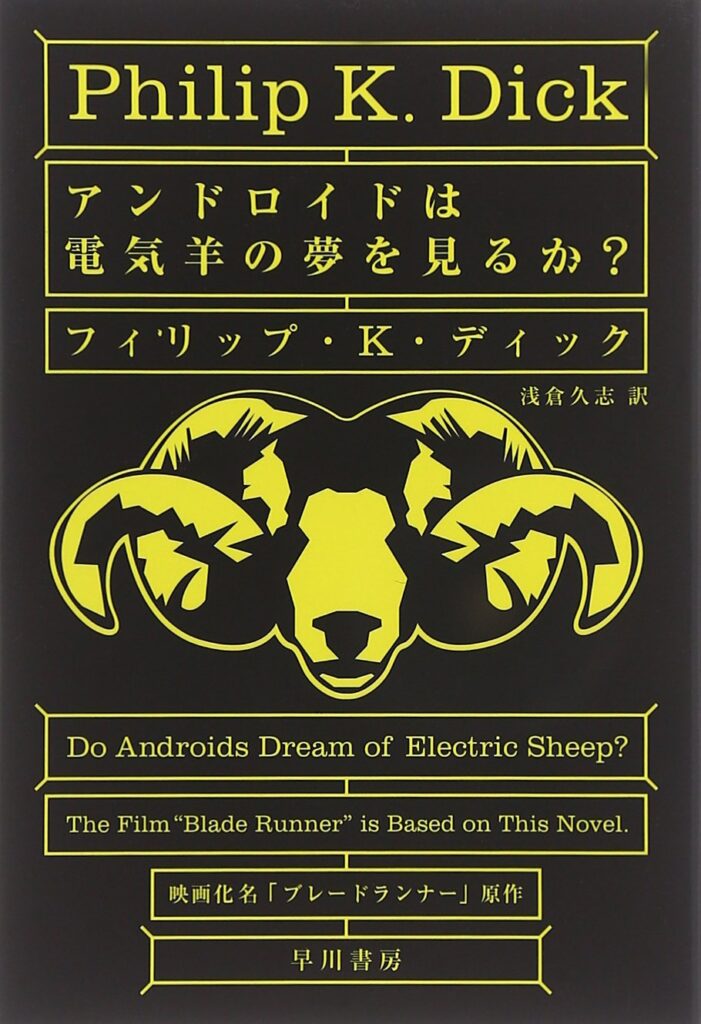vol.0 SFに何ができるか?
vol.1 まとうSF——化粧・ファッション・変身
今回は、SF映画やSFゲームでおなじみの言葉「サイバーパンク」の40年近い歴史を振り返る。2020年に発売された『サイバーパンク2077』や『Cloudpunk』、2022年に発売される予定の『Vigilance 2099』や『Stray』に至るまでサイバーパンクと形容されるゲームは数多い。しかしそもそも、サイバーパンクとはどういう意味なのか。はたして音楽やファッションのパンクとは関係があるのか?
サイバーパンクの誕生
まず「punk(パンク)」という言葉にはもともと犯罪者、トラブルメーカー、青二才、クズ野郎などの意味があるという点を押さえよう。そして1970年代にロック音楽のジャンル名として音楽批評家達に使われ始めた。「cyber(サイバー)」という言葉はコンピュータやネットワークを意味する。「ハッカー」という言葉が英語圏のメディアで広がったのも、日本の任天堂が「ファミコン」ことファミリーコンピュータを発売したのも1983年だ。この頃コンピュータが広く知られるようになり、サイバー空間やサイバー犯罪という概念が認知を広げ始めたわけだ。まず押さえるべきは、サイバーパンクというサブジャンルの物語構造は、スパイ小説やハードボイルド要素、あるいは複数勢力の闘争が多い点だ。これは国家間の緊張が高い冷戦期の小説だったことと不可分ではないだろう。
1981年にヴァーナー・ヴィンジが発表した中篇『マイクロチップの魔術師』は、ネット上で相手の正体と真の名前を互いに探り合う様子が未来予測として的確だったうえに、オンラインのロマンスや強大なコンピュータ知性(AI)を描いた最初期の作品でもあった。
しかし金字塔的な作品となったのは、ウィリアム・ギブスンの1984年の長編『ニューロマンサー』だ。身体にネットワーク接続口を設けるハッカー、異様な権力を持つ巨大企業、東アジアの大都市といったサイバーパンクの定番イメージを築いた。第一部の題名は「千葉市憂愁(チバ・シティ・ブルーズ)」である。
ブルース・スターリングもまた1980年代の短編群や『スキズマトリックス』(1985)といった長編、そして評論活動によってサイバーパンクを代表する作家となり「書記長」の二つ名を得た。ギブスンより現実から遠い、宇宙進出以降の未来を舞台に書くこともしばしばで、〈機械主義者/工作者〉シリーズでは機械化されて能力や寿命を拡張した人間を登場させた。
サイバーパンクの名付け親
ところで、サイバーパンクという言葉を発明したのはギブスンではない。米国の作家ブルース・ベスキの、1983年に「アメージング」誌に掲載された短編「サイバーパンク」(未訳。本人が全文を公開している)が出どころである。本人いわく1980年から執筆していた短編シリーズの一編だという。主人公は15歳の少年。彼が2歳年上の先輩と共にコンピュータを使った非行に走り、遠くの寄宿舎つき私立校に隔離され、いつの日か先輩に必要とされてお呼びがかかるのを待ちわびるという内容の不良小説だ。
題名を一人歩きさせるきっかけを作ったのは、SF作家でアンソロジストのガードナー・ドゾワである。1984年の「ワシントン・ポスト」紙への寄稿で彼は、80年代の新鋭作家達を自然発生した一派としてあえて定義するなら「ときどきサイバーパンクと呼ばれる」者達がいると書いた。
少し後になると、テーブルトークRPG(TRPG)がサイバーパンク文化を貪欲に取りこむ。1988年、米国のR・タルソリアン・ゲームズ社がTRPG『サイバーパンク』を発売した。同社は1989年にRPGゲームを主な役務として米国でcyberpunkの商標を出願した。ポーランドのゲーム会社CD Projektが開発した『サイバーパンク2077』はこのTRPGシリーズを原作とし、同社から商標を承継している。
なお1989年には、米国のFASAコーポレーションもファンタジーとサイバーパンクを融合させたTRPG『シャドウラン』を発売した。こちらもサイバーパンクっぽい世界観を広める要因となった。
ノー・フューチャーな現実と陰鬱な世界観
サイバーパンクの特徴の1つは退廃性だ。1970年代の若者文化を表わすキャッチフレーズに「セックス、ドラッグ、ロックンロール」があるが、サイバーパンクにはその余韻があった。
「20世紀半ばの米国の主流SFは、しばしば勝利主義的で軍国主義的で、アメリカ例外主義の一種のプロパガンダでした。私は未来としてのアメリカに、白い単一文化の世界に、中流階級以上出身の善人の主人公にはうんざりしていました。私はもっとゆとりが欲しかった。アンチヒーローが存在する余地を作りたかったのです」(筆者訳,“William Gibson, The Art of Fiction No. 211”,Paris Review,2011)
ブルース・スターリングが発表したエッセイ「80年代サイバーパンク終結宣言」(1991)には「たしかにサイバーパンクは、相当に荒涼としているが、誠実だからこそ荒涼としているのだ」(P.492,金子浩訳,山岸真編『90年代SF傑作選(上)』,ハヤカワ文庫SF,2002)という一文がある。サイバーパンクの中心作家達は社会の行き詰まりを敏感に感じとっていた。ゆえにしばしば現実より荒んだ社会を描き、ユートピア(理想郷)小説の対義であるディストピア(悪い場所)小説に分類される。
サイバーパンクの中心人物達が相次いで母国アメリカを離れたのは必然的かもしれない。ギブスンは1967年にカナダに移住し、スターリングは2000年にセルビアに居住し、2007年からイタリアに移った。また別のサイバーパンクの立役者で、しばしばロック音楽をテーマにする特徴を持ち、2015年に「スシになろうとした女」(嶋田洋一訳)で星雲賞海外短編部門を受賞した女性作家パット・キャディガンも1996年に英国に移住した。米国で夢を見られなかった作家達がかつて夢を託したのは、日本だった。
映画『ブレードランナー』と怪しい日本要素
1982年の映画『ブレードランナー』は、サイバーパンクという言葉が確立する以前に公開された。そもそも原作はフィリップ・K・ディックの1968年に出版された長編小説『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』だ。『ブレードランナー』の暗く猥雑な未来のロサンゼルスの風景には、リドリー・スコット監督が来日した際に見た新宿歌舞伎町の印象が重ねられた。広告が輝く都市の空中を車が飛び交う風景の元祖こそ『ブレードランナー』である。同作は後からサイバーパンクのイメージに合流したわけだ。
サイバーパンク作家達が小説に日本を登場させたのは、当時は日本経済に勢いがあったからだろう。未知の国であればこそ想像力を自由に遊ばせる余地があったわけだ。情報の少ない時代に書かれた、ときにおかしな日本描写は、日本に住む日本人の多くにはおもしろおかしく受容され、しばしばパロディも試みられる。2010年から公開されているウェブ連載小説〈ニンジャスレイヤー〉シリーズで大盤振る舞いされる怪しげな日本要素もその一例である。
日本だけが夢見られたわけではない。ジョージ・アレック・エフィンジャーは『重力が衰えるとき』から始まるシリーズ(1987年〜)で21世紀の中東を舞台にした。
独自の発展をみせた日本のサイバーパンク
当の日本でのサイバーパンクの起源を振り返りたい。大原まり子は「女性型精神構造保持者(メンタル・フィメール)」(1985)で一千億のテレビディスプレイに覆われた東京を想像し、都市を司るコンピュータが恋に狂う話を書いた。東野司は「赤い涙」(1986)でデビューし、患者の脳波を読み取ってアンドロイドに再演させ、患者が鑑賞して自分を客観視する精神療法というアイデアを描いた。しかし東野はサイバーパンクを意識したつもりはなく、関心はもっぱら人間の脳にあったという。(「電子版あとがき」,『赤い涙 マルチタスク Vol.1』,アドレナライズ,2017)
1987年にハヤカワSFコンテストに入選し、「邪眼(イーヴル・アイズ)」でデビューした柾悟郎もまたサイバーパンクよりジェイムズ・ティプトリー・ジュニア「接続された女」(1973)の影響のほうが強いと語った。(P.549,「解説」,早川書房編集部編『SFマガジン・セレクション1987』,ハヤカワ文庫JA,2012)「邪眼」も「接続された女」もコンピュータを利用した変身の話という点で共通する。
さらに『攻殻機動隊』で知られる士郎正宗は、1983年に同人誌「ブラックマジック」でコンピュータに意志決定される社会を描いた。つまり日本の初期サイバーパンクは、急速に注目されたコンピュータを題材にした創作が一斉に花開いた平行進化の産物であり、必ずしも米国のサイバーパンク小説の影響下にあるわけではない。
また、日本におけるサイバーパンクのイメージの一部は、ある1人の翻訳者の文体で形づくられたといっても過言ではない。翻訳家の黒丸尚(1951-1993)は独特のこだわりのある文体で、『ニューロマンサー』(ハヤカワ文庫SF,1986)ほかウィリアム・ギブスンの翻訳を多く手がけた。氏の翻訳には原文のクエスチョンマークをそのまま使わず代わりに……を使ったり、漢字の訳語の横にカタカナでルビを振るのを多用したり、彼や彼女といった代名詞をなるべく人名に置き換えるといった特徴があった。
作家の伊藤計劃(1974-2009)は中学生の時に読んだ『ニューロマンサー』のかっこよさにしびれ、文体に影響を受けたという。
「とはいえ、今にして思い返すと、あれはギブスンというより黒丸尚さんのカッコよさだったのかもしれません」(「著者インタビュー:伊藤計劃先生」,アニマ・ソラリス,2008)
かつてサイバーパンクは、サイバー技術が組みこまれることで未来の生活がどう変わるのか、道筋の少し先を照らし出した。だが皮肉にも、未来予測から外れた部分――例えば空飛ぶ車や身体の一部分を機械化した人間のほうが、魅力的な懐古趣味としてサイバーパンクの特徴になっている。もはやコンピュータやインターネットがない未来のほうが想像しがたいため、サイバーパンクは滅びない(Cyberpunks not dead.)。それでは80年代以降、サイバーパンクはどう変わったのか。続きはまたの機会にしたい。
「われわれに未来がないのは、われわれの現在があまりにも流動的であるからだ」(P.59-60,ウィリアム・ギブスン『パターン・レコグニション』,浅倉久志訳,角川書店,2004)
Edit Sogo Hiraiwa