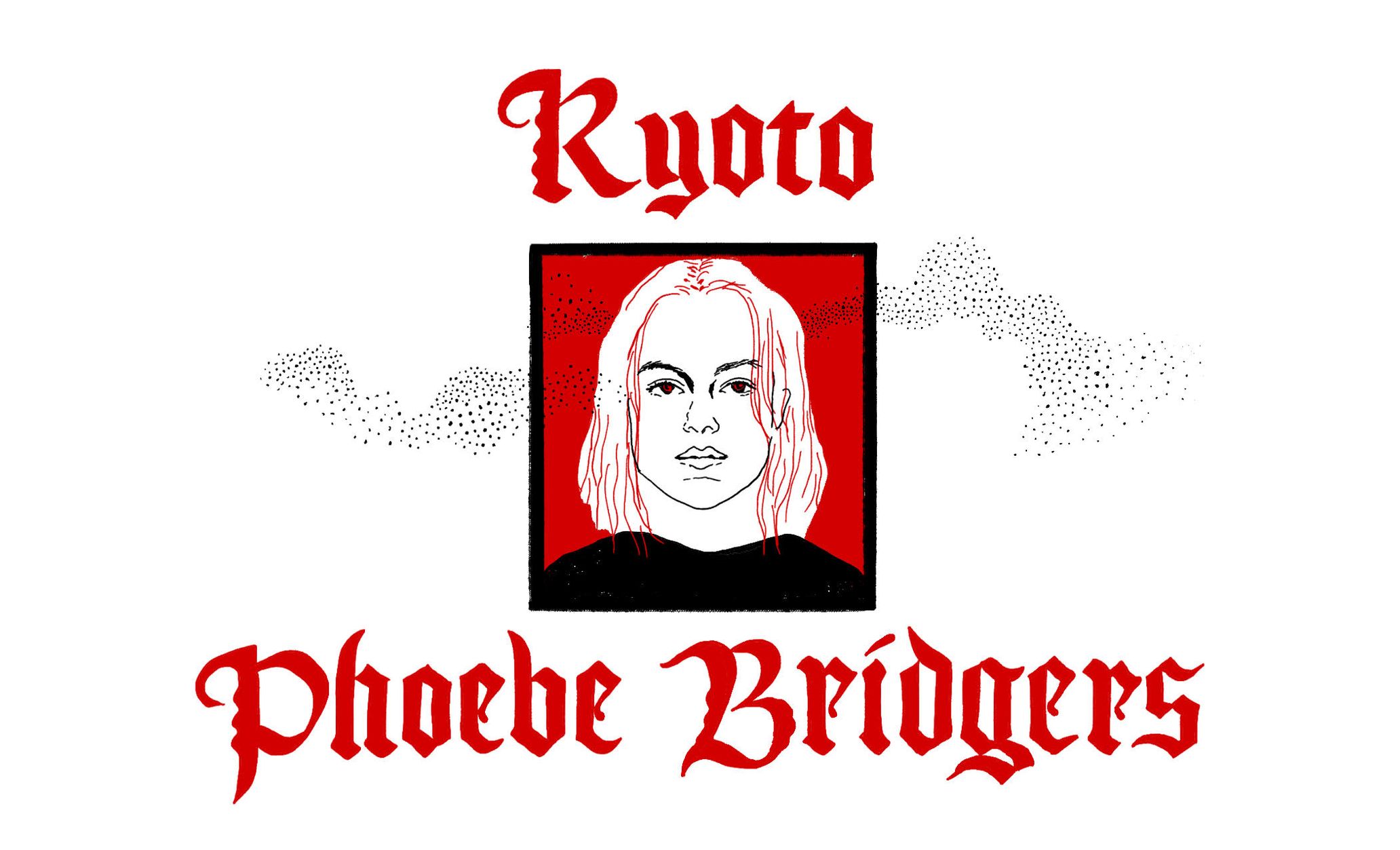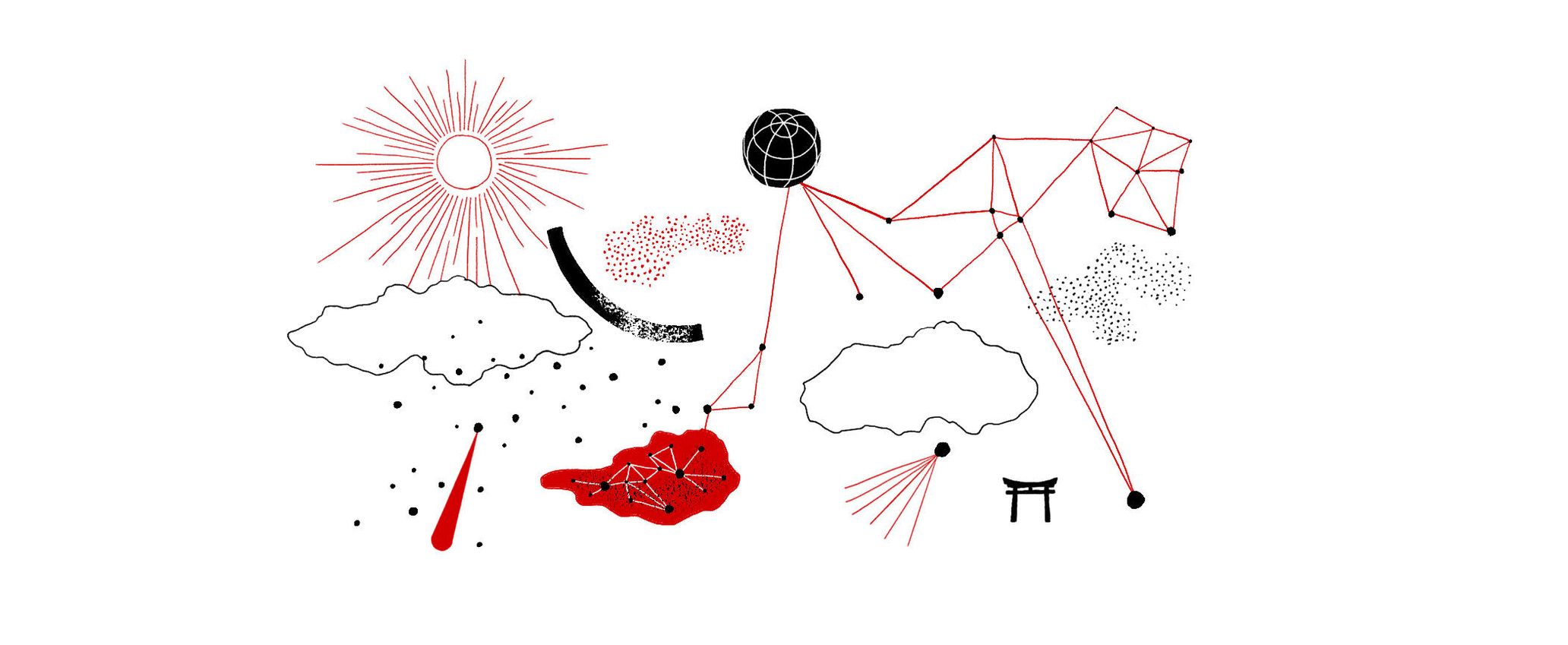世界情勢がハイスピードで変化する中、さまざまなアーティストたちが自らの言葉や声を駆使してメッセージを発信し続けている。古来より歌は人々の心に寄り添い、時に鼓舞してくれる大切な存在であった。たとえ政治や社会とは直接的な関連性を見出せない歌詞であっても、そのバックグラウンドを踏まえ、観察することで違う一面が見えてくるのが興味深い。現在ブルックリンに住む作家の新元良一が、誰もが知っているポップソング、ニューカマーの話題作の歌詞からアメリカ、そして世界を取り巻く情勢を読み解く。
6月に入り、2人のミュージシャンの話題作が発表された。その1人、ボブ・ディランは新作『Rough and Rowdy Ways』のリリース直前に、『ニューヨーク・タイムズ』の誌面に珍しくインタビュー記事が掲載されたが、そこで興味深いコメントを残している。
「我々は過去に浸りたがるが、それはわれわれ(の世代)に限っている。若者たちはそんなものになびかない。彼らには過去がなく、目に見え、耳にでき、信じられると思うものを認知する」。
もちろん年月とともに経験を重ねれば、若い世代の思考や言動も変わるだろうから、彼ら自身の寄りかかれる「過去」も出てくる。それでも生まれた時にはネットが普及していた、デジタル・ネイティブと呼ばれる世代についての次のディランの指摘は示唆的だ。
「テクノロジーには誰もが脆さを持つ。だが、若い連中はそんなふうに考えず、知ったことじゃないと思っている。遠隔でのコミュニケーションや高度なテクノロジーがそろった世界で生まれた世代だからね。我々の世界など時代遅れだな」。
このコメントを目にし、前述のもう1人のミュージシャンであるフィービー・ブリッジャーズのことが頭に浮かんだ(彼女の最新作『Punisher』の発表は、『Rough and Rowdy Ways』の前日)。正確に言うと、彼女を大きく取り上げた『New Yorker』誌5月25日号の記事を思い出したのだ。
ロック・グループ、ザ・ナショナルでリードヴォーカルを務めるマット・ガーニンガーはライヴやレコードで彼女と共演しているが、この記事の中で「フィービーは、退屈と悲しみについて素晴らしい曲を書く」と話している。この“退屈”と“悲しみ”が見事に開花するのが、アルバムより先行リリースされたシングル「Kyoto」である。
一日休んで京都
お寺にいて退屈になった
セブン-イレブンで店内を見渡した
バンドの連中は新幹線に乗り
鳥居を見に出かけた
行こうかなと思ったけど、行かなかった
あなたが公衆電話から電話してきた
ここはまだ公衆電話があるんだ
通話料は1分1ドル
お酒をやめるって話よね
手紙も届いたよ
だけど読む必要ってあるかな
(拙訳)
曲のタイトルとなる京都という場所について、印象など何か示されているわけではない。彼女の父親との関係に加え、日本滞在時の体験からインスパイアされたといわれる歌だが、日本の古都の美しさやその特徴が表現されているとは言い難い。では京都とは無関係なのかといえば、曲全体から醸し出される感情を考えると絶妙にフィットする。その感情とは、前述した孤独と退屈を作り出す環境ながら、そこから出ていく気配もなく、とどまる様子がどこか京都の佇まいと重なり合う。“そこにとどまる”と書くと、暗く閉鎖的なイメージを持たれるかもしれない。だが逆に、混迷するばかりの外の世界と距離を置き、内側に居て独自の世界を築き上げる様子に、創造性と体制(外側)に屈しない反骨精神を見出すことができ、固有の文化を生み出してきた京都との共通点が見つかる。それはまた、現在の米国のポップ・カルチャーでよく話題にのぼるユトーピア対デストピアの構造をも反映している。若い世代のSNSとして知られるTikTokで、利用者が現実(外側)からサンプルしたものに音楽やダンス、イラストなどを加えし、独創性に満ちあふれたバーチュアル空間を生み出すように、「Kyoto」でも自由奔放な世界観が広がっている。
ただじゃおかないからね
そっちが先手を打たないなら
東京の空で夢見つつ
世界を見てみたかった
だから海の上を飛んだ
でも気が変わった
夕暮れって見世物ショーだよ
だから週末が来て
郊外までドライヴに行き
グッドウィルで車を止め
ケムトレイル(飛行機雲に似たもの)を見つめる
一緒にいるのは弟
彼の誕生日に電話してきたって聞いたよ
10日も違ってたけど
気持ちは汲み取ってあげる
トラックを修理したことおぼえてる
わたしたちに運転させてくれて
25年なんてあっという間
許す気にはなれない
だからって、こだわりを持たせないで
さそり座の空の下で生まれたから
世界を見てみたかった
あなたの目を通じて。でもそのときになり
気が変わった
(拙訳)
曲の中で、語り手やその弟に連絡を取る人物(父親?)は、アルコールの問題を抱え、自身が混乱しているのがうかがえる。混迷する外の世界の象徴のようにも見えるが、語り手は嫌悪感を表しつつも、縁を完全に断ち切ろうとはしていない。
それはある意味、現在20代半ばのフィービーを含めた若い年齢層が生きていくために備えた、外側と内側を共有するためのバランス感覚とも思える。政治の腐敗や経済格差、環境破壊など厳しい現実を横目で見つつも、その世界にどっぷりと浸らず、自分の手でもうひとつの現実を作り、我が身を守る術と言うべきか。注目されるのは、たとえ内向的であっても、「Kyoto」で描かれる世界では悲壮感や絶望感が漂ってこないということ。軽快なメロディも手伝い、むしろどこか突き抜けた明るささえ感じるから不思議だ。
もしかするとそれが、ディランが示す、ネット文化を体感して育った世代の強みかもしれない。いくら退屈で孤独でも、遠くにいる自分を理解して、気持ちを共有してくれる人たちとつながる事実が、支えとなり、自信のようなものを彼/彼女たちに与えるのだろうか。
(発売元:ビッグ・ナッシング / ウルトラ・ヴァイヴ)
Text Niimoto Ryoichi
Illustration Masatoo Hirano
Edit Sumire Taya