素晴らしい本と出会い、その世界に入り込む体験は、いつだって私達に豊かさをもたらしてくれる。どんなに社会や生活のありようが変わっていこうとも、そんなかけがえのない時間を大切にしたいもの。激動の2022年が終わろうとしている今、ライター・嘉島唯がこの1年間に出版された数多くの本の中からお気に入りの5冊を紹介する。

嘉島唯
新卒で通信会社に営業として入社、ギズモードを経て、ハフポスト、バズフィード・ジャパンで編集・ライター業に従事。現在はニュースプラットフォームで働きながら、フリーランスのライターとしてインタビュー記事やエッセイ、コラムなどを執筆。
Twitter:@yuuuuuiiiii
『信仰』村田沙耶香(文藝春秋)

宗教という存在に対して意識が揺るがされた7月の前夜、2022年6月に上梓された短編集。タイトルを飾る『信仰』は「俺と、新しくカルト始めない?」というセリフから始まり、パンチの効いた冒頭からのめり込んでしまいました。カルト宗教の存在を頭ごなしに否定する物語ではなく、とても真摯に描かれているので読んでいて切なさを覚えました。ラストにかけては「自分もその1人なのでは?」と主人公に共感せざるを得ない「普遍的な問」が打ち立てられているので、背筋が凍る人も少なくないはず。
村田沙耶香さんの作品は「普通、こうでしょ」という感覚に対する暴力性を読み手に淡々と伝えてくれるのですが、本作はその色が特に濃く、背中にナイフをあてられているような感覚で読み進めました。
また本書の中には村田さんのエッセイも収録されており、これも小説と同様に「自分に潜む平凡な暴力性」について考えさせられます。「きっとこれまで私は何も考えずに誰かを傷つけてきたんだろう」という反省とともに、そうした想像力を少しでも養っていきたいという気持ちを喚起させられる1冊でした。
『新潮』2022年7月号(新潮社)
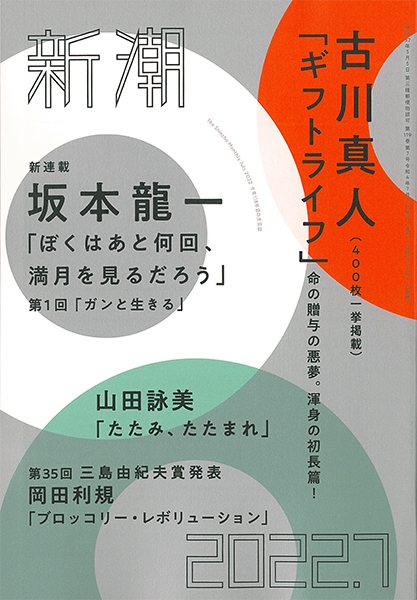
坂本龍一さんの連載『ぼくはあと何回、満月を見るだろう』の初回が掲載された号。連載は12月現在までで6回分が公開されていますが、その第1回のトピックが「がん」や「死生観」でした。
がんの「ステージ4」認定や余命宣告、せん妄体験……精神がおかしくなりそうな闘病生活を生々しく語りつつ、「一気に不信感が芽生えました」「患者に対しての言い方ってもんがあるだろう、と正直頭にきてしまいました」など、等身大の感情を明かしており、坂本さんの人間くさい一面が惜しげもなく披露されています。
さらに『戦場のメリークリスマス』に対する”常に戦メリを期待されてはうんざりする、この代表曲をこえる曲を作りたい、でもそれを終生の目標にして良いのか”という複雑な感情も吐露。飾り気のないエッセイを読んでいると、他人の目を気にしては一喜一憂するのがばかげている行為のように思えて、気分が軽くなるのです。不思議と心が澄んでいくような気がします。
この『新潮』の巻頭を飾る山田詠美さんの『たたみ、たたまれ』も衝撃作でした。文芸誌は音楽フェスのようなさまざまな出会いの場だと思います。
『母親になって後悔してる』オルナ・ドーナト(新潮社)

「もし時間を巻き戻せたら、あなたは再び母になる事を選びますか?」。この質問に「ノー」と答えた23人の女性にインタビューを行い、まとめたのが本書です。15ヵ国で話題になり、日本でも今年大きな議論を生みました。黙殺されてきた情念が明らかになり、共感や反発が生まれたのです。
私もその1人で、この本を読むまで「母親」という生き物は「減私奉公する存在」だと勘違いしていました。
母は私が8歳の時に他界しましたが、専業主婦として私に尽くしてくれましたし、当時はそれが「女の幸せ」といわれていたような気がします。
数年前、20年越しに母の遺品整理をしていると、母の給与明細や昔の恋人から届いた手紙を発見しました。母は私に愛情をいっぱい注いでくれている中でも「母親にならなかった人生」を考えていたのかもしれません。
本書でも書かれていますが「母親になって後悔している」とは「子どもを愛していない」わけではありません。23人の後悔の念は、私にとって母親という存在を人間に戻してくれました。母親になったとしても、自分の人生は手放さなくていい。この本の要旨はここにあると思います。
『この部屋から東京タワーは永遠に見えない』麻布競馬場(集英社)
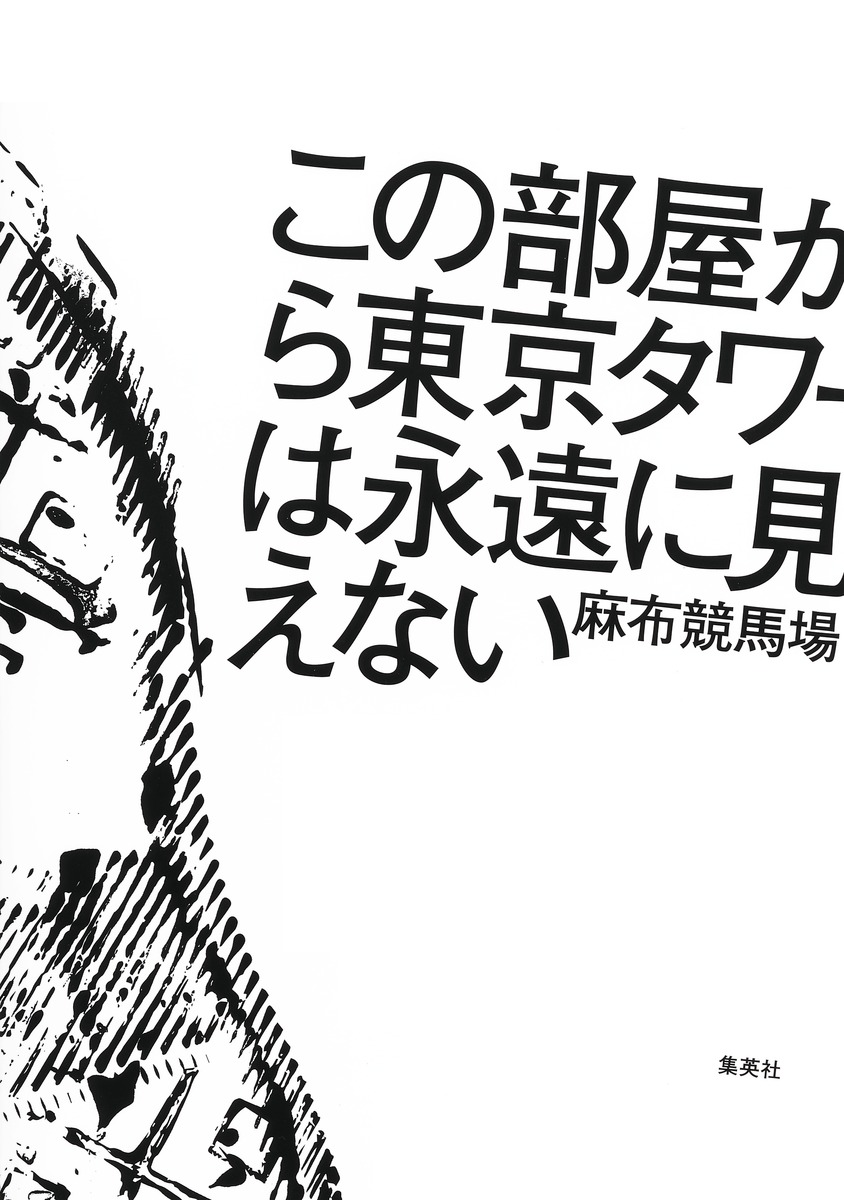
Twitterで「リアルすぎる描写」と話題になった投稿が「文学」として昇華された1冊。Twitterの連続投稿をもとに作られた短編集で、気がついたら読了していました。それぐらい没入感があります。
読んだ瞬間「現代の『なんとなく、クリスタル』だ」と思った人は多いのではないでしょうか。東京で暮らすアッパー層の固有名詞にまみれた物語は、きらびやかに見えつつも、軽薄で空虚で刹那的。男女のさまざまな物語が展開されるのですが、精緻すぎる描写に腹わたを刺されるような感覚に陥ります。
「どちらかというと乃木坂のほうが近い大衆海鮮居酒屋」は毎日のように通っていたなぁとか、セクハラとパワハラをする上司は「セパ交流戦」とか「日本シリーズ」とか呼んでたなぁとか、大江戸線の、地の底まで永遠に続くような階段を下りる元気が湧かなくなったこともあったよなぁと、登場人物達と似たような行動をしている自分が浮き彫りになり、ハッとするのです。
インターネットの普及によって場所にとらわれなくなったといわれて久しいですが、いまだに東京のパワーは健在であることを実感させられる昨今です。
『そして誰もゆとらなくなった』朝井リョウ(文藝春秋)

平成生まれの直木賞作家・朝井リョウさんのエッセイ。本書はこれまで発行してきたエッセイ『時をかけるゆとり』(2014)『風と共にゆとりぬ』(2017)に続く3作目。どうやら「ゆとり3部作」の完結作なのだそう。
朝井作品といえば、現代に生きる若者達の心情を、心の皮を1枚1枚剥ぐように丸裸にしていく筆致で、多くの人を虜にしている印象があります。
そんな朝井さんのエッセイは、小説とは異なり軽快でコミカル。電車内で読むと思わず吹き出してしまう内容で、周囲から訝しがられます。「ゆとりとか言ってられない年齢になった」という一文から始まる本作は、同世代の自分としてはうなずかずにはいられない言葉が目白押しです。
「もう社会人十年目とかだよね? 下の世代も育ってきてるよね? “できない自虐”みたいなので笑ってもらえる期間、とうに過ぎてるからね?」。
この雰囲気が、少し物悲しいタイトルに結びついているそうです。加齢による体型の変化、引っ越し、習い事での失敗談など、大人になるための身近なトピックが満載でスイスイ読み進められます。繰り返しますが、公共交通機関内で読むと大変なことになるのでご注意ください。

