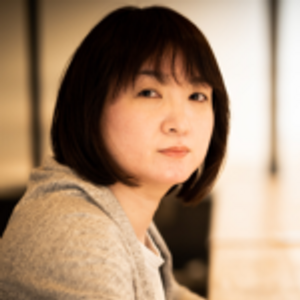大西諒
1989年兵庫県出身。映画美学校フィクションコース修了生。IT企業の営業から映画配給会社への転職を模索して映画関連のワークショップに参加した際、制作に魅力を感じて30歳で映画美学校に入学。映画制作未経験で一から学び、在学中に複数の短編作品を制作。『はこぶね』は卒業後に制作した初長編作。
Twitter:@cap_mora
初の長編映画『はこぶね』が、若手作家の登竜門となる田辺・弁慶映画祭、TAMA NEW WAVEでのグランプリなど、6冠を獲得した映画監督の大西諒。同作は、とある小さな港町で生きる、視力を失った男・西村芳則(木村和貴)が、さびれても美しいこの町で、感性を失わず生きようとする姿が、周囲の人々の心を振るわせていく様子を描く。障害や介護、地方の疲弊といった厳しい現実を題材としながら、西村の知覚と感情を追うような、観賞者自身が感覚を研ぎ澄ませる独特な観賞体験が、観るものの心を惹きつける。
8月4から10日まで「テアトル新宿」で上映され、多くの賞賛のコメントがSNSに投稿されるなど話題となり、9月9日からは「ポレポレ東中野」で公開されるほか、今後は他の都市でも順次公開される予定だ。
数年前までIT系の会社で営業をしていたという大西監督がいかにして、『はこぶね』を完成させたのか。これまでの歩みとともに、その制作背景を聞いた。
ITの営業から映画監督へ


——大西さんは、もともとは映画とはまったく関係ない仕事をしていたところから、映画を撮りたいと思って学校に行かれたそうですね。
大西諒(以下、大西):もともとIT企業で営業をしてたんです。最初は仕事で得た知識が役に立つんじゃないかと思って、映画の買い付けや配給のワークショップに行ったんです。その後に制作系のワークショップに行ってみようと思って、映画美学校の1年間の講座に通うことになったんです。
——どのような授業だったんですか?
大西:映画と言うのは、映画が始まる時と終わる時で登場人物の関係性が変わっていくものだという考えで授業が行われていました。基本的には町に出てとりあえず「撮ってこい」という感じだったのですが、僕の場合は、本当に未経験だったので、1分間のシーンにどのくらいの撮影時間がかかるのかということも知らなくて、1分のシーンなら準備も含めて10分くらいで撮れると思ってたくらいだったんです。受講生の中には経験者もいたので、むしろ撮影現場で同級生から学ぶという感じもありました。
——そんな状態から、実際にこの映画を撮るまでは、どれくらいだったんでしょうか?
大西:2019年に学校に入って、コロナもあったので仕上がりに時間がかかったんですが、2020年と2021年に撮影をして2022年に映画ができあがりました。
——その学校に行ってた時からすると、長編1作目とは思えない仕上がりで、けっこうなスピード感ですよね。
大西:映画にとってルック(映像のスタイル)は大事だと思うんですけど、そこは学校の同級生で今回撮影を担当してくれた寺西(涼)くんのおかげというところはありますね。学校には本気で映画を撮りたい人が多くて、みんな監督をしたくて学校に来ていて、お互いの作品を手伝いあってるんです。そんな気心の知れた同級生が関わってくれているというのは大きいんです。
——この映画の脚本をまず、ネットで公開されたと聞きました。
大西:自主製作映画の募集をかけられる「シネマプランナーズ」というサイトがあるんですが、そこにまずは脚本をアップしてみました。1日に何十件も脚本が上がっているので、その中から自分の企画を見てくれる人がいるとも思ってなかったんですけど、その脚本を見て、(主演をすることになった)木村知貴さんが直接コンタクトを取ってくれました。

——映画を製作するのに、金銭面はどうされたんですか?
大西:そこは10年間、会社員をしていたので、これまでの貯金を使いました。もともと木村さんが主演に決まった段階では、短編の脚本だったんですけど、木村さんと話していて「作るんだったら長編で評価されたほうがお互いにいいのではないか」ということになり、そこから一緒に長編化をすすめていきました。
——『はこぶね』の脚本を書く上で何か参考にしたものはあったんですか?
大西:『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(伊藤亜紗・著、光文社新書)という、視覚障がい者やその関係者のインタビューをまとめた本の影響が大きいです。「あなたの体は世界をどう見ているんですか?」という好奇心で書かれた本なんです。映画美学校が終わったタイミングで時間ができて、図書館でいろんな本を読んでいたら、その本が1番面白かったんです。ある評論家の方が、『はこぶね』についての感想を書いてくれていたんですが、僕がその本を読んだ時の感想とすごく近くかったんです。もちろん、この本のことは評論家の方は知らずに映画だけを見て感想を言ってくれたんだと思うんですけど。それは、すごく興味深いなと思いました。
——実際、映画を作る中で大変なことはありましたか?
大西:そもそも撮影現場に、僕は10回も行ったことがなかったんですよ。なので、映画を作っている作業が大変すぎて、途中は自分がもともと何をやりたかったのかが、かすれていく感じはありましたね。観終わって編集して映像を繋ぐ過程で何をやりたかったのかを思い出すこともありました。映画撮影に関わってくれた映画美学校の同級生って、本来ならお互いはライバルで、好みも違っているものなんですよ。そんないろんな考えの人がいる現場で、統率ができているわけじゃないから、いかに乗ってやってもらうかということが重要でした。その中でも、撮影や音楽をやってくれた寺西くんとは、脚本の段階から適宜コミュニケーションをしていました。
——音楽がシーンとタイミングがあっているところは多かったですね。終盤で車を運転しているシーンとか。
大西:あそこは粗編集をする時に、ヘンリー・フリントのエレクトリックヴァイオリンを使った音楽をかぶせていたので、その要素が入っているかなとは思います。そのイメージをベースに木村さん演じる主人公の西村芳則が運転をするシーンで、隣にいる大畑碧(高見こころ)がハンドルをつかんで西村が感じているものをつかみ取ろうとしていることが、より強調できる劇伴をつけてくれました。既成の音楽ではできないところだったと思います。ほかでいうと、船の汽笛がなるシーンもそうでしたね。
——セリフとしては、釣りをしている主人公の西村が、水の中が見えるんだっていうシーンが印象的でした。
大西:僕も釣りをするんですけど、目をつぶって水の中を想像しながらやってたんですね。目の見えない方がそうするとは限らないんですけど、そういう感覚を取り入れてみた場面です。

衝突することでしか得られないものを描く

——物語の舞台が、閉塞感のある街であるというのは、どのような意図があったんでしょうか?
大西:僕もそうですけど、今って都会に住んでると人と衝突しないじゃないですか。それって、コミュニケーションを避けようと思えば避けようがあるからだと思うんです。でも、都会ではない田舎の狭いコミュニティの中であったりとか、選択の余地のない家族という関係になると、コミュニケーションを避けようがない状況っていうのんがあるんじゃないかと思いました。僕自身、いろんな映画を見ていて、本当は避けられるものを無理やり避けられない問題にしているように映しているものはあまり好きではなかったので、どうにも避けられない状況というのを考えた結果、そうなりました。

——ご自身的には、コミュニケーションに対して、どのように思っていますか?
大西:自分の家族の問題だったりすると、もちろん避けられないところはあります。でも衝突することは必ずしも嫌なことではないし、避けられない状況を通ってみないと得られないものもあると思います。今回の映画でも、衝突がネガティブなものとも描いていないんですよね。
——内田春菊さんが演じる主人公のおばさんなんかも、衝突が起こるキャラクターではあったけれど、一方で、西村にとって、おばさんからのケアというのもかなり大きいわけですよね。同級生の女性との距離感にしても、人間関係の不思議なバランスが描かれていましたね。
大西:映画を撮っている最中には、「こんなに何も起こらない作品を、人は最後まで見てくれるんだろうか」という不安もありました。でも最終的には「とはいえ、何か変わった感覚が残るものになればいいのかな」と思いました。

——『はこぶね』を観ていて、どうにもならない問題をどうにもならないままに描いている感覚が、イ・チャンドン監督を思い出したりもしたんです。
大西:確かに、イ・チャンドン監督は好きですね。そうかもしれないですね。どうにもならない問題への興味がすごくあるので。
——映画のワークショップに行く前は、どのような映画を見てきたんでしょうか?
大西:僕自身は映画はそこまで観ていなくて、どちらかというと音楽からの影響が大きいですね。音楽については幅広く聞いてきましたね。僕は撮影予定地に行きながら脚本を書いていくんですが、その時にプレイリストを作って、物語に流れているであろう曲を聞きながら書いていました。映画の文法とかはあまり意識していなくて、むしろその時に聞いている音楽のリズムや文法の方からの影響があると思います。あと、映画として成立しているとすれば、撮影の技術とお芝居の強度によるところは大きいと思いますね。通常の映画的な感覚だと、バス停で2人が会話をするまでの尺とか、歩いている時間の尺が長いとか、そういう指摘もありました。そのあたりは当時聞いていたプレイリストのタイム感が反映されていると思います。
——映画よりも音楽に関心があった大西さんが映画を撮るようになった理由はなんですか?
大西:僕はあらゆるものの反復練習が苦手で。楽器も反復練習がまったくできなくて、やりたくても上手くできなかったんですよね。ただ映画の脚本は、歩きながらとか、シャワー浴びながらとか、どのタイミングで考えてもいいし、机の前とか、1箇所に止まってずっと考えなくてもいいというのはあったかもしれません。それと人間への興味があって、相手が何を考えているのかということに関心があり、それを表現しやすいのが映画だったのではないのかなと思います。
「西村の役は木村さん以外には考えられない」

——シーンとしていいなと思ったのが、木村さん演じる西村が空を見上げているところでした。あのシーンは、言葉とかでは説明できないものがあると思いました。あそこは脚本や演出はどのようにしましたか?
大西:脚本にも書いていたんですが、人って、落ち込んでいる時に太陽を浴びれば何かちょっと気が晴れたりすることってあると思うんです。僕自身、いろんなことにとらわれているなと思っていた時に、太陽の光を浴びて、何か気分が変わったことがありました。演技に関しては、目をこうしてほしいなんてことは言ってないし、そういうことを意識もしてほしくないという気持ちがあったので、何も言ってないんですけど、そこは木村さんがばっちりやってくださいましたね。

——脚本を書いた時は西村という役を誰かイメージして書いたりはしていなかったんですか?
大西:どのキャラクターに関しても脚本を書く時には実在の人物は想定していなかったですね。変化したというと、短編ではおじいちゃんは出てこなかったんですけど、長編になっておじいちゃんが出てきました。人の身体の変容による、五感や感性の感じ方の変化というものに興味があったので、認知症のおじいちゃんというキャラクターが増えました。
——木村さんと西村のイメージがぴったり重なっているように見えましたが、大西さんの中ではどうでしたか?
大西:西村の役は木村さん以外には考えられないですね。すごいなと思うのは、脚本を長編化して適宜確認してもらっている時に、俳優であれば、自分がどう演じたいのかという俳優としての自意識を脚本に反映させたくなると思うんですけど、それを彼自身が極力、排除しようとしていたところです。たぶん、木村さんがどんな役を演じたいか以前に、西村というキャラクターに対しての強い興味があったのだと思います。途中からは、プロデューサー目線で、物語としてどうなのか、この人物像が自然な動きをとっているかという目線もあったと思います。
——閉塞した街で、人と人がどうケアしあうかというところも、関心の持てるテーマだと思いました。
大西:いろんな興味が重なってるんですけど、1つは僕のおばあちゃんが認知症で、何度も同じ話を繰り返していて、でもそれに反応してくれることで、うれしく思ったり、また反対に面倒くさいと思ったりする感覚があったんです。もう1つは仕事で僕が人に頼るのが得意じゃないので、人にいかに頼れるようになるかというのが個人的な課題でもありました。あるお医者さんの本に、障がい者にとっての自立とは、いかに依存先をふやすかということが重要で、それこそが自立だと書いていたのを読んで、そういうさまざまな関心が重なって今のような話になりました。話の推進力としてこのようなテーマを選んだということもあるにはあると思いますが、この問題とこの問題を無理にくっつけようというわけではなかったですね。現実の多くの問題が複合的だと思っているので、現実の単純化はしないように意識してました。
Photography Masashi Ura

■『はこぶね』
9月9日〜最終日未定@ポレポレ東中野
10月27日〜11月2日@京都シネマ
11月4〜10日@元町映画館
※福岡・kino cinéma天神、大阪・シネ・ヌーヴォ、東京・CINEMA Chupki TABATAは近日公開予定、その他全国順次公開
出演:木村知貴、高見こころ、内田春菊、外波山文明、五十嵐美紀、愛田天麻、森海斗、範多美樹 ほか
監督・脚本:大西諒
撮影・音楽:寺西涼
配給:空架 -soraca- film
https://hakobune-movie.com