東京藝術大学音楽学部作曲科を卒業し、同大学院音楽研究科修士課程を修了。2016年以降には2枚のソロ・アルバムをリリースし、近年は大貫妙子やDAOKOなどさまざまなアーティストの右腕としてアレンジ等に携わるなど、ポップ・ミュージックのフィールドでもその名を大きく知らしめつつある音楽家/作曲家、網守将平。
前作『パタミュージック』における、「ポップ」を過激に分解/再構築する表現を経て、このたび1月22日発表する最新アルバム『Ex.LIFE』では、自身のヴォーカルやめくるめくリズム・フィギュアを封印し、より「素直」なメロディーや、自身の弾くピアノを中心とした静謐なテクスチャーが全体を覆う、全く様相の異なる音楽世界を作り上げた。そこには、このコロナ禍以前から彼が抱いていた「音楽が純粋に音楽であることの困難さ」に対するオルタナティブなストラテジーが見え隠れする一方、この間の社会変容がもたらした新たな趨勢/思想や、あえて自身の音楽的蓄積に身を晒そうとする彼自身の姿が映し出されている。
また、これまでと同様、「一人で音楽を作る」ことに拘りつつも、永井聖一(ギター)、西田修大(ギター)、ゴンドウトモヒコ (ユーフォニアム)、 坂本光太(チューバ)、増田義基(ファシリテーター)、玉名ラーメン、Elena Tutatchikovaといった多彩なゲストを迎えた本作は、有り体に想像されるような「作曲家による自足的なソロ作品」とも決定的に異なり、いわば社会的な眼差しに貫かれてもいる。それ自身自律的(であるようにも聞こえ)ながら、一方で時間や空間に密着的である音楽。この類い稀な作品を作り上げた鬼才に、じっくりと話を訊いた。
時代が変化する中で表出された「素直な音楽性」
――音楽の受容のされ方が変化した1年だったといわれていますが、網守さんにとってはいかがでしたか?
網守:こう言うとなんですが、「自分にとって音楽というものはこうあってほしい」という状況に少し近づいたような気がしています。もちろん、ミュージシャンにとって経済的に大変な状況ではあるけれど、「ちゃんと音を聴く」とか、「一人で音楽を作る」ということに関しては以前よりもやりやすい環境になった気がしていて。
――前作リリース時のインタビューで、音楽が純粋に音楽そのものとして成り立たない状況に対して批判的な視座を投げかけるような発言をされていたと思うのですが、それが解消されてきたということでしょうか?
網守:そう感じます。この10年、コミュニケーションや人間関係が先にある中で作られる音楽が過剰にあふれているように感じていたんです。20世紀はコンテンツ消費の時代で、ゼロ年代はメディア消費、テン年代はコミュニケーション消費の時代だったという見方がありますけど、コロナ禍の結果、今このインタビューで使っているZoomとかも含めて、さまざまなオンライン・メディアが急速に浸透してきました。その結果、今一度メディアにまつわる問題意識が前景化しているように思うんです。僕はもともとそういうところからアプローチする人間ですし、コミュニケーションを前提とした表現っていうのは根本的に向いていなくて(笑)。それこそ前作は厳密にそういった問題意識から出発してガチガチにコンセプトを固めて作っていったアルバムでしたね。
――その点、今作は前作に比べて、より「素直さ」みたいなものが表出しているようにも思いました。
網守:そうだと思います。結局、幼少期から教育されてきた作曲家としてのアイデンティティや影響元からは逃れ得ないという吹っ切れのようなものもあって。もともと自分に身体化されていた音楽が素直に出てきた、というか。
――今回はミニマルな構成のインスト曲や即興演奏曲が収録されているにせよ、前作よりもむしろ「聴き下し」のしやすい印象でした。
網守:まさにそうですね。特定のアイデアから出発した曲もありますが、今までの作品の中で一番聴きやすいものになっていると思います。
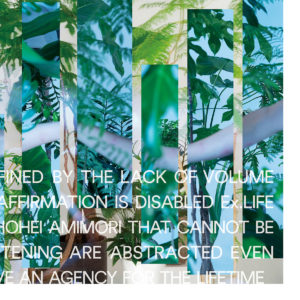
――新しいアイデアということでいうと、⑦「Non-Auditory Composition No.0」は「非聴覚作曲」という方法を考案し制作されたそうですね。
網守:はい。自分を含めたメンバーがライン楽器のみを演奏して即興を行っている中、ファシリテーターが任意のタイミングでヘッドホンのモニター音声をオン/オフするという形です。突然自分達の演奏している音が聞こえなくなったり、聞こえたりすることで、耳がどう機能して、どう演奏に反映されるかというのを記録しました。
――なぜそういう方法を試したんでしょうか?
網守:やはりコロナ禍におけるオンライン・メディアの浸透が大きいです。Zoomとかだと、各所で鳴っているごちゃごちゃした音が無理やり対称性を帯びたりする。要は、音の聞こえ方がテクノロジーによってあからさまに変質されている。そういうツールを使っていると、われわれ人間側も、以前よりもすべての音に対して耳を澄まさなければ音の聞き分けが難しくなる。すると、この環境的変化が結果的に人類の耳の感度というか、処理可能な解像度を上げるんじゃないかという仮説を設定してみたんです。そこから導き出されたのが、通常の聴覚に極端なバイアスがかかった状態で作曲/即興を行うというこの手法でした。
「良いメロディー」を突き詰めた先に立ち現れたもの
――一方で、練り込まれたメロディーの美しさが際立った曲も多い印象です。
網守:売り物としての音楽作品を作る時は、やっぱりメロディーをどう捉えるかというのは大きなテーマになってきます。クライアント仕事をやっていると、スタッフの人から「キャッチーなメロディーでお願いします」とかよく言われるわけですよ。その場合、耳に残りやすいとか中毒性とかそういう方向で「良いメロディー」というものが捉えられていることが多いんですが、自分からすると、それは鬱陶しいってことと表裏一体でもある。実際、ミュージシャンにしても聞き手にしても、そのあたりを聞き分ける審美的精度がすごく落ちていると思うし、それを続けていると結局メロディーは消費されるものでしかなくなってしまう。じゃあ自分の考える「良いメロディー」ってなんだろうということを突き詰めてみよう、と思ったんです。
――なるほど。ではずばり「良いメロディー」の条件とは?
網守:それ自体が聞き手の能動性をほんのり呼び起こすメロディー。聞いていると自然と追いかけたくなるメロディーとも言えるかも。そのほうが、聞き手への規定性や束縛性が強い俗的な意味で「キャッチー」なメロディーより普遍的な存在なんじゃないか、と。要するに、時間の流れを感じさせてくれるメロディーですね。
――以前、『ミュージック・マガジン』誌2020年3月号の「ミュージシャンが選ぶ生涯の愛聴盤」という特集の中で、テクスチャーをどのように物語としての時空間に貼り付けるかという意識と、自律した作品への憧れが同時にある、という趣旨のコラムを書かれていたと思うのですが、今の優れたメロディーについての話は、時間とも密接であり自律的でもあるという意味で、その発想とも近しいもののように思いました。
網守:確かに。無意識的にその両要素を意識して作っているんだと思います。例えば⑫「Aphorican Lullaby」では、フィールド・レコーディングの背景音とメロディー(主題)を同化させつつ、徐々に旋律が個別的に立ち現れてくるという構成を取っています。能動的にメロディーの生成そのものを聞き手が追いたくなるのを狙って作りました。
――そういう能動性を喚起するという意味で、通常の意味での背景音楽や、狭義のアンビエントとも性格が違うように感じます。
網守:まさしくそうだと思います。
――一方、すべてがゼロから生成していく感覚でもなくて、例えばガムランやファンクや、ネオ・クラシカルなど、ある特定のジャンルを想起させる要素も各所に内包されているようにも聴こえました。
網守:作っている途中に「〇〇っぽい」と気付くことはありますけど、恐らくほとんどは幼少期からの蓄積が自然に表出しているということだと思います。昔「癒やし系」ってあったじゃないですか。いい感じにリリカルなピアノ・ソロとか、壮大なワールド・ミュージックみたいなのがたくさん入っているコンピレーションとか……。
――ああ〜、『image』とか『feel』的な。
網守:そう。もはやそういうちょっと恥ずかしいルーツにすら素直になったのかもしれない(笑)。だから「〇〇っぽい」は絶対あると思う。それは、今回のように隙間が多くて、映像喚起的な音楽だと特に表れやすいものだと思います。もちろん藝大在学中に学んでいたこともどうしても自然と入り込んできているとは思います。先日も、大貫妙子さんのオーケストラ・コンサートのために書いた自分のアレンジ譜を見返していたら、「ああ、ここ武満(徹)っぽいことしたかったんだなあ」って気付いたり(笑)。
ポップ・ミュージックの「品格」と「社会性」
――その大貫妙子さんをはじめとして、前作リリース以降多くの音楽家とコラボレーションを重ねていますよね。そういった経験から得たインスピレーションもあるのでしょうか?
網守:すごくありますね。特に大貫さんとの対話から受けた刺激はとても大きい。「こんな音楽をやってみたい」というヴィジョンがほぼ全く一緒、という気がしています。さっき言ったメロディーの普遍性についてもそうですし、ポピュラー・ミュージックにおける「品格」という考え方でもそう。品があれば、下世話であっても良い、という。
――「下世話」と「下品」は違う?
網守:そう。例えば、レナード・バーンスタイン風の、「ジャッジャジャーン」みたいなベタでロー・コンテクストなキメとかでも、そこに品があれば普遍的な魅力を感じられるけれど、マーケティングから逆算されたようなアディクション重視の「ポップ」の場合は違う。大貫さんが以前「結局、イントロとカウンター・メロディーさえ優れていれば素晴らしいポップスは成立する」と言っていたんですけど、まさに、下世話で単純なメロディーにも品が宿るというのは、そういう部分を突き詰めることなのだろうな、と思いますね。
――他にも、インスタレーションやサウンド・アート、映像制作等、さまざまな分野でも創作を行っていますよね。その上でなおポピュラー・ミュージックに携わり続けるのはなぜなのでしょう?
網守:結局僕は、音楽を作っている時もアート系の仕事に携わっている時も、「この作品が社会に存在するというのはどういうことなのか」ということを考えてしまうんです。その意味では、ポップ・ミュージックというのは宿命的に社会に内在的なものであるし、自分もそこから離れられないのかなと。
――ポピュラー・ミュージックは、その根源的性質からして自足的な存在でなく、おのずから聴衆をはじめとした社会的存在に縁取られたものである、と。
網守:そう。僕は東浩紀さんを尊敬しているんですが、例えば彼がゲンロンで行っているのも、思想を内閉的な存在にするんじゃなく、広義の「観客」へ開いていこうとすることですよね。そういう考え方にも影響を受けていると思います。
――世に出るものを創るということは、それが一人で成されたものであっても、はじめから社会的な活動である?
網守:はい。翻ってミクロな視点で見たとしても、音楽においては結局、サイン波の音量が音色やテクスチャーを含めたすべてを規定するし、それは結局のところ数的な理論でもある。でも、視野を広げれば、微小な数的要素の重なり合いと連続が社会を構成しているわけで、そういう意味においても、計量的な存在としての音楽は社会から逃れることはできない……。
――おもしろい考え方ですね。音楽を還元主義的に突き詰めていくと、つい非社会的な存在と捉えられがちだけれど、実は結局のところ社会とつながっている。
網守:はい、そういう思考が僕の音楽に対する根本的な考え方を形作っていると思うし、今作のジャケットには、それを抽象的に表現したテキストを載せています。
――今後取り組んでみたいことを教えて下さい。
網守:しばらくソロ・アルバムはいいかなあっていうのが正直なところですね(笑)。最近興味があるのが「エフェメラリティ」(一過性)という概念で、彫刻とかインスタレーションに触れることで刺激されることも多くて。自分なりに、音楽におけるエフェメラルとは何かというのを考えた上で作品創りを行ってみたいなと思っています。
*
網守将平
1990 年東京生まれ。音楽家/作曲家。東京藝術大学音楽学部作曲科卒業。同大学院音楽研究科修士課程修了。学生時代より、クラシックや現代音楽の作曲家/アレンジャーとして活動を開始し、室内楽からオーケストラまで多くの作品を発表。2016年、初のフルアルバム『SONASILE』をリリース。複雑な電子音響とポップなメロディーの共存を提示した。2018年にリリースされた『パタミュージック』はポップ・ミュージックと実験音楽をコンセプチュアルに配置した音楽性が話題となり、BBCなどヨーロッパ各国のラジオ局で多数のオンエアを獲得し、イギリスの音楽雑誌WIREなど多数のメディアに批評が掲載された。近年はポップ・ミュージックからサウンド・アートまで総合的な活動を展開。さまざまな表現形態での作品発表やパフォーマンスを行う傍ら、大貫妙子やDAOKOなど多くのアーティストの作編曲に携わる。CMやテレビ番組の音楽制作、音楽領域以外のアーティストとのコラボレーションワークも行う。
www.shoheiamimori.com
Twitter:@shoheiamimori

