終息に至らないコロナや大国による軍事侵攻、歴史的な円安などなど。2022年に刻まれた様々な出来事は、私たちの日常のありかた・感覚に少なくない変化をもたらした。しかし、そんな変動の時代の最中においても、音楽は変わらず鳴り続け、今年も素晴らしい作品がいくつも生まれた。その中でもとりわけ聴き逃せないベストミュージックを、音楽ライター・石井恵梨子が紹介する。
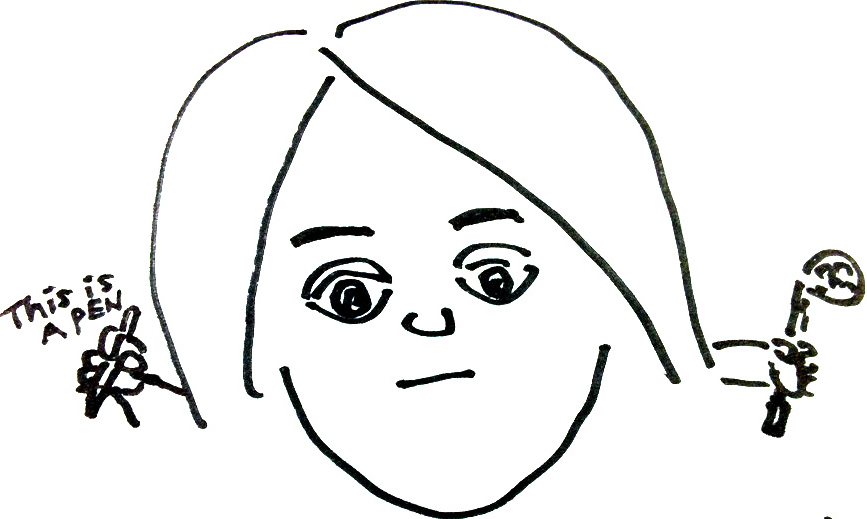
石井恵梨子
1977年石川県生まれ。「CROSSBEAT」への投稿をきっかけに、97年より音楽誌をメインにライター活動を開始。パンク/ラウドロックを好む傍ら、ヒットチャート観察も趣味とする。現在「音楽と人」「SPA!」「リアルサウンド」などに寄稿。 Twitter:@Ishiieriko
Awich『Queendom』
今年一番毅然と輝いていた音と声。さらに言えば今年一番格好良く各フェスティバルに降臨した人だと思う。フジロックのレッドマーキーは泣きながら見た。これ中学生の時に見ていたらわたしはラッパーを目指していたかもしれないな、と感じながら。自分の言葉で自分の来た道を語っているだけなのに、それが過去のシーンの男性優位性を恥ずかしいほど浮き彫りにしていくところも素晴らしかった。とはいえ普段はライブハウスにいるアナタ、さほどヒップホップに詳しくないよねと訊かれたら、その通りですと頷くばかり。ただポップ・ミュージック/レヴェル・ミュージックとして圧倒的な強度があった。憧れます。
the hatch『shape of raw to com』
日本アンダーグラウンド/オルタナティヴの2022年金字塔。本作のリリースを機に拠点を札幌から東京に移したそうだが、どこに居るかという地域性が重要なのではなくて、誰ともつるまない、誰にも見つからない、誰にも踏み込めない場所で蠢いているドキュメント性にやられた。異物感のカタマリ。赤子の命はただ輝いているのではなくて、ぬるぬるの胎盤や羊水と一緒に飛び出してくる、なんてことも思い出す。スカスカなのに途切れることのない見事なリズム構成。その中で繋がる不協和音、ファンク、ジャズ、ポストハードコア。あとは妙に歌謡っぽい抒情性。なんだこれと背筋が震えたし、解はいまも出ていない。
String Machine『Hallelujah Hell Yeah』
友達に偶然教えてもらった作品。深く追いかけていたわけでもなく、ペンシルバニア州ピッツバーグの7人組インディ・フォーク・ロックだと後で知った程度。ただ、このユルユルでとぼけた空気感が好ましく、気づけば中毒になってしまった。特筆すべきはピンボーカルを立てず、歌いたい人がみんなで歌うというスタイル。同時期にアジカンの『プラネットフォークス』が出たことや、GEZAN with Million Wish Collective のライヴを見たこともあり、「みんなで歌う」ことは時代の嫌なムードに抗っていく行為なのだと発見。そしてこの人たち、闘争とか商業に無縁の底辺インディー感がとてもいいです。頬が緩む。愛おしい。
black midi『Hellfire』
登場から数年、確かにすごいバンドだろうけど、私にとっては知能指数高すぎのプログレでいまいち夢中になれない存在だったUKウィンドミルのブラックミディ。「すいません! ようやく面白さがわかりましたぁ!」となったのが本作。スキル、スピード、アジテーションの凶暴さはもちろん、狂気とユーモアが絶妙に混じり合う感じ、危機迫るサスペンスの匂いとバカ楽しいファンク・セッションが一緒に鳴ってしまうところ、あとは超絶技法をあくまで踊りながらやっている姿などを見て、最高のエンターテインメント集団だなと認識を改めた。笑いがあるって重要。あと『地獄の業火』という日本語帯もナイスでした。
Alice In Chains『Dirt(2022 Remaster)』
ふざけているわけではなくて。実は今年一番愛聴したのはボルチモア拠点のTURNSTILE『Glow On』で、2021年夏に発売されたこの作品には、90年代前半のUSハードコア・パンクやオルタナティヴを彷彿とさせるエネルギーが溢れ返っていた。今アメリカで何が起きているのかと戸惑い、同時に興奮もする。で、TURNSTILEばかり聴いていた半年後、ぬらりと蘇ったのが30年前に発表されたグランジ名作リマスター! 十代の熱狂が戻ってくるのはもちろん、歌やハーモニーの聴こえ方が全然違うことに衝撃を受けた。ビートルズのリマスターに毎回飛びつくおじさんの気持ちが初めてわかった。そんな年齢になった。
