
加藤修平
バンドNOT WONKを藤井航平(Ba.)、高橋尭睦(Dr.)と共に2010年結成。北海道・苫小牧を拠点に活動する。2015年に1stアルバム『Laughing Nerds And A Wallflower』をリリース。2019年6月に3枚目にしてメジャー初アルバム『Down the Valley』を、2021年1月に4枚目のアルバム『dimen』をリリースした。2022年からソロプロジェクトSADFRANKを本格始動。「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2022 in EZO」へ出演し、Hygge STAGE 初日のトリを務める。11月にはファーストシングル「Quai」を配信リリース、 そして北海道モエレ沼公園・ガラスのピラミッドにて開催した初めてのバンドセットライブが話題を呼ぶ。SADFRANK待望のデビューアルバム『gel』を3月1日にリリースした。
Twitter:@sadfrancis_
Twitter:@sadbuttokay
Instagram:@sadfrancis_
バンドNOT WONKの加藤修平によるソロプロジェクトSADFRANK(サッドフランク)がデビューアルバム『gel(ゲル)』を3月1日にリリースした。同アルバムには石若駿、本村拓磨(ゆうらん船)、香田悠真のコアメンバーに加えて、くるりの岸田繁や松丸契など、多彩なメンバーが参加し、加藤自身初となる全曲日本語詞による全9曲が収録されている。
NOT WONKというタグを外し、加藤修平という1人の音楽家として、他のミュージシャン達と1対1で向き合ったという本作がいかにして誕生したのか。その思考に迫る。
SADFRANKの始まり

——今作『gel』は加藤さん史上初めての全曲日本語詞ということを含め、ご自身の歌心と言葉に向き合って、自分という人間の心奥に潜っていく楽曲ばかりだと感じました。音楽的に言っても、弦や鍵盤の美しい音色が前に出つつも、整合性を求めず心の中を自由に泳いでいく感覚が強い。総じて加藤修平の輪郭をはみ出していくことで自分と何なのかを探す旅のようなアルバムだと思ったんですが、ご自身の手応えはいかがですか。
加藤修平(以下、加藤):おっしゃった通りだと思いつつ、でも、いまだによくわかんねえ作品だと思ってます(笑)。
——はははははは。
加藤:録音からミックスダウンまで1年ちょっとかかったし、作曲から考えたらもっとかかったアルバムなんですよ。とはいえ音楽って、長い時間をかけたからいい成果を得られるってものでもないじゃないですか。なのでこの『gel』という作品に対してかけた時間は判断基準に入ってこないんですけど、ただ、自分のやりたいことは目一杯やり切ったと思えてますね。で、いろんな段階での「これをやりたい」を積み上げて作品にした結果、これは何? って自分でも思っちゃった(笑)。
そもそも僕は、「これは本当に俺が作ったんですか?」って言いたくて毎回取り組んでいるんです。自分でもよくわからないところに行きたくて音楽をやっているし、それはNOT WONKの時にも込めていた気持ちで。ただ今回の場合は、バンドという形じゃなく最初から最後まで自分の作品なわけですよね。だからこそ、俺が作ったはずだけどこれは一体なんなんだ? っていう感じが今まで以上に強い。自分から出たものなのに、自分のどこから出てきたものなのかがわからないっていう感覚です。
——その異物感は何によってもたらされたんだと分析できます?
加藤:NOT WONKをやっている時は楽曲にも言葉に大元が常にあって、自分がこう考えたからこうなったっていうのを音楽的にもマインド的にも説明できるんですよね。でも今回は日本語で歌詞を書いたのが初めてだし、歌においてもどこからどこまでをOKとするのか、基準が全くないところからのスタートだったんです。そういう行程を1つひとつ経て歌を探っていったので、今回の歌は自分でも説明がつかない。参照点がなく、俺が気持ちいいかどうかだけで進めていった過程がこの異物感に繋がっているんだと思います。この作品で鳴ってる音はDTMの時点から自分で入れていたし、作り方自体はNOT WONKと変わらないのに説明がつかないんですよ。それが面白いですね。
——制作に多くの時間をかけたとおっしゃいましたが、SADFRANKの始動自体は2019年の3月まで遡りますよね(2019年3月4日にTwitterアカウントを開設し、SoundcloudにSADFRANK名義の楽曲がアップされた)。
加藤:はい。
——そしてSADFRANKの始動とNOT WONK年表を照らし合わせると、『Down The Valley』のリリースより3ヵ月も前にSADFRANKという名前がついて、このプロジェクトは一旦産声を上げていた。そこから4年間の心の旅が『gel』にはたくさん入っていると思うんですが、そもそも加藤さんのソロプロジェクトとしてSADFRANKが始まったきっかけは何だったのかを教えてもらえますか。
加藤:2019年の3月といえば『Down The Valley』を録り終えていた時期ですけど、その頃に「これはNOT WONKじゃできないかもな」って感じた曲が1つ出てきてしまったんですよ。で、その曲を歌ってみたいなと思ったところから、じゃあ自分1人で歌ったらどうなるだろうっていうアイデアが生まれたんです。その曲はメロディと同時に日本語のイメージが湧く曲で、作ったというより出てきちゃった感が強烈にあったんですけど。
——日本語詞という部分が、NOT WONKでやる曲じゃないという感覚に繋がった?
加藤:そうなんでしょうね。当然言葉が違えばメロディも変わってくるから、その全部をひっくるめての感覚だとは思うんですけど。で、その曲が出てくる以前から、周りのバンドマンやスタッフから「加藤くんは日本語で歌うことを考えたりしないの?」って言われることは多くて。当時はなんとなく誤魔化してたんですけど、でも実際に日本語の曲が出てきちゃったもんだから、これはいよいよ歌わなきゃいけないのかもしれないなぁと思いながら2019年を過ごしてたんですよ。でもNOT WONKはavexと契約してガンガンやっていこうと思っていた時期だから、その曲は弾き語りで歌うくらいに留めていたんですよ。なのでSADFRANKという名前がついた頃は、NOT WONKとは違う曲を1人で歌う場所っていうくらいの意味あいだった気がします。
NOT WONKとの違い

——ただ、日本語で歌おうと思う以前に日本語詞の曲に自分が呼ばれたわけですよね。そのことについて、2019年当時の自分のマインドとリンクするものは思い当たります?
加藤:大きいのは2019年の末に「your name」(地元・苫小牧のELLCUBEで開催されたNOT WONKの主催イベント。加藤の直筆・手刷りのインビテーションが届き、個々の名前を呼び合い1人ひとりが繋がる空間を志した)をやったことで。あの時って、自分がNOT WONKとしてステージに上がる時間よりも、それ以外の時間のほうが人に何かを伝えられた感があったんですよ。だとすれば、この気持ちとこの場所を音楽として表現したいという気持ちが強まっていって。ステートメントを書いたり場所として感じてもらったりするより先に、最初から直接的に歌ったほうがいいのかもしれないなって思うところもあったんですよね。それもあって、普段使っている日本語でより直接的な歌にするっていうアイデアは自分の中で大きくなっていきました。
——イベントの「your name」を開催するのに先立って、「your name」という楽曲を発表していたじゃないですか。イベントの屋号でもあり、社会的に押し込められていく個人の尊厳を「名前」というミニマムな部分から掲げていくための歌だったわけですけど、そういう強い気持ちの楽曲の中に〈あなたの名前〉という日本語詞はすでに登場してましたよね。
加藤:「your name」というイベントは超最高でしたけど、ただ、あんなに大変で回りくどいことをしなくても1曲だけで伝わり切っちゃう可能性があるのかもって思っていた節はあります(笑)。自分が言いたくてしょうがなかったこと、自分が本当に表現したいことって何なんだろうっていうのは、イベントの「your name」以前と以降ですごく考えてたんでしょうね。「your name」という場所や時間の過ごし方によって「あなたの存在」というものを伝えようとしていたけど、それって実は回りくどい方法だったんじゃないかなって思い返すことがあったし。じゃあなぜ直接的な伝え方じゃなく場所や時間で伝えようとしていたのかと考えると、単に俺の照れだったんだろうなって思ったんですよね。で、そういう照れみたいな部分とか、今まで歌にしてこなかった感情とか——そこから紐解いて歌にしてみたいなっていう気持ちが膨らんでいきましたね。
——今までにない歌を歌う、つまり自分の照れとか弱さとか、目を向けようとしなかった感情を歌える場所としてSADFRANKを動かしていこうと考えた。
加藤:そういう感じかもしれないです。時系列で言うと——デモの整理をしていて判明したんですけど、今回の1曲目に入っている「肌色」のデモは2020年の5月に作ってたんですよ。『dimen』の「200530」を作っていたのと同じ時期で、「肌色」みたいにミニマムな楽曲と「200530」を並行して作っていたのが自分でもびっくりしたんですけど(笑)。
で、自分でも謎だと思うくらい、「肌色」ではメロディと同時に〈明日が来るかどうか不安になるたびに/辛くなって笑う顔さえも君は綺麗だね〉という歌い出しが出てきたんです。メロディと歌詞が同時に生まれるなんて「肌色」が初めてで、それはNOT WONKの時にはあり得ないことだったんですよ。だからこそ「肌色」が自分の中でキーになったし、「肌色」を作れたことによって、こういう言葉を歌うのを自分に許せるんだって思えるようになりましたね。
——〈明日が来るかどうか不安になるたびに/辛くなって笑う顔さえも君は綺麗だね〉というような、不安や弱さを感じさせる歌が今作には多いわけですけど、そういう歌を綴るようになったことで、自分から出てくる音楽も変化していったんですか。
加藤:「肌色」を作っていた段階では音楽的にどうするかを全然考えてなくて、ひとまずメロディと歌の方向性が掴めてきたくらいでしたね。ただ、ちょうどその頃に「リーバイス(Levi’s)」のCM音楽の話をいただいて。NOT WONKでやってもいいと言われてたんですけど、いい機会だからSADFRANKでやってみたいと答えたんです。もっと言えば、他の人と一緒に演奏してみたかったんですよね。石若駿、本村拓磨、香田悠真と一緒に演奏してみて、そのコアメンバーで作品を作りたいと思うようになっていって。で、くるりの岸田さんにアレンジをお願いした曲(「I Warned You」)を最初に録音してみたんです。
そこから一旦NOT WONKで『dimen』の制作に移ったんですけど、『dimen』を作ったことによって、なおさら次は日本語で歌わなくちゃいけない気がしてきて、SADFRANKに本腰を入れ始めて。それで『dimen』が出た後に1年かけて座組みを考えつつ曲を作って、『gel』の制作に入っていきました。
「自分らしさとして勝手に語られていたものから遠ざかっていくのが第一目標」

——『dimen』の取材の時に話してくれたことは今も覚えてますが、「your name」以降、加藤さんは人と対話することで他者とどう混ざって、人と人のわかり合えない部分をどう理解していくのかということにより一層興味がいってたと思うんですね。実際に『dimen』で従来のNOT WONKからはみ出すような音楽を作ったことも、人が何を感じて解釈するのか、そこからどんな対話が生まれるのかの試金石だったように思うし。「リーバイス」のCM音楽を「NOT WONK以外のメンバーとやってみたかった」とおっしゃったことも、ある意味それと通ずるところがあるんじゃないかと思ったんですけど、当時の自分の欲求はどんなところにあったんですか。
加藤:2020年のアタマからコロナ禍に入った時、今までよりもさらに苫小牧にいなくちゃいけなくなって。そうするとやっぱり退屈なんですよ(笑)。毎日面白いことが起こるわけじゃないし、毎日人に会うわけでもない。その中で、自分は苫小牧にないものを求めて毎週東京に行って人と会っていたんだなっていうことを逆説的に理解したんです。そもそも東京なんかダメダメだから田舎でスローライフを送りたいっていうタイプでもないし、やっぱり僕は人が好きで、いろんな人といろんなことをやってみたい気持ちがもともと強いんですよね。で、閉じこもる生活を経たことで、自分の根本的な部分——もっといろんな人と対話して、いろんなことをやってみたい欲求がさらに強烈になった気がするんですよね。
16歳の時からバンドをやって、苫小牧に住みながらも東京に出て、レーベルがついてくれる中で音楽を作ってきた。そのチーム自体はずっと一緒だったし、avexに入った時も同じ制作チームだったし。そうしていろんなことが固定化されていく上での風通しの悪さが……恐らくは嫌だったんだろうなってことにも気づいて。それこそ「your name」をやった時に、自分で決めて動きさえすれば何かがチェンジしていく感覚を覚えられるんだなと実感しましたし。だから『dimen』のタイミングでも全然会ったことのないillicit tsuboiさんにエンジニアをお願いしてみたし、ゲストミュージシャンも呼んだし、自分主導だったアートワークも誰かの作品に委ねてみたし。「your name」以降、他者とどう交わるのかにどんどん興味が移っていったし、SADFRANKはより一層自由に人と交わるためのチャンネルっていう意味合いも持っていったと思います。
——それは、単純に人と出会って混ざり合うことへの興味だったのか。あるいは、バンドマンではなく音楽家としての自分に対する興味があったがゆえに今までの自分を一度脱ぎたかったのか。それこそ、今までにない歌が出てきたっていうことも含め、今作からは従来の自分の外へ行こうとする感覚が聴こえてくるから、こう訊くんですけど。
加藤:全部ひっくるめて音楽に対する探求だとは思うんですけど、自分の気持ちとしては……NOT WONK、あるいは俺個人にも、たくさんのタグがつき過ぎちゃってる気がしてたんですよ。苫小牧にいて、元・銀杏BOYZのアビちゃんのレーベルで、みたいな付箋がペタペタ貼られていってるだけで、それがNOT WONKや加藤修平だと見られている感じがあった。でもそれは俺自身の話じゃないんだよなって思っちゃって。
——それこそ「your name」で伝えようとした「あなたはあなたで、俺は俺だ」ということが自分に跳ね返ってきたような感覚?
加藤:“your name”と謳った俺自身はどうなの? っていう感じですよね。これは細かい話ですけど、ジャーンとギターを弾いた時に「やっぱり北の音だね」とか言われたりするわけですよ(笑)。そういうのはいい加減にしてほしいと思ってたし、北の音がどうとかじゃなくて俺は俺の音楽をやってきたんです。で、自分らの表層についたタグに対する評価で飯を食ってるんだとしたら、それは絶対に嫌だと思ったんですよね。
音楽の手練達に対して僕個人が音楽家として向き合えるのかどうかを試したかったし、そこから逃げたくなかった。自分達の音楽に対して「パンク」や「ロック」っていうタグをつけて、アマチュアリズムと紙一重なジャンルに逃げる人もたくさんいると思うんです。だけど僕は、自分のやってきたことに言い訳をしたくなかった。だから今回一緒にやった素晴らしいミュージシャン達と1対1で向き合いたかったし、その人達に「加藤は面白い」と思ってもらえたら、苫小牧のパンクバンドとか、どこのレーベルに所属してるとか、そういうタグを1つひとつ外していける気がしたんですよね。タグを外してみて、そこで見える俺の姿はどんな感じなんだろうっていう興味があったというか……なのでさっきの質問に答えるのであれば、音楽家として新しいところへ行くことと、いろんな人と関わってみることは僕の中で同じ意味合いですね。
——そこで「肌色」について伺うんですが、人間誰しもが外的なタグによって自分の輪郭を作ってしまうところがあると思うんです。どこに所属しているとか、すでに名前のついている思想とか、性別とか、経歴とか、生まれ育ちとか。で、SADFRANKのスタート地点になった「肌色」で歌っていることを見ると、そういうアウトラインを剥がすことで本当の自分が見つかるのかどうかを実験している向きが強いと思うんですよ。自分という人間の輪郭を取っ払うことで本質的な「自分」の概念を見つけようとしたり。他者との間にある線を曖昧にして混ぜてしまうことで、最後の最後に残る自分らしさを感じようとしたり。こう言われてみて、当初の「タグを外す」という目標はどういうところに向かっていったと思います?
加藤:今おっしゃったことが今作の99.9%を占めていると言っても過言じゃないです(笑)。本当にそうで、苫小牧がどうだとか、ギターの音がデカくていいとか、自分らしさとして勝手に語られていたものから遠ざかっていくのが第一目標だったんです。なので、曲を作っている最初の頃はギターを弾くのもやめようと思っていたんですよ。ギターの音がいいよね、と人に言われることが多いなら、ギターを置いても僕は僕なのか。そういう意味での実験がありました。とにかく、いろんなタグを外してもなお残る自分らしさはあるのかどうか、それを見てみたい気持ちが強かったですね。ガワの部分を剥がしてみて初めて、僕を僕たらしめているものが見つかると思ったんですよ。
例えば事故に遭って指がなくなったり、歳をとって同じ声が出なくなったりしたら僕は僕じゃなくなるのかって考えたら、そうではないじゃないですか。だとすれば、僕が僕である根拠とは何なんだろうっていうのが大きな疑問で、その模索自体がこの音楽になっていった気がするんですよね。本質的な自分とは何なのかを考えれば考えるほど、自分を象っているあらゆる線を取っ払うことから始めないといけなかった。
——ギターじゃなく弦と鍵盤が前に出ている楽曲が多い理由がわかった気がします。
加藤:ピアノは全然弾けなかったんですけど、それこそゼロからスタートしようと思ってめちゃくちゃ練習しました(笑)。それでちょっと上達したのが嬉しくて、インスタの親しい友人に向けてピアノを弾いている動画をシェアしたことがあったんですね。歌も乗せず、何の曲かもわからない映像だったんですけど。そしたらWisely Brothersの晴子ちゃんから「すごく加藤くんっぽいね、加藤くんの歌みたいだね」というリプライがきて(笑)。
——あー。自分っぽいと言われるものから離れたかったのに、どうしたって滲んじゃうものがあった。
加藤:そうなんですよ!(笑)。そのコメント自体は嬉しかったけど、反面、えーっていう気持ちもあって。ピアノにまで「加藤くんの歌っぽいね」と言われちゃったわけだから。まあ……今思えば、その頃から「俺はどこまでいっても俺なのかもな」っていうことを徐々に受け入れ始めた気がするんですけどね。固定観念から離れたいと思えば思うほど、やっぱり自分っぽさがにじんじゃうものなんだっていう腹の括り方が生まれていったというか。じゃあどこまでも行き切っちゃうほうがいいよなって思えるようになっていった気がします。
——一旦使わないと決めたギターも、「Quai」の後半で飛び出しますよね。しかも叫ぶようにエモーショナルな鳴りで。
加藤:そうなんですよね。ギター弾かないと決めたのに、結局ギターを持ってしまった。結局は自分なんだなっていう気持ちが必然的に曲に入ってきたというか、全部引き連れてやろうと思えたんでしょうね。
大事なのは人と対話し続けること

——一番最初に「自分の歌心に向き合っている」と申し上げましたが、その核心を話していただいた気がします。歌以外の音もやっぱり歌っちゃってるんでしょうし、NOT WONKの時には「音楽とリリックは別で考えている」とおっしゃっていたのが、今回は歌と音楽が呼び合っているところが強いんじゃないかと思うんです。
加藤:「肌色」や「Quai」を作っている時、メロディと同時に自然と歌詞がついちゃったのはそういうことなんでしょうね。「Quai」で言うと、冒頭の<恋やテロ>が自然と出てきちゃって。自分でも「〈恋やテロ〉って何だよ」と思ったんですけど、歌い出しはそれ以外にないと思ったんですよね。
——〈恋やテロ〉というラインには、人間のミニマムな営みと、人間の一番暴力的な側面の両極が並列されていて。これもまた、自分を自分たらしめるものの境界を探っていく中で出てきた言葉なんですか。
加藤:境界線っていうワードで言うと……自分とは? っていう思考を深めれば深めるほど、自分の中の気持ちと人の気持ちの間には境目すらないんじゃないかっていう気がしてきたんですよ。
——というと?
加藤:例えば最高にハッピーな気持ちで起きた日だとしても、換気扇の下でタバコを吸っている時に「理由はわからないけど死にたいな」って思っちゃうことがあるじゃないですか。結局は本質的な「自分」の輪郭なんてなくて、名前のつけられない気持ちがグルグル回っているだけなんじゃないかって思ったんですよ。どんなに探っても自分の形なんて結論づけられなかったし、喜怒哀楽っていう感情の名前すらつけられないものなんだな、名前をつける必要すらないんだなと思ったんです。で、特別でもなんでもない俺がそう感じるのなら、周りの人もそうなんじゃないかと考えるようになって。自分も人も、名前のない感情をずっと巡っている。だとしたら、人と自分の境界線なんてそもそもないのかもしれないんですよね。俺が家で彼女と過ごしている時に、テロのニュースを見逃すこともある。トルコでひどい地震が起きていても、俺がその時に幸せであれば影響は受けないという現実もある。逆に、俺が組んだイベントの対バンがどんなに盛り上がっていても、俺がその時に電車の事故を見て凹んでたら「こんな時に盛り上がってんじゃねえ」って思っちゃうこともあるんです。
そういうふうに、なんて言ったらいいのかわからない曖昧な感情の中で俺は生きていて……自分っていう枠組みを外して本質的な自分を探そうとすればするほど、何も折り合いがつかないんだって気づくことばっかりだったんですよね。でも折り合いがつかないことは悲しいことじゃなくて、その曖昧な感情の織りとか色彩が、外からはきれいに見えるのかもしれないなって思うようになって。
例えば俺が悲しい気持ちになっていることと、悲しい気持ちの俺がそこにいるっていうことは、ちょっと別の話なのかもしれないなっていう感覚。それが「Quai」を書いている時の気持ちでしたね。折り合いがつかないままの自分が誰かにとって美しく見えればそれでいいのかもしれないし、元も子もない話ですけど、結局自分の目では自分のことは見えないんだなっていう感覚になっていったんですよね。
——凡庸な言い方で申し訳ないですけど、やっぱり自分は自分だけで成立しているわけではないし、外の世界に影響されない絶対的な形を持っているわけではないということですよね。
加藤:結局、見てもらわないと自分のことはわからないんですよね。逆もしかりで、僕は僕のことを見られないけど、人のことは見られる。鏡のような関係、パッチワークのような関係の上で「自分」という概念は成り立ってるんだなって。そんなことを考えて「Quai」を書きました。
——本質的な自分を見つけ出そうとしてきた結果、自分とは何かっていう思考自体から解き放たれたとも言えますか。
加藤:そうかもしれないですね。自分にも人にも、なんならすべてのことに折り合いをつける必要がないし、折り合いがつくはずがないんです。だってそうじゃないですか。家族や友達が亡くなった後に「あ、今悲しくなくなったわ!」みたいなタイミングなんて自分じゃわからないし、どんなに時間が経っても、亡くなった人の持ち物を見たら悲しみが蘇ったりするでしょうし。で、悲しくて酒飲んでたら葬式で久しぶりに親戚に会って嬉しい気持ちになることがあるかもしれないですし。結局、1つの形で括れるものなんてないですよね。そういうことばっかりなのに、いちいち整理して答えを出そうとするから余計ややこしくなるんじゃねえかって気もするし。
——そうですよね。人と人が受け入れ合えず争いを繰り返している今で言っても、いろんなものを1つの型に押し込めようとするから歪みが生まれ続けてるんじゃないかと思うんです。だからこそ、自分も他者も1つの形に括れるものじゃないと考えることから寛容さが生まれていくはずで。
加藤:大事なのは人と対話し続けることで、最初から綺麗にハマる形なんてあるはずがないんですよね。人と人は鏡の関係なんだと思ったと話しましたけど、関わる人の数だけ鏡があって、どんどん自分は1つの側面で語れなくなっていくものなんですよね。
母親の息子である加藤修平の時もあれば、子供に勉強を教えている修平くんの時もあれば、彼女と一緒にいる修ちゃんの時もある。他の人だってそうで、鏡になる人の数だけいろんな側面を持ってる。それを1つの正解に収めることなんて無理だし、折り合いをつける必要すらないんですよね。で、僕はどこにいても本当の僕でいられたらいいなと思ってるし、それを追い求めて音楽をやっている気がするんですよ。
だからこそ、タグだけで語られたり、ミュージシャンとしての側面と個人としての側面をごっちゃにして定義づけられることが気持ち悪い。どの側面の自分も自分であって、何にも縛られない自分であれたらいいなと思ってるだけなんです。じゃあそういう自分でいるためにどうするのかって考えたら、音楽を作って歌う以外のこともちゃんと紐解いて、それを歌にしていくプロセスが必要だったんです。
だから今回はふがいないところも全部出さなくちゃいけなかったし、自分の弱さも歌に込めるっていうタスクがあったんですよね。じゃないと自分という人間の全部を引き連れていけないと思ったし、そういう道筋を丁寧に収めたアルバムなんじゃないかなって思います。
——元も子もない言い方ですけど、「自分とは何だ?」っていう思考自体が自分自身を縛りつけていく気がするし、自分らしくいなくちゃいけないという刷り込み自体に苦しめられている人もいると思うんです。で、加藤さんはそこに自覚的だった気がするんですよ。結果として、人はハナからオリジナルだっていうことを証明している自由な楽曲ばかりになったんじゃないかと。自分らしさに縛られなければ人は寛容になって混ざり合っていけるんじゃないか、そうすればいまだに増え続ける社会の歪みを越えていけるんじゃないかっていうヒントまみれの話でした。
加藤:「折り合いをつける」っていう言い方を何度かしましたけど、いろんな物事に折り合いをつけて納得していくのは俺自身じゃないですか。でも俺が折り目をつけて納得したとして、折り目の分のシワはどこかに寄っているかもしれない。だからきっと何事においても、折り合いをつけることと物事を解決することは違う話なんですよね。社会に目をやってもいろんなところで問題が山積みですけど、折り合いをつけたところでその問題が解決するわけじゃない。やっぱり1つひとつの本質を捉えないと本質的な解決には繋がらないんですよね。そういう意味で、今回のSADFRANKは、自分の中のネガティヴな感情や不甲斐なさに特段フォーカスすることで、まずは自分の本質から逃げないようにしようと思ったんですよね。
例えばデートの日の朝にテレビでテロのニュースが流れていて、俺はそれをシカトして眉毛剃ってたとか……そういう自分のカッコ悪さとか、なんて言ったらいいのかわからない悲しみとか、そういう気持ちを無視しないことが、自分を取り巻く世界に対峙する最初の一歩だと思ったんです。挙げ出したらキリがないほどの悲しみや怒りのフォルムをちゃんと捉えることから始めないと、その悲しみや怒りの対象に立ち向かうのは難しいんですよ。そうして感情のフォルムに向き合って初めて、自分が何に苦しんでいるのか、何が人を悲しい気持ちにさせているのか、この社会に蔓延している気持ち悪さの正体は何なのかということがわかってくるんじゃないかなって気がします。
Photography Leo. Y
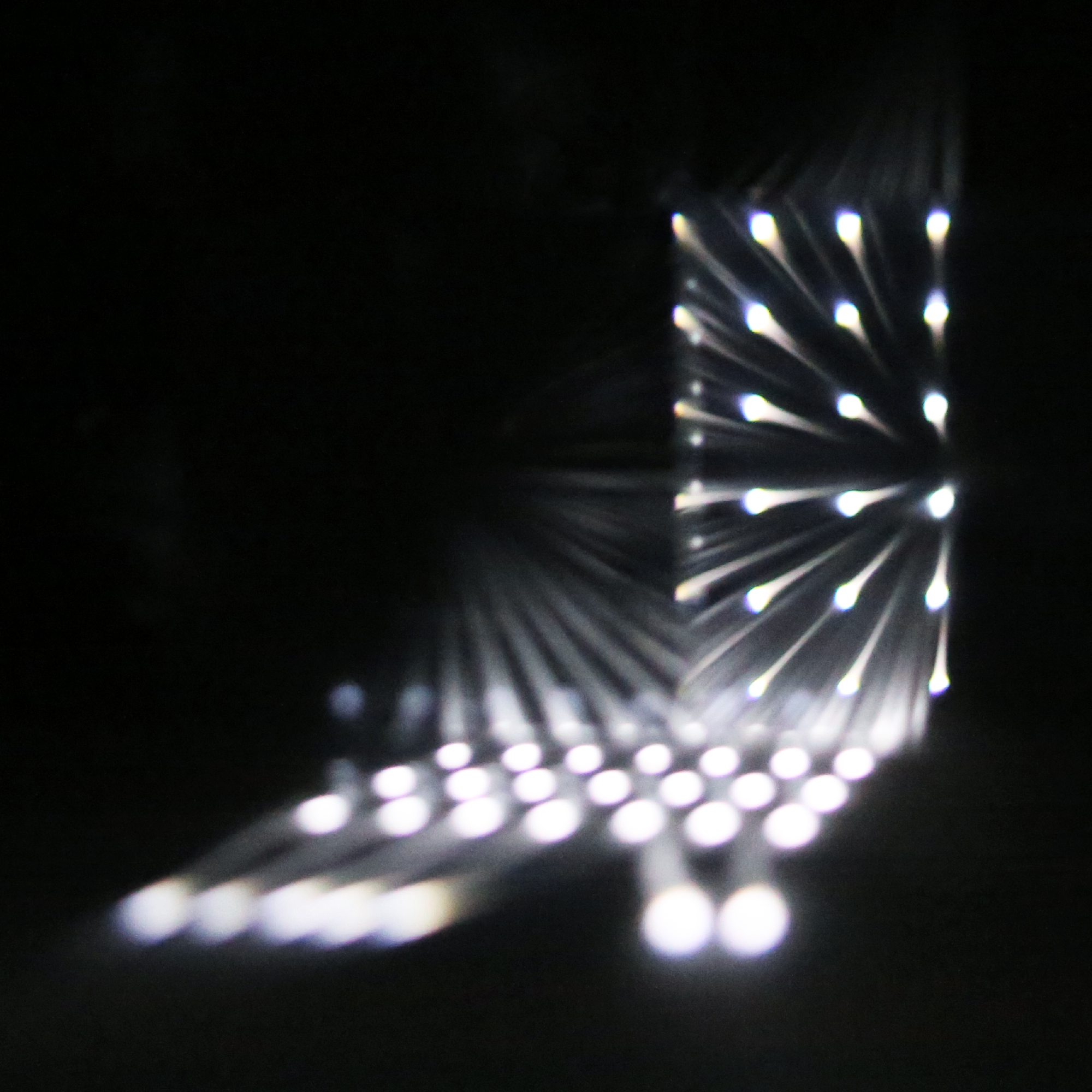
■SADFRANK 1stアルバム『gel』
リリース日:2023年3月1日
All Music & Lyrics : 加藤修平
Total Produce:加藤修平
1. 肌色
2. 最後
3. I Warned You
4. per se
5. 瓊 (nice things floating)
6. offshore
7. 抱き合う遊び
8. the battler
9. Quai
https://friendship.lnk.to/gel
