
2019年11月、前作アルバム『けものたちの名前』を発表した際、ROTH BART BARON(ロットバルトバロン)の三船雅也は、「2020年には、大きく世界を変動させることが起こるはずだ」と言っていた。それが具体的にどんなものになるのかについては言及しなかったが、彼の推測どおり、こうして今世界は変動の只中にいる。
バンド史上最大規模となるはずだった東京・めぐろパーシモン大ホールでのファイナル公演を含めて、前作のリリース・ツアーを半ばで途絶せざるをえなくなったバンドは、その後もオリジナル・メンバーの中原鉄也の脱退を経験するなど、このコロナ禍の進行とともに、内外においてさまざまな辛苦を引き受けることとなった。
しかしながら、三船一人体制となった新生「バンド」は、それらの困難を突き放すかのごとく、新たな創作へとのめり込んでいくことになった。前作からわずか1年足らずで、新作『極彩色の祝祭』をリリース。隔離生活の中で始められた作業は、むしろその短くないキャリアにおける最も大きな果実となって現れたようだ。合奏するということの歓びがと狂おしさが、このように強靭な作品として結実するとは、この数ヵ月間の災禍の中にあって、いったい誰が予想し得ただろうか。
物理的な祝祭空間が封じられている中、あなたとわたしの間にある空気(ディスタンス)を強く振動させることによって、今再び祝祭を寿ぐ。これまでもバンドが金看板としてきた圧倒的スケール感のオルタナティブなフォーク・ロックを研ぎ澄ませ、信頼のサポートメンバー達がそこへさまざまな極彩(演奏)を織り込むことで、ROTH BART BARONの音楽は新たなフェーズに到達した。
人が集まるということでしか作り得ないものを作る

「こういう状況になると、『音楽は儚い存在だ』みたいな見方も出てくると思うんですけど、むしろ今まで実体的なものだと思われていた都市のシステムとかのほうが、その脆さを露呈してしまったと思うんです。その点、音楽は物理的な実体がないぶん本質的なレベルでは強いと思っていて。もちろん、経済的な苦境に立たされているのは明らかで、正当な補償はなされるべきというのが前提ですが。
確かに一人の生活者としてはしんどいことも多かったし、メンバーの脱退もあったし、世界が大火事になっている中で自分の家も火事になってしまった感覚でした。でも、大きなカオスの中でさらに新たな困難が起こると、妙に実感が湧いてこない部分もあって。ライブもできない、新しい体制も模索しなければならないっていうお尻に火がついている状況だったから、落ち込む暇もなかった。自分達よりはるかに大変な思いをしている人達が世界中にいるし、近所の商店街をみていても、通常営業はできないけど工夫して食材を売ったりとか、たくましく立ち向かっている人達がいる。そんな中で、自分も前に進むしかないんだとポジティブな気持ちになっていったんです」。
そういった「前向きながむしゃらさ」のようなものは、実際にアルバムの内容からも強く匂い立つように感じる。
「正直、曲を作っているときは『音楽的なふくよかさとか小さな差異を楽しむ』みたいな気持ちすら起きてこなくて。自我の悩みとか苦悩する創作者とか、そういう伝統的な芸術家像がいかにも牧歌的に見えてしまうような惨事が起きてしまったわけで、今となってはさまざまな要素を取り繕ったような温度の低い音楽を作ることはできないなと思ったんです。それではもう人の心は動かせない。だから、リアルタイムで生まれてくるものをロック・バンドとしていかに熱量を持ったまま世界へ提示できるか、その純度を高めるにはどうすべきかを一番に考えていました。
一方で、音響面のアプローチについてはより綿密に詰めていきたいという気持ちもありました。サポート・ギターの岡田(拓郎)ともよく話していたんですけど、ブレイク・ミルズの新作『Mutable Set』からはすごく刺激をもらいましたね。今の状況で聴くとややパーソナル要素過剰にも思うけれど、フィジカルな快楽が濃く漂っていながら、同時に音の空間配置がすごく巧み。まだまだ未開拓のサウンド・アプローチがあるんだということを気付かせてくれました。
録音に関しては、暫時的な方法としてリモート・セッションでの制作も選択肢として考えうるけど、それだと『やってみました』以上の音楽が出てこないような気がしていたんです。幸いなことにこの国では6月以降ある程度人が集まることが可能な状況だったし、レコーディングもできるだけ通常運転でやって、人が集まるということでしか作り得ないものを作ろうと思いました。緊急事態宣言が明けてすぐ、自分も含めて長く人と一緒に音を出していなかった演奏者達が一同に集まって音を鳴らしたとき、みんな初心に帰ったように『やっぱり楽しいね』って言っていたのが印象的ですね。そこには素直な歓びがあったし、自分の予想を越えた強度と新しい景色を持った音が生まれたように思います。プレイバックしていても、本当に素晴らしいものが録れたと確信しましたね。まさに『祝祭的』だったと思います」。
無形性こそが「祝祭」の本質

アルバム・タイトルにも掲げられたように、その「祝祭」こそ、本作の重要なコンセプトだという。しかしそこには、一般的な「祝祭」の語義理解をはみ出すような意味性も据えられているようだ。
「祝祭って、中心点が不在だけれど多くの人が何かしらの歓びを共有できている状態だと思うんです。例えば音楽フェスでもステージを見ずに踊っている人がいるかと思えば、体を揺らしてご飯を食べている人がいたりとか、てんでバラバラなようでいて、あらゆるところに楽しいという感情がある。アーティストの演奏が歓びを『配っている』というより、当人の中でそれぞれ湧き上がっている感じというか。スポーツ観戦でも、超人的プレイをするアスリートに注目が集まっていることは確かだけど、観客はそれぞれ思い思いの感慨を抱きながら熱狂していて、『熱狂それ自体の中心』みたいなものはないと思っていて。
一方でコロナ禍によって、今まで資本主義を回転させていたさまざまな経済活動とか、新製品や新サービスによって焚きつけられるインセンティブが一旦停止してしまうと、妙なすがすがしさとか開放感を感じたりするじゃないですか。そういうとき、根源的な祝祭の可能性が蘇ってくるような気がしたんです。実をいうとこの祝祭というタームは、前作リリース直後、コロナ以前から考えて部屋に毛筆で書いて貼っていたものだったんですけど、こういう状況になってみてより鮮やかにその意味が浮き上がってきたように感じて。
音楽イベントをはじめ、人が物理的空間に集まる旧来の形態での祝祭は一時的に封じられているけど、音楽作品のみを通して祝祭を生むことも可能なんじゃないかなと思ったんです。最初に言ったとおり、そもそも音楽自体は物理的に手に取れるものでなくてあくまで空気の振動なわけですけど、むしろその無形性のような性質のおかげで歴史的にもいろいろな祝祭において音楽が重用されてきたと思うし。そう考えると、祝祭にとって『たくさんの人が集まっている』ということ自体は副次的な要件でしかなくて、そういう無形性こそが本質的な要素なんじゃないかなと思ったりしますね。例えば、タイタニック号がどんどん沈んで聴衆も消えていく中最後まで演奏を続けた楽団のエピソードとかにも、祈りであるとともにどこかしら祝祭性を感じてしまうんです」。
根源的な次元で「大きい」音楽を作りたい

並行して、前作『けものたちの名前』から続く、「人間以外の視点」というテーマのさらなる掘り下げがなされているのも本作の特徴だろう。
「コロナ禍以前から作っていた曲もありますけど、レコーディングの前に人里離れた山小屋へこもって作業したことも大きかったように思います。イノシシとか鹿が普通にその辺りにいるような所だったんですけど、森は何もなかったようにいつもと変わらず青々としているし、結局のところ今回の騒動はあくまで『人間にとって』の惨事であるにすぎないということに深いレベルで気付かされて。人間目線でばかりものごとを捉え過ぎることによって、不調に陥ってしまう。そこをいかに越えていけるかというのは歌詞を作るにあたっても考えていましたね。言葉自体はもちろん人間のものだけれど、苦悩する人間の目線からその言葉を開放するというか……。例えば『極彩|IGL(S)』の『君の物語を絶やすな』というフレーズも森の中に身を置いたからこそ出てきた言葉だろうと思います」。
ここで歌われる「極彩色」は、「祝祭」と並んで、おのずと「多様性」という概念とも接続してくるふうだ。そしてそれは、多様性の裏面的事象として位置づけられてしまいがちな「分断」という時代診断をも溶かそうと試みる。
「分断という時代把握自体が、ある種恣意的に設定されているものじゃないかと思うんですよ。例えば、グレタ・トゥーンベリの地球温暖化に対しての発言というのは、なにか特定の集団を益したり傷つけたりするものではなくて、イデオロギー関係なくそもそも人類総体にとっての問題提起であるわけですよね。それが発信元が彼女だったからという『見方』によって、賛成/反対の議論が起きて、『何を言ったか』でなく『誰が言ったか』が焦点化されていく。そういうことを繰り返しているうちに、みんなが乗っている船自体が沈んでいっているという最も重要なことが忘却されてしまう。BLMもそうですよね。あの切迫した怒りを生んだ現状や歴史とかが共有されずに、誰と誰が敵同士なのかという話に収斂してしまう。それは想像力の欠如によるのかもしれないし、あるいは特定のルール・メーカーによって設定されたルールに『従いすぎている』ということなのかもしれない。だから、そういうグラウンド・ルールに対しては、『サッカーでハンドをしまくる』みたいな視点の大転換があっていいのかもしれないなと思っています。実際僕もバンドとして生き抜くために、業界的には常識はずれのことをたくさんしてきましたし(笑)。
まあ……何がいいたいかというと、シンプルに『分断は流行らない』っていうか、『分断っていう言説を流行らせている場合じゃないよね』ということですかね。もっと巨視的な構えから物事を考え始めたい。こういうのは、僕自身の音楽観にも通じていることなのかもしれない。いろんな文脈を端正に配置した箱庭的な美しさのあるものより、もっと根源的な次元で『大きい』音楽を作りたいと思ってやってきたので」。

最後に、早くも今月からスタートする全国ツアーへの意気込みも聞いた。
「まずはいつも通りいい音楽をならして、それを観に来てくれるお客さんに最良の状態で届けることを目指しています。まだコロナは収束してない状況だしこの先も危険は続くと思うんですけど、こういうときだからこそ、それへの向き合い方を学んでおきたいし、状況に合わせた『祝祭の場』をどう作ることができるのかについて経験則を獲得していかないと、未来はどんどん厳しいものになっていくと思うんです。
僕らも含めて、ミュージシャンの全員がその経験則においては一年生なわけだけど、ずっと一年生で足踏みしているわけにもいかない。たとえ運良く収束という状況になったとしても、一度変わった価値観が元通りになることは難しいと思うし、配信と生ライブという選択肢が並列する状態は続いていくと思いますしね。いろいろなことに気を配りながらも、この鍛錬を楽しめるように演奏していきたいなと思っています」。
ROTH BART BARON
三船雅也(vo/g)を中心に、東京を拠点とし活動しているフォーク・ロック・バンド。2014 年に1st AL『ロットバルトバロンの氷河期』を発表。2019年11月に4th AL『けものたちの名前』を発表し、<Music Magazine>ROCK部門第3位をはじめ多くの音楽メディアから賞賛を得た。2018年からコミュニティー”PALACE” を立ち上げ、独自のバンドマネージメントを展開。ASIAN KUNG-FU GENERATION 後藤正文主宰 “APPLE VINEGAR MUSIC AWARD 2020"にて大賞を受賞。2020年10月28日にはニューアルバム『極彩色の祝祭』をリリースし、全国ツアーを行っている。
https://www.rothbartbaron.com
Photography Toki
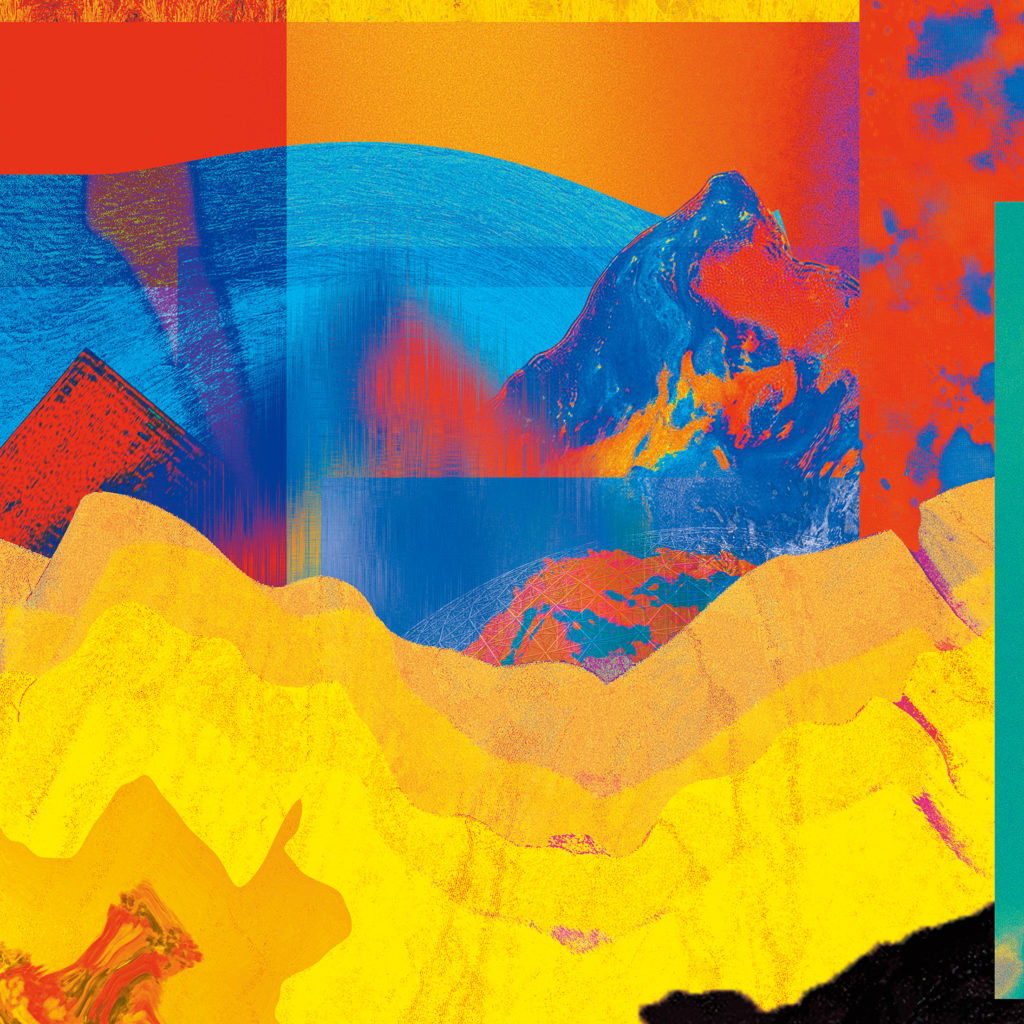
ROTH BART BARON
New Album『極彩色の祝祭』
[CD]¥3,000
[Track]
01. Voice(s) 02. 極彩 | I G L (S) 03. dEsTroY
04. ひかりの螺旋 05. King 06. 000Big Bird000
07.BURN HOUSE 08. ヨVE 09. NEVER FORGET 10. CHEEZY MAN
<LIVE INFORMATION>
■ROTH BART BARON Tour 2020-2021『極彩色の祝祭』
2020年
11月7日 広島・クラブクアトロ
11月14日 静岡・浜松 舘山寺
12月5日 京都・磔磔
12月12日 東京・渋谷 WWW
2021年
1月16日 愛知・名古屋 The Bottom Line
1月21日 福岡・百年蔵
1月22日 福岡・the Voodoo Lounge
1月23日 熊本・早川倉庫
2月6日 石川・金沢 Art Gummi – Guest Act:noid –
2月7日 富山・高岡市生涯学習センター1F リトルウィング
2月13日 大阪・梅田 Shangri-La
2月20日 北海道・札幌 モエレ沼公園 ガラスのピラミッド
2月21日 北海道・札幌 Sound Lab mole
2月23日 宮城・仙台 Rensa
■ROTH BART BARON『けものたちの名前』Tour Final めぐろパーシモン大ホール
2020年12月26日(土)OPEN 17:00 / START 18:30
2020年12月27日(日)OPEN 15:30 / START 17:00
特設 website
https://www.rothbartbaron.com/persimmon
■ROTH BART BARON POP UP STORE & EXHIBITION
日程:2020年11月21〜24日
会場:KATA (LIQUIDROOM 2F)
住所:東京都渋谷区東3-16-6 LIQUIDROOM 2F
時間:13:00〜20:00
※11月21日は14:00オープン/11月24 日は18:00クローズ
http://kata-gallery.net/
