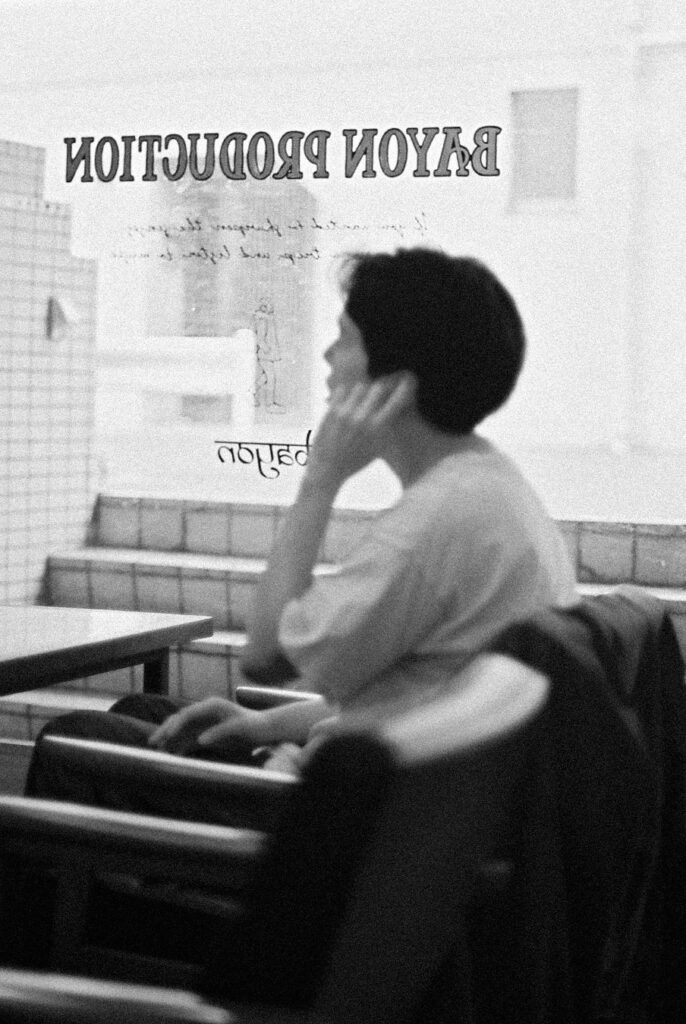あたたかく、素朴で、豊かな奥行きと響きを持つ曲の数々。never young beachの安部勇磨による初のソロアルバム『Fantasia』は、バンドとは大きく異なるパーソナルなサウンドで、聴く人の心に染み入ってくる。ゆっくりと、深く。親交深いデヴェンドラ・バンハートがギターで参加し、最も敬愛する細野晴臣がミックスに加わったこの名盤を、「過度に持ちあげられたらむしろ困る」と笑いながら彼が語った。
“仕事としての音楽”から“日常の延長線上にある音楽”へ
――ソロ作品の構想はいつごろからありましたか?
安部勇磨(以下、安部):2年くらい前ですかね。never young beachの4枚目のアルバム『STORY』を作ったあとぐらいから、どこか息苦しくなってしまったというか。ネバヤンだからこういう音楽をやらなきゃとか、自分はいまこういう音楽が好きだけど、それをバンドメンバーに少しでも押し付けてしまうのは申し訳ないなとか。前はもっと自分の好きな音楽を作るという作業をわがままにできてたんです。メンバーもそんなこと気にするなって言ってくれるんですよね。でも5、6年バンドでやってきて、いろいろな面で少しだけプレッシャーを感じることがあって。それでソロなら気にせず、自分勝手にできるじゃんって漠然と思い始めたんです。
――ということは外側からの圧みたいなものを感じつつ、自分の気持ちに素直でありたいという内面的な変化も起きてきて。
安部:それがすごくありましたね。だからひとりで音源を作り始めたときは「この作品をたくさんの人に聴いて欲しい」みたいな感じはまったくなくて、人に向けて歌うことそのものが押しつけっぽいから、あ、こんなのあるんだぐらいの聴き方をしてもらえたらいいなって。そういう始め方でした。
――結果的に初のソロアルバム『Fantasia』は、バンドサウンドから大きく飛躍した作品になりました。
安部:コロナ禍で時間があって、初めはバンドの曲を作ろうかと思ったんです。でもバンドでいま何を歌えばいいんだろうって。これは世の中に対して感じることでもあって、前向きな歌があまりにも多い気がするんですね。「がんばろう」とか、ポジティブなものばかりになってしまってる気がして。もちろんそれもいいんですけど、自分はそういう状況に疲れてしまったので、ひとりごとみたいな、友だちだけに聴かせるくらいの気持ちでやりたいなと思いました。

――「ひとりごと」とか「友だちだけに聴かせる」とか、今回の作品のイメージはやはりパーソナルなものだったんですね。
安部:内向的というか、バンドほど外に開いてないなと。これをバンドのテンションで「うわー!」とかやるのは全然想像できないなって。いろいろなことに興味が湧いてきたから、やっぱりそんな作品になっていきましたね。あとはこれまでより生活に近い、「暇だったらベース弾いてくれない?」みたいな気軽さで、友だちとただ遊んでる感じでやりたいとも思いました。それはメンバーとともに数年間、ずっと一緒に活動しているからこそ。責任感の違いなのか、バンドだと「そんなの駄目だ」とか「今のテイク変えよう」とか言うのに、友だちとやってると自然と許せるんです(笑)。ベースとドラムがズレてたりしても、それもおもしろいなって。
――仕事になってしまった音楽に対して、もう一度日常の延長線上にある音楽に立ち返ろうとした?
安部:あ、そうですね。リスナーの人たちと一緒で、この曲カッコいいなと思ったら、その曲を何度も聴き直して自分の曲を作ったりとか、そういう気持ちだけでやってました。ただただ楽しかったです。
“力”を込めないこと、“わかりやすさ”に抗うこと
――1曲目を聴いて、聴いた瞬間に心をつかまれました。今回の作品で大きく変化したもののひとつがヴォーカルスタイルです。メロディに声をポンと乗せただけみたいな、力をこめて歌いあげない歌というか。
安部:実はちゃんとレコーディングして、ピッチ修正もした歌があったんですけど、今回の作品では違うなと思ってほとんどのヴォーカルを家で録り直したんです。だから家の電力が足りなくて、ヒスノイズがけっこう入ってる。僕の好きな昔の音楽にもけっこう入ってるし、気にしすぎても駄目だなって。ある方が、最近の音楽はノイズを排除する傾向にあるけど、どんな環境でも無音はあり得ないと言ってたんですよね。確かに普通に過ごしていても、風がそよぐ音や葉っぱがこすれる音は聴こえてくる。だからその方の言葉を聞いて、なるほどなと思ったんです。でも僕は1990年に生まれて、そういったものを排除するのが当たり前の時代を生きてきたので、それを残す作業はすごく怖かったです。いまだに大丈夫かなみたいな変な気分なんですよね。
――でもそのせいか、サウンドは空気を含んだものとして聴こえてきます。歌も、演奏も。
安部:なるべく空気を録りたいみたいな気持ちはありました。だから声を張りあげることで潰れてしまう何かがあるなって。僕はデヴェンドラ・バンハートが好きだし、坂本慎太郎さんのソロ作品も好きだし、もちろん細野晴臣さんもそうですけど、やっぱりどれも空気がある気がするんです。それはバンドだとなかなか難しいというか……音楽をやっていて、声を張りあげて誰もが共有できることを歌うのはポジティブだし、いいことだと思うんですよ。でもそれが行き過ぎると、音楽じゃなくて感情のぶつけ合いみたいになってしまう。感情ってぶつけられると、返したくなるじゃないですか。だからそこは1回フラットにして、距離を置いて話し合いたいみたいな感じだったと思います。そういう距離感を音に出したいなと。最近、養老孟司さんの本をよく読むんですけど、人間は意味のないものをどんどん排除しようとするって養老さんが言うんですね。たとえば雑草は除草剤で処理したりとか。でも意味のないものがどれだけ豊かさをもたらすかということを話していて、もしかして養老さんの言いたいことと違うかもしれないけど、自分も意味がわからなくてもいいやとか、そういうものもとりあえず入れておこうとか、そういう感覚で全体的に作ってました。
――頭で考えず、それが意味があるかどうか判断しないまま、感覚的に作っていくみたいな。
安部:考えたら駄目だと思いましたね。今回デヴェンドラに入れてもらったギターも、同じフレーズを彼がもう一度弾けるのかと考えると、たぶんそういう計算はしてないと思う。日々の蓄積と感覚。自分はそういうことを意図して狙わないとできないので、まだまだですね。
――今回のアルバムを聴いて、どれも力を感じさせない曲だと思いました。世の中を見ると、例えばインフルエンサーと呼ばれる人たちが影響力をあからさまに見せつけるようなシステムができあがっていたりして、誰も力から逃れられない。でも『Fantasia』は力に抗う音楽ですよね。演奏はとてもシンプルだし、音数を徹底的に削ぎ落して。
安部:音数は今後もっと減らしてみたいですし、そういうもののよさがいまになってわかる気がします。最近アンビエントを聴くようになって、環境音楽やモート・ガーソンの『Mother Earth’s Plantasia』を聴いてるんですけど、自分の思いとか、直接的にそれをわからせようとする言葉もないのに、伝わってくるものがあるんですよね。それは人間の想像力だったり、相手を思う気持ちだったりに訴えかけてくるからかなって。いまは何でもそうですけど、わかりやすいところに行くじゃないですか。でも僕が子どものころは、わからないものに行きたい、調べたいみたいな、そういう楽しさがもうちょっとあった気がするんです。いまはわからないと見てもらえないし、ある程度わかりやすくないとヒットしない。自分はやっぱりそうじゃないものに憧れがあるのかなと。
――それは歌詞にも言えることですよね。バンドと比べると言葉数が少なくなって、その分抽象度が高くなった気がします。一方ですごく具体的な歌詞もあったりして。
安部:バンドでは、特にライブを考えると、ある程度みんなが共有できる歌詞がいいと思うんです。でも今回は自分しかわからない言葉でもいいかとか、もっと直接的に言っちゃってもいいかとか思って。「素敵な文化」という曲も、自分は餅をついていたっていう歌詞なのによく歌えるよなと(笑)。バンドで同じことを歌ったら、お客さんは困っちゃうような気もするんです。でもこれならいいよなと思ったし、そういうふうに書けたのが楽しかったから、今後もやっていこうと思いました。
――それは聴く人に委ねる覚悟ができたということですか?
安部:”委ねる”というよりは”放置してみる”というニュアンスの方が近いかもしれないです(笑)。作って、そのまま置いておくので、食べたい人がいたら食べていいですみたいな。興味のない人は全然触らなくていいですよって。これは理想論かもしれないし、現実的には不可能に近いと思いますけど、聴く人が何も意識してないときに、SNSや告知に触れないまま、ふと出会ってほしい。それがベストですよね。予定を組むときもそうですけど、友だちと遊ぶ予定を立てて、当日になってなんか面倒くさいなと思うときがあるじゃないですか。それより「いま暇? 遊ぼうよ」みたいなのがいちばん楽しかったりしますよね。予期せぬ楽しさというか、そういう感覚を音楽でも出せたらなっていう思いはありました。
自然体が引き寄せた、デヴェンドラ・バンハートと細野晴臣とのコラボレーション
――音楽との予期せぬ出会いが、いまはなかなか難しいのかもしれません。その壁をこの作品が突破できたらすばらしいですよね。そういう出会いのなかった人が、たまたまこの作品と出会ったときにどう反応するのか、ちょっと気になるなって。
安部:気になりますけど、あなたはあなたの考えで違うと言ってくれてもいいし、そういう距離感でいようねみたいな感じです(笑)。でもこの作品を作った結果、ひとつ突破できたと思うのは、特に何も決めずに始めたのに、気づいたらデヴェンドラがギターを弾いてくれたり、細野さんがミックスしてくれたりすることになって。デヴェンドラとのコラボレーションは、これまでスタッフさんに動いてもらってもうまく行かなかったんですよね。でも自分で直接やりとりしたらなぜかできたので、自分が楽しいと思っているほうにちゃんと行けば、失敗することもあるだろうけど、なんとかなるのかもしれないなと思いました。これが細野さんのよく言う「行き当たりばったり」というやつかって(笑)。細野さんを始め、自分が尊敬している人たちにはどこか飄々としたイメージがあって、「え? 別に何も考えてないよ」みたいな人たちが多いんです。そのほうがうまくいくということなんでしょうね。僕もこれで少し自信がついたし、そういう部分ではこの作品を作って感動したというか、自分の中でいままでにない発見がありました。
――今後、このソロ作品はバンドにどうフィードバックされていくと思いますか?
安部:いや、難しいですよね。前からバンドでもこういうことをやろうと思ってたんですけど、たぶんやろうとしてたから疲れちゃってたんです。シンセだけの曲を作ったらどうなっちゃうんだろうとか、ライブを考えたらもうちょっと曲に盛り上がりが欲しいよねとか。それぞれの場所によって、いろんなスタイルがあっていいのかもしれないですけどね。
――もしかしたらバンドとは違う場所として、今後はこういう場所も持っておくみたいなことかもしれないですね。
安部:そうですね。今回は違うプレイヤーとやるだけでこんなに音が違うんだということもわかったので、そのときどきの形態で音楽をやっていけたら、一生音楽ができるかもなと思いました。そういう“逃げる”場所があるほうが、きっと長い目で見て音楽は楽しいですよね。

安部勇磨
1990年9月4日東京生まれ。2014年に土着的な日本の歌のDNAをしっかりと残しながら、USインディなど洋楽に影響を受けたサウンドを軸にnever young beachのボーカル&ギターとして活動を開始。全ての詞曲を手掛ける。FUJI ROCK FESTIVALやSUMMER SONICなど日本国内ミュージックフェスティバルに多数出演し、Devendra Banhart、The Growlers、Mild High Club、HYUKOHなど海外アーティストとも共演。日本のみならず上海、北京、成都、深圳、杭州、台北、ソウル、バンコクなどアジア圏内のライブツアーやフェスティバルにも出演し海外での活動も拡げている。冨田ラボ、neco眠るの楽曲へ作詞、歌唱での参加やNTTコミュニケーションズのプロモーション動画でのカバー楽曲参加。2017年頃から敬愛する細野晴臣との対談やラジオ出演などを果たし、音楽活動50周年を記念したイベント「イエローマジックショー3」へ出演し話題に。また細野氏の2019年の著書「とまっていた時計がまたうごきはじめた」の解説を執筆。
Instagram : @_yuma_abe/
Thaian Records : https://thaianrecords.co
Photography Mikako Kozai