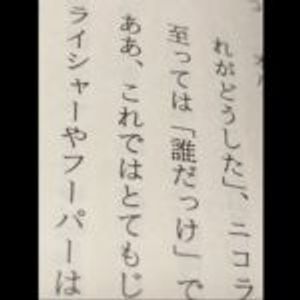地元神奈川・藤沢の同志ともいうべきラップグループ、DINARY DELTA FORCEとともに、現在にタフなブーンバップサウンドを体現する2MC、BLAHRMY。まとまった作品としては実に9年ぶりとなる彼らのアルバム『TWO MEN』がようやく届いた。2人の内なる音を具現化した盟友NAGMATICによるビートの上で行われる硬派な掛け合いは、ヒップホップシーンが様変わりした2021年の今だからこそ、よりタフにリスナーの心へ突き刺さる。
現場主義のその名の通り、ライヴ活動は常に継続しつつも、変化する互いの環境によるすれ違いを経て、ここに再び足並みをそろえたBLAHRMY。未だベールに包まれた部分も多い2人に、馴染みの地元であるMOSS VILLAGEにていろいろと話を聞いた。
藤沢の地だからこそ生まれた!? BLAHRMYとその音楽性
――DINARY DELTA FORCEもしかりですが、DLiP RECRDS周辺の人達はネーミングのセンスが独特ですよね。
MILES WORD(以下、MILES):確かに(笑)
SHEEF THE 3RD(以下、SHEEF):デビューEPの『DUCK’S MOSS VILLAGE』からそうっすね。「MOSS VILLAGE」は「藤沢」のことなんですけど、「DUCK」は「みにくいアヒルの子」のこと。「俺らって、周りと全然違えよな」みたいなところから来てるんですけど、ほとんど地元の奴と話してるノリですよね。なんか話してる時に、「これじゃね?」 みたいなのをそのまま発表しちゃってるっていう(笑)。
――身内で通じる一種のコードというか、そういうジャーゴン、スラングはヒップホップで欠かせない要素ですよね。こじつけですけど、藤沢がそうさせるんですか? 地元で音楽を続ける理由もそこだったり……。
SHEEF:うーん、関係ないんじゃないですかね。藤沢って、いっても東京に近いじゃないですか。電車で1時間ぐらいで行けるし。
――2人から見て藤沢はどんな街ですか?
SHEEF:ちょっとイナタい場所かもしんないですね。地元感が強い気がする。華やかなイメージとかはあんまないし、店で言うなら109とかそういうのよりはドンキみたいな。
MILES:やっぱ村みたいな感じなんですよね。人がいっぱい集まっても知らないヤツがいたらすぐわかっちゃう。それだけに、ここで何かやらかしたら、その時点で「やらかした奴」って見られちゃう。もちろん、それを挽回するチャンスもいっぱいあるんですけど。
――そういった街と、自分達がヒップホップをやろうと思ったことに関わりがあると思います? 自分達の音楽性や、ここで音楽をやり続ける意味にしても。
MILES:関係してるのかもしれないですけど……。でも、なんでここにいるかっていったら、結局は友達が一番多くて、「今何やってんの?」って楽に電話できる奴がいるかいないかなんで。
DINARY DELTA FORCEが介したユニットの始まり
――なるほど。そもそも2人が組むことになったきっかけを改めて教えてもらえますか?
SHEEF:結成したのは確か2008年の10月31日とかかな? ちょうどハロウィンだったんで覚えてるのもあるんですけど。俺らの結成にはDINARY DELTA FORCE(以下、ダイナリ)がカギで。その頃、よくダイナリのライヴにくっついて観に行ってて。その中に俺もMILESもいたみたいな。で、よく「バックDJ頼むわ」とか言われることもあって。「今日はMILES、そん次は俺」みたいな。そんなことをやってたら、お互いソロで活動していたのもあって、ふいに「お前ら組めば?」みたいなことをDUSTY HUSKYに言われて。
MILES:ダイナリは年が2コ上なんですよ。で、SHEEFはダイナリとタメだから、クラブとかで会っても、当時の俺からしたら(SHEEFは)先輩の友達みたいな。入り口はそんな感じでしたね。
――そこから一緒に音楽やるまでは早かった?
SHEEF:そうっすね。次第に2人で遊ぶようになって。DUSTY HUSKYに言われたのもあって「やりますか!」って感じになった。そしたら、遊びながらですけど、すぐ「デモ作ろう!」みたいなノリになって。そっからはずっとMILESのウチで曲作ってましたね。
――やるにあたって2人で突き詰めて話したりしました?
SHEEF:音楽について明確に「こうだよね」とかそういう話はしてないすね。ただ、ビギー(=THE NOTORIOUS B.I.G.)のアルバムとかNASのアルバムがヤバイとか話したりしてて。自分で掘ってきたレコードとかCDを聴かして「これやばくね?」とか。そういう話ばっかりしてました。
BLAHRMY 「FIST (AHRMY GLOVE)」(2014)
個々の歩みを経て、ここにそろった足並み
(DLiP RECORDS)
――その後リリースが始まって、近年はソロや別ユニットの作品、BLARHMYとしてもアナログや配信リリースがありましたけど、2人のアルバムとしては『TWO MEN』は9年ぶりになりますね。これだけ時間がかかった理由とは?
SHEEF:前のEPから7年ぐらい経ってるんですけど。EPが完成したあたりで自分が結婚とか、子どもができたとかあって、自分の中で生活のリズムが変わってきたのもあって。ずっとライヴはし続けてたんすけど、がっちり曲を作ろうっていうことについては、どこかMILESと足並みをそろえるのが難しくなって。
――MILESさんはその間、Olive Oilさんとのコラボはじめ、精力的なペースで作品を発表してましたよね。
U_Know(Olive Oil x Miles Word) 「WAKABA」(2018)
MILES:自分はずっとスイッチが入ってる状態だったんですけど、そこで無理に一緒に作ろうよって感じよりかは、ちょっと1人でやってみようかなみたいな気があったっすね。家庭ができて音楽やめたりする人もいると思うんですけど、SHEEFにはそうなってほしくなくて。で、もし自分が活発にやってたら、(SHEEFも)「俺もやりてぇ!」ってなるかな?っていうのがありましたね。
SHEEF:実際、その思惑通りというか。MILESの動きを見て「やっぱり悔しい、俺もやりてぇ」って気持ちは大きくなってったかもしれないっすね。ただ、最初はバタバタ過ぎてそれどころじゃなかったから、そういうふうに考えられたのもちょっと時間が経ってからだったかもしんない。
――じゃあSHEEFさんにとってはRHYME BOYA(DINARY DELTA FORCEのメンバー)さんらとのコラボはいわばリハビリのような感じというか。
SHEEF:いや、リハビリって意識は特になくて。俺も曲を作りたいってなった時にタイミングがバッチリ合ったのがRHYME BOYAだったってだけですね。まあ、結果的にはリハビリみたいにはなってたんすけど。
RHYME&B × SHEEF THE 3RD feat. JAMBO LAQUER 「La La La」(2016)
――逆に、その間MILESさんは外部の人達と数多く制作を経験して、BLAHRMYやDLiPの仲間の音楽の見え方が変わったようなことはありませんでした?
MILES:やっぱDLiPは村みたいな感じがあったのかなって思うすね。外と関わりがなかったんで。全部自分らで完結させられると思ってたし。俺的には曲を書きたいって思うビートに、ただ書いてるだけだったんですけど、結果的にはいろいろ見えたものはあったかもしれないっす。
――NAGMATICさんの全曲プロデュースしかり、シンプルなタイトル(『TWO MEN』)しかり、今回のアルバムは原点に戻った1作にも思えますが。
SHEEF:原点に戻るって気持ちはなくて、今までの流れのまんまで、セカンド作ろうってなった感じっすね。その時、トラックはNAGMATICのビートでやろうっていう話をずっとしてたから、それがようやくできた感じ。1回離れてまた合流してみたいな、そういう感じではないんですよね。アルバムを作ってなかっただけで、ライヴも続けてたし、みんなで遊んでる中に2人とも常にいたし。
MILES:その間、シングルとかも作ったしね。
BLAHRMY 「10 ROUND」 (2019)
――アルバムとしてはどういう構想で?
MILES:1stアルバムのアップデート版にしたいっていうのはあったっすね。メチャクチャ何か変えようとしたってわけではないですけど、今の時代だからできたものにしたいみたいな感じは3人で話して。
――コロナの自粛期間も挟んで、制作で変わったようなことはありませんでした?
SHEEF:曲の作り方は前と明らかに変わったっすね。制作途中はお互い別々にRECしたのを送り合って、本撮りした時に集まる、みたいに別々で作り上げてく感じっすね。制作中に集まってこうしようみたいな曲とかはあまりないかもしれない。こうしたいと思ってたらMILESも自然とそうしてたし。
――お互いに意思統一みたいなことはない……と。
SHEEF:もう1stの時点でそれは済んでるから改めてする必要がなかったっすね。
MILES:でも、メチャメチャいいのができたと思います。熟成されてるっすね。パッと勢いだけでできた感じじゃないかな。
SHEEF:熟成かぁ……。例えば?
MILES:だからなんつうの、最近できたもんじゃないからさ。けっこう貯めてた曲も多くて。そこに改めてスクラッチとかスキットが入ったらさらにガチっと固まっていい作品になったし。
わき目振らず、自ら欲する音に向かったアルバム
――日本でもトラップが主流となって、1stを出した頃とヒップホップシーンも大きく変わりましたけど、そこに何か思うことはありませんでした?
MILES:特に考えてないですね。今回もそうですけど、単純にこのビートでやろうって気になったビートでやってるだけなんで。
SHEEF:ヒップホップがすごいはやってるならそれはいいことだと思うんで。その中で自分達が好きなものを本気でやっていれば他は特に気にはならないっすね。実際、あっちのヒップホップもトラップだけじゃないし。
――じゃあNAGMATICさんとも方向性について特にすり合わせるようなこともなかったわけですか。
SHEEF:そうっすね。NAGMATICから「この感じ!」みたいなビートが来て、そっからそれぞれ書きたいビート選んで書いて。実際2人で書いてても漏れている曲も結構あって、それはちょっと熟成の樽に入れとこうみたいな 。
MILES:やっぱ熟成してんじゃん(笑)。
――ははは。1990年代のヒップホップレジェンド達を歌詞に盛りこんだ「Recommen’」1つにも、改めてサンプリングオリエンテッドなヒップホップに対する意地やこだわりを見た気がしましたが。
SHEEF:「Recommen’」は今の時代にこういうのあったらおもしろいんじゃないかなっていうノリっすね。別に音楽じゃなくても良くて。例えばうまいメシ屋とか掘ったりするじゃないですか、なんとか系のラーメンはここがうまいとか。俺、結構キャンプ好きなんですけど、テントはここのブランドやばいぞとか、もっとヤバイグッズあるぞとか、なんか自分の好きなものを人に教えてる時って、こういう曲みたいになるんじゃないかなって。
BLAHRMY 「Woowah」(2021)
パーティは終わらないし、ライヴは続く
――ともあれ、BLAHRMYはライヴが何より強みだと思うんですけど実際、今の活動の状況はどうですか?
SHEEF:自分らで主催するパーティは、今もノリでずっとやり続けてるんですけど、呼ばれてたパーティとかはやっぱりコロナでなくなっちゃうことが多くて。結構くらってるっすね、やっぱり。
MILES:でも、パーティ自体は減るかもしんないけど、絶対なくなんないって逆に確信できたっすね。こんな状態でもパーティをやったら結局人が集まるってことは、やっぱりみんなパーティしたいんですよ。
SHEEF:今後はとりあえずツアーで全国をいろいろ回って、着地でワンマンとかしてみたいっすね。そろそろ、ハコ側もイベントやったほうがいいって思ってるっぽいじゃないですか。上から押さえつけられても、それじゃあ食っていけねえしって思ってる人も多いと思うし、オリンピックも引き金になる気がする。
――シーンの景色が変わった分、今回のアルバムで逆にブーンバップに根を張るBLAHRMYのカラーも色濃く伝わるのかなと。その先にツアーも見えてくるわけで。
MILES:昔ながらとかそういう意識は特にしてないですね。実際、USのHIPHOPもブーンバップでかっこいい新譜はいっぱい出てるんで。ただ、今の日本の中では際立つかもしんないですね。俺らもこのアルバムで爆発したいし。
SHEEF:そういえば、俺らのアルバムと同じ日に地元のスケートチームのDOBB DEEPが、DVD出したんすよ。『DOBBB2B』っていう。このタイミングでスケーターの奴らやラッパーの奴ら、ヒップホップ好きな奴らもガッと1つになりたい。他にも、仲間のRHYME&BのミックスCD、『D.jones』も出たし、丸ちゃん(BLAHRMY、DOBBDEEP、RHYME&Bの各作品のヴィジュアルも担当)っていう藤沢のドンが7インチ「RETURN OF THE LIFE」も出たんで。盛り上げていきたいっすね。
BLAHRMY
MILES WORDとSHEEF THE 3RDの2MCユニット。2010年のEPを経て、DLiP RECORDSから2012年に『A REPORT OF THE BIRDSTRIKE』でアルバムデビュー。その後、MILESはEPとNAGMATIC、Olive Oilとの連作、SHEEFがアルバムにRHYME&B、DJ BUNTAとの共作と、近年はユニットと並行して個々のリリースを活発化。ひさしぶりのまとまった作品となる今回のアルバムに続き、早くもSHEEFのソロEPの発表が予定されている。
http://dliprecords.com/
Instagram:@dliprecords/@sheefthebis
Photography Daisuke Mizushima