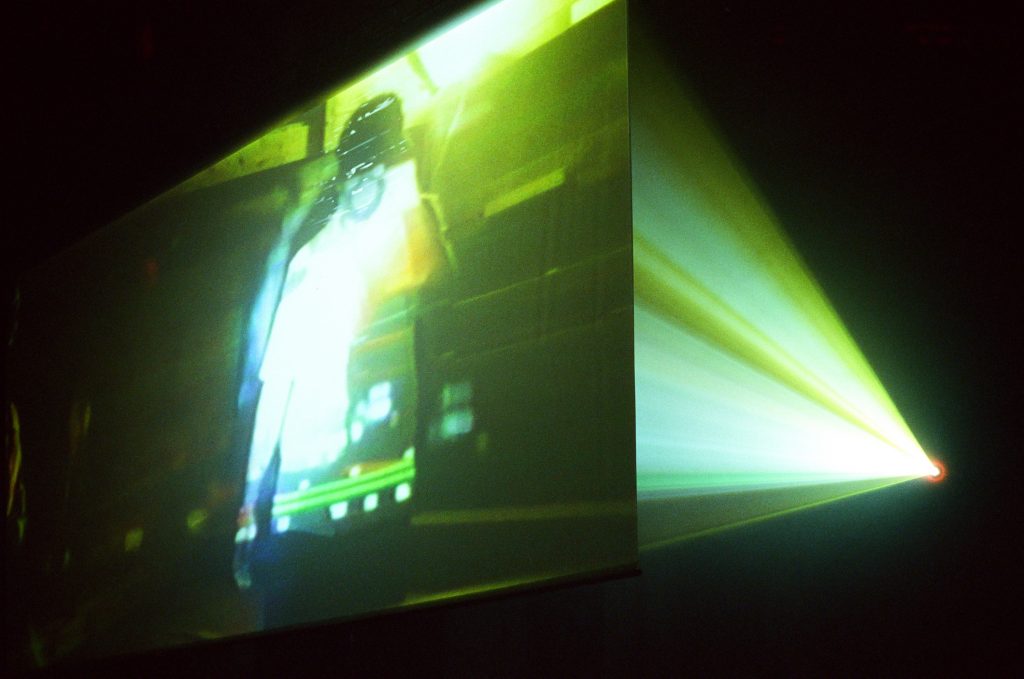否応なしに人生の“一時停止”を強いられた2020年、国と国とが分断され、人と人とのコミュニケーションは希薄なオンラインが主流となった。世界中のジェットセッター達のスケジュールは真っ白になり、環境問題を危惧していたドイツ人アーティストは二度と飛行機には乗らないとまで宣言した。人生の“re-start”ボタンが押されたとともに、私達は徐々に日常を取り戻しながら、パンデミック前と変わらない生活に戻ることはもう2度とないのだと悟る。
しかし、打ちひしがれている時期はもうとっくに過ぎ去った。人も街も、そして、アンダーグラウンドシーンも再び動き出している。それは、単なるシーンの復活を祝うものではなく、1年以上もの長い沈黙を貫いてきたのはこのためだったのかと思えるほど、奥底に眠っていたカルチャーへの不屈の精神が浮き彫りになった瞬間でもある。
実験音楽の最高峰“ベルリン アトナル”の再構築版“メタボリック リフト”は、今まさに世界が知りたいと願うベルリン・アンダーグラウンドカルチャーの姿だ。エキシビションツアーとライヴパフォーマンスに分かれて開催された同プロジェクトを特集にてお届けする。
「人間は自然から生きている。つまり、自然は私達の体であり、私達が死なないためには、自然との対話を続けなければならない。人間の肉体的、精神的生命が自然と結びついているということは、自然が自分自身と結びついているということであり、人間は自然の一部なのである。」
カール・マルクス「METABOLIC RIFT」
「メタボリック リフト」が示す、新しい時代におけるカルチャーのあり方
“ベルリン アトナル(以下、アトナル)”といえば、毎年8月末にクラフトワーク、トレゾア、OHMを会場に5日間ぶっ通しで開催される実験音楽のフェスティバルとして世界的にも高い評価を得てきた。通常では観ることのできないトップアーティスト同士のコラボレーションをワールドプレミアで披露するだけでなく、インダストリアルなクラフトワーク内にノイズやビートがぶつかり合って反響し、規格外の巨大スクリーンに映し出されるトリッピーな映像に打ちのめされるあの感覚は唯一無二だ。
アトナルは1982年にスタートし、1991年にいったん休止となったのち、2012年に復活、そして、2020年に再び中止を余儀なくされた。パンデミック以前から前途多難な道のりをたどってきたフェスとも言える。ロックダウン中に一度だけ、3つの会場が立ち並ぶケーペニッカー通りを訪れたことがある。当時の街の様子を記事にするためだったが、重苦しいシャッターが閉まったままのグレーの世界は陰鬱と絶望しかなかった。
しかし、9月25日から10月30日の長期間にわたり開催された「メタボリック リフト」によって、完全なる復活と進化を遂げたのだ。環境研究家カール・マルクスの『資本論』から由来されたタイトルは、膨張し過ぎた資本主義、自然と共存しなくては生きていけない人間、新しい時代におけるカルチャーのあり方、さまざまなことを考えさせられる。参加アーティスト達は一体どんなメッセージを作品に込めたのだろうか。
これまでとは全く異なるアプローチの体験型エキシビションツアーは、想像をはるかに超えた先にあるさまざまな潜在意識が具現化したような世界だった。
知り尽くしているはずのテクノの聖地トレゾアは、誰も知らないパラレルワールドへの入り口と姿を変えていた。暗闇の中、かすかな光を頼りに恐る恐る先に進んでいくと、DJブースの前ではスポットライトに照らされたブロックの氷がシュールに溶けていく。中国人アーティスト、パン・ダイジンの作品を発見したところから、アトナルが仕掛けた世にも奇妙な“トリック”が幕を開けた。
ツアーグループに同行していたガイドスタッフからは何の説明もない。自分の目で見て、聴いて、感じるだけ。作品展示は、普段は通ることのできない裏導線や存在さえ知らなかったバックヤードにまで及び、その緻密さやサプライズに終始感心しながら移動していた。そうしているうちに自分が今どこにいるのか分からない迷宮に入り込んでしまった。これもきっとトリックの一部なのだ。そんなことを考えながら歩き進むと、突如目の前で踊り狂う巨大なスカイダンサーが現れた。
フランス人アーティスト、シプリアン・ガイヤールとシカゴが拠点のジャマール・モスことハイエログリフィック・ビーイングによるインスタレーションは、クラブやフェスで踊る機会を失われた人間の代わりに、伝説のキラサン・サウンドシステムの“壁”の前で無機質なビニール人形が激しいエアーに吹かれて舞い、無言のまましぼんでいくといったキネティック・アート。その一連の様子に哀愁を感じながら、地を這うウーハーの迫力にダンスフロアが無性に恋しくなった。
クラフトワークのメインホールを占拠していたのは、ニューヨークのアンダーグラウンドヒップホップシーンを牽引するアーマンド・ハマーのラップ映像だった。アルケミストとジョセフ・モールトによって手掛けられた映像は、前後左右に設置された巨大スクリーンからそれぞれ違った映像が流れ続けるマルチチャンネル・ビデオインスタレーションであり、フロアに敷かれたビーズクッションにもたれ掛かりながら身を任せた。
最も興味深く、個人的に好きだったのは、グランドフロアーに展示されていたダニエル・リーによる大掛かりなインスタレーションだ。年代を感じさせる古びたつぼが配置された空間を天井から吊るされた垂れ幕のような大きな布が交差する。生花で覆われた美しい柱は圧倒的な存在感を放ち、土、穀物、種子など古代から人間が必要としてきた自然界の素材が多数用いられていた。至るところに流れていた水は、朽ちていく褐色の世界と鉄筋コンクリートの無機質な空間の中で、オアシスのような癒やしを感じさせた。
リリアン・F・シュワルツのビデオ制作に携わった映像クリエイター・田中弘雄が“メタボリック リフト”を語る
コンピューターアートのパイオニアの1人として知られるリリアン・F・シュワルツのビデオ制作に携わった田中弘雄に“メタボリック リフト”について語ってもらった。彼は以前、TOKIONでもインタビューしたベルリン拠点の映像クリエイターであり、アトナルの撮影クルーでもある。
「“メタボリック リフト”とは、マルクスの思想から着想したコンセプトですが、過去に電力を供給していた建物の地下から18階相当にも上る屋根裏部屋までを存分に使った展示は、ツアーで回る観覧者のアートに対する考えを変える代謝(メタボリック)のようなもの、と聞かされていました。
リリアンの作品は、その内蔵部分の最下部、地下ツアーの最終地点に置かれた映像作品でした。リリアンは1970年代から活躍するビデオアーティストで、その実験的な作風で伝説的な存在でもあります。自分がイギリスの大学院でアートを研究していた時期にも至るところに作品が登場しました。のちに半盲となってしまい、息子であるローレンスの助けを借りて作品を作り続けてきました。クレヨンやマジックを使い、手探りと色を頼りに顔のドローイングを描き続けてきましたが、それらを編集して、エフェクトをかけるというのが今回の僕の仕事でした。
最初はかなりランダムに思えたドローイングですが、彼女が長年培った映像のルールであるXY軸のポジショニングで画用紙の中に目や顔のパーツが配置されており、ナンバリングに沿って編集していくと、目が瞬きをするような瞬間があったりして驚きの連続でした。
テクノロジーの進化によって、CGアートの世界が変わろうとしている時代に、そのルーツである方達の原点回帰の作品にコンピューターでエフェクトをかけ直すという作業は、もはや冒涜にも感じてしまいましたが、リリアンとローレンスとのメールでのやりとりでは常にオープンで、その姿勢に救われました。 ローレンスからは、人間の目の構造やアートに対する世界の認識や創作哲学など、強烈なインスピレーションを多数もらいました。学生の身で研究していた方との再会を数年越しにさせてもらったのは光栄としかいえません。なので個人的にも、もう一度創作の原点に戻らせてくれた“メタボリック リフト”というコンセプト、そしてそれが世界や人が大きく変わろうとしてる2021年に行われたことに不思議な運命を感じています」
すでに20%しか残されていない片目の視力と息子の手助けによって描かれたリリアンのドローイングは、サイケデリックと純真潔白が激しく入り混じるサブリミナルな世界で、コンクリートの洞窟の奥底に吸い込まれていった。
次回は、カナダのエクスペリメンタル・コンポーザー、ティム・ヘッカーも出演したライブレポートをお届けする。