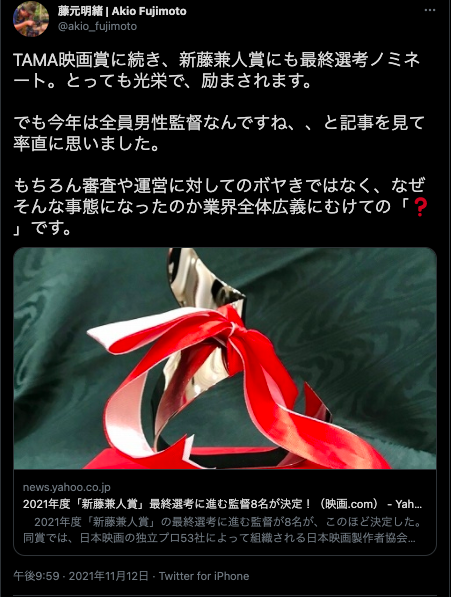2021年11月上旬に上京し、「東京国際映画祭」「東京フィルメックス」に参加した。
前回の「タイが生んだ、編集の魔術師、リー・チャータメーティクン祭り in 東京」で紹介した4本のうち、タイのジャッカワーン・ニンタムロン監督作品『時の解剖学』は、第22回「東京フィルメックス」にて、最優秀作品賞を受賞。そして、度肝を抜かれた、アピチャッポン監督作品『MEMORIA メモリア』は2022年3月4日から全国公開されることが決定した。恐るべし、編集の魔術師。
それから11月下旬は福岡に行き、日中は福岡市総合図書館映像ホール・シネラで中国映画特集を観て、夜は「Asian Film Joint 2021」、第2回で取り上げた「福岡で特集上映される、タイの奇才アノーチャ監督」の特集上映に参加した。東京と福岡の合間に、ノーマルスクリーンさんの特集「クィア東南アジアの今 その声のいくつか」に合わせて、「スコールが通り過ぎるのを待つように。東南アジアの性的少数者映画をめぐる近況」も寄稿した。その福岡では、アノーチャ監督に「東南アジア映画の現在地」について、お話を伺った。
この11月を振り返ってみると、性的少数者映画とアノーチャ監督特集関連で、女性映画について考えた期間だった気がする。性的少数者映画についてはすでに寄稿しているので、今回は、11月に観た映画を絡めながら、アジアの女性監督の近況について書いてみたい。
女性監督作品が印象に残った東京国際映画祭
今回の「東京国際映画祭」は、最高賞にあたる東京グランプリ/東京都知事賞をコソボのカルトリナ・クラスニチ監督による長編デビュー作『ヴェラは海の夢を見る』が受賞したことに象徴されるように、女性監督の作品が印象に残った。
そのうちの1作は、韓国のシン・スウォン監督『オマージュ』(2021)である。
シン・スウォン監督作品 『オマージュ』(2021)
主人公である女性映画監督のジワンは、韓国女性監督としての先達、ホン・ウノン監督のデビュー作『女判事』(1962)の修復の仕事を依頼される。その『女判事』は、一部音声とフィルムが欠落していた。欠落部分を探す修復作業の過程で、女性監督ホン・ウノンが歩んだ苦難の道のりも明らかになっていく。
シン・スウォン監督への東京国際映画祭公式インタビューによれば、「映画に登場する先輩の女性監督達は、いずれも実在の方です。私が10年くらい前に、テレビ用のドキュメンタリーを撮った時に、彼女達の取材をしました。映画にも出てくる韓国初の女性映画監督パク・ナモク、もう1人が『女判事』を手掛けたホン・ウノンでした」。
今回の東京国際映画祭では、ちょうど日本の「女性監督のパイオニア 田中絹代」特集も行われていたので、日本と韓国の女性監督の先人達へのリスペクトという点で重なる部分もあった。『オマージュ』が素晴らしい女性映画であると同時に、映画愛にあふれた作品である点は、ドキュメンタリーとしての要素に、フィクションをプラスして行き詰まっていた監督が先人達のフィルムの捜索という苦難の道のりをたどることで、自身にフィードバックしていく、ある種の再生の物語であることからも明らかだろう。ホン・ウノン監督作品『女判事』とセットでの『オマージュ』の上映も観てみたい。
そしてもう1作、台湾のエンジェル・テン監督による、女性同性愛を描いたドラマシリーズ『最初の花の香り』(2021)にも触れたい。
エンジェル・テン監督作品 『最初の花の香り』(2021)
作品解説によると、「LGBTQ作品に特化した台湾の動画配信サイトGagaOOLala製作のミニシリーズ。平凡な家庭の主婦が、高校の後輩との再会を通して新しい自分を発見するまでを描いた作品」。
GagaOOLalaは、性的少数者に関する映像作品により、アジアに大きなインパクトを与えた、画期的な動画配信サイトだ。2020年に、GagaOOLala主催のシンポジウムを聴いた時は、配信コンテンツの9割近くがG、つまり男性同性愛関連だと発表していたが、女性同性愛のドラマシリーズ製作にも本腰を入れたのかと、GagaOOLalaの挑戦的姿勢に心動かされた。ただし、今回上映されたのは、全話ではなくダイジェスト版であり、また続編も製作中だそうなので、評価は難しいところだが、冒頭の結婚式で2人が再会に至るシーンが秀逸だった。
アン・リー監督作品の『ウェディング・バンケット』(1993)からあと少しで約20年、同性婚合法化以降の台湾での結婚式の様子も垣間見えると同時に、女性同性愛をめぐって、まだ変わらず残る偏見ととまどいを感じさせる導入で、ドラマに自然と引き込まれた。もっとも、全6話をきちんと観るためには、GagaOOLalaに入会する必要があるのだが……。
日本での劇場公開を期待したいカミラ・アンディニ監督作品が映えた東京フィルメックス
続いて「東京フィルメックス」では、中国のクィーナ・リー監督作品『ただの偶然の旅』(2021)と、アフガニスタンの映画作家、シャフルバヌ・サダト監督による『狼と羊』(2016)など、女性監督の作品が上映される中、もっとも惹かれたのは、前回で取り上げた、カミラ・アンディニ監督『ユニ』(2021)である。
カミラ・アンディニ監督作品 『ユニ』(2021)
主人公のユニは、紫色に固執していて、気に入った紫色のものを見かけると、友人のものでも盗んでしまい、先生から注意を受けているくらい。この紫色が画面に映え、画面の色彩を非現実的なものに引き付けていく。カミラ・アンディニ監督の作品は、どこか夢遊的で浮遊感が漂っているのだが、その紫色の夢遊とユニの青春とが重なっている。しかし、映画が進むにつれて、彼女の青春、紫色の夢遊にも、インドネシア田舎の未婚女性達に待ち受ける過酷な現実が影を落としていく。
映画『ユニ』は、カミラ・アンディ二監督を、「巨匠ガリン・ヌグロホの娘」という2世監督のイメージから脱却し、インドネシアを代表する監督へと押し上げる1本と言えるだろう。前監督作品『見えるもの、見えざるもの』と併せて、日本での劇場公開が望まれる。
アノーチャ監督にうならされたAsian Film Joint
アノーチャ監督の過去作については、連載第2回で書いているので、そちらを読んでいただくとして、「Asian Film Joint」で公開された新作映画『カム・ヒア』(2021)と、その姉妹編とも呼べるポム・ブンスームウィチャー監督による短編『レモングラス・ガール』(2021)ともに観応え十分だった。
アノーチャ・スウィチャーゴーンポン監督作品 『カム・ヒア』(2021)
アノーチャ・スウィチャーゴーンポン脚本、ポム・ブンスームウィチャー監督作品 『レモングラス・ガール』(2021)
『カム・ヒア』は、映画『戦場をかける橋』(1957)で知られる、タイ西部のカンチャナブリへのロードムービーの一種と呼べるのだが、過激で優美な迷宮映画の世界のアノーチャ監督だけあって、一筋縄ではいかない。行き先の見えない「迷宮ロードムービー」とでも呼べばいいだろうか。今回はカラー作品ではなく、モノクロ作品だったので、行き先の見えなさ、現実感の希薄さに拍車がかかっていた。そのイメージの衝突、逸脱、そして飛躍を観続けていると、いったい何を観ているのか、わからなくなってくるものの、最終的には「ああ、映画を観ているのだった」と気付かされる。これもまたシン・スウォン監督同様、映画愛にあふれた映画だった。ただし、『オマージュ』と違って、マニエリスムのように、ねじれている。
さらに姉妹編『レモングラス・ガール』を観ると、『カム・ヒア』のメタな視点(メイキングドキュメンタリーとフィクションの融合。しかもこちらはカラー作品)が提示され、『カム・ヒア』が反転し、別の迷宮に誘い込まれる。これらの貴重な「迷宮」映画体験は、『カム・ヒア』と『レモングラス・ガール』をセットで上映するプログラムを組んだ、三好剛平さん(Asian Film Joint/三声舎)の功績である。福岡以外にも、アノーチャ監督の「過激で優美な迷宮映画」特集上映が広がることを期待する。
「Purin Pictures」が助成したインディペンデント映画にハズレなし
「Asian Film Joint」のフォーラムでは、アノーチャ監督とプム監督に、彼女達が運営する、東南アジア圏のインディペンデント映画に特化した製作・活動支援を行う民間映画基金「Purin Pictures」について尋ねる機会を得た。連載第10回「タイが生んだ、編集の魔術師、リー・チャータメーティクン祭り in 東京」の4本と、連載第8回で取り上げた、レ・バオ監督によるベトナム映画の『Vị (Taste)』(2021)も、「Purin Pictures」による助成を受けている。つまり、「Purin Pictures」が助成したインディペンデント映画にハズレなしと断言してもいいくらいだ。
加えて、「Purin Pictures」の助成がユニークなのは、女性監督達も多く選ばれている点にある。フォーラムで、アノーチャ監督に、「Purin Pictures」は女性監督達を優先的に選んでいるのか尋ねたところ、彼女は「東南アジアにおいて、女性監督をめぐる製作状況は依然として厳しいので、毎年2回の助成において、必ず女性監督の作品を選ぶようにしている」と答えてくれた。
この「Purin Pictures」の女性監督達への助成は成果を上げていて、例えば最近だと、2度も助成を受けた、ベトナムのドキュメンタリー映画『Children of the Mist』(2021)は、「アムステルダム国際ドキュメンタリー映画祭」2021で、ハー・レ・ジエム監督に最優秀監督賞をもたらした。彼女は1991年生まれで、連載第8回で取り上げた、「ベトナムのインディペンデント映画黄金世代である、1990年世代」の1つ下で、ほぼ同世代だ。黄金世代と紹介した4人の監督達はすべて男性だったので、ジェンダーバランスが悪いことが気にかかっていたが、ジエム監督が最優秀監督賞を受賞したことで、この世代の女性監督も国際的に評価され、もやもやが少し解消されたと思う。
ハー・レ・ジエム監督作品 『Children of the Mist』(2021)
また、「Purin Pictures」最新の助成においても、映画『ユニ』に続き、前回の連載最後で言及した、カミラ・アンディニ監督の新作企画『Before, Now & Then』が「Purin Pictures」のポストプロダクションの助成にも選ばれている。「Purin Pictures」は、カミラ・アンディニ監督推しだと思う。
日本の女性映画監督について
草野なつか監督作品 『王国(あるいはその家について)』(2019)
少し本筋から脱線するが、自分の担当したフォーラムのあと、三好さんと打ち上げをした時、三好さんが草野なつか監督作品『王国(あるいはその家について)』(2019)も好きだと仰っていて、アノーチャ監督の「迷宮」と草野なつか監督の「王国」と、「過激で優美な彼女達」という点で三好さんの好みが一貫していることに感心させられた。
幸い、現在、この『王国(あるいはその家について)』は、パリ・シネマテークフランセーズの配信プラットフォーム「HENRI」内の「Japan Fringe」特集にて2022年2月1日まで無料配信されている。この「Japan Fringe」特集では、小森はるか、瀬尾夏美監督『波のした、土のうえ』(2015)も 2月15日まで無料配信されている。もちろん、女性監督のみならず、男性監督の作品も配信されていて、「シン・日本映画」のありがたい特集なのだが、日本の「過激で優美」な女性監督達の試みを繰り返し観て、ひたるにも絶好の機会だと思う。
アノーチャ監督が仰っていた、女性監督をめぐる製作状況の厳しさは、東南アジアに限らず、日本にも共通のものである。例えば、先日、「表現の現場調査団」による、現在進行中の日本におけるジェンダーバランスについての調査中間報告においても、「映画賞におけるジェンダーバランス:男性主観の評価が常態化。女性は年齢を重ねると減少傾向」が指摘されている。この記事を読んだ時、映画『海辺の彼女たち』で新藤兼人賞金賞を受賞した藤元明緒監督が受賞前の11月12日のツイッターで、
「TAMA映画賞に続き、新藤兼人賞にも最終選考ノミネート。とっても光栄で、励まされます。でも今年は全員男性監督なんですね、、と記事を見て率直に思いました。もちろん審査や運営に対してのボヤきではなく、なぜそんな事態になったのか業界全体広義にむけての「?」です」という、勇気あるつぶやきを思い出した。
この連載を振り返ってみても、女性監督、より広く女性映画人よりも男性映画人を取り上げてきたなと反省している。もっとも映画祭もそうなのだが、地域の偏りをなくしつつ、男性映画人に偏らないようにアジア映画を紹介するのは、実際やってみると難しい。連載第7回で、「『大阪アジアン映画祭』には、昨年話題を集めた韓国映画『はちどり』のように、アジアの女性映画人達、そして女性達の絆を描くシスターフッド映画を積極的に紹介しようとする、暉峻創三プログラミング・ディレクターの意志を感じる」と述べたが、「言うは易く行うは難し」を痛感した。今のほうが、「大阪アジアン映画祭」への尊敬の念は強くなっている。
そして今回の「東京国際映画祭」では、女性映画人を紹介する方向へさらにかじを切った印象を受けた。そういった新しい動きに対して、むしろ問われるのは書き手のほうかもしれず、私自身、他人事ではない。特に、私のような男性の書き手にとっては、アノーチャ監督達による「Purin Pictures」の助成選出基準「必ず女性監督の作品を選ぶ」を戒めにするくらいのほうがいいのかもしれない。
なぜならば、男同士の絆、ホモソーシャルな欲望に引き寄せられる危険性をある程度、抑止してくれるからだ。
次回以降、原稿で紹介する映画人のジェンダーバランスを地道に改善していきたいと思う。女性映画人が活躍できる環境があればこそ、「シン・アジア映画」の可能性が開けてくるはずだから。