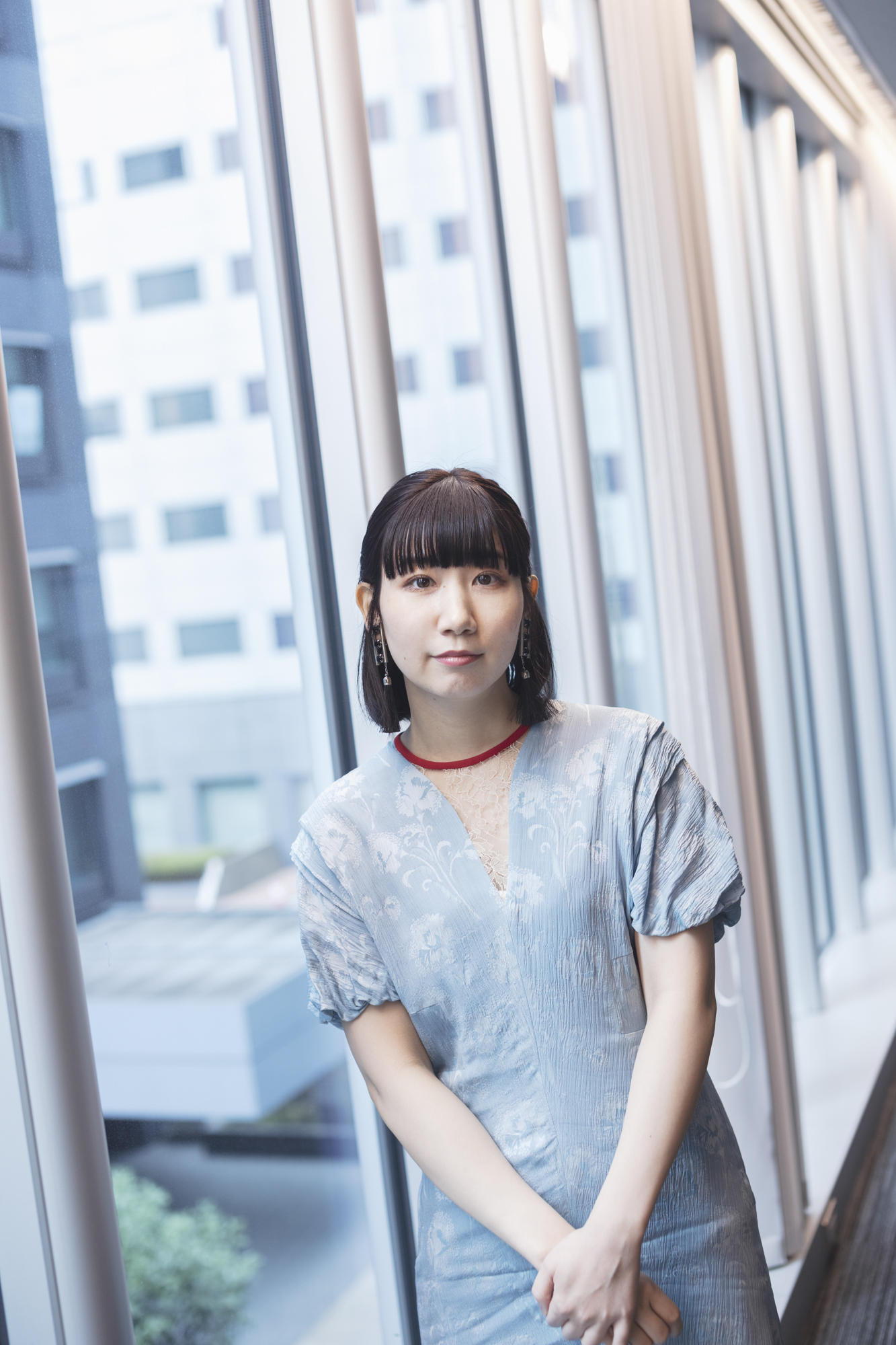19歳で劇団・月刊「根本宗子」を旗揚げし、劇作家・演出家そして、一時は俳優としても演劇界に多くの功績を残してきた根本宗子。昨年、LINE NEWSの動画コンテンツ「VISION」で配信されたミュージカルドラマ『20歳の花』が、今年3月に第25回文化庁メディア芸術祭のエンターテインメント部門の新人賞を受賞するなど、常に新しいことに挑戦しながら、演劇界を盛り上げてきた。そんな彼女が次のフィールドとして選んだのが文学界だ。
初となる小説は、月刊「根本宗子」でも過去3度劇場公演を行った代表作『今、出来る、精一杯。』。東京都三鷹市のスーパーマーケット「ママズキッチン」を舞台に繰り広げられる12人の群像劇だ。小説では、登場人物達が一人称で語り、ストーリーが展開していく。舞台ではなく、文字上で一癖も二癖もあるキャラクター達が複雑に絡み合う今作は演劇とはまた違った緊張感、高揚感に包まれている。
初の小説、その執筆背景は?
――『今、出来る、精一杯。』は初めての小説ですね。
根本宗子(以下、根本):今までも何度か小説のオファーをいただいたことはあったのですが、新作を書き下ろすなら、舞台を書きたいという気持ちがあったのでお断りしていました。今作は23歳の時に書いた舞台が原作ですが、2019年の再演を観てくれた小学館の編集の方から届いたメールがとても熱烈な内容で、舞台を小説にするオファーは初だったのもあって、1度会ってみようかなと。
――実際お会いしてどんな印象でしたか?
根本:私の舞台を愛してくれる人って、まさにこんな人! みたいな象徴のような方で(笑)。演劇はお客さんが目の前にいて、リアクションが即座に届くけれど、小説は完成してから読み手の反応が得られるまでにタイムラグがあるじゃないですか。その創作スタイルは自分に合わないと思っていたのですが、読みたいと言ってくれる人が目の前に現れたことで「あ、そうだよな、こういう風に舞台を見て思ってくれている人っているよな」と心が動き、小説をどこに向けて書けばいいかがわかった気がして。
――それが一番の決め手というか。
根本:そうですね。あとは、小説のルールに則って書いてしまうと、自分らしさを残せないので、ある程度書き終わるまでは放っておいてほしいという要望をOKしてくれたのも決め手でした。
――書き始めてすぐにイメージは固まっていきましたか?
根本:イメージ自体あまりしてなかったですね。もともと12人の群像劇だったものをどう小説にしよう? みたいなところは、最初の段階でかなり考えていて。すべてを一人称、語り口調で書いたのは、今まで自分が使ってきた手法ではあるので、この書き方にしようと決めてからの執筆は楽しめました。
――筆が進まなかったこともありましたか?
根本:西岡という登場人物は「嫌な女」の塊みたいな人物なので、それを一人称で書かなきゃいけないのが本当に苦痛で(笑)。そこで2ヵ月くらい原稿が止まってしまったのですが、なんとか完成できました。
――根本さんは演劇もそうですが、人物のディテールの描き方がずば抜けてますよね。日常から人間観察などしてるのでしょうか?
根本:人間観察が好きなんですか? とはよく聞かれますね。でも、実際は観察しようと意識はしていなくて。結果的に覚えてるって感じですね。初演当時、正論を言っているのに蔑ろにされる久須美という登場人物は自分の経験も重ねて書いていましたが、再演ごとに自分も大人になって、理解はしたくないけれど正論を飲み込めない側の事情も見えてきてしまって。2019年に再演した時は俳優のはるかぜちゃん(春名風花)が演じてくれたのですが、その若いエネルギーを借りて役を作っていく感じで。小説の場合は、役者のエネルギーを取り入れることができないからこそ、久須美を一番繊細に書いたかもしれないです。
――『今、出来る、精一杯。』は根本さんの代表作にあげる方も多いですね。
根本:劇団としては7作目にして、初めて満席になったのと、自分の思うように書けたという意味でとても大きな作品です。自分の作品に対して評価が厳しめなタイプですが、これ今読み返してみても12人を鮮やかに書き分けできていたなと。30代でもう1作、こんな作品を生み出せたらいいですね。
――小説のほうは、読了後になんとも言えない気持ちになったのですが、ご自身でも舞台とはやはり印象は違いますか?
根本:2019年に上演した最新作に関しては、観客の方は絶望の中にも希望があるような印象だったはずです。小説に関しては、読み手に委ねているというか、多分その人の置かれている状況によって、ラストを絶望と捉えるか、希望と捉えるかは変わってくると思います。あまりラストをどう描いたか、みたいなことは自分の中で決めてなくて、本当にそれぞれのタイミングで受け取ってほしい。
――愛☆まどんなさんのイラストをカバーに選んだ理由は?
根本:新しい領域に進むために、タッグを組むなら自分がどんな演劇をやってきたのか理解してくれている彼女がいいなと。年を重ねるごとに、彼女の絵も変化しているように感じるし、そういう方とのクリエイションは刺激になるし、とても楽しくて。
――次回作にも期待しています。
根本:機会があれば書きたいですね。今回は舞台を元にしたものだったので、オリジナルもいつか書きたいなとは思いますし。小説を舞台にするという逆ヴァージョンにもチャレンジしてみたいですね。
稽古から本番までオンラインで行ったコロナ禍での試み
――演劇界へコロナのダメージは大きかったと思いますが、実際の現場はどうでしたか?
根本:マスクをしたままの稽古や、舞台期間中にコロナに感染したら公演を飛ばしてしまうかもしれないというプレッシャーなど、負担や制約が増えました。やり方はいろいろですが、演劇界が止まらないよう、お客さんにずっと楽しんでもらえるように上の世代も含め動いていました。『20歳の花』では、演劇への窓口を少しでも広げ、興味をもってもらえるきっかけづくりになってほしいという思いがありました。結果、役者と新しいクリエイションスタイルを試せたのも良かったですね。2020年に本多劇場から配信のためだけに作った 『もっとも大いなる愛へ』では、公演初日までの稽古をすべてZoomでやりました。
――リアルで顔を合わせない稽古って大変そうですね。
根本:Zoom稽古を想定し、会話の内容と、役者の力で見せられるようなもの書きました。とにかく会話の緻密さが出るよう稽古して、動きは美術模型を見せながら説明して。そもそもZoomを使ったこともなかったので、Wi-Fiの通信環境が悪いとか、各自の環境の違いで苦労はありました。その反面、役者の生活を知ることができたことはおもしろくて。距離は離れていても、密にコミュニケーションが取れている感じもありました。もちろん会って稽古したかったですけど。
――次の舞台は配信ですか? リアルでしょうか?
根本:ちょっと特殊な舞台ではありますが、5月にサンリオピューロランドで「たぬきゅんフレンズ、レッツオーディション!〜3人組は波乱万丈〜」をリアルに上演します。主演がキャラクターなので、当たり前なんですけど、人間と同じスピードで動けないことを考慮しながら作っていく必要があって。
――それはそれでかわいいかもしれないですね。
根本:動きがかわいいのが魅力ですしね。そこに着目して本を書くというのは初めてだったのでおもしろかったです。普段よりもかわいらしいトーンのお話で、もちろん子どもをメインには考えていますが、大人にも楽しんでもらえる内容にすることに注力しています。
「女性の演出家がもっと世に出やすいように、土壌を作っておきたい 」
――根本さんが演劇界で10年間活動されてきた中で、女性であることでの苦労はありましたか?
根本:女性で劇作家と演出家を兼任している方はとても少なくて。少ないというか、正直さまざまな観点から残りづらい。単純に男性の割合が多い仕事なので、そういう意味では男性社会だなと感じることはありました。嫌な目に遭ったとか具体的なことがあったわけではないのですが、男の演出家のほうが現場がまとまる、みたいな空気感があったり。圧を出していかないと勝てない場面があるのですが、かといってそんなふうにはなりたくなくて。
――演劇界で1人でやっていこうと思ったら、かなりのガッツが必要になりますね。
根本:関わらないといけない人数が多いし、作品ごとにメンバーが変わりますからね。女性の演出家がもっと世に出やすいように、土壌を作っておきたいとは思うのですが、現実は厳しい。制作やマネジメントは女性の割合が多く、そうなると男性作家と組むパターンがスタンダードになっていて。語弊を恐れず喋りますけど、演劇の制作って基本的に女性のほうが向いている職業だと思うんですよ。実際女性が本当に多いし。で、特に劇団や作家に座付きでつく制作の人ってその作家の描くものにある意味恋している状態くらいじゃないとやれない仕事で。本当にわりを食う役割だし、評価もダイレクトに受けづらいからモチベーションを保つのが難しいと思う。だからこそすばらしい制作の方は本当に尊敬しているし、頭が下がります。女性作家に男性制作の構図だと、わたしが見てきたことの肌感覚で言うと制作がイニシアチブをとりたがってしまって、作家の色が出なくなってしまう。それで潰れてきた女性作家を何人か見てきているのもあって、私自身は男性の制作と組んだことはなくて。一方で女性2人だとよりなめられがちで難しいこともあります。マジで難しい。これしっかり毎回喋りたいんですけどまだわたしもこの問題をひもとけていなくて。30代の課題です。
――この先もその葛藤はつきまといそうですね。
根本:そうですね。でもだいぶそういうことでのイライラや悲しさみたいなのはたまらないようになってきて。耐性がついたというか、成長できたのかもしれません。
根本宗子
1989年生、東京都出身。19歳で月刊「根本宗子」を旗揚げ、以降すべての作品の作・演出を務める。近年の演劇の作品として『愛犬ポリーの死、そして家族の話』(2018年)、『クラッシャー女中』(2019年)、『もっとも大いなる愛へ』(2020年)などがある。本書が初の小説となる。
Photography Ryu Maeda