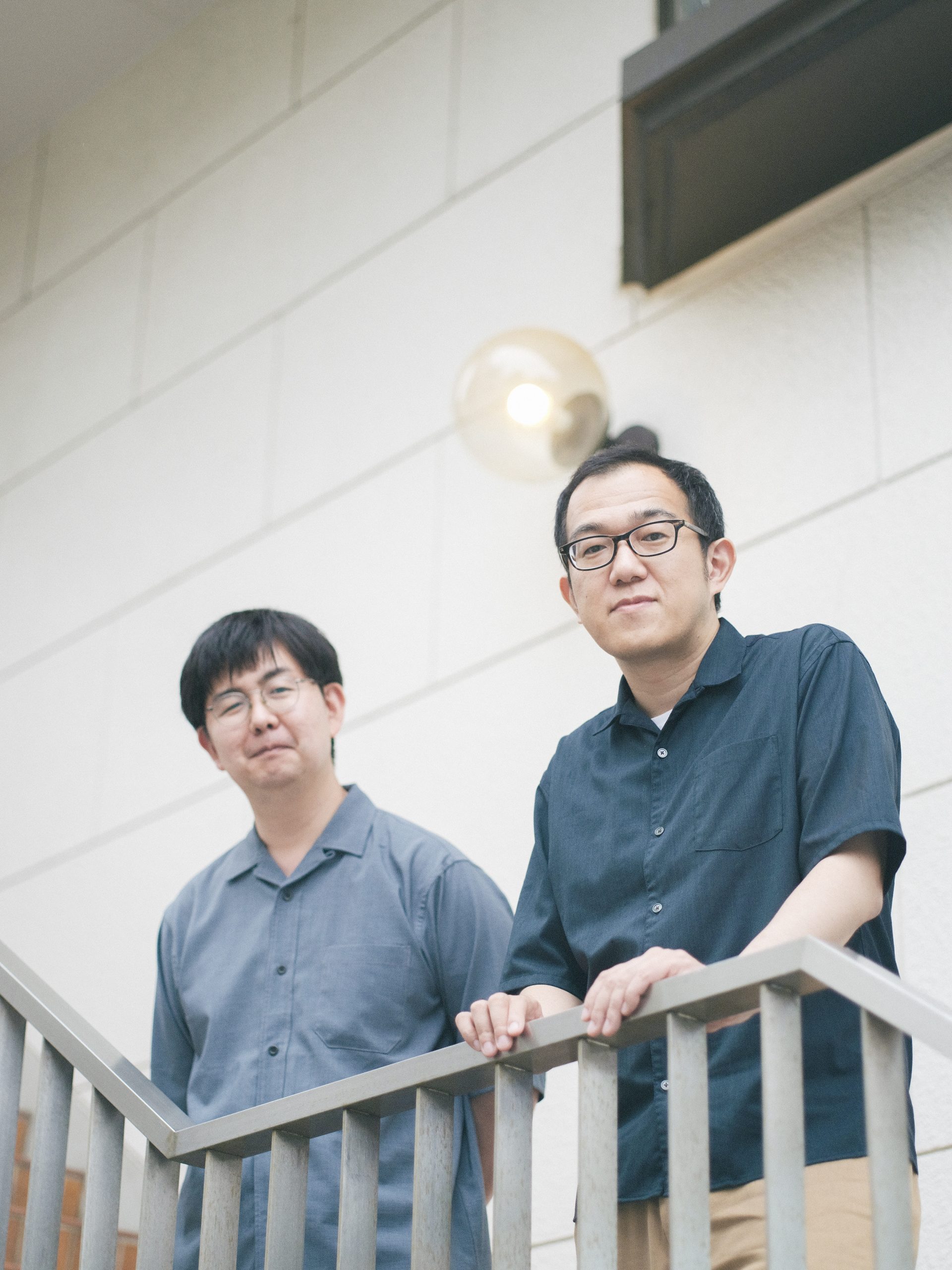
山口淳太
1987年生まれ、大阪府出身。2005年にヨーロッパ企画に参加。映画やドラマ、CM、ドキュメンタリーなど、映像コンテンツの演出・撮影・編集まですべてを行うオールインワンタイプのディレクターとして幅広く活躍。2020年に映画『ドロステのはてで僕ら』の監督を務め、同作は多数の海外映画祭で賞を受賞し、多くの国で配給もされた。また、クリープハイプ「イト」MVや、「あいつが上手 で下手が僕で」、「恋に無駄口」など連続ドラマの監督も手掛ける。
Twitter:@YJunta
上田誠
1979年生まれ、京都府出身。ヨーロッパ企画代表で、すべての本公演の脚本・演出を担当。2017年に舞台『来てけつかるべき新世界』で第61回岸田國士戯曲賞受賞。近年の主な作品に映画『ドロステのはてで僕ら』(原案・脚本)、『前田建設ファンタジー営業部』(脚本)、アニメ映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』(日本語吹き替え版脚本)、『四畳半タイムマシンブルース』(原案・脚本)、ドラマ『魔法のリノベ(脚本/KTV)、舞台『たぶんこれ銀河鉄道の夜』(脚本・演出・作曲)などがある。
Twitter:@uedamakoto_ek
現在公開中の映画『リバー、流れないでよ』は、劇団ヨーロッパ企画が制作を手掛ける長編映画の第2弾。前作『ドロステのはてで僕ら』と同様、劇団の代表・上田誠が原案と脚本を、舞台でも映像を担当する映像ディレクターの山口淳太が監督を務めた。本作のテーマは「タイムループ」。ヨーロッパ企画が拠点を置く京都を舞台に、2分間のループから抜け出せなくなってしまった、老舗料理旅館に集う人々の混乱を描く。普段は劇場をメインに活動している劇団が制作するこの映画は、一体どのようにして生まれたのか、上田と山口の対談から探る。

……と、まずは取材の現場に早めに到着した山口監督のお話から。
始まりは『踊る大捜査線』
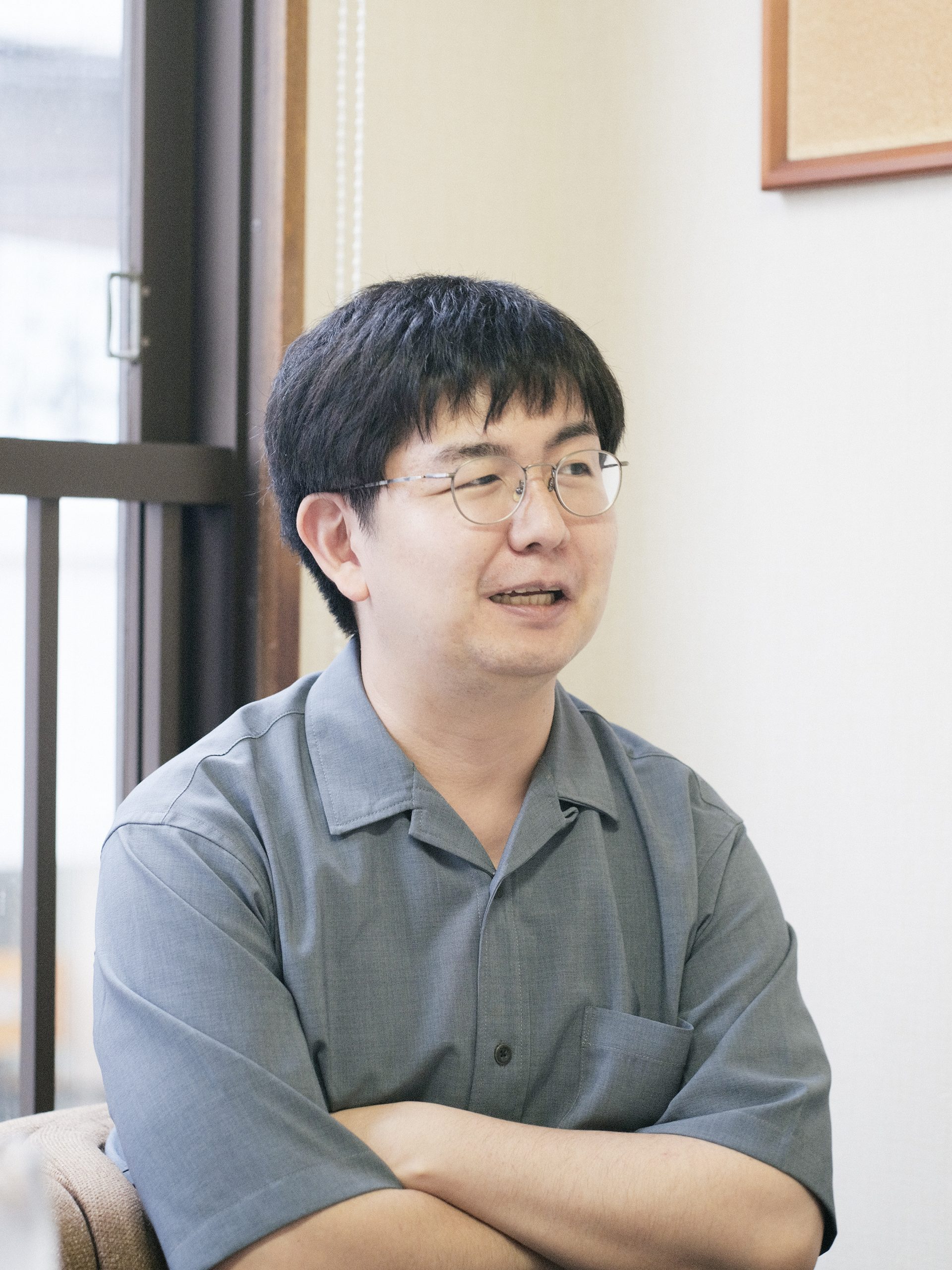
——上田さんがいらっしゃる約束の時間になるまで、先に山口さんのインタビューから始めてもいいでしょうか。
山口淳太(以下、山口):はい、どうぞ。よろしくお願いします。
——まずは、山口さんとヨーロッパ企画との出会いを教えてください。
山口:ヨーロッパ企画の名前を最初に知ったのは、映画『サマータイムマシン・ブルース』(2005年)のホームページでした。もともと『踊る大捜査線』がきっかけで、本広克行監督のめっちゃファンになりまして、2003年に『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』が公開されたあと、次の監督作はこれだっていうことで、『サマータイムマシン・ブルース』の情報が出たんです。まだキャストもあらすじも公開されていなくて、公式ホームページには青空の写真と、タイトルの『サマータイムマシン・ブルース』だけが載っていて、よく見たら端にちょこんと「ヨーロッパ企画」と書いてあったんです。
——映画『サマータイムマシン・ブルース』は、ヨーロッパ企画の同名舞台(第8回公演/2001年)が原作で、脚本を上田さんが書いています。
山口:舞台が原作なんやと思って、そこでヨーロッパ企画という劇団の存在を知りました。それまで舞台とか観てなかったんですけど、調べてみたら、ちょうどヨーロッパ企画が公演中だったんです。大阪のインディペンデントシアター2ndという劇場で、初めてヨーロッパ企画の芝居を観ました。
——その時、山口さんは、おいくつですか?
山口:高校を卒業したばっかりですね。大学に受かって、入学するまでの間です。
——初めて観たヨーロッパ企画の舞台はどうでした?
山口:それがたまたま、舞台の半分くらいがスクリーンで、映像と芝居がリンクする作品(第17回公演『平凡なウェーイ』/2005年)だったんです。僕は映画好きとして観に行ったので、この劇団はこんなに映像を使うんだ、ってびっくりしまして。後にも先にもあそこまで映像を前面に押し出した公演はないのですが、なにぶん最初がそれだったので、舞台が映画化されるほどの劇団だし、映像はふんだんに使うし、俄然興味を持ちました。
——『踊る大捜査線』から始まって、運命に導かれているような展開ですね。
山口:しかも、ちょうど、その時にヨーロッパ企画がスタッフを募集してたんですよ。ジャンル問わず、とにかく何でもいいから劇団のお手伝いをしてくれる人っていう。僕も大学入学前で暇だったんで、すぐに応募しました。
——そこで採用された、と。
山口:時間だけはあったので。ただ、自分は役者志望でもないし、劇団員になりたいわけでもなかったので、映画のほうは自分で勉強しながら、公演の時期には準備とかを手伝いつつ、舞台で映像を使う時はやらせてもらう、みたいな感じでした。
僕がスタッフになってすぐ、映画『サマータイムマシン・ブルース』が公開されて、そこから一気にヨーロッパ企画の知名度も上がりましたけど、当時はまだ同志社大学の演劇サークルの延長線上という感じがあって、僕も大学生でしたし、ひたすら楽しかったですね。
芸風を確立するために「企画性コメディ」を標榜する

(ここで、上田誠さんが到着)
上田誠(以下、上田):どうも、よろしくお願いします。
——いま山口さんに、ヨーロッパ企画との出会いについて話をうかがっていました。
上田:あ、本広克行監督の話ですか。そう、彼は『踊る大捜査線』の熱烈なファンで、当時、本広監督が運営していたファンサイトみたいな掲示板で、ファンと論争とかしてたんですよ。今でいう炎上みたいになってました。だから僕の彼への最初の印象は、映画に一家言ある論客っていうイメージですね。
山口:論客って(笑)。あの頃まだ高校生ですから。
——では、ここからは本題である、映画『リバー、流れないでよ』について。そもそもヨーロッパ企画で映画を作ろうと思ったのは?
上田:僕はとにかく劇団という集団が好きで。もちろん劇場で芝居をするのが主な活動ではあるんですけど、それだけが劇団ではないと思っているんです。劇団が主体となって、テレビ番組を作ってもいいし、劇場で公開する映画を作ってもいい。劇団の拡張ですね。劇団でやれることをどんどん広げていきたいんです。
——原案と脚本を上田さんが担当し、山口さんが監督、そして役者は劇団の俳優陣という座組みで。
上田:同じ座組みだからこそ、映画にしてもテレビにしても、その媒体でしかできない表現を追求することに関してはだいぶ意識してます。なので『サマータイムマシン・ブルース』を映画化した時には、映画でしかできない仕掛けや脚本を模索しましたし、その経験を得た後は、これまで以上に舞台では舞台でしかできないことをやるようになりました。その結果、舞台の映画化の話が全く来なくなりましたけど(笑)。
——ヨーロッパ企画の舞台は、新規性も重要視していますよね。
上田:作品でいうと『ロベルトの操縦』(第30回公演/2011年)から『ビルのゲーツ』(第33回公演/2014年)のあたりで、ヨーロッパ企画は「企画性コメディ」というのを標榜し始めたんです。新しいことや変わった試みを積極的にやっていこう、そこに予算もエネルギーも注ぎ込もう、という宣言ですね。例えば、「迷路コメディ」だと、舞台いっぱいに立体迷路のようなセットを組むとか。
そういう試みは、演劇の常識的な観点でいえば、役者が動きにくくなったり、照明が当たりづらくなったり、いろいろ不具合も出るんですけど、そこは「企画性コメディを標榜する劇団だから」で乗り切る。なんなら、失敗してもいい、くらいの勢いでやってました。
——「企画性コメディ」を標榜したのは、どういう意図で?
上田:企画性を押し出すことで、劇団としてのキャラクターを浸透させたかったんです。舞台美術だけじゃなく、役名をつけなかったりとか、世界観や物語性を後退させてでも、企画性を尖らせて、ヨーロッパ企画の芸風を確立したかった。
——確立した芸風は、映画にも引き継がれていると。
上田:舞台でずっとやってきた取り組みを、今度は映画でもやってみよう、ということで始めたのが映画のプロジェクトです。第1弾の『ドロステのはてで僕ら』は、まさに企画性こそを重視した作品で、もはや企画性だけで骨組みができているような映画。だから、単体の映画として観るとだいぶ奇妙な作りになっていると思います。
それを経ての第2弾『リバー、流れないでよ』は、企画性も大事にしながら、第1弾ではあえて後退させていた、世界観や物語性も取り入れた作品にしました。
劇団で映画を作るからには、自由を謳歌したい


——コンセプトは通底していても、表現方法は舞台と映画ではだいぶ違いますよね?
山口:舞台の時は、役者のセリフの量であるとか、目線の誘導とか、やっぱり舞台ならではの作りになっているので、映画の方法論とは全く違いますね。映画の場合は、群像劇とはいえ、物語を引っ張る人物越しに、そのまわりを撮っていくという方法になります。
ただ、上田さんが現場にいることで担保されている部分は大いにあって。『ドロステのはてで僕ら』と『リバー、流れないでよ』の共通点として、どちらも2分間のタイムループがあるのですが、現場で上田さんが助監督と一緒にストップウォッチを持って2分を計ってるんですよ。劇中で起きている2分間の出来事は、本編中の尺もぴったり2分間にしているので。脚本家が常に撮影現場にいるって、普通はないことですけど、だからこそ、舞台での上田ワールドが映画にもそのまま引き継がれているんだと思います。
上田:他の仕事では、外部の脚本家として映画やドラマの脚本を書くことがありますが、そういう時はいろんなバランスを考えながらやってしまうので、突き抜けたことをやるのは難しいんですよね。だからこそ、自分の劇団で映画を作るからには、自由を謳歌したい。たとえその先に何もなくても、あったらよりいいですけど、未踏の山を越えたいんです。
——シナリオ=設計図としての戯曲と、映画脚本の違いについては?
上田:演劇は言葉の文化というか、耳で聴くことに由来があると個人的には思っていて、それは戯曲が文芸作品として扱われることからも。一方で映画は、もとをたどれば写真に由来する視覚芸術なので、究極セリフがなくてもいい。そこに画さえあれば。なので、映画を作る時は、脚本ありきではなく、ロケーションとか作品のたたずまいとか、全体の画づくりを監督と相談した上で、どういう物語にするかを固めていきます。
——「演劇は言葉の文化」と言いながらも、ヨーロッパ企画の舞台はかなりビジュアルに凝っていますよね。
上田:そこは逆に、言葉の文化である演劇に対するアンチテーゼもあるんです。僕はテレビゲームが好きなんですけど、例えば『スーパーマリオ』は画面の上のほうまでマリオが行けるじゃないですか。ブロックを登ったりして。ビジュアルとしてワクワクする。でも演劇はずっと地べたにいて、高いところに行かないんですよね。空間はあるのに。なので、ヨーロッパ企画の舞台では、役者が上のほうにも行くし、ゲーム画面的なレイアウトを意識しています。
それと、ゲームは非言語で語られていることが多くて、マリオがスタート地点で右を向いていたら、右に進むことがルールだとわかる。その理屈でいくと、舞台でも説明すべきことを非言語で語れるようになれば、言わなくてはいけないセリフは少なくできるんですよ。
——セリフによる説明が不要になる。
上田:そうです。舞台でも映画でも、セリフでは面白い話だけをしたいので、登場人物の背景とかは非言語で伝えたい。例えば、この人が上司で、この人は部下なんだな、とかっていうのは、それぞれの衣装や持ち物、動きとかでわからせればいい。言葉に説明をさせずにすめば、そのぶん言葉の無駄遣いができるようにもなるんです。
自然は何度見ても飽きないし、減らない

——先ほど話に出てきた「タイムループ」について、公式のあらすじ紹介では「2分経つと時間が巻き戻り、全員元にいた場所に戻ってしまう」と書いてあります。
山口:とにかく同じシチュエーションで2分間が30回以上も繰り返されるので、登場人物も同じだし、どうやって画をもたせるかは悩みました。
上田:でも結果的に、その悩みは見事に解消できていると思います。いろいろな方法を駆使してはいますが、中でもキーになったのは自然ですね。タイトルにもなっているリバー、川です。
劇中では何度も川が出てくるのですが、川も含めて自然のものは、いつ見ても違う動きをしてますし、何度見ても飽きないし、減らない。とくに川は、日によっても時間によっても、流れが早くなったり緩やかになったり、動きが豊かなんですよ。
——それは同時に、自然はコントロールが利かない、扱いが難しい、ということでもありますよね。
上田:でもそれは、舞台上の役者も同じなんですよ。シナリオ上ではいろんな計算をして、細かく演出をつけたとしても、舞台に上がってしまえばこっちはコントロールできないわけで。役者自身のバイオリズムとか、体の動きの癖とか、口の形とか、最後は役者に委ねるしかない。人間は演技をするために生まれた存在ではないので、アニメのように制作者の意図を完璧に体現することはできない。人間を起用する以上、自然を相手にしているのと感覚は同じです。
山口:こうは言いながらも、上田さんは本当はめちゃくちゃコントロールしたかったはずなんですよ。でも、いざ自然を目の前にすると、その思いが吹っ飛ぶんですよね。撮影期間中に平気で大雪が降ったりもしましたから。
上田:撮影の日に、外を見たら『ぷよぷよ』の終盤かっていうくらい雪が積もってました(笑)。でもそれも想定内というか、今回は物語のテーマの中に、自然と向き合いながら、自然とともに営みを続けている、というのを入れていたんです。この作品は、厳然としたルールを徹底して守るコンセプト映画であると同時に、自然の中にある老舗旅館を撮る映画でもある。だから、予想を超える天候も自然のお恵みだと思って受け入れるのが、正しい姿勢かなと。

小さい劇団が制作する映画だからこそ、より個人的なことを
——前作『ドロステのはてで僕ら』も、本作『リバー、流れないでよ』も、繰り返される時間が「2分間」と共通しています。
上田:『ドロステのはてで僕ら』を2分間にしたのは、単純に計算がしやすかったからですね。それを引き継いで、今回はキャッチコピーに「また2分。」と書いてあるんですが、「また2分。」って言いたかったという戦略もあります。意外とこういうの大事じゃないですか。
もちろんそれだけじゃなく、ロケハンをした時に、メインの舞台となる旅館と、物語でも大事な場所になる神社が、歩いて1分くらいの距離だったんです。それなら、神社まで歩きつつも、もうちょっとだけ別のこともできるなと。これが3分間だと、神社以外の場所に行けちゃうし、他のこともできちゃうので、あんまり面白くならないと思ったんですよね。
山口:映像作品としても、2分という尺はちょうどいいんですよ。1分だと速くて観続けるのに疲れちゃうし、3分だとちょっと飽きちゃう。集中して作り込める時間として、2分は絶妙なんです。
——100年後の未来とかでもなく、1日でもなく、2分間というスケールの小さい中に、こんなにもドラマがあるのか、と感じました。
上田:より多くの人を楽しませる使命を持った大作映画になればなるほど、物語はポジティブで上向きになっていくんですよね。弱かったチームが大きな目標を持って強くなったり、壮大な敵と戦って困難を救ったり。物語に伴って、役者の演技も大きくなっていきます。それはそれで簡単なことではないし、素晴らしいことですけど、小さい劇団が制作する映画がその路線を目指したところで、ハリウッド大作と張り合えるわけがない。だったら、より個人的な切なさや寂しさを描きたいと思ったし、それが深く刺さるのが映画の持つ魅力の1つだと思いますね。
実験的な作品こそ、芸術から芸能にする
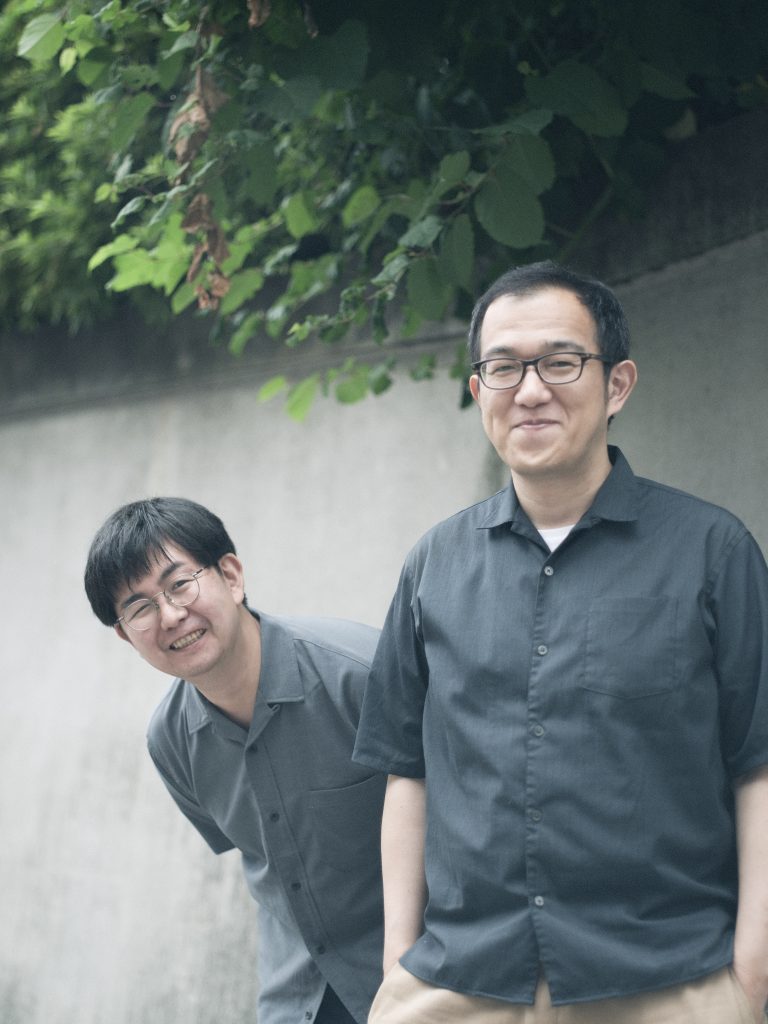
——タイムループものでいうと、時間が巻き戻っていることに本人だけが気づいているパターンと、他の登場人物も気づいているパターンと、大きく2種類ありますよね。
上田:主観の中で起きている出来事なのか、あるいは客観なのか、その違いですよね。それでいうと、今回は登場人物みんなが気づいているパターンです。
タイムリープを題材にした作品だと、過去に戻ることで問題を解決したりとか、そういった物語になるんですが、タイムループの場合は、一定の時間軸の中に閉じ込められるので、その繰り返される世界線からの脱出劇になるだろうな、というのが最初の想定でした。ただ、脚本を進めていくうちに、序盤は客観のチームプレイ脱出劇だったのが、後半から主観のセカイ系逃亡劇にスライドしていったんです。ここは自分でも気に入ってますね。
山口:後半で一気にテンションが変わるので、撮り方も含め、映像の表現方法を変えているんですよ。
——上田さんはタイムリープやタイムループのどこに魅力を感じていますか?
上田:身も蓋もないことを言うと、予算がかからないんです。とくにSFのジャンルでは。例えばロボットものを作ろうと思ったら、美術にしてもCGにしてもばく大な予算がかかりますよね。
基本的に映画は現実を撮るものですけど、やっぱりちょっとは現実離れしたファンタジー要素がほしい。そう考えた時に、お金をそれほどかけずに効果的に作れるのが時間のファンタジーなんですよ。ゾンビも低予算映画の定番ですが、あれも多分ゾンビにそれほどお金がかからないからで。豪華さとは真逆の、ボロボロにすればなんとかなるっていう。
もう1つは、作家的な立場で言うと、僕はもともとプログラミングをやっていたので、伏線の回収とかルールの設定とかは得意で、その能力がいかんなく発揮できる、っていうのもあります。
——手法の他に、物語を作る上ではどうでしょう?
上田:これは最近になってわかってきたことですけど、時間を巻き戻して、同じ時間を繰り返すと、人生をいろんな角度で見られるんですよね。選ばなかった別の世界線を見られたり、一方では、どの選択をしても結局そうなってしまう現実があったり。現実から逃避することもできるし、現実を強化することもできる。そこは物語を作る上で非常におもしろいです。
——映画における、ヨーロッパ企画らしさというか、シグネチャーはどこに見い出していますか?
上田:わかりやすいところでは、長回しの1カットですね。前作でも今作でも長回しは多用してます。監督という立場では、カットを割りたい気持ちもあるでしょうが、ヨーロッパ企画の作品である以上、そこは「企画性を際立たせる」というのが何よりも強い鉄の掟としてあるので。
山口:正直、カットを割りたいシーンは何ヵ所もありました。でも鉄の掟は守らないといけないので(笑)。ただ僕自身、それは楽しんでやっています。
上田:発明をするのが僕の役割だとしたら、それを実装するのが山口の役割なんです。発明って、研究室での実験が成功するだけではダメで、ちゃんと世の中になじませないといけない。もっと言うと、芸術から芸能にしなければいけない。僕がコメディに固執するのは、どんなに実験的な作品でも、お客さんが笑わないと成功したことにならないからなんです。それは映画でも同じだと思っています。
Photography Mikako Kozai(L MANAGEMENT)

■『リバー、流れないでよ』
公開中
出演:藤谷理子
永野宗典 角田貴志 酒井善史 諏訪雅 石田剛太 中川晴樹 土佐和成
鳥越裕貴 早織 久保史緒里(乃木坂46)(友情出演) 本上まなみ 近藤芳正
原案・脚本:上田誠
監督・編集:山口淳太
主題歌:くるり「Smile」
製作:トリウッド ヨーロッパ企画
https://www.europe-kikaku.com/river/

