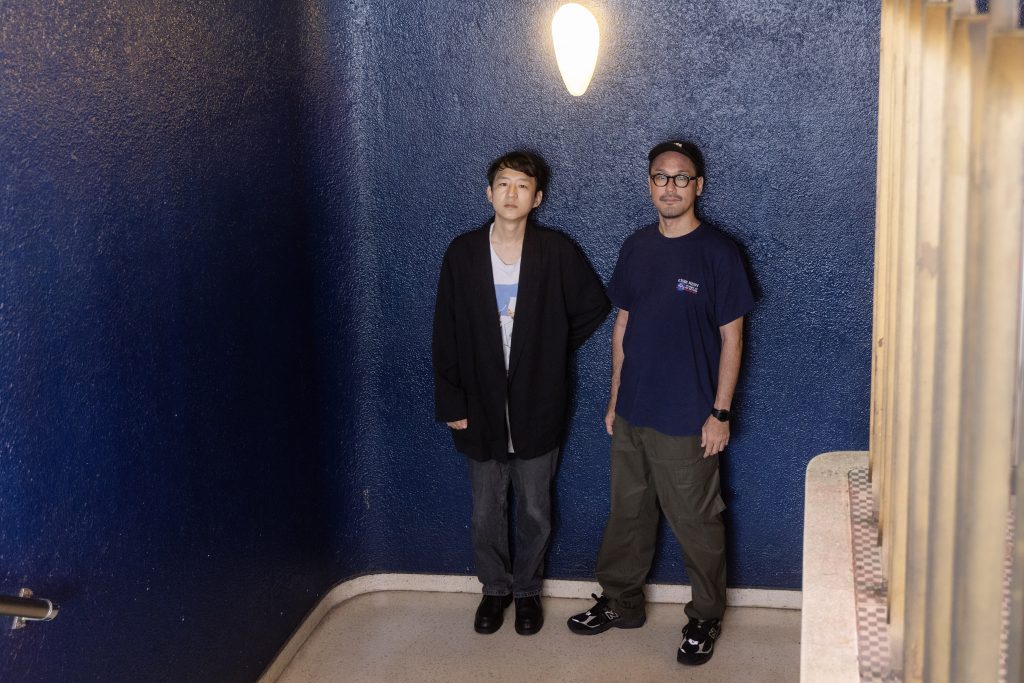
宮崎大祐
1980年、神奈川県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、映画美学校を経て、フリーの助監督として商業映画の現場に参加しはじめる。2011年に初の長編作品『夜が終わる場所』を監督。2013年にはイギリスのレインダンス国際映画祭が選定する「今注目すべき七人の日本人インディペンデント映画監督」のうちの1人に選ばれた。長編第2作『大和(カリフォルニア)』は海外有力メディアでも絶賛された。2019年にシンガポール国際映画祭とシンガポール・アートサイエンスミュージアムの共同製作である『TOURISM』を全国公開し、反響を呼ぶ。大阪を舞台にしたデジタル・スリラー『VIDEOPHOBIA』は映画芸術の2020年の年間ベスト6位に選ばれた。
https://www.daisukemiyazaki.com
Twitter:@Gener80
井手健介
音楽家。東京・吉祥寺バウスシアターの館員として爆音映画祭等の運営に関わる傍ら、2012年より「井手健介と母船」のライヴ活動を開始。様々なミュージシャンと演奏を共にする。バウスシアター解体後、アルバムレコーディングを開始。2015年夏、1stアルバム『井手健介と母船』をPヴァインより発表する。2020年4月、石原洋サウンドプロデュース、中村宗一郎レコーディングエンジニアのタッグにより制作された、「Exne Kedy And The Poltergeists」という架空の人物をコンセプトとした2ndアルバム『Contact From Exne Kedy And The Poltergeists(エクスネ・ケディと騒がしい幽霊からのコンタクト)』をリリース。音楽活動の他、エッセイの執筆、MV映像監督を行うなど幅広く活動している。
http://www.idekensuke.com
Twitter :@kensuke_ide
1970年代に突如現れた謎のロック・バンド、エクスネ・ケディをコンセプトにした井手健介と母船のアルバム『Contact From Exne Kedy And The Poltergeists(エクスネ・ケディと騒がしい幽霊からのコンタクト)』。2020年に発表されて、町田康や坂本慎太郎が絶賛した本作からインスパイアされて映画『PLASTIC』が生まれた。同作は10代の若者、イブキ(⼩川あん)とジュン(藤江琢磨)の物語。ともにエクスネ・ケディの大ファンだった2人は、エクスネ・ケディの音楽に導かれるように出会い、奇妙な絆で結ばれていく。脚本・監督を手掛けたのは、『大和(カリフォルニア)』(2016)、『VIDEOPHOBIA』(2019)などを通じて、国内外で高い評価を得てきた鬼才、宮崎大祐。『Contact From Exne Kedy And The Poltergeists』に衝撃を受けた宮崎は、映画化を熱望してきたという。青春映画であり、音楽映画であり、SF映画のような広がりも感じさせるジャンル分けできない不思議な映画『PLASTIC』はどのように作られたのか、井手と宮崎に話を聞いた。

——宮崎監督はエクスネ・ケディのアルバム『Contact From Exne Kedy And The Poltergeists』のどんなところに惹かれたのでしょうか。
宮崎大祐(以下、宮崎):すべての曲調が違って、それぞれの曲に音楽史的なリファレンスが見え隠れしているんですよね。〈これはどこから引っ張ってきているのかな〉とか〈あれとあれの融合かな〉とか、曲ごとに想像して楽しめる。それって僕の映画の作り方と似ているんです。例えばある昔の映画のシーンをもとに、今ならこうやるとか。あと、曲はバラバラなんだけど、まとめて聴くとコンセプト・アルバムのように楽しめるところも映画的だと思って。それを自分が映画としてどうやって返していこうかと考えるのも楽しかったです。
井手健介(以下、井手):そんな風にアルバムを聴いてもらえると嬉しいですね。アルバムをプロデュースしたのは石原洋さん。この映画にも参加しているんですけど、石原さんが監督、僕が脚本家で俳優も務める映画、という捉え方でアルバムを作ったんです。僕が曲を書き、石原さんが彼の中にある膨大な音楽史と彼自身のアイデアからその曲に合うサウンドやアレンジを当てはめて、それを僕が歌う。そういうことの繰り返しで曲が作られたので、まさに映画的なアルバムなんですよね。
——映画化という話を聞いた時はどう思いました?
井手:エクスネ・ケディというのは僕ではなく別人格なので、スパイダーマンのマルチバースみたいにいろんな世界が存在してもいい。だから宮崎さんが考えるエクスネ・ケディの物語ができるというのは嬉しかったし楽しみでした。だから、口出しをしたり、コントロールしたりしようとは思いませんでした。
宮崎:まず、井手さんにはプロットを読んでもらったんですけど、映画のプロデューサーに読んでもらうのとは違う緊張感がありました。相手は強烈な個性を持ったクリエイターですからね。その後、完成したシナリオを読んでもらったんですけど、そこでは「(アルバムでの)エクスネの設定はこうです」という説明とか、実体験をもとにして気づいたことを言ってくださって。例えばジュンがレコードを売るシーンがあって、店員が査定するのに30分かかるというんですけど30分は短いんじゃないかとか(笑)。
——確かに(笑)。僕もよくレコードを売るのでわかります。1時間以上はかかりますよね。
宮崎:そういうことはつぶさに脚本に反映させていきました。でも、基本的に僕がやりたいことを尊重してくれているのはすごく伝わってきました。そんじょそこらの映画人よりコミュニケーションがうまくて、井手さんはプロデューサー的な資質もあるんじゃないかなって思いましたね。
——登場人物が歌ったり、ラジオから流れてきたり、映画の中でエクスネの曲がさまざまな形で流れます。どんな風に使うか、という点は2人で話をしたのでしょうか?
宮崎:まず、僕が歌詞の内容や曲調を吟味して、どのシーンでどの曲をかけるのかを決めていました。僕は普段、台本に「ここでこの曲をかける」ということは書かないんです。「こういう感じの曲」ということしか伝えないのですが、今回初めて具体的に書きました。そうすることで、キャストやスタッフがシーンをイメージしやすかったと思います。ただ、井手さんとの話し合いで変わった曲もありましたね。
井手:ジュンが車で渋谷に向かうっていうところは、最初は「人間になりたい」という曲が使われていたんですけど、歌詞がジュンの気持ちを説明している風に聞こえてしまう気がしたんです。それで宮崎さんに「ここは歌詞がいらないと思うのでインストの曲を使いたい」と伝えて、そのシーンのために新たに曲を書きました。
宮崎:井手さんの感想はとてもよくわかるんですよね。だから曲を変えることに決めた時、編集のスタッフから「人間になりたい」に合わせて編集したのでそのままにしてください、と頼まれたんですけど、ちょっとチャレンジしてみようよ、と説得しました。映画の後半、時間の流れや物語が抽象的になっていく中、ジュンは自分がいつの時代にいるかもわからなくなって、タイムマシンに乗ったような感じで渋谷に辿り着く。そんな流れをイメージしていたんで、インストの曲に変えて良かったと思っています。
ポップなA面とアブストラクトなB面

——この映画の大きな特徴は、前半と後半のトーンがガラリと変わることですね。前半は青春映画のようにキラキラしていますが、後半になると抽象的で悪夢めいてくる。映画の前半と後半がアルバムのA面とB面みたいに違う世界観を持っています。デヴィッド・ボウイのアルバムでいうと『Low』みたいな感じですね。ポップなA面とアブストラクトなB面。
井手:僕もそう思いました。映画の後半は、映画と一緒に観客が迷子になっていくというか。それが(物語の時代背景である)コロナ禍のムードに近かったのも面白かった。だから、音をつけるなら迷子になるような曲がいいんじゃないかなと思ったんです。そういう意味では、確かに『Low』のB面っぽい雰囲気ですよね。そういえば、映画のエンディングに流れる「妖精たち」という曲は『Low』に収録されている「Sound And Vision」が発想のもとになっているので、ちょっと繋がるところもあるんです。
——そうだったんですか! 今回、井手さんは映画のためにPLASTIC KEDDY BANDを結成してサントラを手掛けています。これはどういったバンドなのでしょうか。
井手:今まで一緒に音楽をやってきた仲間で結成したバンドで、エクスネのアルバムを作った時と同じメンツです。プロデューサーの石原さんやエンジニアの中村宗一郎さんも参加しているんです。今回は時間がなかったので、バンドで曲を作るのではなく、メンバーそれぞれが作曲しました。このシーンのこの曲はあなたがやって、みたいな感じで。そういうやり方は初めてだったので面白かったですね。
宮崎:井手さんはもちろん、石原さんも中村さんもリスペクトしている方々なので、音楽面に関しては完全にお任せしました。
——音響も面白かったです。ギターの響きも他の映画とは全然違う。黄永昌さんという映画の音響スタッフに加えて、石原さんや井手さんなど音楽関係者の感性が加わることで何か変化はありました?
宮崎:ギターのシーンは面白かったですね。ジュンが「高校をやめる!」と言ってギターを弾きまくるシーンでは、映画畑の音響の黄さんがエフェクトを加えてくれた音、井手さんと石原さんと中村さんが作ってくれた音、そして、僕がイメージしていた音が全部違っていて(笑)。それを黄さんと井手さんと僕の3人で聞き比べながら調整して、それぞれがイメージしていた音とはどれとも違う音に着地したんです。でも、それは間違いなく『PLASTIC』の音なんですよね。そういう体験も初めてでした。
井手:イブキが喫茶店で受験勉強をしている時、ジュンとイブキの未来の幻影みたいなものが見えるシーンがあるんですけど、そのバックにBGMみたいな感じで流麗な音楽が流れるんです。最初、ヴォリューム小さめで流れていたんですけど、もっと会話が聞こえないくらい大きくして、諍いの雰囲気だけが伝わるような違和感を狙ったミックスにしたら面白いんじゃないかと思って提案しました。それで現実に戻る瞬間に音を不自然にカットアウトしてハッとさせる。黄さんはカットアウト直前まで少しずつ音楽の音量を上げてミックスしてくれたので、結果的にヌーヴェルヴァーグの映画みたいな効果が出ました。
——ゴダールの音楽の付け方みたいな。
宮崎:ここで告白しておくと、僕は最初からゴダールっぽくやりたいと思っていたんですけど、「じゃあ、ゴダールっぽく」って僕が最初に言うよりも、みんなの話し合いの流れでそうならないかな、と様子を見ていたんです(笑)。
劇中に登場する謎のバンド


——まんまとそうなったわけですね(笑)。そういえば劇中で幻覚のように森の中にバンドが登場しますが、あれはPLASTIC KEDY BANDですか? それともエクスネ・ケディ?
井手:どちらでもない謎のヒッピー・バンドです(笑)。最初はエクスネを出したいという話だったと思うのですが、僕は最後まで出てこないほうが良いと思ったんです。でも、あのシーンでバンドが出てくるのは面白いと思ったので、正体がわからないまま亡霊みたいな存在として登場させようと。
宮崎:とはいえ、エクスネと思う人はかなりいると思いますね(笑)。
井手:まあ、そう思われてもいいんですよ。いろんな世界にエクスネが存在しているわけだから。
——別の世界のエクスネが混線して一瞬姿を現したような感じもありますね。
井手:ああ、「混線」という表現はいいかもしれないですね。
宮崎:この作品は音楽映画でもあるので、山場には限りなくエクスネに近いバンドを登場させたいとは思っていたんです。その一方で、実際にいるバンドをめぐって遅れてきた青春を回収するような作品にはしたくなかった。だから何もない場所に虚構を立ち上げて、それを登場人物の共通の話題にしようと思ったんです。抽象的なクロスポイントを作るというか、それがエクスネだったんです。
——森の中に出てくるバンドは、現実なのか幻覚なのかわからない。そういう点でエクスネに通じるところがありますね。この映画は架空のアーティストから生まれた映画。いってみれば、ファンタジーの合わせ鏡のような物語です。ファンタジーを通じてリアルを描く。あるいは、リアルって何だろうって問いかけているところもあると思いました。
井手:ファンタジーって人間だけができる逃避の仕方だと思うんですよ。結局、僕の曲は根源的には「生きて行くのがつらい」ということがもとになってる。金がない、大好きな人がいなくなってしまった、猫が死んじゃった、とか、そういうつらさを抱えながら何とか生きていくために作った曲がほとんどなんですよね。ただ、それを「井手健介」としてやるとヘヴィー過ぎてしまう。
——シンガー・ソングライターみたいに私小説的な歌になってしまいますね。
井手:そうなんですよね。僕もそういう歌は望んでいなくて。それらをカリカチュアしてユーモアを混ぜて架空のキャラクターとして曲を作る。そうすることで、ほとんどの個人的なものが削ぎ落とされてフォルムとしては全く違うものになるんですが、不思議と最後に、自分が曲を作った時の本質的なエモーションみたいなものがピュアな形で浮かび上がってくるんです。結果として普遍性を獲得することもある。それが創作なんだってエクスネを通じて思えたんですよね。
宮崎:僕の創作に対する姿勢も、井手さんがおっしゃったこととほぼ一緒なんです。自分のプライベートや社会的なことで耐え難いことがあった時に、それをどんな風にユーモラスに加工してアウトプットするか、みたいなことをまず考える。あと、僕は今いる世界がファンタジーだとも思っているんですよ。ジュンが初めてイブキと会った日にカフェで言ってるんですけど、地球の表面にイデアが、真実があって、世界はすべて影絵であるみたいなことを古い哲学者が語っていて。その影絵みたいな世界の中で映画という影絵を作ることで、そのフィクションの交点に真実が浮かび上がるんじゃないかと思っているんです。

——影絵の世界で影絵を作る、というのも面白いですね。井手さんはどんな気持ちで創作されているのでしょうか。
井手:僕は世界と自分ということはあまり考えたことがなくて。僕にとって創作は、この世界で生き延びるための手段。バカなふりをして笑ってもらうことで何とか生き延びているというか。そのバカなことが音楽であり、エクスネなのかもしれませんね。
Photography Kohei Omachi(W)




■『PLASTIC(プラスティック)』
全国順次公開中[PG-12]
出演:⼩川あん、藤江琢磨、中原ナナ、辻野花、佃典彦、奏衛、はましゃか、佐々⽊詩⾳、芦那すみれ 、井⼿健介、池部幸太、北⼭ゆう⼦、⽻賀和貴、⼤⽊ボリス、平野菜⽉、尾野真千⼦、とよた真帆、鈴⽊慶⼀、⼩泉今⽇⼦
監督・脚本:宮崎⼤祐
上映時間:105分
製作:名古屋学芸大学
配給:boid、コピアポア・フィルム
©2023 Nagoya University of Arts and Sciences
https://plastic-movie.jp
