「ものづくり」の背景には、どのような「ものがたり」があるのだろうか? 本連載では、『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら』(宝島社)、『ニャタレー夫人の恋人』(幻冬舎)の作者である菊池良が、各界のクリエイターをゲストに迎え、そのクリエイションにおける小説やエッセイなど言葉からの影響について、対話から解き明かしていく。第13回はコラージュアーティストのM!DOR!が登場。

1986年生まれ、横浜出身。文化女子大学(現・文化学園大学) 編集デザインコースを卒業後、5年間デザイン事務所に勤務。2010年よりコラージュアーティスト/グラフィックデザイナー/アートディレクターとして活動開始。作品の素材には主に1800〜1950年代の雑誌や紙物の現物そのものを使用し、ハンドコラージュ。 仕事ではデジタルコラージュも使用。ルミネ・NEWoManウィンドウディスプレイ、official 髭男dism、Perfume、GLAYなどのアーティストアートワーク、MIKIMOTO、Grand Seikoなどのブランドアートワーク、『VOGUE JAPAN』『装苑』『ELLE』 などの雑誌誌面、山内マリコ『かわいい結婚』(講談社)、H・P・ラヴクラフト『アウトサイダー』(新潮文庫)など、書籍の装画も多数制作。また揖保乃糸ギフトパッケージ、ブランドのテキスタイルデザインにも携わり活動の幅を広げている。
X(旧Twitter):@midori_collage
Instagram:@dorimiiiiiii
オフィシャルサイト:https://www.dorimiii.com/



M!DOR!さんが挙げたのは次の3作品でした。
・岸田衿子・谷川俊太郎・松竹いね子(文)、堀内誠一(絵)『どうぶつしんぶん』(福音館書店)
・ジャック・プレヴェール、小笠原豊樹(訳)『プレヴェール詩集』(書肆ユリイカ)
・吉田篤弘『78(ナナハチ)』(小学館)
さて、この3作品にはどんな“ものづくりとものがたり”があるのでしょうか?
初めての“誰かに見せるものづくり”のきっかけになった、『どうぶつしんぶん』

──1冊めは『どうぶつしんぶん』。岸田衿子さん、谷川俊太郎さん、松竹いね子さん、堀内誠一さんによる共作の絵本です。
これは幼稚園の時に両親に買ってもらって読みました。もう最初に読んだ時のことは記憶にないんです。
親からは表紙に一目惚れしたっていう話を聞いていて。本屋さんで離さなかったから買ったんだよ、って。
──絵本はよく読んでいましたか?
読んでいましたね。『だるまちゃんとてんぐちゃん』とか。『ぐりとぐら』も読みました。あのへんはすごく好きで、たぶん何十回も読んでいますね。
イラストに惹かれることが多くて、けっこうジャケ買いが昔から多いんです。記憶にはないですが、『どうぶつしんぶん』も完全にジャケ買いですよね。
──絵を堀内誠一さんが担当していて、動物たちがかわいいですよね。
そうなんです。色使いもすごくかわいくて、好きな色の組み合わせなんですよね。
それで中を開くと、封筒のようになっていて、中に1枚ずつ新聞がたたんであるんです。
──四つ折りの新聞が4枚入っていて、それぞれ春・夏・秋・冬の号になっています。「どうぶつびすけっとがあって、どうぶつしんぶんがないというのは、どうかんがえてもおかしい」と発刊の辞が書かれています。編集長は「たかくわくまた」という熊。

もともと動物が大好きなんです。この動物が新聞を発行するっていう発想が、今考えても新しいなって。この新聞って4枚しかないですけど、何回読んでも楽しめるのがすごく不思議ですよね。
いろんな動物が連載を担当していて、人生相談だったり、詩が載っていたり。意外とシュールな文章もあって、今読み返すと当時理解できていたのかなとも思いますね。
谷川さんはあとになって詩集を読んだりしましたけれど、たぶんこれが初めての出会いですね。

──この絵本を読んで思ったのは、「自分も動物新聞を作ってみたいな」ってことでした。
そうなんですよね。実は私もこれに憧れてまねできるんじゃないかと思ったらしくて、1ヵ月に1回くらいのペースで自分なりの動物新聞を発行していたんです。両親だけに向けて。新聞を作って、折り紙で動物を折って付録も作ったりして渡したりとかしていましたね。それがある意味、制作の原点かもしれません。
──何かを作るのを初めて意識的にやったってことですね。
絵を描くということはやっていたと思うんですけど、だれかに見せることを意識してちゃんと作るっていうのは、それが初めてだと思います。
そのときリスを飼っていたんですけど、そのリスが書いた体裁の記事を載せていましたね。リスを見ながら絵を描いたりとか、クイズに正解したらリスからの招待状がもらえるとか。
3、4ヶ月は作っていたと思います。
──その新聞は今も残してありますか?
たぶん残していると思います。探したらあるかもしれないですね。
コラージュアーティストとしても敬愛する仏詩人の詩集、『プレヴェール詩集』

──次の本はジャック・プレヴェールの詩集です。この本と出会ったのはいつぐらいですか。
この詩集は2012年ごろに出会いました。大学を卒業してデザイン事務所に勤めていた時期ですね。
高校生ぐらいの時にちょっと絵に苦手意識があったんです。絵じゃない他の表現方法ってないかなって思っていた時に書店でロシア・アバンギャルドの本に出会って。そこのコラージュが使われた絵があってすごく惹かれたんです。
それでスクラップ・ブックみたいなのを作るところから始めて、少しずつコラージュをやるようになりました。
大学に入ってからはグラフィック・デザイナーになりたかったんですけど、コラージュは続けていました。それで大学を卒業して就職したぐらいの時にいろいろ画像検索をしていたら、ジャック・プレヴェールのコラージュ作品が出てきたんです。
──プレヴェールは詩人ですが、コラージュも作っているんですね?
そうですね。詩人として知るよりも先に、コラージュアーティストとして知りました。詩集を読んだのは、そのあとですね。
プレヴェールはケガをして入院している時に、リハビリのためにコラージュを始めたらしいんです。そのコラージュがすごくユーモアがあって、ひと目見た時にすごく惹かれたんです。
そこからプレヴェールって詩人が作ったことを知って、この詩集を読みました。そしたら、すごく心地よく入ってくる感じで。

──詩人との出会い方としては、珍しいですね。
本屋さんで見つけて、この表紙もすごくかわいいなって思って、プレヴェールを読みたかったので買おうと。これもジャケ買いですね。
読んでみると文体もとても読みやすくて、すっと入ってきて、ユーモアもあって。それはコラージュからも感じていたので、詩もコラージュも人間性が出ているなって。
私は「夜のパリ」っていう詩がすごく好きなんですけど。3本のマッチだけでここまで世界観を出せるんだなっていうことにすごくびっくりします。
──ぼくは「鳥への挨拶」という詩が好きです。さまざまな鳥が列挙されて、それに挨拶するという詩なんですけど。
けっこうプレヴェールの詩にも動物が出てきますよね。コラージュも動物の写真を使ったりしています。人間の顔が動物になっていたりとか。そういうところでも、プレヴェールも動物が好きだったんだなって親近感が湧きますね。
──プレヴェールはアニメ映画のシナリオもやっています。いろんなことをやる人だったんですね。
プレヴェールのコラージュ作品を生で見たくて、2014年にフランスへ行ったんです。プレヴェールは1977年に亡くなっているんですが、著作権団体に連絡して、ひたすら好きってことを伝えて。
そうしたら、その団体がプレヴェールの家をそのまま残しているんですけど、そこに招待してもらえて。私はフランス語ができないのでなんとか英語でコミュニケーションしながら。行ってみたら、キャビネットやベッドもそのまま残してあって、今も生活しているんじゃないかっていう温度感がそのまま保たれている感じでした。本棚には古い雑誌がたくさんあって、家具や調度品もプレヴェールの好きなものしか置いてないんだろうなって。
それで作品や家の中に残っているコラージュ素材とか、使っていた道具とかも見られました。
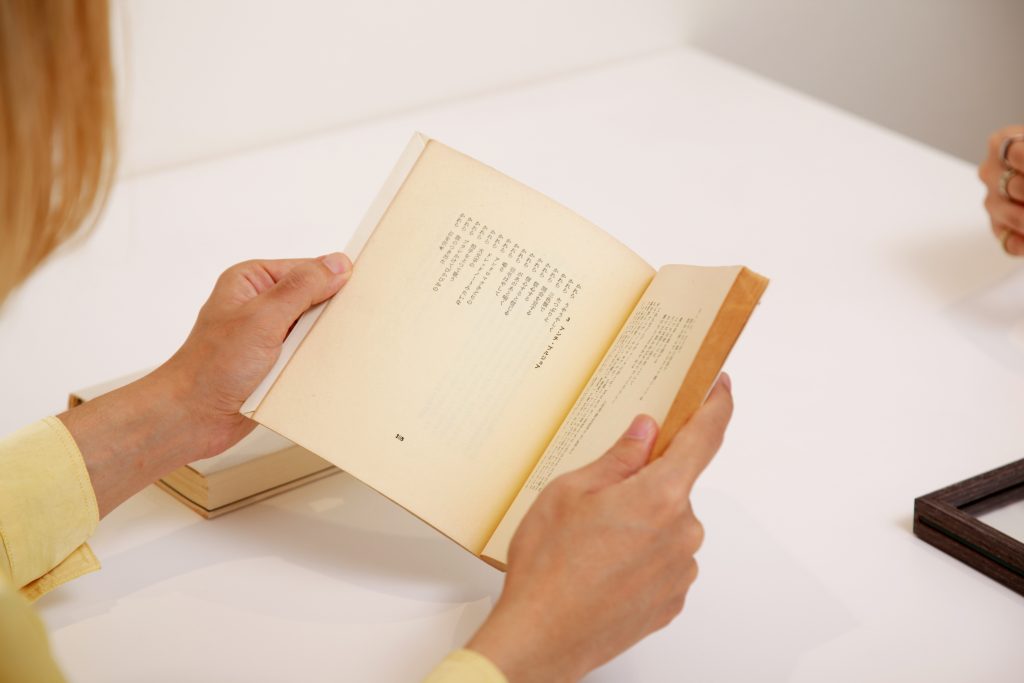
──この詩集を買ったのが2012年とおっしゃっていましたから、それから2年後にフランスへ行ったんですね。
実物を見たいと思ったんです。それを見たら何か変わる気がして。フランスに行くのも初めてでした。
作品を実際に見ると、本で見るよりも大きかったりとか、色とかも違ったりして、すごく衝撃を受けました。
まだ使っていない素材もそのまま保管してあって、これをどういうふうに使う予定だったんだろうなって想像力が湧いて楽しかったですね。
──なんだか“もの”にはパワーが宿りますよね。
そうなんですよね。作品もそうですし、人が使っていたものとかって、その人のことを感じられますよね。使っていた人が今いなくても。
古い雑誌を集めていると、ページのあいだに手紙が挟まっていたりして、どんな人が持っていたんだろうって想像してしまいますよね。
一番好きな小説家の、レコード愛好家にはたまらない短編集『78(ナナハチ)』

──続いては吉田篤弘さんの『78 ナナハチ』。
吉田篤弘さんはたぶん一番好きな小説家さんなんです。
今も新刊が出るたびに読んでいます。すごく独特な、吉田さんならではの不思議な世界観があって、毎回すごく惹かれています。
この『78(ナナハチ)』は、私がレコード好きっていうのもあって、78回転のレコードの話で始まるこの作品を選びました。好きで何回も読んでいます。
──この短編集の特徴はレコードがモチーフなことと、独立したそれぞれの話が少しだけ他の話とつながっているところですよね。
そうなんです。それぞれの話が微妙にいつもどこかでつながっていて、「あ、ここにつながるんだ」って、読んでいくうちにどんどん物語がつながっていく感じの流れも好きです。

──1つひとつは短編ですけど、少しずつつながっていて、大きな絵になっていく感じがあります。
吉田さんってたくさん小説を出していますけど、他の作品を読んでいるうちに「前にもこういうひと出てきた気がする」って思っていると、また違う物語が広がったりとか、そういうつながりもすごくおもしろいんです。
この本だと、短編ごとに実際にあるレコードのタイトルになっているんです。章扉もそのレコードのラベルになっていて。その音楽を聴きながら読むのも楽しいですよね。そのレコードを聴きながら読むと、またちょっと雰囲気が変わったりして、そういう仕掛けもいいですよね。
この小説の最後のほうに「ノアルイズ・レコード」って書いてあるんです。
──「Special Thanks to Noahlewis’ Record」と書かれていますね。
このお店って、78回転レコードを多く扱うお店なんです。
実は私もそのお店で初めて78回転のレコードを聞いたので、最後にこのお店の名前を見つけて、そういうところもつながったので思い入れがありますね。
──それはこの本と関係なく行っていた?
そうなんです。78回転レコードといえば、というような有名な店なんですけど。
レコードは父からプレイヤーをもらったのがきっかけで集めるようになりました。
もともとはザ・ローリング・ストーンズのレコードを手に入れて、どうしても聴きたいけどプレイヤーがないって状態の時に、父から使っていないレコードプレイヤーをもらいました。
ザ・ローリング・ストーンズからロックやパンクにハマっていって。パンクだと、レコードしか出していないバンドがいるんですよね。
──レコードで聴くことは特別な体験ですか?
CDで聴くのと、レコードで聴くのとでは全然違って聞こえます。
中古レコード屋さんに行って、ひたすら見ていって、「あ、あった」みたいな。ジャケ買いするのも楽しいですし。やっぱりジャケ買いが好きなんですよね。
アートとして成り立つけど、ちゃんとした音楽の媒体だっていうところもレコードってすごいなって思うところですね。そういうところが『78(ナナハチ)』でも物語になっていたので好きですね。
──プレヴェールの家に行ったのもそうですけど、実物に触れたいんですね。
そうですね。実物で、ちゃんと自分の目で見たいですし、好きな人には会いたいですね。
そうしたほうが、さらに好きになれたりとか、そこから吸収できるものが多いんじゃないかなって思います。
なので、やっぱり実物が好きですね。
──きっとジャケ買いも、実物がもたらす力なんでしょうね。M!DOR!さんのコラージュ作品にも、実物のパワーが宿っている気がします。ありがとうございました。

Photography Tasuku Amada

