
カルチャー、ライフスタイル、ファッション、社会運動など幅広いジャンルの執筆活動をし、著書『Weの市民革命』では若者が率先する「消費アクティビズム」のあり様を描いたNY在住の文筆家の佐久間裕美子。キラキラした世代と描かれることも多い一方、高齢化、気候変動や所得格差など緊急の社会イシューとともに生きるZ世代(1990年代後半〜2012年頃の生まれ)についての解説を求められる機会が増え、それなら本人達の声を聞き、伝えたいと考えるに至ったことで、実現した対談企画。
第6弾の対談相手はフォトグラファーやエディターなど、肩書きにはあてはまらない幅広い活動を通して表現を続ける、中里虎鉄。前編では、子ども時代に触れたカルチャーや学生時代に編集者を志すようになったきっかけについて聞いた。

中里虎鉄(なかざと・こてつ)
1996年、東京都生まれ。編集者・フォトグラファー・ライターと肩書きに捉われず多岐にわたり活動している。雑誌『IWAKAN』を創刊し、独立後あらゆるメディアのコンテンツ制作に携わりながら、ノンバイナリーであることをオープンにし、性的マイノリティ関連のコンテンツ監修なども行う。
Instagram:@kotetsunakazato
日本のテレビドラマが見られなかった
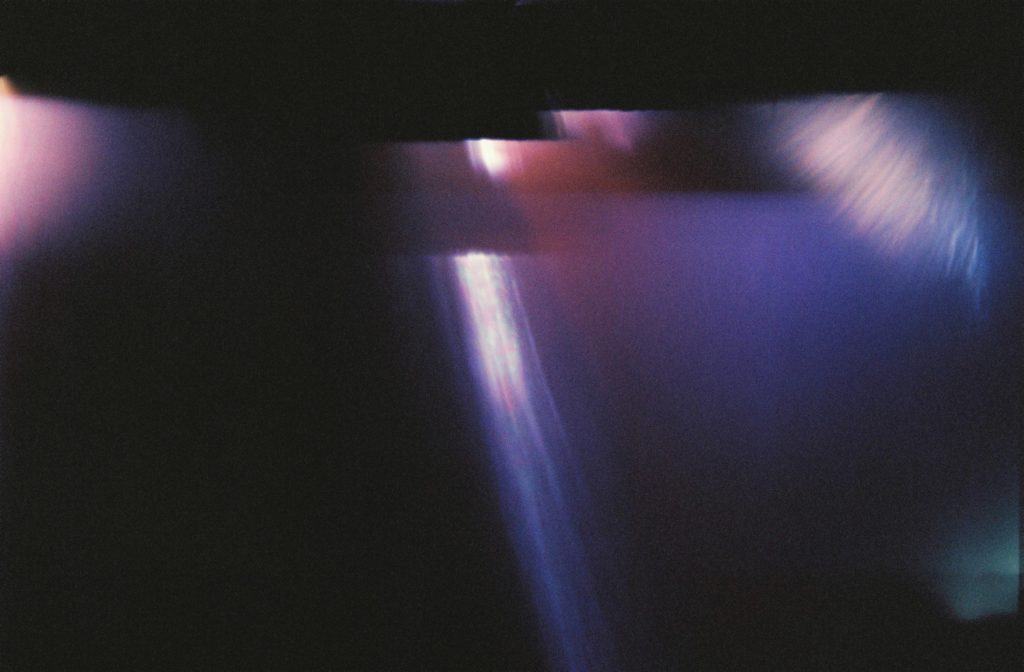
佐久間裕美子(以下、佐久間):写真や編集のお仕事をされていますが、そういった表現活動を始めたきっかけは子ども時代にあるのでしょうか。
中里虎鉄(以下、中里):両親は共働きでラーメン屋さんをやっていて、帰りも遅いので家では姉弟だけで過ごすことも多い子ども時代でした。家はどちらかというと貧困家庭で、子どもの頃はお小遣いやおもちゃを与えられず、当時流行っていたたまごっちも買ってもらえないので、2歳上の姉と一緒に段ボールで手作りして、通信ごっこをしたりしていましたね。ない物は自分達でどうにかするしかない、という姿勢は幼い頃からありました。9歳下の弟ができてからは、弟と一緒に絵を描いたり、おもちゃを作ってあげたり。でも当時はそれが表現活動とは全く思わなかったですね。美術や音楽の芸術面では、姉のほうが表現豊かな人で、親からもずっと比べられて「お姉ちゃんは上手だけど、虎鉄は真似しかできないよね」と言われていて。小中高と学校が一緒だったこともあり、姉のセンスに反発する気持ちもあったし、自分に何かを作り出す才能は一切ないと思っていました。
ただ、家族旅行の時、家にデジカメがなかったので、「写ルンです」を与えられて、自然と写真を撮る係になっていました。そうやって、特に写真自体が好きというわけではなくても、身近にはありましたね。
佐久間:時代特有のカルチャーで、影響を受けたり印象に残ったりしているものはありますか?
中里:我が家はテレビ以外には電子機器がほとんどなかったので、いわゆる日本のポップカルチャーにはあまり触れていなかったと思います。触れていたのは、父がケーブルテレビで見ていた『コメットさん』や『あばれはっちゃく』といった昭和のドラマですね。CDプレイヤーもないので、父の趣味のレコードで、ほとんど1960年代70年代の歌謡曲を聞いてきました。今でも歌謡曲は好きですし、影響は受けてきたと思います。
姉弟と家で過ごす時間が多かったため、そんな時間をかわいそうに思った両親が唯一導入してくれたのがケーブルテレビでした。小学6年生の時にケーブルテレビで『ハンナ・モンタナ』を見始めたのをきっかけに、音楽やファッションといったアメリカのポップカルチャーの影響を受けるようになっていきました。
それ以前の日本のテレビドラマはイケメン俳優と美人俳優の組み合わせばかりで、「イケメンの俳優さんのドラマを見ていたら、自分のセクシュアリティがバレちゃう」と謎な考えを持っていて……。
子どもの頃に受け取った、同性愛への眼差し

佐久間:小学生の頃から「セクシュアリティがバレてしまう」と感じていたということは、ご自身のセクシュアリティには早い時から自覚があったんでしょうか。
中里:早かったと思います。保育園の時から仲良しの男の子と一緒にいたがっていましたし。父が「男は坊主、女はおかっぱ」という人だったので、自分は坊主頭だったんですけど、学童にあるスカートを履いて 「私、シンデレラ」と言いながら校庭を走り回ったりしていました。それは小学校低学年の頃までは、周囲から「かわいいオカマちゃん」という感じで扱われてはいましたが、小学3年生に上がる頃には、周りの子が異性や男女というものを強く意識し始めて、いろんな言葉を覚えていきますよね。自分は男の子に好意を持つことが多かったから、直感的に「自分はみんなと違うんだろうな、それを出すのは良くないんだ」とも思っていました。
佐久間:子どもに「バレたらまずい、良くない」と思わせる何かが社会にあったのではと思いますが……。
中里:どの世代にも共通しますが、テレビなどでは同性愛を笑いものにしたり、“異質なもの”という眼差しを向けられたりすることが多い。一緒に見ている家族も笑っているから、「同性愛は、笑われたり、バカにされたり、嫌われる対象である」というメッセージはさまざまなところでされる表象から受け取っていましたね。
「自分のセクシュアリティが悪いわけではない」

佐久間:コンテンツや表現に関わる道を選んだのはいつ頃ですか。
中里:中学生の頃に海外アーティストを好きになり、英語のセレブゴシップサイトの情報を翻訳して、どこよりも早く発信するブログをやっていたんです。当時は日本語でその類の情報を仕入れられるのが洋楽雑誌『イン・ロック』や『ゴシップス』だけで、毎月買っていました。雑誌の編集者になれば好きなアーティストに会えると考えて、英語・デザイン・コミュニケーションなどを勉強できる高校を選びました。
佐久間:翻訳は独学でされていたんですか?
中里:独学です。英語は辞書で調べたり、ブログ制作はHTMLで背景をデコったりしていましたね。ただ、ブログ運営会社がなくなってしまい、そのブログ自体は消えてしまいました。ネット上の情報は永遠に残ると言われていたけど、全く残らないこともあると痛感しました。
佐久間:もったいない! そのブログ、読んでみたかったです。中学生で編集者の道に興味を持ってから、どんな経緯で実際に出版社に勤めることになったんですか?
中里:高校2年生の時にある人を好きになり、自分のセクシュアリティにはっきり気付いた体験がありました。自分が幸せになれると思えずに絶望し、自暴自棄になって雑誌の編集者になる夢を1度諦めたんです。でも、中高生の頃に海外のコンテンツや海外アーティストの発信を見てきたおかげで、自分は決して一人じゃないし、自分のセクシュアリティが悪いわけではないとはわかっていたから、それを悪いと思わせる社会を変えたいと感じました。
高校3年生で性的マイノリティに関する課題について動画を作ったことをきっかけに、社会課題解決のプロセスを専門的に学びたくて、コミュニティデザインというまちづくりの学科がある山形の大学を選びました。 地域に関するリトルプレス/ZINEを作る課題がきっかけで、やっぱり自分は雑誌が作りたいし、海外にも行きたいと再認識しました。その大学には留学制度が充実していなかったので、働いて貯金をして海外に行こうと。大学を辞めた時にアルバイトした出版社で、初めて編集というものに近くで関わるようになりました。
佐久間:高校生の時に作った動画作品はどんなものだったんですか?
中里:同学年の30人くらいに、性的マイノリティについてどう感じるかを質問して、答えをスケッチブックに書いてもらったスライドショーのようなものだったと記憶しています。「(当事者の)あなたが考えるほど、みんなは変には思ってないよ」というメッセージを伝えたかったのと、自分でも安心したかったのもあると思います。
佐久間:社会を変えたいという意識が作品制作やコミュニケーションに繋がったんですね。
中里:中高生の頃は海外セレブからの影響が強くて、あんな風になりたいと思っていました。最初はマイリー・サイラスを好きになり、そこからレディーガガやワンダイレクション、ホットシェルレイやオールタイムロウなどのポップやパンクが好きになり、ガチで追っかけもしてたんです。海外のゴシップサイトをチェックし尽くしているから、いつどの便で日本に来るかがわかる。学校を休んで、ホテルの外で待機してました。
佐久間:高校時代の虎鉄さんが、自分のセクシュアリティが悪いわけではないと理解できたのは、マイリー・サイラスやレディー・ガガが表現していたようなことの影響でしょうか。
中里:当時は特にレディー・ガガが性的マイノリティのコミュニティをサポートする内容の発信をしていて、アライとして声を上げる姿にすごく励まされました。海外に行けば、自分のことを言葉にして肯定してくれる世界があることを知っていたから、日本がおかしいんだと。もちろん、当時仲良くしていた友達のサポートも大きかったと思います。
Photography Kotetsu Nakazato
Text Lisa Shouda
中編へ続く

