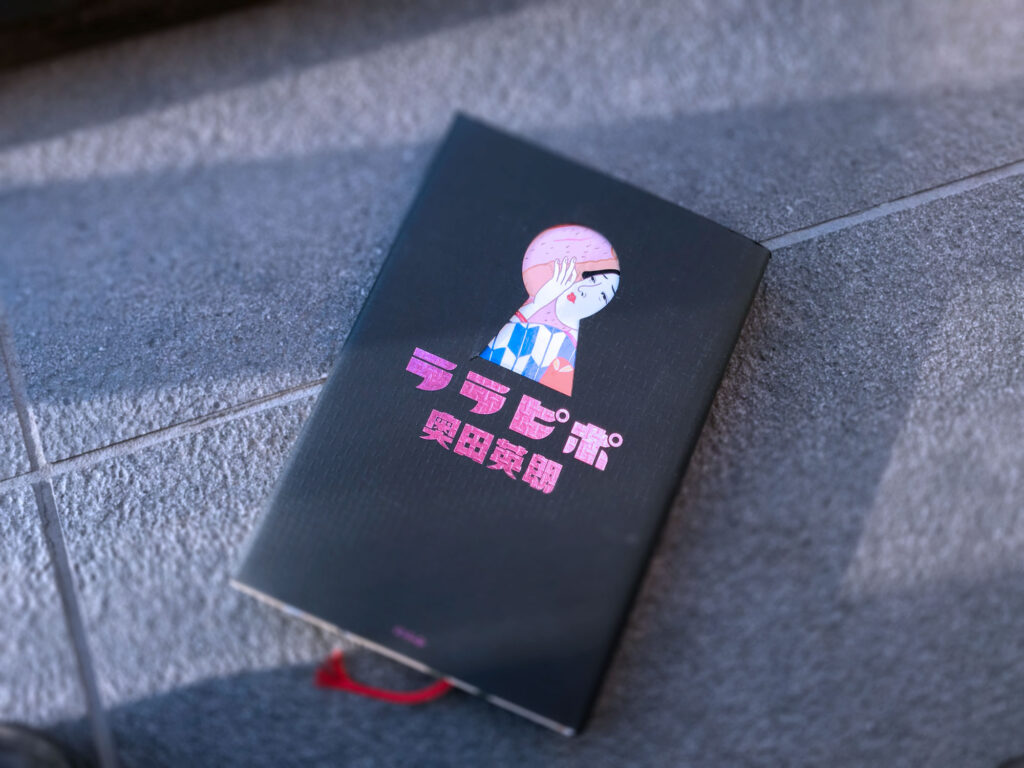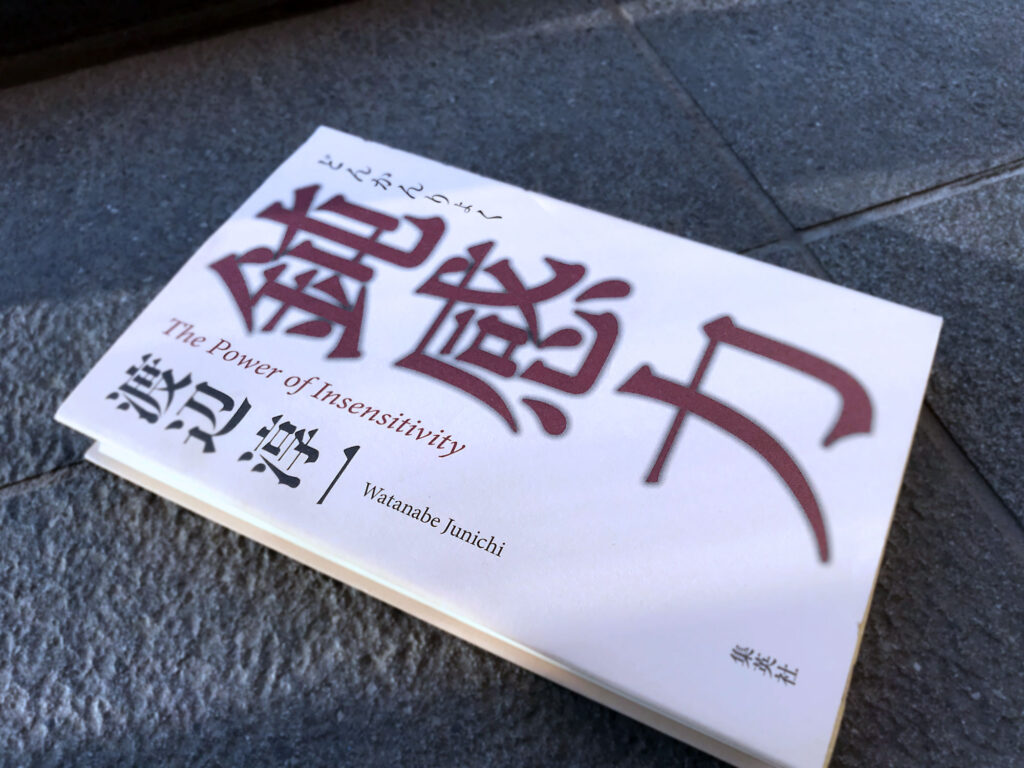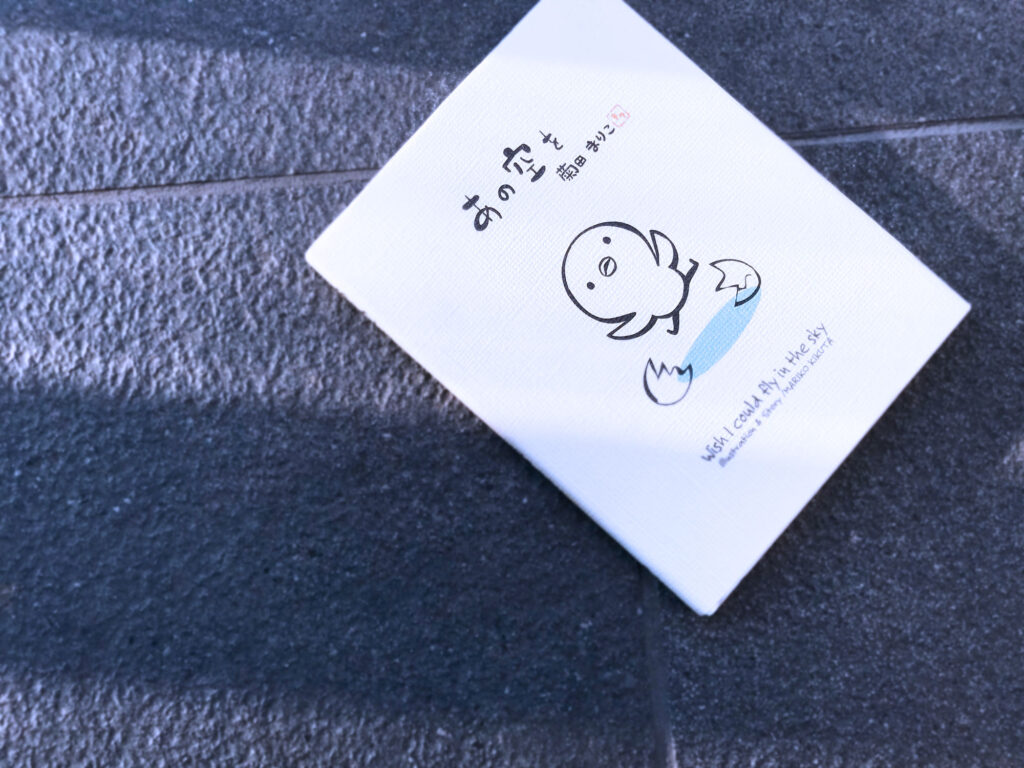「ものづくり」の背景には、どのような「ものがたり」があるのだろうか? 本連載では、『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら』(宝島社)、『タイム・スリップ芥川賞』(ダイヤモンド社)の作者である菊池良が、各界のクリエイターをゲストに迎え、そのクリエイションにおける小説やエッセイなど言葉からの影響について、対話から解き明かしていく。第2回のゲストはおもちゃクリエイターの高橋晋平。
「∞(むげん)のアイデア」の背後にある3冊の本とは
おもちゃクリエイターの高橋晋平さんは、バンダイ勤務時代に「第1回日本おもちゃ大賞」を受賞した『∞(むげん)プチプチ』をはじめとした数々の話題作を手掛けた後、2014年に独立。株式会社ウサギを設立し、全47都道府県の民芸品を戦わせ合う『民芸スタジアム』や、子どもから大人までキャリアについて気付きを得られる『職業診断ゲーム わくわくワーク』などユニークなおもちゃ・ゲームの企画・開発支援を手掛けるとともに、アイデア発想術に関する著書の執筆や講演を行うなど、多岐にわたりご活躍されています。
そんな高橋さんが提示したのは以下の3冊でした。
・奥田英朗『ララピポ』(幻冬舎)
・渡辺淳一『鈍感力』(集英社)
・菊田まりこ『あの空を』(学習研究社)
さて、この3冊にはどんな意味があるのでしょうか?
「小説」に対するイメージを覆してくれた、奥田英朗『ララピポ』
『ララピポ』は2005年発行の小説。フリーライター、スカウトマン、カラオケボックス店員など、6章6人を主人公にしたオムニバス形式の群像劇。著者の奥田英朗は1997年に『ウランバーナの森』でデビュー。2004年に『空中ブランコ』が直木賞を受賞し、映像化もされている。『ララピポ』も2009年に映画化。
──この本は奥田英朗さんの著書で、2005年に出版されています。いつ頃読んだのでしょうか?
高橋晋平(以下、高橋):出版されてすぐですね。社会人2年目の時です。人にもらったのですが、読み始めたら止まらなくなって。ぼくは夜早く寝たいタイプなんですけど、深夜の2時か3時まで一気に読みました。当時住んでいたアパートで「すげえすげえ」って独り言を言いながら。それで、奥田英朗さんの大ファンになりました。
──それまで小説は読んでいたのでしょうか?
高橋:ほとんど読んでいなかったんです。大学生の時はビジネス書やノウハウ本ばかり読んでいました。今の言い方だと「意識高い系」みたいな感じでしょうか。小学生の時は『ズッコケ三人組』を読むぐらいですね。しかも、好きなエピソードだけ何回も読むんです。そのくせは今もあるんですけど、ほかに小説は特に読んでいませんでしたね。でも、『ララピポ』をきっかけに奥田英朗さんの小説は全部読むぐらいにのめり込みました。
──ぼくも読んですごくおもしろかったです。この小説は6章に分かれていて、それぞれの章に主人公がいるオムニバス形式です。いわば短編が6つ入っている形ですね。
高橋:その形式がよかったんだと思います。短編なのが、非常に読みやすくて。高校の授業で夏目漱石の『こころ』とかやるじゃないですか? 小説ってそういうものだと思っていたんです。長くて難しいものだって。そしたら、この『ララピポ』は1章が簡潔で、コミカルで読みやすくて。あ、小説って短い話でもいいんだなと衝撃を受けたんです。しかも、1章読むだけでもおもしろいのに、2章、3章と読んでいくうちに、1章に張られていた伏線に気がつくという。こんなやり方があるのかとびっくりしました。
──いい意味で裏切られて、ハマったわけですね。
高橋:ほかの作品、『イン・ザ・プール』『空中ブランコ』なんかの精神科医・伊良部シリーズもすごく読みやすくて。読書が苦手な人間でも、ほんとうにつぎからつぎとおもしろい。読めば読むほど、奥田英朗って作風がすごく多彩で、どんどん憧れていきましたね。
──この本は装丁もすごくおもしろいです。表紙に穴があいていて、鍵穴の形になっているんですね。それが6人の人物の人生をのぞくっていう作品のコンセプトとも合致している。こういう仕掛けもなるほどなとぼくは思いました。
高橋:そうそう、鍵穴になっている。この本のあとにいろいろ玩具を学んでいく中で、「余白がある時はなんでも遊べる可能性を考えろ」みたいな考え方を知って。例えばお菓子のパッケージなんか、書けるスペースがあったら小ネタが書いてあったりするじゃないですか。動物ビスケットの箱の裏に動物の図鑑が載っているというような。この表紙を最初に見た時はなんとも思いませんでしたが、あとから考えると、こういう遊び心も大事なんだなって思いますね。
「対話」しながら読むことで自己認識を新たにした、渡辺淳一『鈍感力』
『鈍感力』は2007年発行のエッセイ。さまざまなエピソードを引きながら、人間は鈍感力があるほうが生きやすいと説く。「鈍感力」は流行語にもなった。著者の渡辺淳一は多数の著作がある小説家。1970年に『光と影』で直木賞を受賞。ほかに『失楽園』『愛の流刑地』など。
──続いて挙げていただいたのは渡辺淳一さんの『鈍感力』です。
高橋:この本もすごく衝撃を受けました。ぼくはどっちかと言うと、繊細な人間だと思うんです。すぐ傷つくし、ちょっと痛いと不安になるみたいな。だから、今も鈍感力に憧れているんです。この本って今で言う「繊細さん」みたいなことで悩んでいる人にぶっ刺さったんだと思うんですよ。この本の中に、確か蚊に刺された時も敏感なやつよりも鈍感なやつのほうが強いという話があったと思うんですが。
──ありました。
高橋:それがまず衝撃で、めちゃくちゃ腑に落ちる。わかりやすい。その後、この本ってずっと鈍感な人のほうがいいって言い続ける構造ですよね。
──そうですね。手を変え品を変え、著者がいろんなエピソードを引き合いに出して鈍感なほうがいいと。
高橋:短いエピソードで、わかりやすいのにすごく納得感もある。こんなシンプルで短くてわかりやすいってすごいなと。奥田英朗さんの時もそうですが、この本を読む前もまだビジネス書って長くて内容が充実していて、書いてあることもかっこいい、そういうのがすごい本だと思っていたんですが、その先入観がぶっ壊されました。それに自分でそれまでのことを振り返りながら、自分なりに解釈して読むことができたっていうのが、すごく味わい深かった記憶があるんです。
──本と初めて対話ができた。
高橋:その感じを初めて得られたんです。これを読んだのって社会人3年めの暮れか、4年目ぐらいで、それまでは「本に書いてあることは絶対」って思っていたんです。でも、この本は読みながら「鈍感力めっちゃおもしろいし、めっちゃほしい!」と思いながらも、「いやいや、そんなわけないだろ……」とちょっとツッコミながら読むみたいな。ある意味対話しながら読めたことで、それで自分に自信が持てたというか、自分を肯定できたような感覚だったんですね。すごくよく覚えています。
──この本が出たのは2007年で、『ララピポ』の2年後ですね。
高橋:2007年ってぼくがバンダイにいた時で、『∞(むげん)プチプチ』というおもちゃを発売した年だったんです。「シンプルで簡単でわかりやすいものってすごいよね」みたいな考え方がいろいろとハマって、ヒット商品になりました。そういった価値観が強く受け入れられたタイミングだったのかもしれません。
──確かにこの本は『鈍感力』とタイトルが短いのに、言いたいことはこれだけでドカンと伝わってきますよね。
高橋:普通はもっと長いタイトルにしたくなっちゃいますよね。もっとわかりやすくって考えちゃうと。ぼくも本を書く時はついそう考えちゃうんです。タイトルで1人でも多くつかむみたいな。僕には、簡単、短い、シンプルへの憧れがあって、この本のチョイスにもそれが反映されている気がしますね。うん、偶然だけど。
──『鈍感力』は3文字。奥田英朗さんの『ララピポ』もわずか4文字ですね。
高橋:うん、そうですね。『ララピポ』は一見意味がわからないんですけど、いいタイトルですよね。
折にふれ読んでは泣く、菊田まりこ『あの空を』
『あの空を』は2004年発行の絵本。空を飛ぼうとする小鳥を描いた作品。菊田まりこは絵本作家。1999年、デビュー作でもある『いつでも会える』がボローニャ国際児童図書展のボローニャ児童賞・特別賞を受賞。ほか著作多数。
──3冊めは菊田まりこさんの『あの空を』。こちらは絵本ですね。
高橋:はい。たぶん時系列で言うと、これが一番最初に読んだ本ですね。菊田まりこさんの絵本との出会いは大学時代で、その時にインフルエンザにかかって病院に行ったんです。そしたらその病院に菊田まりこさんの絵本があって。インフルエンザにかかって、高熱出ている中なのに、菊田まりこさんの『いつでも会える』という絵本を読んで号泣したんですよ。なんでその絵本を手にとったのかわからないんですけど、「すごい、こんな泣ける絵本があるのか」って驚いて。
それでほかにも菊田まりこさんの絵本を読んでみたんです。シリーズが4冊あって全部買いました。『あの空を』もそのうちの1冊でめちゃくちゃ泣いたんですよ。どういう心境だったのかわからないんですけど、泣いちゃって。社会人になってからも折にふれて読んでは泣いていたんです。自分の人生と重なったんでしょうね、きっと。
──この本もシンプルな短いことばと、それと絵で構成されていますね。
高橋:そう、文字はほとんど載ってないですよね。この絵本にひよこが出てきて、空を飛ぶ練習をするじゃないですか。そもそもそのひよこが大人になったら空を飛べるタイプの鳥なのか、飛べないタイプの鳥なのか気になっていたんです。それによって意味合いがめちゃくちゃ変わってくると思うんです。
──その視点は気付きませんでした。確かに変わりますね。
高橋:うん。そうなるとかなわない夢をいつかかなうと思って夢を追っていることになって、全然変わる。
ぼくは初めて読んだ時に飛べない鳥だと思って、その後の何年間かはずっとそう思っていたんです。飛べないけど、一生懸命頑張っていつか飛ぼうとしていると思うと、もう泣けてしかたないみたいな。それからしばらくして久しぶりに読んだら、「あれ? ひょっとしたら飛べるのかな?」と思ったりして、また解釈が変わったんです。
──読む時期によって見方が変わったんですね。
高橋:はい。ぼくは大学時代に落語研究会に入っていたんですけど、お笑いが好きでM-1グランプリも毎年心待ちにしているんです。で、誰が優勝しても感動するんです。結果が出るかわからないことに対して頑張り続けている人へのリスペクトが強くて。
お笑い芸人さんや漫画家の方とかもそうですけど、ひょっとしたら一生結果が出ないかもしれない世界で結果を出そうと努力している人を見ると、もうほんとうに感動してしまうんです。
ぼくほんとうは嫉妬深い性格なんですけど、そういう世界で成功している人を見ると、ほんとうに嬉しい気持ちになるというか。とにかく素晴らしいなと尊敬するんです。
──M-1グランプリは4分の漫才ですべてが決まるとても厳しい世界ですよね。
高橋:だからやっぱり短くて強いものへの憧れをすごく持っているんだと思います。長さや時間、ボリュームが短いものへの。漫才なんて、始まってすぐ笑わせて、5分ほどできれいにオチをつけるという。自分がつくるおもちゃでも、すぐにルールがわかってサッとやれるものを作りたいと思っています。たださわるだけなのに笑っちゃうとか。うん、偶然ですけどなんだかぜんぶつながったような気がします。
話すことで見えた3冊の共通点
小説、エッセイ、絵本と3冊のジャンルはバラバラでしたが、そこに「短いこと」「シンプルなこと」「インパクトがあること」という共通点があることがわかりました。高橋さんはおもちゃクリエイターです。高橋さんが手掛けるおもちゃを見ていて気持ちいいのは、やはりひと目で楽しいことが伝わるからでしょう。話の中にも出てきた『∞(むげん)プチプチ』。その形状と名前を見れば、即座にどう楽しんだらいいのかわかります。このような直感に訴えかけるクリエイティブへの指向が、高橋さんのつくるものや選ぶ本からもうかがえます。

高橋晋平
1979年生まれ。おもちゃクリエイター、株式会社ウサギ代表。東北大学大学院情報科学研究科修了後、2004年に株式会社バンダイに入社。第1回おもちゃ大賞を受賞した『∞(むげん)プチプチ』や『∞エダマメ』、『瞬間決着ゲームシンペイ』など数々のヒット商品の企画・開発を手掛ける。2014年に株式会社ウサギを設立し、代表取締役に就任。『民芸スタジアム』『THE仮想通貨』『職業診断ゲーム わくわくワーク』などの企画・開発を担当。著書に『アイデアが枯れない頭のつくり方』(2014年、 CCCメディアハウス)に、『一生仕事で困らない企画のメモ技(テク)』(2018年、あさ出版)など。
Twitter:@simpeiidea
note:https://note.com/simpeiidea