
第62回グラミー賞にノミネートされたコンピレーション・アルバム『Kankyo Ongaku: Japanese Ambient, Environmental & New Age Music 1980-1990』(2019年)が象徴するように、近年、1980年代の日本の環境音楽にあらためて注目が集まっている。そうした中でもひときわ異彩を放つのが、1983年に30歳で夭折した芦川聡の存在だろう。現代音楽やマリー・シェーファーのサウンドスケープ理論などを吸収しながら独自の「風景としての音楽」を提唱した彼は、単に穏やかで控えめなサウンドの音楽を手掛けたのではなく、生活空間で実用化し得る音のデザインも企図し、82年に自社を設立。翌83年、株式会社サウンド・プロセス・デザインを立ち上げた直後に悲劇が訪れた。だが芦川の没後も同社の活動は田中宗隆が引き継ぎ、文化施設や商業施設、交通機関などの音のデザインを手掛けていく。そしてそこで活動したサウンド・デザイナーの1人が広瀬豊だった。
広瀬は1986年、ミサワホーム総合研究所サウンドデザイン室が企画した「サウンドスケープ」シリーズから、唯一の音楽アルバム『Nova』をリリースしていた。長らく廃盤状態が続いていたものの、アンビエント再評価の機運も手伝い、2019年にスイスのレーベル〈We Release Whatever The Fuck We Want〉から未発表音源を加えて復刻。高田みどり『Through The Looking Glass』(1983年)や吉村弘『Music For Nine Post Cards』(1982年)等々と並ぶ重要作の再発は大きな話題を呼んだ。そしてこのたび、そのような広瀬による実に36年ぶりとなるセカンド・アルバム『Nostalghia』が完成したのである。
7曲収録のCDと9曲収録の2枚組LPでアルバム化された『Nostalghia』には、『Nova』発表後の活動、すなわち1987年から91年にかけて空間の音のデザインのために制作された音源を元に、新たに編集し直したサウンドが収録されている。その意味では貴重なアーカイヴであると同時に全く新しい音楽作品であるとも言える。前後編に分けてお届けするインタビューの前編では、『Nova』以降の制作手法の変化、その背景にあるフリー・インプロヴィゼーションやフリー・ジャズの体験などについて話を伺った。
記譜された音楽から即興演奏を用いた制作へ

——今作『Nostalghia』に収録された音源は、1986年の『Nova』リリース後、87~91年にレコーディングされています。当時はどのような狙いがあったのでしょうか?
広瀬豊(以下、広瀬):もともとは立体音響のための作品として制作しました。音楽的なものはすべてやめて、空間で音を構成していこうと思ったんです。『Nostalghia』は左右2チャンネルの音楽としてアルバム化していますけど、当時はミックスしていない状態で8チャンネルぐらいあって、それらバラバラの音源を博物館や科学館の空間でランダムに流して音を構成していました。特定の施設の中で流すための、恒に変化する音として制作したんですね。だから当時はステレオで聴く音楽とは全く考えていなかったです。あくまでも記録として、後になってから2チャンネルにミックスしておいただけで。
——ミサワホームの環境音楽シリーズ「サウンドスケープ」の一環として出された『Nova』にも空間で流すための音楽というコンセプトがありましたが、そこからどのような変化がありましたか?
広瀬:『Nova』の時は譜面を用いて制作しながらパソコンで1つひとつ打ち込みをしていました。その後のミックスの段階で自然音と混ぜて空間構成していくことを考えていたんですが、『Nostalghia』では譜面やパソコンの打ち込みは使わず、インプロで音を配置していったんです。例えば即興的に奏でたメロディやフレーズをいくつも録音し、それぞれの音の塊を「群」として捉え、そこから使用する「群」を持ってきて継ぎ接ぎするように構成していきました。
——なぜ、そういったアプローチに変化したのでしょう?
広瀬:もともと即興的な音楽が好きだったというのもありますが、パソコンの打ち込みで作るとものすごく時間がかかってしまうんですね。人生が終わってしまうんじゃないかと思うぐらい(笑)。だったらとにかく自分の手で弾いてしまって、そこからセレクトして組み合わせていったほうが早いんじゃないかと考えるようになったんです。それに、そのほうが音作りの自由度がすごく増すんですよ。譜面に書いて決めてしまうのではなく、まずは音を出して、この音色とあの音色を合わせたらどうなるだろうとか、片方にはAというエフェクトをかけてもう片方にはBというエフェクトをかけて、それらを組み合わせて少しズラすと変な音色ができるとか、そういったことを自由に試しながら作っていったアルバムなんです。
それと『Nostalghia』では、とにかくメロディをどこかに追いやって、音響的なものに変えていきたいという志向がありました。メロディがあると聴く人はそれに囚われてしまうじゃないですか。なのでいかに音を塊として空から俯瞰するような形で提示できるのか、もしくは音の中に聴く人が入り込めるような形にできるか、そういった音響への志向が強くありました。
——即興演奏で制作することは、そうしたおもしろい音色を生み出すという点でもメリットがあったのでしょうか?
広瀬:そうです。僕の場合はまず低音で下敷きを作って、そこに倍音をどんどん積み重ねていって、最終的に高音を入れていくという組み合わせで作っていました。そうしたことを考えると、音色をいかに作るか、その音色によって自分がどう弾くかが重要で。自分の演奏は音色に引っ張られていく、言い換えると音色が演奏をリードしていくんですよ。それをパソコンの打ち込みでやるとなると、まず譜面に書かなければいけないので、そういった音色のおもしろさがなかなか出てこないんですよね。それよりも器楽的な要素が前面に出てしまう。シンセを使っても楽器っぽくなってしまうんです。そうではないやり方で制作したいと思って即興演奏に取り組んでいました。
デレク・ベイリーの音色に魅了された10代
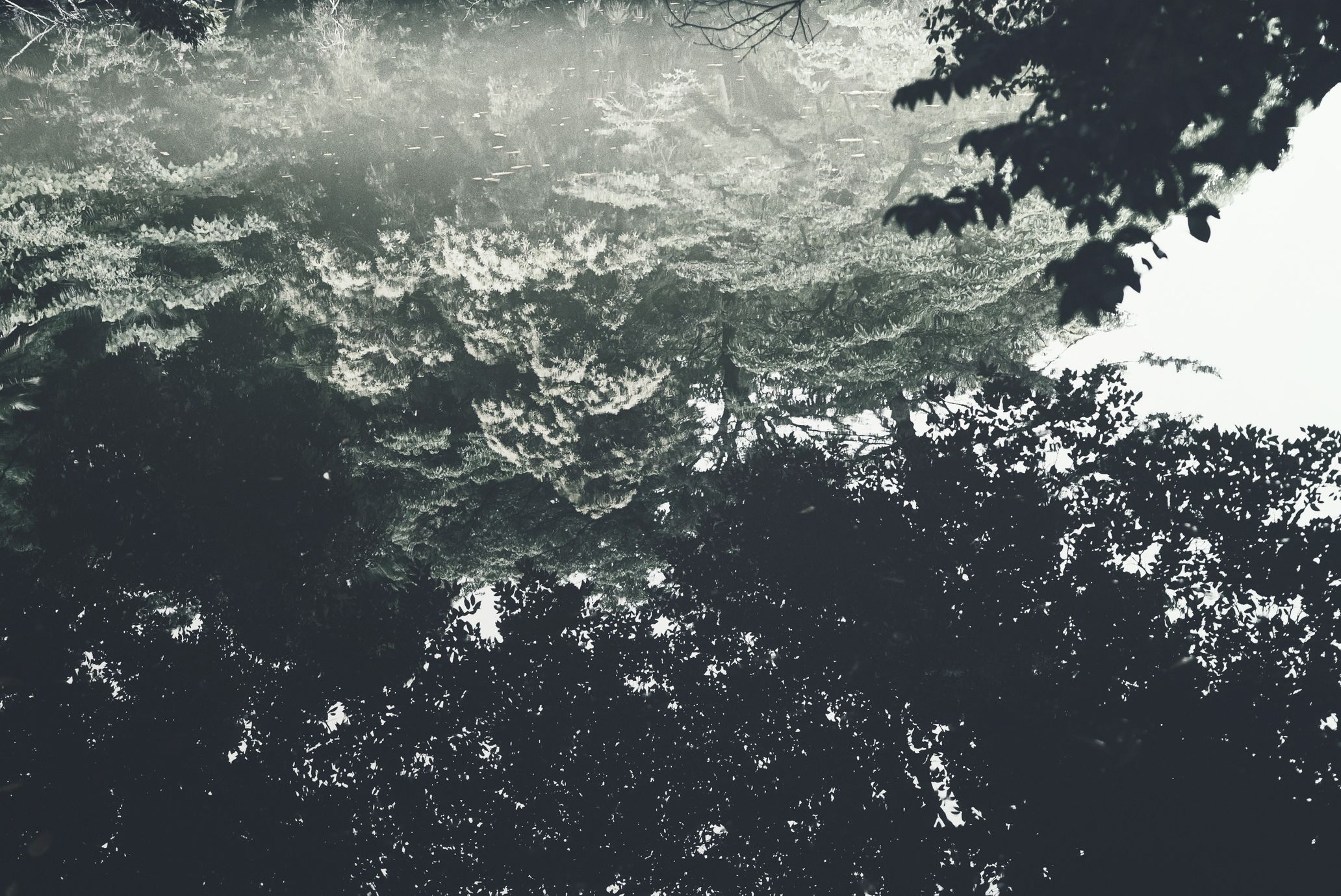
——先ほど「もともと即興的な音楽が好きだった」と仰っていましたが、具体的にはどのようなミュージシャンや作品が好きでしたか?
広瀬:やっぱり〈インカス〉レーベルの作品、デレク・ベイリーやエヴァン・パーカー、トリスタン・ホンジンガーあたりは好きでよく聴いていました。それとアンソニー・ブラクストンも好きですね。10代の時にベイリーの『Lot 74 – Solo Improvisations』(1974年)を聴いて、『MMD計画(田中泯、ミルフォード・グレイヴス、デレク・ベイリー)』での来日公演(1981年)にも行ったんです。
ベイリーのライヴは非常におもしろかったですね。「こういったハーモニクスの使い方があるのか」と感銘を受けて、すごく楽しめました。初めて聴いた時から拒絶することなく素直に入り込めたんです。その後に来日したエヴァン・パーカーの日本青年館での公演(1982年)も素晴らしくて、循環呼吸奏法を交えた無伴奏のサックス・ソロを「気持ちいいなあ」と思いながら延々と聴いていました。お客さんは全然入っていなかったですけど(笑)。
——ベイリーの音楽にアンビエント的なものを感じたことはありましたか?
広瀬:やっぱり音色が魅力的で、点と点を絡める彼のアプローチは別にアナーキーな感じはしなくて、むしろ僕の中ではアンビエントっぽい感じがしています。僕はどちらかというといわゆるアンビエント・ミュージックはあまり聴いていなかったんです。高校生の頃から〈ECM〉の作品を聴き始めて、そのあとはフリー・ジャズに興味を抱くようになっていったので。
——〈ECM〉は1969年に設立されて、当初はベイリーをはじめ尖った作品も多かったですが、70年代を通じて耽美的なレーベル・サウンドを確立していきました。どの時期の作品が好きでしたか?
広瀬:ベイリーとデイヴ・ホランドのデュオ(『Improvisations for Cello and Guitar』1971年)やブラクストンが参加したチック・コリアのサークル(『Paris Concert』1971年)も好きでしたけど、〈ECM〉だと実はエバーハルト・ウェーバーやスティーヴ・キューンが非常に好きで。音色も魅力的ですし、単純に音楽的にきれいだったから聴いていたところもあります。
〈ECM〉の作品の多くは盛り上がりが少ないので、空間的に捉えることもできるんです。空気の流れのように聴くことができるというか、感情を入れ込まずに音として楽しめるんですよね。「ここが聴きどころですよ」という決めつけがないので、いろいろな聴き方ができる可能性があって。〈ECM〉の作品を通じて音の聴き方の自由度はかなり変わりましたね。
制作時にはフリー・ジャズの構造も意識した

——角田俊也さんのライナーノーツによれば『Nostalghia』の制作では「フリー・ジャズの構造を意識した」とのことですが、具体的にはどのような構造だったのでしょうか?
広瀬:一番わかりやすく表れているのは1曲目の「Seasons」です。あの曲はほとんどフリー・ジャズ方式と言いますか、いわば即興演奏の塊なんですね。いろいろな細かい要素を散りばめて、変化していないようなのに最初と最後では全く異なっているという構造になっていて。例えばアルバート・アイラーの『New York Eye and Ear Control』(1966年)とかドン・チェリーのいくつかのアルバムとか、そのあたりの構造をものすごく意識して制作しました。
それと実は即興音楽以上に好きなのが現代音楽で、ヤニス・クセナキスやカールハインツ・シュトックハウゼンをよく聴くんですけど、シュトックハウゼンの「群作法」という技法があるんです。トータル・セリエリズムで管理する構成単位を個々の音ではなくて「群」、つまり音の塊に適用して、それをいくつも用意して散りばめながら変化させていくというような技法です。そうしたアプローチやフリー・ジャズの構造を意識したことなどについて、角田さんと話しました。
——フリー・ジャズといえば、広瀬さんは以前、高校時代に富樫雅彦さんのアルバムが好きでよく聴いていたと仰っていましたよね。
広瀬:そうです。たしか『スイングジャーナル』を読んでいた時に、洋モノだけでなくたまには日本のジャズも聴いてみようと思って、最初に手に取ったのがたまたま富樫さんのアルバムでした。そしたら大当たりで。『Spiritual Nature』(1975年)や『Guild For Human Music』(1976年)、『Essence』(1977年)あたりをよく聴いていました。富樫さんの音楽は響きが東洋的というか日本的なんですよね。それが気になったのと、ドラムやパーカッションがまるで水滴のようにポコポコと鳴っている持続感もものすごく気持ちよくてハマってしまいました。
——日本のフリー・ジャズと言えば、他にも山下洋輔さんや高柳昌行さんなどもいますが、そのあたりはいかがでしたか?
広瀬:山下洋輔さんは聴いていました。けれど当時は高柳昌行さんまでは辿り着かなかったです。僕が聴いた限りではラジオから流れてくることもなかった。たまたま出会うことができた音楽を聴いていました。
——1980年代になると、菊地雅章さんや鈴木良雄さん、清水靖晃さんのように、ジャズの文脈からアンビエント的なサウンドに取り組むミュージシャンも出てきましたが、そのあたりはいかがでしょうか?
広瀬:当時は知りませんでした。出会うきっかけがなかったんですね。
広瀬豊
サウンド・デザイナー。1961年生まれ、山梨県甲府市出身。1986年にミサワホーム総合研究所サウンドデザイン室が企画した「サウンドスケープ」シリーズから、アルバム『Nova』をリリース。同年に、芦川聡が設立した株式会社サウンド・プロセス・デザインに参画し、文化施設や商業施設などで流れるサウンドの制作を手掛ける。2019年にスイスのレーベル〈We Release Whatever The Fuck We Want〉から未発表音源を加えて『Nova』がリイシューされ、世界的に話題を呼んだ。2022年5月に36年ぶりとなるセカンドアルバム『Nostalghia』をリリース。7月1日に〈We Release Whatever The Fuck We Want〉からサードアルバム『Trace: Sound Design Works 1986-1989』がリリース決定。

