
映画「マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)」シリーズとそこで使用されているポップミュージックの関係性について解説した『マーベル・シネマティック・ユニバース音楽考 映画から聴こえるポップミュージックの意味』(イースト・プレス)が出版された。本書は、映画評論家の添野知生と音楽ジャーナリストの高橋芳朗による対談をメインに、MCUシリーズのフェーズ1〜3の23作品で使用された140曲以上のポップミュージックの背景や選曲意図を徹底的に考察しており、映画と音楽の関係性についてより理解が深まるとともに、映画の楽しみ方を拡げてくれる1冊となっている。
今回、映画におけるポップミュージックの役割、そしてMCUが映画界に与えた影響などを、著者の添野と高橋に語ってもらった。後編では、MCU以外の作品をメインに、その映画監督による音楽の使い方について。
ポピュラー・ミュージックと映画の関係を振り返る3作品

——本の中で添野さんが、ポピュラー・ミュージックと映画の関係を振り返るうえで重要な作品として『アメリカン・グラフィティ』(1973年)、『グッドフェローズ』(1990年)、『パルプ・フィクション』(1994年)を挙げています。なぜ、この3作品なのでしょう。
添野知生(以下、添野):(『アメリカン・グラフィティ』を監督した)ジョージ・ルーカスの世代、つまり1960年代末に大学の映画学部を出てからハリウッドに入った世代が出てくるまでは、ジョン・フォードとか1940~50年代の巨匠がまだ普通にハリウッドで映画を作っていたんです。そこに初めて、ルーカスのように学生の時にビートルズやローリング・ストーンズを聴いて育ったロック世代の若者が映画を作るようになった。自分達の話をするんだったらロックは絶対使うっていう、意思表示をし始めたんです。『アメリカン・グラフィティ』という映画は、その良い例だと思います。それまで、ポピュラー・ヒット曲をあれだけまとめて使うっていう映画はなかった。こんなことをしていいんだっていうショックがあったと思うんですよね。
——『アメリカン・グラフィティ』の公開時の宣伝文句は「1962年の夏、あなたはどこにいましたか?」。1962年という物語の世界観を作り上げるために、当時のヒット曲は欠かせないものですね。
添野:そうなんです。それに比べて『グッドフェローズ』の曲の使い方はDJっぽいというか。
高橋芳朗(以下、高橋):確かに、マーティン・スコセッシはそういうところがありますよね。例えば『ミーン・ストリート』(1973年)はロネッツの「Be My Baby」で始まって、ロバート・デ・ニーロが登場するシーンではローリング・ストーンズの「Jumping Jack Flash」が流れますが、歌詞や時代との整合性よりも映像と音のケミストリーを重視した選曲です。そういったスコセッシの選曲術の真骨頂と言えるのが、『グッドフェローズ』の「1980年5月11日、日曜日」のシークエンス。ストーンズやザ・フー、ジョージ・ハリスン、ニルソンなどの曲をぶった切ってつないでいく手法はまさにDJ的でしょう。
添野:あのシーンの音楽の使い方はすごかったですね。何が起きているかわからないけど、観客の血圧がどんどん上がっていく。
高橋:スコセッシが使うのはよく知られている曲ばかりですが、とにかく曲が秘めた暴力性みたいなものを引き出すのが抜群にうまい。例えば『グッドフェローズ』のクリーム「Sunshine of Your Love」が流れるシーン。デ・ニーロの視線と曲だけで完璧に殺意を表現しています。あのおなじみのイントロをあれだけフレッシュに鳴らせる手腕はすごいですね。
添野:『ニューヨーク・ストーリー』(1989年)というオムニバス映画でスコセッシが撮った作品(『ライフ・レッスン』)では、ニック・ノルティが演じる画家が、アトリエでプロコル・ハルム「A Whiter Shade of Pale(青い影)」を大音量でかける。それを聞いて、この曲ってこんなに暴力的な曲だったのかと思いました。曲の持っているブルース的なところが伝わってきたんです。スコセッシは普段からそういう発見を引き出しに入れていて、映画で使っているんじゃないかと思いますね。
——スコセッシの選曲は大体、1960~70年代。守備範囲は狭いですが曲の使い方を熟知していますね。精神病院を舞台にしたサスペンス『シャッター・アイランド』(2009年)では、不安を煽るような現代音楽の曲を使っていて音楽の使い方がわかりやすい。『パルプ・フィクション』を手掛けたクエンティン・タランティーノはいかがですか?
高橋:スコセッシと同じくDJ的ですよね。やはり映像と音のケミストリー重視、グルーヴ重視の選曲が多い印象です。
添野:歌詞と物語のつながりはほとんどない。そこはジェームズ・ガンとの大きな違いだと思います。
ソフィア・コッポラ、ウェス・アンダーソン、ポール・トーマス・アンダーソンの音楽

——タランティーノは映画自体もDJ的というか、過去の映画のイメージをタランティーノ・ミックスで再構築しているようなところがありますね。タランティーノ以降の監督では、ソフィア・コッポラやウェス・アンダーソン、ポール・トーマス・アンダーソン(PTA)といった監督達が既発曲を巧みにサントラに使っています。
高橋:PTAは、例えば『ブギー・ナイツ』(1997年)の音楽の使い方に関しては完全にスコセッシ的ですよね。ウェス・アンダーソンは使える曲とそうでない曲とが自分の中で明確に線引きされているように思います。
——ウェス・アンダーソンの場合は、作品というより、自分の感性に合う合わないで曲を選んでいるようにも思えます。ある意味、セレクトショップ的というか。
高橋:確かに。ジョン・レノンだったりヴァン・モリソンだったり意外と有名アーティストの曲を使うことが多いですが、自分の世界観にフィットする楽曲を的確に選び出してきますよね。
——ソフィア・コッポラもそういうところがあるのではないでしょうか。監督の作家性が反映されているから、どのサントラもトーンが似ている。彼らに比べるとPTAのサントラは、映画に密着している気がしますね。『リコリス・ピザ』(2022年)のサントラは『アメリカン・グラフティ』みたいに物語の世界観を作る大きな役割を果たしていました。
高橋:収録曲の大半をすでに別の形で持っていたとしても、これはこれでサウンドトラックとして所有しておきたくなりますね。『リコリス・ピザ』は『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(2019年)の選曲から微妙に影響を受けているような節もあります。
——こうして話を伺っていくと、MCUのサントラのユニークさが浮かび上がってきますね。曲の背景や歌詞の内容を理解したうえで、選曲に意味を持たせていく。それが1人の監督の主義ではなく、映画会社の方針になっているというのがおもしろい。
高橋:それはテムズによるボブ・マーリー「No Woman No Cry」のカヴァーとケンドリック・ラマー「All Right」をコラージュした『ブラックパンサー:ワカンダ・フォーエヴァー』(2022年11月公開予定)の予告編でも徹底されていました。もはやポップミュージックの巧みな引用がMCU作品の大きな「売り」になっていますよね。
添野:それはやっぱり、ケヴィン・ファイギっていう統括責任者が許しているというか、奨励しているからじゃないかなって思うんですけどね。
——ケヴィンさんは音楽好きなんでしょうか?
添野:ケヴィン本人の趣味嗜好や生い立ちのわかる情報はほとんど出てなくて。ただ、MCUっていうシリーズを特異なものにしているのは彼の個性だと思います。音楽の使い方とか、作品に社会的な意味を持たせることとか、全部彼が考えているんじゃないでしょうか。
音楽が印象に残っているシーンは?
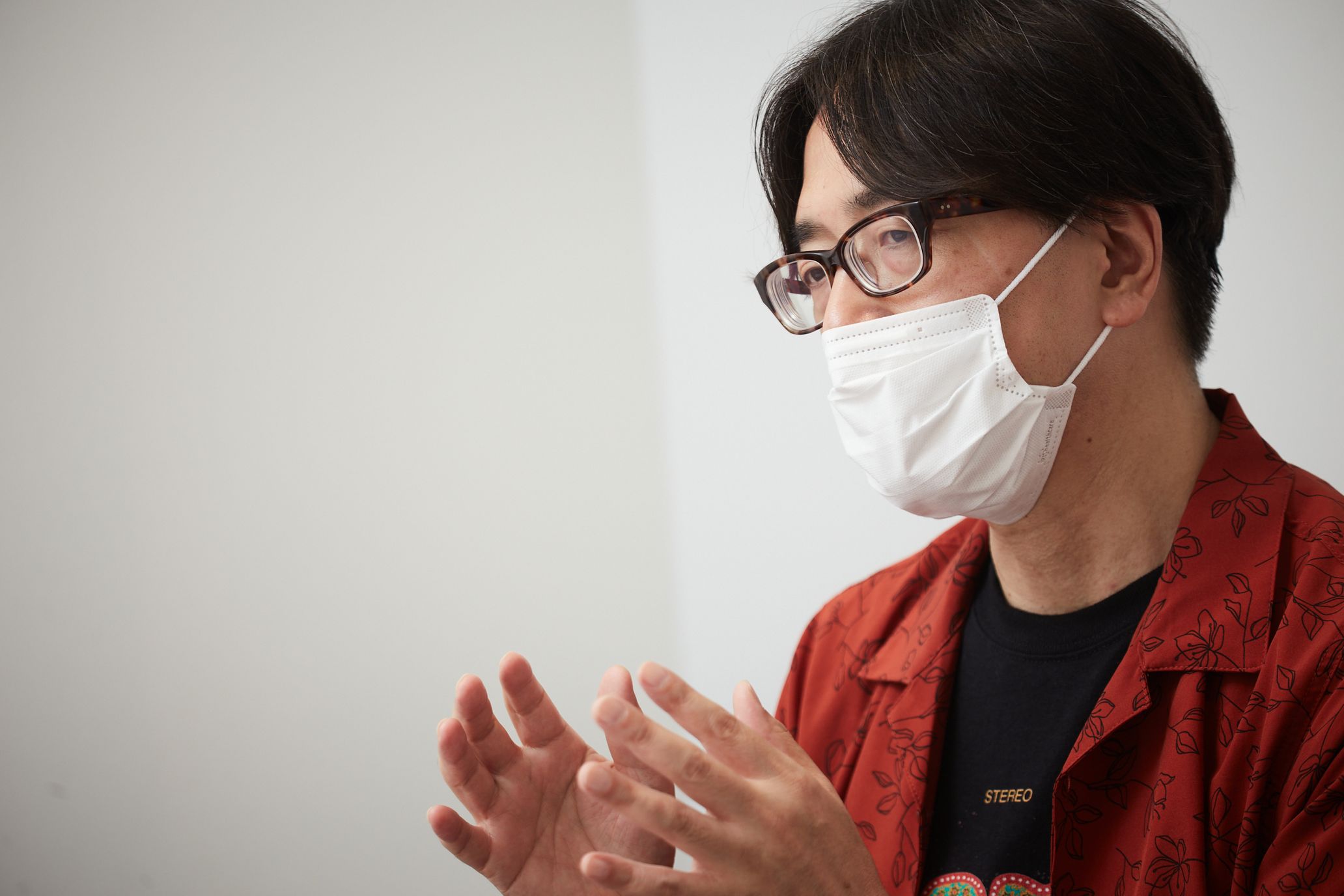
——ケヴィンさんにもプレイリストを作ってほしいですね(笑)。ちなみにMCU以外の映画で、音楽が使われたシーンで、お2人の印象に残っているものってありますか?
高橋:パッと思いつくものとしては、シャーリーズ・セロン主演の『タリーと私の秘密の時間』(2018年)。ワンオペ育児でノイローゼになったセロン演じる主人公が現実から逃れようとモラトリアム期を過ごしたマンハッタンに車で向かう際、車内でずっと青春時代に聴いたシンディ・ローパーの『She’s So Unusual』を流しているんです。要はこのアルバムが過去に立ち返るタイムマシン的な役割を果たしているわけですが、断片的ではあるものの『She’s So Unusual』の収録曲がほぼすべてかかるんですよ。
添野:それはすごい!
高橋:『ザ・ロイヤル・テネンバウムズ』(2001年)でストーンズの『Between the Buttons』のレコード片面ほぼ全曲かかるシーンがありますが、それを超える大胆な選曲ですね。監督のジェイソン・ライトマンは『ヤング≒アダルト』(2011年)でもシャーリーズ・セロンを主演に起用しているんですけど、そこでも似たような音楽の使い方をしていて。セロン演じるヒロインがハイスクールの同窓会に向かう車中でティーンエイジ・ファンクラブの「The Concept」だけを当時のカセットテープでひたすら繰り返し聴いているんです。きっとあれも彼女にとってタイムマシン的な装置として機能しているんでしょうね。
添野:ライトマンみたいにポップスやロックに詳しい監督が、自分の生活に密着した形で映画を作ることが最近増えてきましたね。ポール・ラッドがレコード会社のオーナーをやっている主人公を演じた『40歳からの家族ケーカク』(2012年)もそうだったけど。
高橋:落ち目のミュージシャンとしてグレアム・パーカーが本人役で出てくるんですよね(笑)。
添野:おもしろいですよね(笑)。僕は最近、ジャック・リヴェットの『メリー・ゴー・ラウンド』(1981年)という映画を見たんですけど、お金が切れて明日のフィルムがない、みたいな現場で撮ったので話はつながっていないし、途中でメインキャストの俳優が入れ替わってしまう変な映画なんです。それで話がうまく繋がらないところに、必ずジョン・サーマンというフリー・ジャズのサックス奏者とバール・フィリップスというベーシストが出てきて2分くらい演奏するんですよね。そうすることで映画が成立している。こんな映画の作り方があるのか!って驚いたんですよ。
高橋:やっぱり、2人の演奏は即興なんですか?
添野:そうですね。演奏シーンが出るたびに笑っちゃうんですよ。あ、また話が飛ぶなって。
——それって、あの映画みたいですよね。ジョナサン・リッチマンが出てくる……。
高橋:『メリーに首ったけ』(1998年)ですか?
——そうです!
添野:はい、そんな感じです。『メリーに首ったけ』のジョナサン・リッチマンも良かった。
高橋:ファレリー兄弟も音楽の趣味が良いですもんね。
——日本でも音楽にこだわった映画が出てきてほしいですね。
高橋:おそらく使用料の問題からだと思いますが、現状ワンポイントで使うケースが多いですよね。『紙の月』(2014年)でのヴェルヴェット・アンダーグラウンド「Sunday Morning」だったり。
添野:あれは大冒険でしたね。でも、日本ではロックの曲をいろいろ使ったとしても観客がピンとこない、というのもあると思います。ロックがまだ文化として日本に根付いていないので。歌謡曲をうまく使った映画は過去にもいろいろあったと思いますが。
——日本にロック文化が根付いていない、というのは大きいですね。ロックを題材にした映画の多くが、青春映画みたいな描かれ方から逃れられていないですし。だからこそ、ロック好きが喜ぶサントラを日本映画で作ってほしいですね。
高橋:スコセッシみたいなことをやりたい監督もきっと大勢いると思うんですけどね。Netflixオリジナル作品とかで実現しないかな?
添野:ほんと、そうですよね。既発曲がサントラに使われるようになったのは1980年代くらいからで、90年代に入ってから作家性に音楽が組み込まれている監督が出てきた。その時期に『映画秘宝』の連載を始めたのですが、当時の観客は使われている音楽を意識していなかったので、「この曲にはこういう意味があるんですよ」と伝えることに意味があった。最近だとネットですぐに調べられるようになりました。だから、観客も音楽に興味を持つようになってきたと思います。そういう時代になって良かったと思うし、日本映画のこれからにも期待したいですね。

右:添野知生(そえの・ちせ)
東京都出身。映画評論家。『SFマガジン』『映画秘宝』『キネマ旬報』などに連載歴あり。SF映画を中心に劇場用パンフレット、文庫解説、ラジオ出演など多数。SFマガジン『SF映画総解説』監修。マイケル・ベンソン『2001:キューブリック、クラーク』監修。90年代、米国ギターポップとオルタナ・カントリーのファンジン『Jem』参加。2008年、レコード・コレクターズ誌のアラン・トゥーサン特集を監修。2012年、田中啓文『聴いたら危険! ジャズ入門』(アスキー新書)に寄稿。YouTubeの新作解説番組「そえまつ映画館」に出演中。
Twitter:@chise_soeno
左:高橋芳朗(たかはしよしあき)
東京都出身。音楽ジャーナリスト/ラジオパーソナリティー/選曲家。著書は『新しい出会いなんて期待できないんだから、誰かの恋観てリハビリするしかない~愛と教養のラブコメ映画講座』『ディス・イズ・アメリカ 「トランプ時代」のポップミュージック』『ライムスターのライブ哲学』『ラップ史入門』など。ラジオの出演/選曲はTBSラジオ『ジェーン・スー 生活は踊る』『アフター6ジャンクション』『金曜ボイスログ』など。Amazonミュージック独占のポッドキャスト番組『高橋芳朗 & ジェーン・スー 生活が踊る歌』も配信中。
Twitter:@ysak0406

■マーベル・シネマティック・ユニバース音楽考 映画から聴こえるポップミュージックの意味
価格:¥2,200
出版社:イースト・プレス
発売日: 2022年7月17日
ページ数:368ページ
https://www.eastpress.co.jp/goods/detail/9784781620961
Photography Kazuo Yoshida
