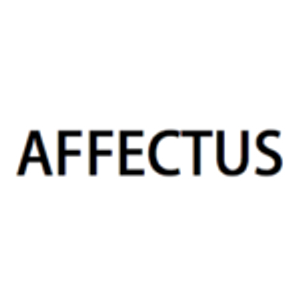「タナカダイスケ(tanakadaisuke)」のデザイナー、田中大資の手にかかれば、繊細ではかなげなはずのビジュー刺しゅうやレースは、ダイナミックな美しさを備えたジャケットやスカートに生まれ変わり、私達を現実のどこかにあるようで、現実のどこにもない、甘くも辛い世界へといざなう。
田中は、ファッションデザイナーとしてコレクションを発表する一方で、刺しゅう作家としてアーティストの衣装制作も行い、ブランドは卸ビジネスには注力せず、自社ECによる受注生産をメインにしている。そう、活動スタイルもビジネスタイルも独自の道だ。それを可能にするのは、「タナカダイスケ」の服にひとびとを魅了する大きなパワーがあるからだ。
ファンやアーティストの心を捉える服は、どのようにして生まれているのだろう。田中の創作の源をたどるインタビューは、重要なインスピレーション源になっているアニメの話から始まる。

田中大資(たなか・だいすけ)
1992年大阪府生まれ。2015年に大阪文化服装学院ファッション・クリエイター学科ニットコースを卒業後、コレクションブランドでの経験を経て独立。2021年に「タナカダイスケ」を本格的にスタートし、コレクションの発表とともに、刺しゅう作家としてアーティストへの衣装制作も行う。緻密な刺しゅうを施したアイテムの数々は絵画的なエレガンスを備え、幻想的な体験をもたらす。
https://tanakadaisuke.jp
Instagram:@daisuketanaka18 / @tanakadaisuke_official
アニメと刺しゅうと衣装制作
——子どもの頃にアニメをよく観ていたということですが、思い出に残っている作品はありますか?
田中大資(以下、田中):当時、観ていたのは『セーラームーン』『おジャ魔女ドレミ』『満月をさがして』などで、僕は平成4年生まれなんですけど、いわゆる女の子が観ていたものを姉と一緒に観ていました。
——どんなところに魅力を感じていましたか?
田中:地球を救うのは女の子なんだと、強いのは女の子なんだと思っていました。『カードキャプターさくら』も大好きで、さくらちゃん(主人公・木之本桜)が世界を救って、ともよちゃん(大道寺知世)というさくらちゃんの友達がいるんですけど、その子がさくらちゃんの衣装をつくって、2人でタッグを組んで進んでいく物語なんです。僕もともよちゃんになりたいと思いました。
——『カードキャプターさくら』も、女の子が世界を救う物語なんですね。当時は、アニメのキャラクターが着ていた服におもしろさを感じていましたか?
田中:『カードキャプターさくら』に関しては、衣装が毎回違うので、それがとても刺激的でした。毎回、物語によって衣装が違っていて。最終形態というか、バージョンアップした衣装もあって、そこに注目しちゃうというのはありましたね。
——ちなみに最近お気に入りのアニメはありますか?
田中:『宝石の国』というアニメがあって、いろんな宝石が擬人化された話なんですけど、お話しはもちろん、画も美しいんです。
——ダイヤモンドやサファイアなどが擬人化されていて、どこか田中さんのコレクションに通じる雰囲気を感じます。やはり、アニメは重要なインスピレーション源なのでしょうか?
田中:そう思います。
——では、本格的にブランドデビューする前に、SNSにアップされていたさくらんぼの刺しゅうマスクがすごく注目されていましたが、あのマスクをつくったきっかけを聞かせてください。


田中が制作したさくらんぼの刺しゅうマスク(田中大資のInstagramより)
田中:以前から、さくらんぼの刺しゅうだけは先にデザインしていて、ガーゼにさくらんぼ刺しゅうをした生地がけっこう大量に余っていたんです。そのタイミングでちょうどコロナ禍に入って、その時はガーゼでマスクをつくることが一般的だったので、それなら1個つくってみようとつくってみたら……。
——ものすごい注目を集めたのですね。刺しゅうのテクニックはどこで学んだのでしょうか? それとも独学ですか?
田中:当時通っていた学校は、みんなそれぞれ極めたい分野が違うから、刺しゅうに関しては自分でやっていくしかなかったです。アドバイスはもらえるんですけど、自分でディテールのアップが載った本などを見て、「自分だったら、どうできるんだろう?」と手を動かしながらまねていきました。「ここまでいけるんだ!」と思ったり、「ここまでは今の実力じゃ無理なんだ」と気付いたり、それをどんどん自分の味にしていきました。
——田中さんはコレクション制作だけではなく、アーティストの衣装制作も手掛けていますが、コレクション制作とアーティストの衣装制作で、進め方の違いはありますか?
田中:アーティストの仕事だと、直接アーティストさんとやりとりすることもありますが、ほとんどはスタイリストさんが間に入ってつくるケースが多いので、スタイリストさんの好みをくみ取ることを意識しています。もちろん、アーティストさんが好きなものも大切ですけど、スタイリストさんがまとめたい世界観を意識して、刺しゅうやデザインを考えています。
——例えばですが、アーティストの衣装制作で提案したけれど、採用されなかったデザインはどうされているんですか?
田中:スタイリストさんに5つ提案したとしたら、採用されるものは1つなので、そうなると残り4つは死んでしまいます。でも、4つの中にも自分のお気に入りがあるので、それを「タナカダイスケ」のコレクションのヒントにし、さらに自分らしくして発表することもありますね。

着る人がそれぞれの物語を描けるように
——次は、最新2023SSコレクションのテーマについて教えてください。




「タナカダイスケ」 2023SS collection “SHARP BRIGHT DARKNESS”
田中:僕は学生の時に腰あたりまで髪を伸ばしていて、専門学校に入っても伸ばしていたんですが、「そのままだと、東京のアパレルに入れないよ。どうするの?」って先生に言われたんです。当時は男性らしくいこうか、女性らしくいこうか、すごく悩んでいた時期でした。
その時、何かこういうものが世にあったら自分はそっちに振れていたかもみたいな、もし髪を伸ばしたままだったらもう1つの生きる軸があったかもしれない、こういうものが当時の自分に必要だったと思うようなものを今回のコレクションでつくってみました。
——もしかしたら、もう1つあったかもしれない、別な自分の世界観をつくるようなことでしょうか?
田中:そのきっかけになるようなクリエーションになればと。例えば、制服でも2023SSコレクションのような組み合わせで着ている人がいたら、自分ももうちょっとこの世の広さというのが感じられたんじゃないかなと思います。
——“shade enamel bijou skirt”は昔のヨーロッパ絵画に描かれた踊り子のような、アンティークでロマンティックな雰囲気が印象的ですが、このスカートのデザイン背景やアイデアはどういったものでしょうか?

「タナカダイスケ」 2023SS collection “SHARP BRIGHT DARKNESS”
田中:このスカートは、ランプシェードのような形にしたいと思ったことから始まっています。それと学生の頃、姉の影響で『KERA』という雑誌をよく見ていたので、ロリータファッションも好きでした。その点もちょっと入れたいなと思ってこの形になりました。でも、だからといって甘ったるくはしたくなかったので、レザーの手袋と黒いソックスで締めています。それに、このスカートに関しては挑戦していることもあります。
——それはどんな挑戦でしょうか?
田中:今は、男女ともにヌーディな表現は難しいじゃないですか。そこで「タナカダイスケ」として、どこまで許されるんだろうかと。例えば、「アレキサンダー・マックイーン(Alexander McQueen)」ならアートとして許されるけど、日本のどこかのアパレルがやったら怒られることもあるじゃないですか。その中で、自分はどこまで触れていいんだろうというのをやってみたくて、ちょっと攻めてみました。
——レースのグローブをはめた生身の手と、機械の手が写るビジュアルも印象的でした。本格的な機械が登場するのは「タナカダイスケ」では珍しいように感じました。このビジュアルの意図は?

「タナカダイスケ」 2023SS collection “SHARP BRIGHT DARKNESS”
田中:少女っぽい世界と機械や配線のムードが好きで、そういったものがすごく混じり合っていた時だったので、それをわかりやすく組み合わせています。
——ニットを使ったルックは、「タナカダイスケ」の象徴である刺しゅうをまったく使っていませんし、アーマー、ストロング、クールといったイメージを感じて、これまでブランドが発信してきたイメージとは違う新しさを感じました。


「タナカダイスケ」 2023SS collection “SHARP BRIGHT DARKNESS”
田中:これこそなんだろう、「装着してかっこいい」という、自分をカスタムするような気分で甘いけど強さもあるようにしました。レザーのショートパンツを合わせて、その下にまたニットのレッグウォーマーがセットになっていて、セットアップで着ていただけたら嬉しいです。
——コレクションを制作する時に、物語性を考えているのでしょうか?
田中:アイテムひとつひとつを見た時には物語性を言えたりするんですが、それを線にしてと言われると、自分ではすごく難しいです。そういえば、次のコレクション、できれば今回のコレクションでやりたいと思っていたことがありました。
——それはなんでしょう?
田中:いつか小説家の村田沙耶香さんにお願いして、1つの物語をつくってもらえたら嬉しいです。自分は点では出せるけど線にはなかなかできないので、その部分を誰かにお願いしたいんですよ。
——田中さんなら線にできそうな気もしますが、どうでしょうか?
田中: おそらく自分で線にできるとは思うんですが、自分の物語になり過ぎるといいますか。それだとすごい押し付けに近くなってしまうので、買う側もそれを意識しなきゃいけなくなると、なんだか嫌だなと。それなら、第3者的に誰かにひと解釈を入れてもらうのがいいのかなと思います。今のままだと、やっぱり男女をすごい言ってしまうことになってくるので、それも大事なことであるけど、一番ではないと言いますか。
——では今、重要視していることはどんなことですか?
田中:今は生き様というかリアルを求められている時代のムードですが、ファンタジーを描ける自分でいたいです。また、これを言葉で説明するのではなく、もので語れるようになりたいですね。

オリジナリティが眠る場所を見つける
——これから「タナカダイスケ」をどんなブランドにしていきたいですか?
田中:「東京国際映画祭」のレッドカーペットで橋本愛さんに着てもらったのですが、その時、橋本さんがインタビューで「東京国際映画祭だから、日本のブランドをフィーチャーしたかった」と話されていたんです。ああいった場だと、海外ブランドを着られる方が多いと思うんですが、橋本さんはいろんな好きなブランドがある中から、今回は自分に声をかけてくれた理由の1つがそれだったんだなと。やっぱりあの場に立てるブランドというか、あの場につくったものを出せるブランドでいたいですよね。
——ブランドをこれまでやってきて、喜びを感じるのはどういった瞬間ですか?
田中:橋本愛さんもそうですけど、映像作家の柳沢翔さんだったり、自分が好きだった人、憧れていた人と仕事ができる瞬間で、そこからまた次の機会が生まれたりして、つながっていくのはやはり楽しいです。

——ちなみに、今後一緒に仕事してみたい人はいますか?
田中:最近だと、真木よう子さんが海外のイベントで着てくれたのですが、真木さんと何を表現したいです。
——どのような服になるのか楽しみです。ではクリエイションのために普段から心掛けていることはありますか?
田中:浅草橋と日本橋が大好きで、頻繁に通っています。正直、行くたびにお店の商品が変わるものでもないんですけどね。でも売っているものは変わらないけど、目に飛び込んでくるものは、その時の自分の気分で変わってくるので、とにかく同じルートを何度も回ることをずっとやっています。
——コレクションの制作プロセスはいつもどのように進んでいきますか?
田中:テーマも決めつつですが、やはり自分が手を動かしてつくりたいものが、優先されてきちゃいます。「今、ビーズの刺しゅうがしたい!」とか、「今、レースを触りたい!」とか、つくりたいものの欲求と、テーマを同時につくって、その落としどころを探すようになります。
——手を動かしているうちに、発想が浮かんでくるパターンが多いんでしょうか?
田中:それがすごく多いです。むしろ、手を動かさないとわからないです。ビーズや糸は、太さと大きさに限界があるので、素材と組み合わせた時に一番きれいに見える形っていうのを探さなきゃいけません。やはり絵だけ描いても仕方ないですし、手を動かすことが大切ですかね。
——本当に今、自分がやりたいものをとにかくつくるということでしょうか?
田中:なるべくそこで勝負して、どこまでいけるんだろうとすごく考えています。無理して「ニットの着やすい服」みたいなものって、自分ではつくらなくてもいいのかなと。
——今の「タナカダイスケ」が勝負するのは、別の領域ということですか?
田中:大きな規模感でやっているブランドなら、着心地もよくてクオリティもよいものを安く出せますし、そういったブランドは他にもあると思います。だから今の規模感の自分がすべきことは、より装飾的なものづくりで技術を上げて勝負したいです。
——今のお話は、僕らもオリジナリティを見つけるためのヒントになりそうです。
田中:ライバルが「グッチ(GUCCI)」って言ったら大げさですけど、「グッチ」がおそらくできないことで、自分ができることは絶対あると思います。すごく大きな規模のブランドだと手が出せないようなコアな世界で、まだ小さいブランドだからこそ触れていいところがきっとあるはずなので、そこで勝負していきたいです。

世界で唯一無二のオリジナリティが求められる一方で、ひとびとから着たいと思われる魅力が求められる。そんな矛盾をデザインすることが、デザイナーとブランドの使命なのかもしれない。
インタビューの終盤で田中が語ってくれたことは、オリジナルの世界を見つけるために必要な、1つの道しるべではないだろうか。自分の中に潜む、一見すると狭く小さく見せる場所にこそ、世界に響くクリエイションの源泉が眠っている。まだまだ、つくりたい服がある。「タナカダイスケ」の探究心が果てることは決してない。
Photography Shinpo Kimura