『Fleeting Future』。日本語に訳すと、儚い未来、あるいは、束の間の未来、という意味になる。フランス生まれで、現在はロンドンを拠点にしているという作曲家/マルチ奏者のAkusmiことパスカル・ビドー(Pascal Bideau)は、自身のデビュー作となる本作に、そんな意味深で悲観的とも受け止めることのできる名をつけた。だが、本作から鳴り響いてくるサウンドは、そんなタイトルとは裏腹に、極めてオプティミスティック。彼は、インドネシアを訪れた際に没頭したというガムランのスレンドロ音階をふんだんに用い、スティーヴ・ライヒやテリー・ライリーのミニマリズム、ジョン・ハッセルの第四世界というコンセプト、レイヴ・ミュージックの快楽性、モータウン譲りのビート、あるいは『AKIRA』や日本の都市風景を巧みにコラージュしながら、壮大で有機的なエレクトロアコースティック・サウンドを、ポップに響かせているのだ。そんなエクレクティックな音世界を自由連想のように構築するAkusmiのサウンドの背景にはいったい何があるのだろうか。そして、なぜ『Fleeting Future』というタイトルをつけたのだろうか。メール・インタヴューを試みた。

フランス生まれでロンドンを拠点に活動する作曲家でマルチインストゥルメンタリストであるパスカル・ビドーによるプロジェクト。英レーベル〈Erased Tapes〉の立ち上げに大きく貢献したアダム・ヘロン主宰によるロンドン・ベルリンの新レーベル〈Tonal Union〉と契約し、2022年6月に1stアルバム『Fleeting Future』をリリース。ミニマリズム、コズミックジャズ、 第四世界の影響を受けた、幻覚的かつジャンルを超えブレンドされたサウンドで各メディアから注目を集める。
Akusmi フランス生まれでロンドンを拠点に活動する作曲家でマルチインストゥルメンタリストであるパスカル・ビドーによるプロジェクト。英レーベル〈Erased Tapes〉の立ち上げに大きく貢献したアダム・ヘロン主宰によるロンドン・ベルリンの新レーベル〈Tonal Union〉と契約し、2022年6月に1stアルバム『Fleeting Future』をリリース。ミニマリズム、コズミックジャズ、 第四世界の影響を受けた、幻覚的かつジャンルを超えブレンドされたサウンドで各メディアから注目を集める。
Photography Alex Kozobolis
ガムランとの出会いが、世界中の音楽から受けた影響をミックスするための道を開いてくれた
——昨年『Fleeting Future』をリリースされましたが、スティーヴ・ライヒのミニマリズム、レイヴ・ミュージックの残滓、ジャズの混沌としたハイブリッド性、ジョン・ハッセルの第四世界の概念、あるいはモータウンなど、さまざまな音楽から影響を受けているように感じました。しかし、あなたはそれらの音楽のディシプリンに引きずられることなく、それらとは異なる音像を作り上げているように見えます。こういう言い方が正しいかどうかわかりませんが、あなたの音楽は、“聴くたびに違う風景を見せてくれる音楽”のようです。『Fleeting Future』を作り始めるまで、どんな音楽を聴き、どんな挑戦をし、どんな経験をしてきたのでしょうか。
パスカル・ビドー(以下、パスカル):記憶している限り、私はこれまで常に世界中の音楽に触れてきました。私の両親は、今も昔もとにかく旅行が大好きな人達で、いつも旅先から音楽や楽器を持ち帰ってきたんです。だからこそ、ペルーのフルート、チベットのホルン、中近東のリズムなど、西洋音楽という箱の外から聞こえてくる多様な音にいつも囲まれてきました。とはいえ、私は西洋音楽、特に既成概念の枠を越えて、ルールと戯れるような西洋音楽に対する愛着を持ちながら大人になっていったのも事実です。ジャズやミニマリズム、そして電子実験音楽の中には、そういった要素が確実に存在していますね。
私が作曲を始めてからずっとやりたかったのは、これらの全く異なる影響を1つにミックスできるような方法、もしくはジャンルを見つけることでした。そして、何年もの間、模索と失敗を繰り返してきたんです……。バリ島旅行の帰りにゴングのセットを買って初めて、その道が見つかったかもしれないと思ったんです。それが『Fleeting Future』に取り掛かったきっかけです。
——この『Fleeting Future』では、ガムラン・スレンドロの音階が印象的に使われています。インドネシアを訪れた際、ガムランやゴングの伝統音楽にどっぷりと浸かったと聞いています。このような音楽のどこに魅力を感じ、また伝統的なガムランや鉦の音楽があなたの音楽に何をもたらしたのでしょうか?
パスカル:バリのガムランで非常に興味深いのは、その音楽が担う社会的な役割の大きさです。それらは全てバンジャールという村落内の小さなコミュニティーグループに由来しているのです。どの村落にも小さな「広場」があり、そこに譜面台があって、ガムラン・アンサンブルの演奏が行われます。ガムランは、稲作など他の重要な活動と同様に、地域社会の生活において重要な役割を担っています。村の人々によって演奏されるガムランは、ユニゾンとパートの共有が重視されます。稲作農家が生産効率を最大化するために間断灌水という手法(田に水を満たした状態と水を抜いて干した状態とを交互に繰り返すこと)を発展させたように、ガムラン音楽家は最大限の表現をするために連動するメロディーをうまくまとめあげていくのです。ガムラン音楽の中には、加速し始めると、ペアになった演奏者との協力なしには物理的に演奏が不可能なほどの速さになる曲もあります。そして、これこそがガムランの真の魔法と言えます。つまり、人と人との協力が、ある高みへの到達をもたらしてくれるということです。その音は個人の個性を超え、不可能を可能にするのです。
それぞれの音が連動し、協調し合うようなパートを書く自分の作曲手法においても、この点から大きな影響を受けています。2つ以上のパートを重ねることで、どの楽器からも出ていない音なのに、聴き手にははっきりと聞こえる新たなパート、別の音楽フレーズが生まれることがあります。それは、全体がもたらす結果なのです。
『Fleeting Future』に参加した演奏家達、『AKIRA』から受けた影響
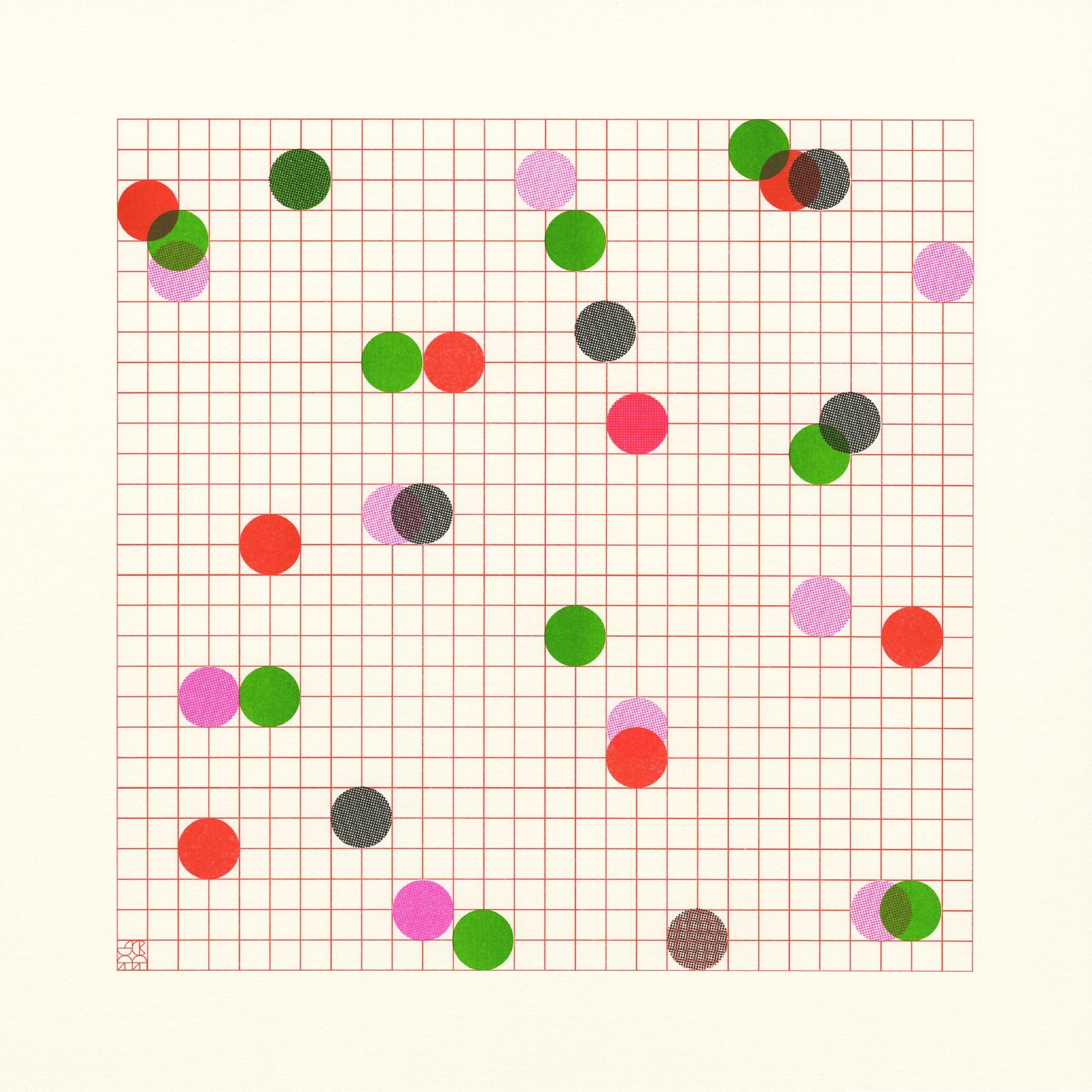
——2017年から2019年にかけて『Fleeting Future』を制作されたそうですね。このアルバムはどのような制作過程だったのでしょうか?また、このアルバムにはルース・ヴェルテン、ダニエル・ブラント、フローリアン・ユンカーといった演奏家が参加していますが、彼等はこの作品に何をもたらしてくれたのでしょうか?
パスカル:アルバム全体の作曲は、ロンドンのカムデンにある私のスタジオで行い、そこでほとんどの楽器を自分で録音しました。しかし、サックスのパートの中で、はっきりと聞こえるクリーンな音色が欲しい部分があったので、偉大なアーティストであるはルース・ヴェルテンにお願いして、この冒険に加わってもらいました。さらに、フローリアン・ユンカーには、トロンボーンで参加してもらうよう依頼をしました。私自身、トロンボーンは演奏しないのですが、フローリアンが見事に表現する音色のパレットを組み込みたかったのです。ダニエル・ブラントとは、何年も前からコラボレーションをしている仲で、彼のリズムや音に対するアプローチにはとにかく感心させられるばかりです。彼のドラムのパートはすべてベルリンで録音しました。
——ハイテンションな「Neo Tokyo」は、アルバムのハイライトの1つだと思いました。「Neo Tokyo」は、大友克洋監督の『AKIRA』にインスパイアされたと聞いています。『AKIRA』のどこに惹かれ、そのインスピレーションを音楽でどう表現しようとしたのでしょうか?また、映画『AKIRA』では、日本の音楽集団、芸能山城組の音楽が印象的に使われています。彼等の音楽について、どのように思われますか?
パスカル:13歳の時だったでしょうか、フランスで公開された『AKIRA』を初めて観て、衝撃を受けて以来、ずっと心に残っているんです。オープニングでネオ東京が映し出されるロングショットと、芸能山城組の素晴らしいポリリズムを目の当たりにした時、首元の毛が逆立つのを感じたことを今も覚えています。大橋力氏が分子生物学者であることを知ったのはずっと後になってからですが、そのことは、自分の中で完璧に腑に落ちたんです。音楽的、リズム的なモチーフやアイデアが、異なるペースで相互に作用し、互いに弾き合う。それこそ、私が『Fleeting Future』でやろうとしたことで、「Neo Tokyo」はその典型的な例です。この曲は、起点も終点もない、言ってしまえば慌ただしい作品です。さまざまな要素がてんでんばらばらに響きつつ、その小さなオスティナート(一定の音型を奏で続けること)の組み合わせによってグルーヴが生まれ、全体が成り立っています。この曲は、レーザー光線が四方に広がり、記念碑のようにそびえる巨大な高層ビルが明滅する『AKIRA』の近未来的な東京を私に連想させたんです。
——最後の曲「Yurikamome」は、日本の風景や都市をドライブしている人のYouTube動画からインスピレーションを得たと聞きました。「Yurikamome」は、曲が進むにつれてさまざまな音が重なっていく荘厳な展開が特徴的です。日本の風景や都市のどの部分からインスピレーションを受け、なぜこのような荘厳な展開の曲を作ろうと思ったのでしょうか?
パスカル:「Yurikamome」はアルバムの最後の曲であり、作曲も最後に行いました。エンディングでもあり、同時に新たな始まりでもある曲です。この曲に関しては、新橋からお台場、豊洲まで、東京湾やレインボーブリッジ、お台場の島々を通過するモノレール「ゆりかもめ」のYouTube動画に、直接的に着想を得ています。まずこの曲で最初に聴こえるピアノのモチーフを思いつき、映像の中の風景の変化を見ながらそれを展開させ、レイヤーを足していきました。この曲が荘厳に聴こえるとしたら、それは私が東京に対して抱いているイメージだからです。
根底に息づくグルーヴと即興性、「Fleeting Future」という言葉に込めた想い
——この作品で印象的だったのは、ダンスを誘発するような要素があることです。「Divine Moments of Truth」はその代表格だと思います(「Longing for Tomorrow」や「Neo Tokyo」もそうです)。あなたにとってダンスとは何ですか?
パスカル:まず音楽に合わせて体を動かすのが好きですし、リスナーがグルーヴを刷り込まれ、つい反応してしまうような、脈動のある音楽が好きなんです。『Fleeting Future』に収録されている楽曲はすべてグルーヴ感があって、非常にリズミカルなものばかりですよ。
——この作品には即興演奏の要素が随所に感じられます。即興演奏の魅力は何だと思いますか?また、即興演奏と作曲の違いは何だと思いますか?
パスカル:ある意味で、すべてが即興から生まれているような気がしています。演奏や作曲をしようと思ったら、まず即興で演奏してみるんです。楽器を手に取り、そこで出てきたものを録音します。そのなかで良いものもあれば、そうでないものもあります。そしてここで、作曲のプロセスが始まるんです。即興演奏のどの部分を残し、さらに発展させるか、また他にどの部分を作りこんでいけば、自分が進みたい方向性に持っていけるかを決めていくのです。
——本作のタイトル『Fleeting Future』も印象的です。どこか楽観的な印象のあるこの作品に、なぜこのタイトルをつけたのでしょうか。あなたにとって、なぜ未来が「儚い」のでしょうか。その辺りの想いを聞かせてください。
パスカル:このタイトルは、初めてタイトル曲に使われているフレーズを思いつき、それを展開させて演奏した時に思いつきました。「Fleeting future」という言葉は、私の指からごく自然にキーボードに落ちてきたというか……。まるで言葉が、音楽と一緒にやってきたかのようでした。
このコンセプトはさまざまな意味を帯び得るものです。もちろん、緊急な行動を要する気候の非常事態を表現していると受け取る人もいるでしょうし、人類の未来が儚いものであることに警鐘を鳴らしていると考えることもできるでしょう。しかし、私が言いたいのは、私たちは未来に対して直線的なアプローチから離れ、私達の行く末を占うあらゆるデータや情報が飛躍的に増え続ける、樹木のような未来に突入してしまったのではないかということです。そして、それこそが未来を儚くさせているのです。ある枝をたどれば、その枝がどうなっていくかを垣間見ることはできるかもしれませんが、全体像が進化することによって、その予測はまったく意味をなさなくなるかもしれないのです。
——最後に、もしあなたが『Fleeting Future』をレコード棚に並べるとしたら、どんなアーティストのどんなアルバムを隣に並べますか?また、その理由も教えていただけると幸いです。
パスカル:テリー・ライリーの『In C』、それもおそらくアフリカ・エクスプレスが指揮者のアンドレ・デ・リダーと組んだバージョンはあるでしょうね。これはオーケストラ的な作品というより、ライリーの作曲法そのものを表したものだと言えます。あとは、とにかくお気に入りのアルバム、ジョン・コルトレーンの『A Love Supreme』もありますね。『Fleeting Future』は、この『A Love Supreme』のテーマの核となる部分に負うところがかなり大きいと思います。ムーンドッグの作品も間違いなく棚に並んでると思います。ロンドン・サクソフォニックの共作の『Sax Pax for a Sax』がいいでしょうね。それからファラオ・サンダースの作品(例えば『Jewels of Thought』など)、あとはエチオピアン・ジャズ、そしてバリやジャワの音楽も間違いなく入っているでしょうね。
Translation Shynichiro Sato(TOKION)
