柳瀬二郎が主宰するbetcover!!がすごいことになっている。『卵』を2022年末にリリースしてから、全国ツアーを回り、捉え切れない速さで、音に熱をのせ撒き散らしている。計測不能な何かが、制御不能な何かが更新されている気がする。そう熱を帯びて語りたくなる何かが今の彼らの音楽にはある。海外のレヴューサイトからも熱い反応が返ってくる等、フォークを咀嚼した日本ドメインの音楽とプレイアビリティ光るバンドの演奏が国境を超えて音楽リスナーの芯に迫る事実にも納得がいくところだ。
エイベックスを離れた後の2021年にリリースされた『時間』。その後1年でリリースされた『卵』について。古くから営まれる時間が壁や椅子に染み付いた三軒茶屋の喫茶店で、生姜焼き定食を食べたり、タバコを吸ったり、クリームソーダを飲んだりしながら、2時間たっぷりと話を聞いた。
今作を「音楽」っぽくしたくなかったという言葉とは裏腹に、こだわりぬいた音の鳴り方のあるべき形と歌詞としての言葉について柳瀬二郎が語り尽くしてくれた。
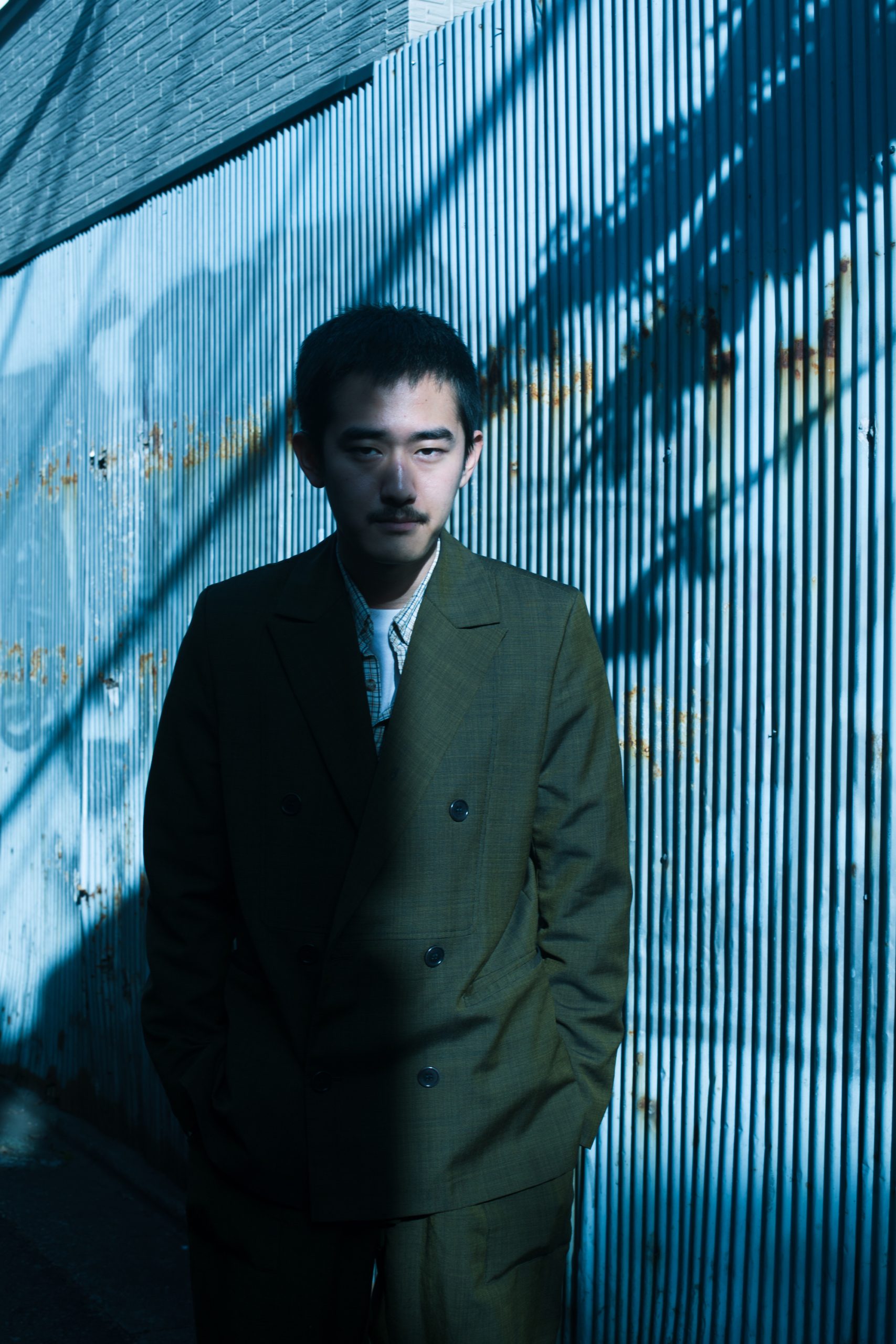
柳瀬二郎
東京都調布市出身のシンガーソングライター。ロックバンドbetcover!!のヴォーカル。
https://linktr.ee/betcover
「バンド」として音を鳴らすことで生まれた幽玄な音世界
−−現体制になってからの動きをざっと教えてもらえますか?
柳瀬二郎(以下、柳瀬):2021年の1月付けでエイベックスを離れて。ゆうらん船を呼んで、『時間』に含まれる曲でワンマンをやったのが現体制の始まりですね。それから「自分の金でアルバムを作るぞ」みたいなモードになって。2016年からずっとレーベルがついてて、全部お金も出してもらっていたし、版権を持ってなかったから、自分の金出して作った方が「責任」を持てていいなと思って。その時貯金が若干あったので、「センティーン」の時からお願いしているエンジニアさんにHMCスタジオでとらせてもらったのが『時間』です。
−−エイベックスを離れてから一番の変化はなんですか?
柳瀬:より「バンド」になっていって「自分がボス」という実感が増えましたね。今までは自分がアレンジまで考えて詰めていたのが、バンドメンバー各々のプレイに任せることが多くなって。そもそも(日高)理樹さんに「これやって」といってもやれないし(笑)。コードはこれです、って感じで伝えて。その中で泳いでもらうようなやり方をするようになりました。間とテーマが合っていれば問題ないなと。
−−自身の創作面における心境の変化はありましたか?
柳瀬:いえ、そこは全然変わってないですね。「異星人」の頃も、『時間』の頃もやっている側として気持ちに大きな変化がないんです。そもそも楽曲自体もAメロ/Bメロ/サビとかないのがいいと思って昔からやってきたし。僕自身がこういう表現がしたいからこの音を使うみたいな。うん。だからやりたいことは一貫して変わってないと思います。
−−ただそのやりたいことのニュアンスがより緻密になってきているし、素直にそれを表現できるようになったということ?
柳瀬:そうですね。エイベックスにいた時はもうちょっとメジャー志向だったので。「せっかくメジャーに入ったし、なんか売れてぇな」みたいな(笑)。売れる感じの曲がいいと思っていたんですけど。でも、わかったんです。普通に現時点で能力がなかった、と思って。「狙うこと」が僕には多分……そういう系の才能は持っていないのを痛感して。それで当時の自分にできること、最大を出せるやり方を目指して『時間』を作ったんですよ。
−−そういう意味で、現体制のメンバーでバンドアンサンブルをビルドアップしていく期間だったのかもしれないですね。『時間』を出してからの2年間というのは。
柳瀬:そうですね。メンバーが現体制になったのもその時期くらいからなので。基本はみんなで「ジャーン」で一斉にとって。歌は重ねてとったり、曲によってはドラムを全部分解して録ってみたり、10日くらいでとったんですけど、実験していました。
あとアルバムトータルで作品を作ろうとしていたので。前はコンセプトがあったんですけど、もう少し曲単位だった。でも今作は作りたいテーマやイメージが膨らんで、コンセプト自体が全体を通してになっていったんです。そういう意味では、なんならあの時より今のほうがよっぽどキャッチーでポップだと思うんですけどね。
−−捉え方次第では、そうなのかもしれない。
柳瀬:前より素直になっていったんです。何度もインタビューしてもらっていますけど、初めて会った時はもっと尖っていたと思うんですよ。でももう取り繕うことはどうでもよくなってきて。毎日「すみません〜」とか言ってる感じで。だから最近はいつもそう思っていたのが、今回はより出ていったのかもしれないですね。

“架空の劇のサウンドトラック”がイメージ。『卵』が過去作と一線を画す理由
−−今回のアルバム作りのプロセスで、どのような青写真があったのですか?
柳瀬:僕はずっと「劇伴」をやりたいと思ってたんです。
−−劇伴?
柳瀬:“架空の劇のサウンドトラック”を作りたいなって思ったんです。僕らの音楽は主体じゃなくて、何かの物語の付属であるくらいのテンション。「音楽」主体ではなくて、そのくらいの感じ。だから今回のアルバムはインパクトがないんですよね。そのインパクトのなさが俺にとって大事で。
−−特に今作は、ここにいて今「卵」を聴いてるんだけど、今ここで聴いていないというか。過去と未来が混ざって、時制にとらわれないでいられる浮遊感があって。その理由を知りたかったです。
柳瀬:嬉しいですね。そういうことを表現したいと思っていました。今までで一番やりたかった音なんです。なんか『時間』は海外でも評価してもらい、あの時はあの時で、やりたいことできたんですけど。今回はもっと「音楽」としてあんまりキャッチーじゃないのがいいという感じがして。今のモードとしては、音に隙間や空間を作りたかった。
−−それはどうして?
柳瀬:「世界感」というか、情景がより伝わるように。内容をロックオペラにしたいわけでもないし。あくまでバンドミュージックだから。「劇伴」を作りたいけど、本当に「劇伴」になるわけではないので。そのバランスという意味で。
−−ああ。例えばヴィンセント・ギャロの『When』の感じとか?
柳瀬:あ、わかります。結構そっち系です。あとはニック・ケイヴ&ザ・バッド・シーズのメンバーのウォーレン・エルスが在籍するダーティ・スリーとかアンビエント系のアルバムの感じ。情景がすごい浮かぶんですよ。こういう系を当時(日高)理樹さんから教えてもらって。
−−他にはどういうもの教えてもらったんですか?
柳瀬:あとはジョン・ケージのアンビエントとか。日本のシンガーでいうと三上寛もそうだったかな。詩がよくて。
−−そういう物語の情景を想起させる作品を作りたかったと。
柳瀬:はい。エイベックス在籍当時から信頼しているHMCスタジオの人に劇伴をやりたいと相談をしていたけど、「まだ早いよ」と言われて。というのも、1回ちゃんとそういう路線の音楽をやった上で、受け入れられてから「やる」という。なんなら“売れない路線‘’にいくことだから。もうちょっとやりきってからだと言われて。それで「これだ」という方向性のアルバムを1枚作るのを『時間』でやれたので。だから今回は遂に満を持したタイミングで、やりたいことをやりきろうっていう。
−−ずっと出したかった音の世界観って、「昭和的なテンション感」だと捉えていたんです。影響を受けて来たものが、舞台の「野田地図」であったり、映画の「犬神家」シリーズみたいな音楽以外からもあって。そこで捉えた感覚や情感をその世代じゃない人が鳴らしている、という感じがあって。けれど、『時間』から最新の「卵」にかけては、今の時代の空気が自然と鳴っている気がして。それって不思議だなと。
柳瀬:確かに、時々考えるんですよ。その頃の音楽も好きだけど、憧れてそれをやりたいというわけではない。そこが違うのかなと思うんです。誰かの表現をみていて「懐古主義だな」って思う時は、昭和のムードをそのままやりたい人で、その昭和の時代の人になりきりたいんだと思う。だから僕は言い方が悪いけど、その時代の音を「使う」「利用する」っていうテンションだから。
−−確かにその像を目指しちゃったら、懐古的になってしまう。でももともとやりたいヴィジョンがあって、世界観があって、それを実現する要素として引用しているというか。
柳瀬:うん。これがちょうどいいからという感じなのかな。あとはなんかいっぱい混ぜていますし、いろんな時代の音楽を。正直、必ず毎曲元ネタあるので。1曲に対して3曲くらいはオマージュを入れるから。しかも時代も国も違うものを。
−−なるほど。
柳瀬:古い音楽や映画を「古い」と思って今聴いたり観たりしてないですからね。年齢とか関係なしに、誰にとってもそのはずじゃないですか。時代劇を初めて観た時は誰にとっても新鮮で、そういう感じ。
今のモードを出せたので、曲がしっくりきているし、一番真面目に作ってるかもしれない。『時間』はもっといい意味でノリな感じだったし。ちょっと「コメディ要素」はずっと路線としてあったけど、今回は全然ないから。
−−「イカと蛸のサンバ」なんてタイトルからして最高だなぁって思いましたけど。
柳瀬:いや、あれが実は一番悲しい時に作っていますから。一番エモーショナル。あの曲が最後にできたんです。「ウオォ、泣ける。これじゃ!」つって。そんな感じだったんですよね。
−−Spotifyのプレイリストで公開された参考曲もジャンルも多岐にわたってて。その中でも、印象的だったのは、ラルクの「花葬」で。
柳瀬:はい。「ばらばら」は歌詞とか考えすぎないでそもそも歌っていて。アレンジを考えていたんですよ。もともとはめっちゃ遅い曲で。で、その時たまたまラルク アン シエルを聴いて。「花葬」で言ってる「バラバラに散らばる」って言葉が「ばらばら」の中で既に書いていた歌詞とリンクしていたし、この感じのテンポでいこうと思って。
−−影響を受けたのはむしろテンポのほうなんだ。アルバム全体を通じて目指したのはどの質感なんでしょうか?
柳瀬:今まで話したテーマに通じますが、ずっと時代に影響されない、あんまり関係ないものを作りたいんです。情けなさとか人間臭さとか。結局、「情」とかふしだらな人間の話がしたい。こういうことあるよね、みたいな物語というか。
――人間そのものを描きたかった、と。
柳瀬:そうですね。「普遍性」があるものを作るためには、「時代性」がないものを作らないといけないじゃないですか。でも、その時々で音楽で自分が表現したいことをやってると、時代とかはもはや関係なくなるんですよ。僕はそんなに重くない。軽い。大したことはあんまり言えないですし。何か代弁するようなことを言うほど偉くないですし。そういうのをやるのは60代になってからかなって。だから歌詞も自分を主体にしないで、物語に置き換えているんです。

僕はメトロノームが嫌いで「なんで演奏するのに軸を作るんだ」って思うんです。
−−音像もどこか遠くで鳴っているような距離感の不思議な鳴り方ですよね。
柳瀬:はい。参考にしたのはアンビエントとかクラシックとかジャズの録音ですね。クラシックとかジャズの録音って、1本のマイクでとるんですけど。ドラムが特に重要で、普通は1本1本マイクを立てるんですけど。今回のアルバムは基本1本で足りないところを補うだけ。だからほとんど、外からの音なんですよ。
あとは2000年代とかその前後のバンドとかってたまにやってる人がいましたけどね。それこそ54-71とか。よく聞くと結構重くない感じを参考にして。
――なぜそうした音像を目指したんですか?
柳瀬:今って打ち込みの技術とかが進化しているから。あんまりドラムって意味がなくなってきちゃっていて。なのに、メトロノームをつけて練習して「クリック音」を意識して。それって本当に人間がやる意味あるのかなって。
メトロノームをつけないだけで、だいぶ今っぽさがなくなって音に揺らぎが出るんですよ。僕らBPMのタイム感が良くないんで走ったり、遅くなったりするんですよ(笑)。それが人によっては気持ち悪いってなると思うんですけど、そうじゃない人にはむしろ一発どりのほうがいいかなみたいな。
――その揺らぎを聴いてほしいと。
柳瀬:僕はメトロノームが嫌いすぎて。「なんで演奏するのに軸を作るんだ」って。まじで謎。「俺は走りてえんだよ」って。
−−(笑)。
柳瀬:基盤がこうですっていわれている上で、演奏するのってめっちゃ気持ち悪くないですか。それって実はあとでミックスしやすいとか、修正しやすいためとかだったりの理由だったりして。「それってもはや音楽じゃねえじゃん!」って思っちゃうんですよね。
――自分たちで鳴らす意味があることしかやりたくないと。もともと学生時代に吹奏楽でクラシックをやってきたのも関係しているとか?
柳瀬:それがあるのかもしれないですね。クラシック音楽だとアンダンテとかクレッシェンドとか。それが音楽的な流れじゃないですけどあるから。僕らが演奏して速くなるところって、速くしたいから速くなるんですよ。
――そもそも音楽ってそっちが普通だったのに、という気持ちがある。
柳瀬:はい。でも最近は感情のことをやらなくなってしまった、いつの間にか。ドラムも「こうやってここはちょっともたついてるからキックだけ前に」とかあんまりしたくない。もう歌が下手だったらピッチ修正するんじゃなくて、歌が上手くなるように練習すればいいし、ドラムだったら、ドラムを練習すればいいだけなのに。
――だからこそ一発どりにこだわったという。
柳瀬:はい。あとは、時間がなかったんですよ、単純に(笑)。だから制限が生んだ一発どりでもある。
――その理由は?
柳瀬:銀座にあるはっぴいえんどとか坂本龍一さんとか矢野昭子さんがレコーディングするスタジオでどうしてもとりたくて。そこのスタジオを2日間だけ借りたから。マネージャーもいないし、完全セルフプロデュースだから2日で10曲。なんでもできるとなるとなんでもやっちゃうから。それで結果、方向性を見失うみたいなことにならなくて済んだのはありますね。やれることを全力でやったんです。
今回はデモがあったものをリハで何度もやっていましたし。1年かけてアレンジもライヴで作っていって、それを録音した感じですね。プレイング自体はライヴと一緒なんですが、ミックスしないことにはライヴ音源みたいなパワー系になっちゃう。だから音圧もあげないでわざとすごいしょぼい音にしたんです。
――しょぼい音にする?
柳瀬:はい。マスタリングという作業をしなかったんですよ。普通はミックスしてからマスタリングで音圧をあげるという作業があるんです。音圧をあげるってつまり、音をつぶすことなので、上をつぶす。でっぱってるところを凹まして均等にするみたいな。だからそれってオーケストレーションの揺らぎを消して、聞きやすくするという作業のこと。通常音圧をあげると音量がでかくなって、かっこよく聞こえるんですよ。でも、それをやるとクラシックとか昔の音楽が持っている本来の豊かな部分を殺しちゃうなと思って。
――なるほど。
柳瀬:今回は音圧をいじらず。音量だけをなんとかあげる。だからミックスの状態なんですよ。
――レコーディングの仕方と空気感の味わい方。時間軸が定まってなくて、どこにでもいけるという浮遊感を感じたのですが、それにはそういう事実があったからこそなのかもですね。
柳瀬:そうかもしれないですね。意識的に今バンド音楽でこういう音を出している人たちがいないから。

町田康に教わった言葉について
――海外のbetcover!!ファンがYouTubeで熱を帯びて語っていたり。多分それって、いろんな海外の音を聞けるようになったからだし。フィッシュマンズの音楽に簡単にアクセスできるという文脈があった上での話と思うんだけど。なんでそんなことが起きてると思いますか?
柳瀬:わかんないっす。「やったあ! うれしいなあ」って感じ。でも日本が大好きなので、文化的に伝わってるのが嬉しいですね。
――海外の人に聞かれている理由って、そこに日本的なものがあるからなのか。具体的に日本文化のどこが好きですか?
柳瀬:言葉ですね。僕しゃべりが、すごい軽くて苦手なんです。あんまり自分のことを話せない。まあだから曲にしているんですけど。僕が一番苦手としている。でもだから文字とか詩になると……うん、大事な部分です。
あとは曖昧な表現ができるのすごいですよね。歌詞だと特に主語と述語がはっきりしないとか。日本語って前後の並びもある程度ずらしても伝わるし、単語も並び方がいろいろある。組み合わせで解釈がなんとでもなるし。あとは、一人称がいっぱいあるのもすごい。英語だと「You」だけなのに、日本語だと「君。あなた。われ。てめえ。貴様」何でも使えるし、全部に背景があるじゃないですか。
――確かに。
柳瀬:だから歌詞の接続部分を後で全部入れ替えるんですよ。そういうズレ感があっても伝わればいいなって。
――直接的にわかりすぎないように、ニュアンスを濁すのはどうして?
柳瀬:全部わかってしまうのが嫌だから。なんか今の時代ってあらゆるものがはっきりしているじゃないですか。画質とか画素がいいとか、それこそ音がクリアなのがいいとか。でもクリアじゃないのが懐古(主義)なのかと聞かれると、本当のところはそうでないかもしれない。この喫茶店がドトールに比べて、クリアじゃないけど懐古主義なのかっていうとそうともいえない、みたいな。
昔、町田康さんと対談した時に言葉について教わったんですよ。町田さんは「俺らが若い頃、音楽をやっていた頃は、10メートル先が見えなかった。真っ暗だからなんでもできた。今って全部見えてるからそれができない」って。僕が中学生の時には既にスマホがあったし。だから便利すぎる、整頓されすぎるのも嫌なんですよ。整頓されてないものとか、朧なものの方がむしろ新鮮に響くというか。
――「時間」以降海外のリスナーの反響がある理由って、その朧な像に日本的なものがあるからだと思いますか?
柳瀬:どうなんですかね? 海外の人からみて日本的な響きってどういうふうに感じられているんでしょう。でも、一方で僕らも海外の曲のニュアンスがわかりますよね。うん、わかる気がするんですよ。ブラジル音楽のガル・コスタとかが好きで。日本語じゃないけど、ソウルがわかる。響きだけでも伝えられてる。そういう音楽は格好いいと思います。僕の音楽もそうだといいなと思いますね。
今日本の次に聞かれているのが、なぜか南米で。また、ゆくゆくは海外のイベントにも出ていきたいんです。ぜひ、呼んでほしいですね。予想を裏切るような場所でやれたらいいなと思ってます。

Photography Mayumi Hosokura

