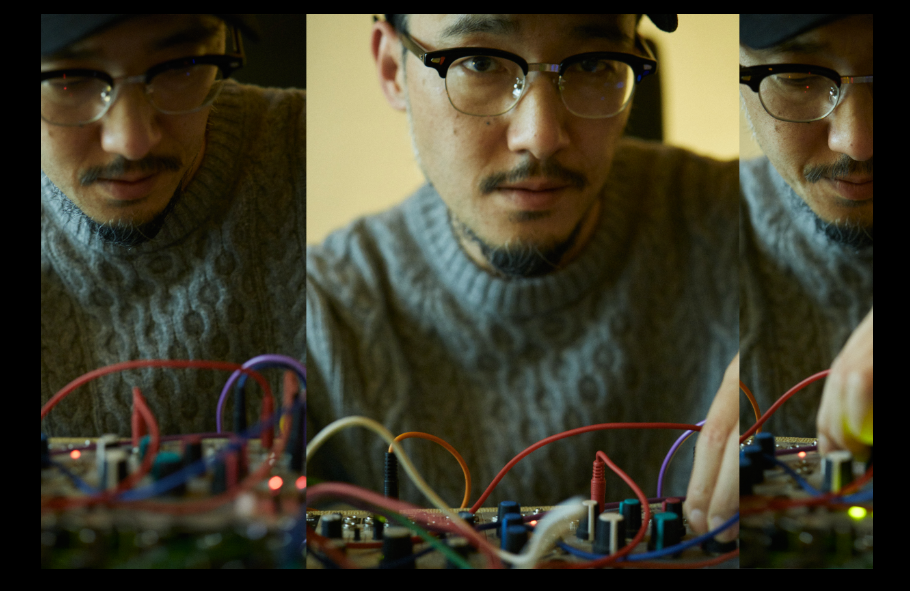ギアボックス・レコーズから新作『Late Spring』をリリースしたChihei Hatakeyama(畠山地平)がアンビエント・ミュージックに取り組み始めたのは2000年代初頭のことだった。当時を振り返ると1990年代から2000年代にかけて、東京をはじめウィーンやベルリン、シカゴ、ニューヨーク、ロンドンなど世界各国の都市で新たな即興音楽のシーンが同時多発的に勃興。時に「即興音楽の新たなパラダイム」あるいは「音響的即興」とも呼ばれたそれらの新潮流にリアルタイムで接していた畠山は、2000年代後半には自らも即興音楽シーンと関わりを持つようになり、アンビエント・ミュージックの制作プロセスにおいても即興演奏の手法を取り入れるようになっていったという。
前編に続くインタビューの後編では、1つの音楽的バックグラウンドである2000年代前半の東京の即興音楽シーンの魅力、あるいは音楽制作における即興演奏の効用やライヴと録音物の関係性、さらに今現在注目しているミュージシャンまで伺った。
「新しい試みが次から次へと出ていた」2000年代前半の即興音楽シーンの魅力
——後編では主に即興音楽と畠山さんの関わりについてお伺いしたいのですが、前編の最後の方で「2000年代前半はインプロ系のライヴによく行っていた」と仰っていましたよね。東京の即興音楽シーンの拠点の1つとして知られる代々木オフサイトがオープンしていた時期とも重なりますが、特に印象に残っているイベントなどはありますか?
畠山地平(以下、畠山):オフサイトには何回か行きましたね。たしかSachiko Mさんのイベントと、あとは伊東篤宏さんや秋山徹次さんのライヴだったと思います。インプロ系のライヴで一番衝撃的だったのは、アーストワイル・レコーズのジョン・アビーが主催しているアンプリファイ・フェスティバル。2002年に吉祥寺のスターパインズカフェで開催されたんですが、あれはめちゃくちゃおもしろかったです。しかもインプロ系のライヴなのに、なぜかお客さんが大量に来るんですよ(笑)。それはまあいいんですが、国内外のミュージシャンが集結してさまざまな組み合わせでライヴを披露したイベントで、特にトーマス・レーンとマーカス・ シュミックラーのデュオがすごかったですね。トーマス・レーンがEMSというアナログシンセを使用していたんですけど、非常に新鮮でした。
——当時の畠山さんは即興音楽にどういった魅力を感じていましたか?
畠山:僕は読書が好きなんですが、ちょうど2001年に佐々木敦さんの『テクノイズ・マテリアリズム』(青土社)という本が刊行されて、その衝撃がものすごかったんです。あそこに「二一世紀のフリー・インプロヴィゼーション」という章があって、大友良英さんやSachiko Mさん、デレク・ベイリーなどについて書かれていて。今思えば同じ本の中にミカ・ヴァイニオやジェフ・ミルズ、芦川聡も出てくるというのがすごいですけど(笑)、でも当時は例えばアルヴァ・ノト(カールステン・ニコライ)と杉本拓さんを一緒に語ることもごく普通にありましたからね。とにかくその本を手掛かりに、それまで聴いたことのない音楽と出会っていくことの新鮮さがありました。それと当時は機材のテクノロジカルな発展が目に見えるように進んでいたので、今と比べて、それ以前の時代には明らかに存在しなかった音楽がどんどん出現していたんです。インプロ系も当時は機材を含めて新しい試みが次から次へと出ていて、それもあって魅力的に感じていました。
——弱音を中心としたストイックな演奏や無音の多用など、当時のいわゆる音響的即興に畠山さん自身が取り組むことはなかったのでしょうか?
畠山:最初のアルバム(『Minima Moralia』)を出す前にいくつか録音を試みたことはあったんですが、どうもしっくりこなかったんですよね。インプロ系のライヴを聴くのは好きだったんですけど、いざ自分が作品を制作するとなると、やっぱり自分の感覚を頼りにしなければならない。そうしないと作品の価値を測る物差しを持つことができないので。それで自分にとってしっくりくる音楽はなんだろうと探った時に、ビートが入るとかせになってしまうので、とりあえずビートを排除した静かめの音楽で、ときおりメロディも見え隠れするもの、といった方向性で始めて、それが2006年に『Minima Moralia』というアルバムに結実したんです。なので最初はアンビエントやドローンをやろうというわけでもなかったんですね。
——音響的即興に接して、ご自身の音楽制作を行う上でヒントになったことはありましたか?
畠山:あんまりこういう風に捉える人はいないかもしれないですけど、当時のインプロ系のシーンから受けた影響で言うと、「音で作る風景」が大きかったです。例えば中村としまるさんとか秋山徹次さんの音楽って、イマジナリーなところもあるというか、音の風景が移り変わっていったり、時間とともに風景の「見え方」が生まれてきたりするところがあると思うんです。そういった音場感には刺激を受けましたね。なので『Minima Moralia』は、アンビエント・ミュージックとカテゴライズされることが多いですけど、音の使い方や構成の仕方、あとミックスの方法には、実はそういったインプロ系の音楽とつながるところがあると思っているんです。
『Late Spring』における、手法としてのインプロヴィゼーションの活用
——畠山さんは具体的な手法として即興演奏を用いることもありますよね。例えば今回の『Late Spring』では「即興一発録りで良いテイクを探していく」ということが1つのコンセプトとしてありました。
畠山:そうですね。若干手を加えた曲もあるにはあるんですが、基本的にはほぼすべて一発録りです。アコースティックギターの即興演奏を録音した7曲目の「Thunder Ringing in the Distance」も、なるべく録りっぱなしの状態で、後から音を足さないように、オーバーダブしないようにしようというコンセプトがありました。逆に言うと、楽曲ごとに「こういう即興演奏にしよう」というコンセプトは決めていて、その流れで何回か同じような演奏を録音して、良かったテイクを採用していったんです。
——まるでジャズのソロ・アルバムのような「即興演奏の一発録り」というアイデアはどこから浮かんできたのでしょうか?
畠山:いくつかあるんですが、1つは中村としまるさん、秋山徹次さん、それとエレクトロニクス奏者の池田謙さんと集まって飲んだことがきっかけになりました。コロナ禍になる前の話です。その時に雑談の中で「やっぱりオーバーダブで構築するよりも、1回の演奏でバチっと決める方がいい作品ができるよね」という話になったんです。あとは僕、レコーディング・エンジニアとしても仕事をしているんですが、今はDAWが便利になって簡単に一部分だけ差し替えてしまうことができるんですよね。それでジャズのセッションでもアドリブ部分だけ差し替えるみたいなことをやっているうちに、「本当にこれでいいんだろうか?」って疑問に思うようになったりして(笑)。そういった個人的な経験もあって、なるべく演奏を丸ごと録音しようと思うようになりました。
——それはマイルス・デイヴィス『On The Corner』の未編集バージョンの方が好きだという感覚とも近いのかもしれないですね。7曲目「Spica」の音飛びのようなグリッチ・ノイズも即興演奏の一発録りなんでしょうか?
畠山:そうです。それもモジュラーシンセを使用してリアルタイムで操作した演奏なんです。その意味では、演奏性の痕跡みたいなものが音の中に転がっていると思うので、そこらへんを聴きながら探してもらえると、普段ジャズを聴いているという人でも楽しめるところがあるかもしれないですね。
——それこそ菊地雅章さんのシンセ・ソロと並べて聴いてもおもしろいのではないかと思います。『Late Spring』では即興演奏の一発録りが採用されていますが、例えばすべて事前にDAWで構築することでは得られない、即興演奏ならではの音楽的要素はどのようなものだと思いますか?
畠山:1つはやっぱりタイム感でしょうか。DAWですべて作るとなると、どうしても拍子に縛られてしまうので。もちろん設定次第ではどんどん拍子が変わる音源も作れるんですが、その作業を打ち込みでこなすのはとても大変ですからね。けれども即興演奏だと、例えば4分の4拍子の曲でも、少しずつズレたり伸びたりするタイム感をその場で出すことができる。最近のモジュラーシンセのシーケンサーだと一応拍子が合わさるんですけど、アナログなので、ラップトップのDAWで作る音源と比べるとちょっとズレてる感じも出ていて、それはそれでアリだなと思っています。
「表面的には全く違うジャンルの音楽でも、たどるとジョン・ケージに行き当たる」
——ところで私が畠山さんのことを最初に知ったのは、実はアンビエント・ミュージックの文脈ではなくて、『Improvised Music from Japan 2009』という雑誌がきっかけだったんです。畠山さんがサウンド・アーティストの大城真さんと共同で主催していたイベント・シリーズ「AFTERWARDS」についてインタビュー記事が掲載されていますよね。なぜ大城さんと共同でイベントを企画するようになったのでしょうか?
畠山:単刀直入に言うと家が近かったからですね(笑)。というのも、僕はもともと藤沢に住んでいたんですが、2007年頃に上京して西荻窪に引っ越したんです。その時期に虹釜太郎さんから「みんなで花見をやろう」と誘われて、40人ぐらい集まったんですが、その中に大城さんもいて。話してみたら大城さんもまだ上京したばかりで、しかも家が歩いて行ける距離にあるということが判明した。それでよく飲みに行くようになって、一緒にイベントを企画しようという話になったんです。その後、2008年6月に最初のイベントを開催しました。
——記事によるとAFTERWARDSは夏目漱石の小説『それから』が由来で、「音楽の『それから』をイベントを通じて考えること」が1つのコンセプトとして掲げられていました。
畠山:そうですね。全然別のタイプのミュージシャンやアーティストが混ざり合ったライヴを企画していたんですが、2010年頃までは、むしろそういう異質な組み合わせの方が楽しいという雰囲気が残っていたんですよ。なので今振り返るとかなりカオスなラインアップになっているなあとは思います(笑)。ただ、文脈をたどると繋がる部分もあって、例えばアンビエント・ミュージックをさかのぼるとまずはブライアン・イーノに行き着くじゃないですか。そしてイーノはジョン・ケージから影響を受けている。その意味ではサウンド・アートやライヴ・エレクトロニクスと同根とも言えますよね。表面的には全く違うジャンルの音楽でも、たどっていくとケージに行き当たるところがある。逆に言うと、そこまでたどらないと繋がらないということでもありますが。
——畠山さんは今もケージの音楽を好んで聴くことがよくあるのでしょうか?
畠山:僕が最近よく聴いているのは、むしろケージが師事していたアルノルト・シェーンベルクですね。無調や十二音技法を使用した聴感的にカオスな音楽を作る一方で、暗いメロディーをつけたり歌を入れたりすることもあるじゃないですか。あのバランス感がとても好きなんです。それと、シェーンベルクの音楽をたどり直すと、途中で2度の世界大戦が発生して社会情勢が不安定だったこともあってか、音楽がまともに発展するのが難しい時期だったなと感じることもあります。戦後になるとケージが活躍し始めて、1952年に「4分33秒」が世に出ますよね。それって飛躍しすぎている感じがするというか、本来あったはずの歴史がケージの登場によって素っ飛ばされてしまったというか。あまりにも過激じゃないですか。なのでシェーンベルク以降、音楽の歴史がまともに積み重なっていたらどうなったんだろうと考えてしまうんです。
——なるほど、それほどのインパクトがあったからこそ、「たどるとケージに行き当たる」ということにもなると言いますか。
畠山:それと、デレク・ベイリーがフリー・インプロヴィゼーションの探求を始めるのは1960年代半ば頃なので、時系列的にはケージよりも後の時代になりますけど、音楽的にはベイリーはケージ以前に感じるところもあるんですよね。それはベイリーの旋律がシェーンベルクの弟子のアントン・ヴェーベルンから影響を受けているというところもあるかもしれないですが、一気に先に行きすぎてしまったケージに対して、ベイリーはその前に戻ってシェーンベルクまで続いていた歴史を解釈し直しているということなんじゃないかと思うんです。
「ライヴと録音物を行き来する、相互にフィードバックする関係」
——シェーンベルクの時代と比べると、ベイリーの活動には録音物というファクターが重要な一側面として加わってきますよね。1970年にベイリーはエヴァン・パーカーらとともに自主レーベルのインカス・レコーズも立ち上げています。1回性を重んじる即興演奏と反復聴取が可能な録音物は反りが合わないと言われることもありますが、畠山さんにとってライヴと録音物はどのような関係にあるのでしょうか?
畠山:今はコロナ禍でなかなかできないですけど、僕の場合はライヴ活動が重要なポジションを占めていて、ライヴと録音物を行き来することで次のステップに進むこともよくあるんですね。ライヴで実践した演奏方法を録音作品で試してみたり、自宅でレコーディング中に考えたことをライヴで演奏してみたり、そういった相互にフィードバックする関係です。それで、ライヴを自分1人でやるとなった時に、やっぱり録音物のようにDAWで緻密に構築したサウンドをそのまま再現することは不可能なので、毎回異なる音楽を作ろうとして、即興演奏の手法を手掛かりにすることはありますね。
——録音物を制作する上で即興演奏を手法として取り入れるようになったのはなぜでしたか?
畠山:アンビエント・ミュージックをやり始めた当初はDAWでキッチリと構築して音楽を作っていたんですが、そうするとどうしても自分の予想通りの作品しかできなくて、行き詰まることが多かったんです。そもそも何かを計画して作ることが苦手でもあったので(笑)。ただ、やっぱりラップトップPCで編集できるようになったのは大きかったですね。そうすると、その場で何かを弾いて、その素材を後でいくらでも編集することができる。『Minima Moralia』をリリースしてからは、意識的に即興演奏の手法を用いて、機材を前に精神を落ち着かせて何も考えずに演奏するようになっていきました。
——畠山さんはレーベル運営とイベント企画も手掛けていて、ライヴ/録音物の両面でプロデューサー的な役割を担うこともありますが、即興音楽と関連して、今注目されているミュージシャンはいますか?
畠山:注目しているミュージシャンはたくさんいますが、最近だとiwamakiさんという、シンセサイザーでノイズやドローンをかなりマニアックに重ねていくタイプの人がいて、彼女はすごく良いなと思いましたね。時々、僕のイベントにも出演していただいています。あとは水道橋フタリでよくライヴをやっていてものすごくレコードに詳しいサウンド・アーティストの岡川怜央くんとか、彼と一緒にこの前『Undercurrent/Wanderlust』というデュオ作をリリースしたヴォイスの鈴木彩文さんにも注目してますね。鈴木さんはギターの弾き語りでも活動しているんですが、それもすごく良いんですよ。
畠山地平
2006年にChihei Hatakeyamaとしてシカゴの前衛音楽専門レーベルKrankyより、ソロ・アルバムを『Minima Moralia』をリリース。以後は、イギリスのRural Colours、Under The SpireやオーストラリアのRoom40、日本のHome Normalなど、国内外のインデペンデントレーベルから多くの作品を発表し、海外でのライヴ・ツアーもおこなっている。海外での人気が高く、Spotifyの2017年「海外で最も再生された国内アーティスト」ではトップ10にランクインした。4月にイギリスのギアボックス・レコーズからアルバム『Late Spring』を発売した。
Photography Teppei Hoshida
Edit Jun Ashizawa(TOKION)