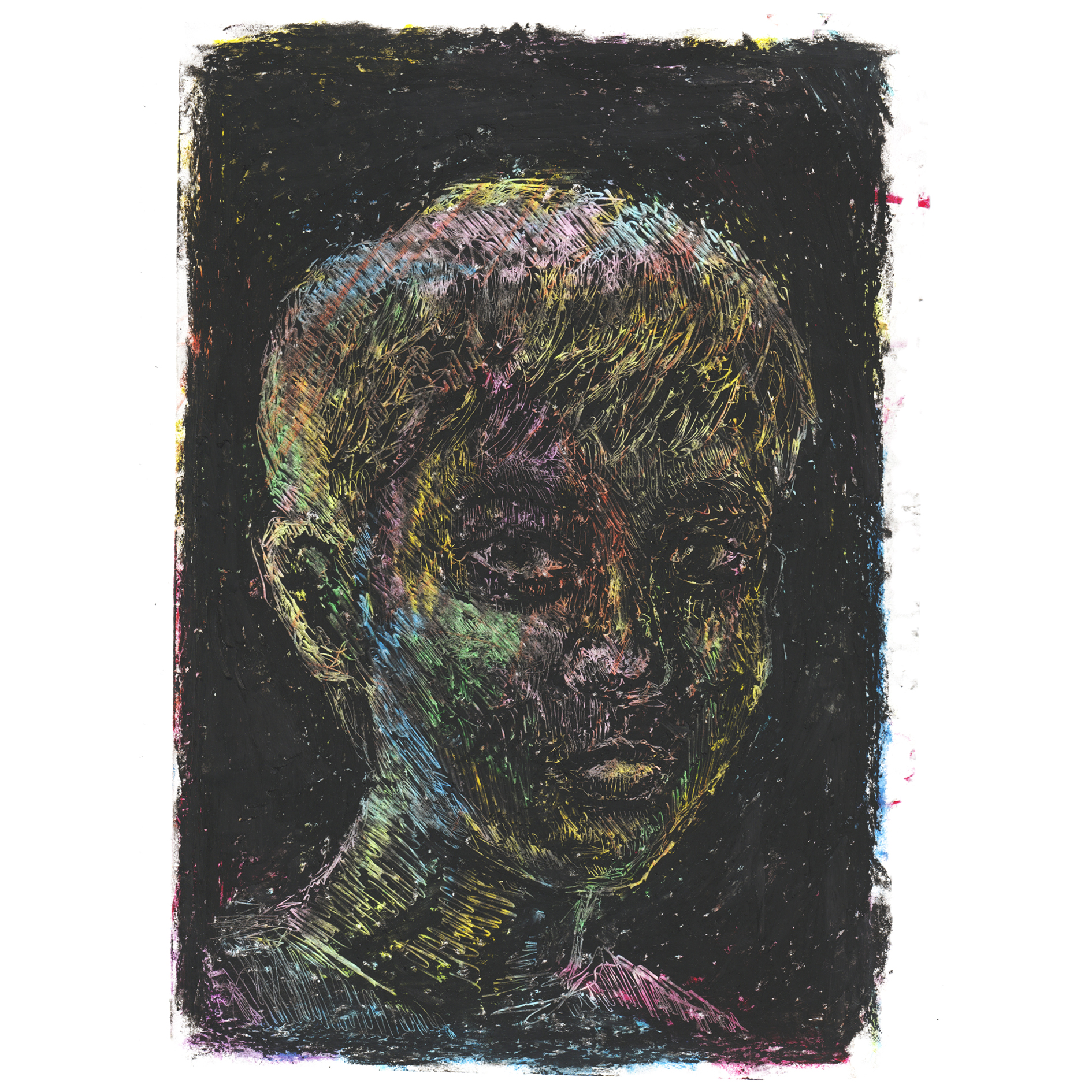2018年に折坂悠太が発表したアルバム『平成』は平成元年生まれの彼自身の姿を重ね合わせながら1つの時代の幕引きを描く、壮大ながらも強く“個”が出た作品であった。まとまった音源作品としてはそんな傑作『平成』以来、約2年半ぶりとなるミニアルバム『朝顔』が完成した。フジテレビ系月曜9時枠ドラマ『監察医 朝顔』の2シリーズ続いて主題歌となった「朝顔」を核として、シーズン2から新たに挿入歌となった「鶫」を含む5曲が収録。全曲に導入されている波多野敦子によるストリングスがサウンドを象徴しつつ、大衆の想いを引き受けて願いをささげるテーマが通底した、いわば『平成』と対極をなす“公”の歌にトライアルしたコンセプチュアルな作品だと言えるだろう。本作の生まれた背景と、折坂が今の時代に寄り添う「願い」にフォーカスして本人に話を聞いた。
「ドラマのタイアップ曲で終わらせず、自分なりの形で結実させたかった」
――2019年に発表した楽曲「朝顔」が再びドラマ主題歌となる中で、今回改めてご自身でリリースすることになった経緯から聞かせていただけますか。
折坂悠太(以下 、折坂):もともとシングル「朝顔」のリリースは配信だけだったんですけど、CDでも出そうというのがスタートです。ドラマを観ている方や自分の親戚、地元の友達にも「CDないの?」と言われるんですよ。CDで聴かない人が増えているといってもまだばかにできないものがあるなと。また今回「鶫」を新しくドラマのために作ることになったんですが、その2曲をつなぐ対句のような曲を作っていこうとなり、最終的には5曲入りになった形です。
――その「朝顔」と「鶫」に加えて、ミニアルバムとして仕上げたのはどういう狙いでした?
折坂:「朝顔」も「鶫」もこれまでの自分だけで判断できる曲作りとは違って、ドラマとすりあわせながら作っていったので苦労したんですよね。今までやってきた音楽とは別のベクトルの物差しがある中で、自分をいかに打ち出せばいいのかのキワキワを突いていくような作業でした。そうやってできたこの2曲には格別の思い入れがあるんですけど、一方で異質な感じがしていて。自分の音楽とはちょっと溝があるような……。だからドラマのタイアップ曲で終わらせず、自分なりの形で結実させたかった。だから2曲をシングルにするのではなく、そこに橋を架けてくれるような曲と一緒に出そうと。
――なるほど。「鶫」に関してドラマに提供する2曲目としての難しさはありましたか? 本作には「針の穴」という曲も収録されていますが、この言葉にも表れているような気がしていて。
折坂:まったくその通りなんですよ(笑)。「針の穴」というワードを思いついたきっかけは「鶫」を作ることに苦戦していた最中でした。「朝顔」も苦労しましたが、「鶫」はそこに加えて、「朝顔」をある種の基準として作る必要があったので、すごく複雑に考えてしまって。完成するまでに半年くらいかかりました。
――苦労を重ねた結果、「鶫」はどのようなテーマで作られましたか?
折坂:まず「朝顔」はポジティブで希望のある歌でもありますが、ちょっと憂いがあると捉えていて。もうここにいない人に対して思う気持ちとか、逆にもういない人はどう感じているのだろうかというのがテーマでした。その次の曲として「鶫」を作るタイミングで自死のニュースが入ってきたり、新型コロナで自粛期間になったり、嵐が来ていることを感じて、やっぱりこの状況を踏まえないと自分の表現として成り立たないなと。そこで出てきた歌詞が“夜が明ける”という簡潔で、ある種使い古されている言葉でした。
――“夜が明ける”には「朝顔」を象徴する歌詞“願う”の対句にも感じられます。この言葉を選んだ意図をもう少し教えていただけますか?
折坂:「朝顔」で歌われている“願う”は自ら発していますけど、“夜が明ける”はただ今を切り取っているだけで。そこに希望を読み取ることはできるけど、朝を迎えることが怖い人もきっといるでしょう。例えば今にも死んでしまいそうな人に対して、自分は歌い手としてどういう言葉をかけるのか考えていたんですね。そしたら安易に応援したり、希望を掲げたりすることはできなかった。最後のほうに出てくる“どうして 夜は明ける”という言葉には、含みみたいなものを持たせられる気がして。だからただ朝が来るのを一緒に見ている状況を映すことで、寄り添おうとしました。
――今の話は本作には収録されていないですけど、昨年発表された「春」とも共通性を感じました。この曲でも春が来ることをただ切り取っている。でも折坂さんの曲には、どうにか現実をポジティブな方向に持っていきたいというもがきがにじんでいる気がします。
折坂:ポジティブな歌を歌いたいとは思っています。でもそこには前提みたいなものが必要だと考えていて。まず「自分達が今いるところはこうだよね」という部分をちゃんと描かないとそこが活きてこないなと。「朝顔」と「鶫」は表層だけ見るとすごくポジティブだから、どういう状況で歌っているのかという前提や行間をちゃんと補足するのもこのミニアルバムの目的ですね。
――「針の穴」は正しくそんな状況を歌っていますね。
折坂:そうです。“嵐の只中”や“大しけの日”みたいな言葉が出てくる。明日も生きていられるかはわからない気持ちになることが自分にも度々あって。みんなそれぞれいろんな苦しみがある中で生きているということが、コロナになってより可視化された気がするんですよ。そのことを歌にしました。歌詞はただつらいですけど、ポジティブな方向にしたかったので曲調で痛快さを表しています。
――「今私が生きることは 針の穴を通すようなこと」と生活のつらさが表れていますが、どこか大変さをわかってくれることで救われるような心地になりました。
折坂:昨年出した「トーチ」という曲でも「私だけだ この街で こんな思いをしてる奴は」と歌っていて、その感覚とも近いですね。
――また「安里屋ユンタ」は以前からライヴでも披露されている八重山民謡です。このタイミングで収録したのはなぜでしょう?
折坂:ずっとライヴのレパートリーでしたが、「朝顔」が生まれてからは並びで演奏することも多くて。歌詞にある「マタハーリヌ ツィンダラ カヌシャマヨ」は「また逢いましょう、美しき人よ」という意味で、そこがなんとなく「朝顔」のテーマと親和性を感じていたので入れたかったんです。
――そもそも折坂さんがずっと「安里屋ユンタ」を歌っている理由はなんですか?
折坂:不思議と演奏していて気持ちがいいんですよ(笑)。基本的に歌う時は気合を入れるんですが、この曲を歌っている時は、もうなんかお風呂に入っている感覚なんですよね。なぜかはわかりませんが、そういう自分のリラックス状態を引き出してくれるので歌い続けているのかなと。
――インストゥルメンタル「のこされた者のワルツ」にはある種「針の穴」とは対照的に嵐が過ぎ去ったあとの平穏が描かれているような印象を受けました。
折坂:当初は4曲入りの予定でしたが、どれもドラマチックな抑揚を持った歌がそろって。だからもっとフラットな生活のBGMのようなものを入れたくて、録音の直前に作った曲です。ドラマ自体も亡くなったお母さんを思いながら、のこされた人達が生活している様が描かれているので、そこと地続きのイメージでした。
活動初期と現在をつなぐ、「願う」という感覚
――ドラマに合わせて作った曲をしっかり自分の音楽として結実させるための本作ですが、この経験は今後の活動にどう活きてくると思いますか?
折坂:それですよね……正直まだ整理できてなくて。今は「朝顔」と「鶫」という曲を自分の中にようやく落とし込めた感覚です。ドラマが関わるからこそできる曲が作れたという達成感はあるけど、かなり苦労したし、デモを作っている最中はこのままだと自分の音楽を信じられなくなるかもしれないという気持ちにまでなった瞬間もありました。危なかった(笑)。表現者としてこの経験を活かしていきたいですが、どう活きるかわかってくるのはこれからですかね。
――大変な作業ですが確実に新しい扉を開けてくれる機会になったのではないでしょうか。
折坂:そうですね。「朝顔」を作っている時にドラマサイドともやりとりする中で、歌詞も何度か変わっていきましたが、変わる言葉も自分の中から出てくるものじゃないと意味がないと思っていて。それで自分の思いをてらいなくシンプルにそぎ落とした結果、出てきた言葉が「願う」だったんですよね。「こんなことを歌うようになるなんてなぁ」と思っていましたし。
――以前別のインタビューで最初の作品『あけぼの』(2014年)の頃から「『願い』みたいな感覚があったのかもしれない」とお話しされていました。ずっと根底にはあったけど、「朝顔」でようやく歌えるようになったような感覚ですか?
折坂:そもそも自分が音楽を始めた頃は、僕のおばあちゃんに聴かせて良いと言ってもらえるような歌を歌いたいと思っていたんです。つまり日常的に音楽を聴くことがない人、表現や芸術の分野から遠い人に対して、自分の音楽を届けたかった。遠いかもしれないけど、思想や感覚、文化の違いを飛び越えて、ある一部分だけで共有できるのが音楽の気がします。そこには「あなたがどういう人か僕は知らないけど、あなたの幸せを願っています」という前提があると思っていて。だから今、テレビの向こうの人にドラマを通じて「願う」と歌えたのはすごく良かった。自分が歌い始めた時に思い描いていた、自分のおばあちゃんに良いと思ってもらうことともリンクしているなと。
生々しさや揺らぎを見せるライブ
――もう1つ折坂さんの表現の新たな変化という視点で、昨年「FESTIVAL de FRUE」に出演された際のコメントで「自粛前と考え方が少し変わって、ライヴの現場においては音楽をパッケージ化するのをやめようと意識しました」と仰っていました。演奏についてどのような心境の変化があったのでしょうか?
折坂:自分のライヴ表現において何が強みなのかと考えた時に、生々しさやその場の揺らぎにフォーカスするほうが意義のあることじゃないかなと思ったんです。最近のClubhouseとかインスタライヴも確実なものを届けるのではなく、途中の揺らぎの部分に何かを見出すようなものですよね。自粛期間で人に会えなくなって、「何話したか覚えてないけど今日はこの人と出会って楽しかったな」みたいなことは減りましたし、誰かと確かじゃないことを話すような、言い淀んでいる声みたいなものも大事だったなと思えてきて。
――最近インスタライヴをしたり、SoundCloudに多重録音のトラックを上げたりされていますよね。
折坂:プロモーションの意味もありますが、今見てもらいたいのは自分が今生きている姿なんじゃないかなと。だからライヴ表現においては作品としてパッケージされたものではなく、今生きている記録として出していきたい。
――それは昨年ライヴ音源集『暁のわたし』をリリースしたことも影響しています?
折坂:あるかもしれませんね。本当はもっとうまくいった演奏はあったんですけど、あそこに入っている音源は試行錯誤しながらやっているとか、この時の自分がすごく高まってたとか、その場所の空気感が出ているものを重視して選びました。自分のこれまでの音楽の中で自分自身が聴きたいと思うものは、必ずしもバッキバキにうまくいった演奏ではないのかもしれない。
――制作方法もアウトプットの形態も増えていく中で、次のアルバムに向けた狙いは見つかっていますか?
折坂:なんとなくはあるんですけど、まだそれぞれの取り組みで固めてきたものを分解してまた並べなおす作業をするのだろうというくらいです。2019年から京都のミュージシャン達と「重奏」編成(yatchi、senoo ricky、宮田あずみ、山内弘太)をやっているんですが、最近僕がいない時に京都で重奏メンバーに、quaeruの若松ヨウジンさんが入って演奏することもあるんですよね。客観的に見ていてそれがすごくよくって、今このバンドにどんどん引かれていってます。まだ彼らと作品を作れていないので、彼らの良さを最大限に引き出しながら、自分を反映させるようなものをやりたいですね。

折坂悠太
平成元年、鳥取県生まれのシンガー・ソングライター。幼少期をロシアやイランで過ごし、帰国後は千葉県に移る。2013年からギターの弾き語りでライヴ活動を開始。2018年10月にリリースしたセカンド・アルバム『平成』が「CDショップ大賞」を受賞するなど各所で高い評価を得る。2019年7月クールのフジテレビ系月曜9時枠ドラマ「監察医 朝顔」主題歌としてシングル『朝顔』を発表し、2020年11月2日放映開始の続編でも引き続き主題歌を担当している。また、2020年11月20日公開の映画『泣く子はいねぇが』の主題歌・音楽も手掛けた。
https://orisakayuta.jp