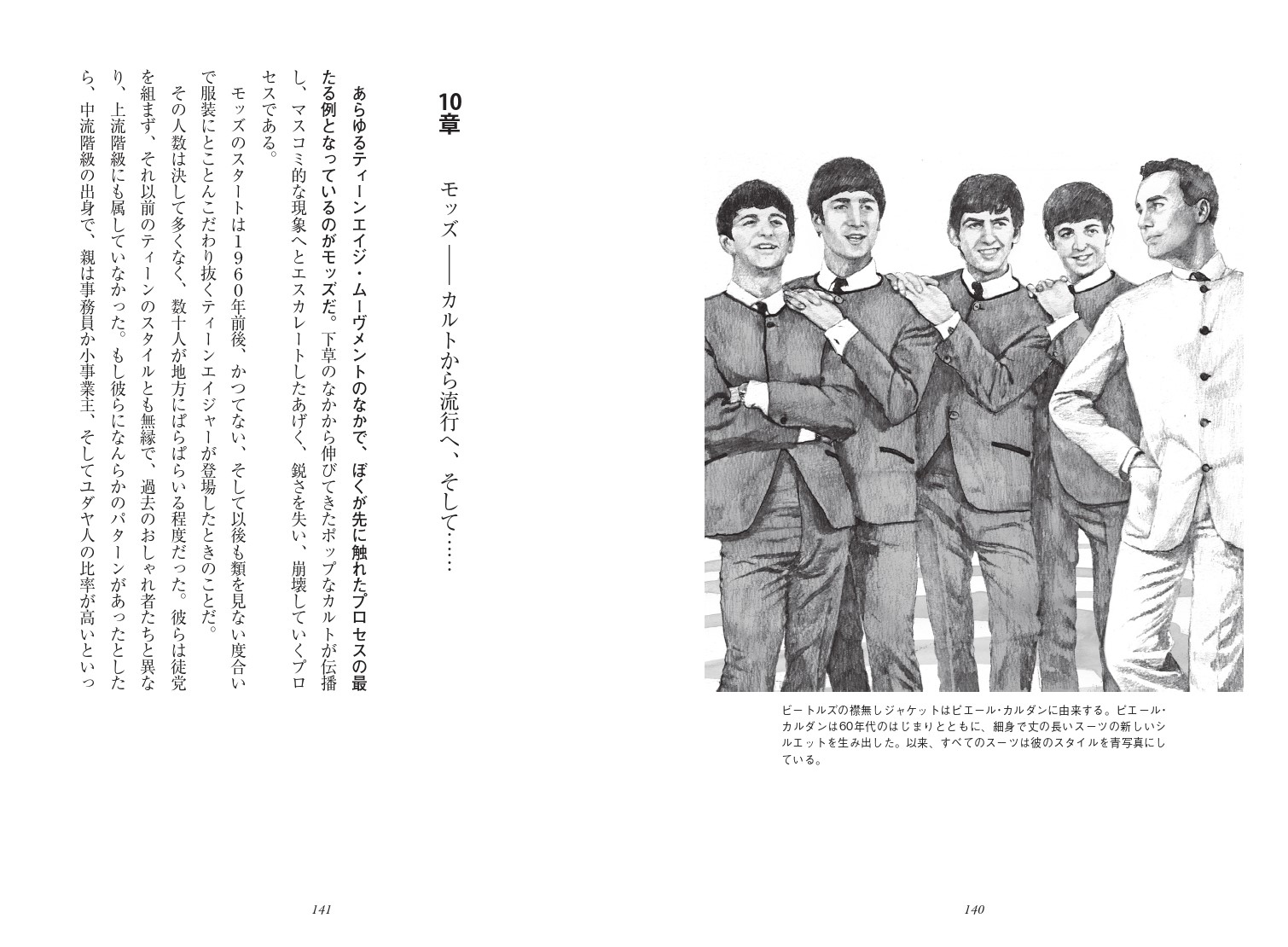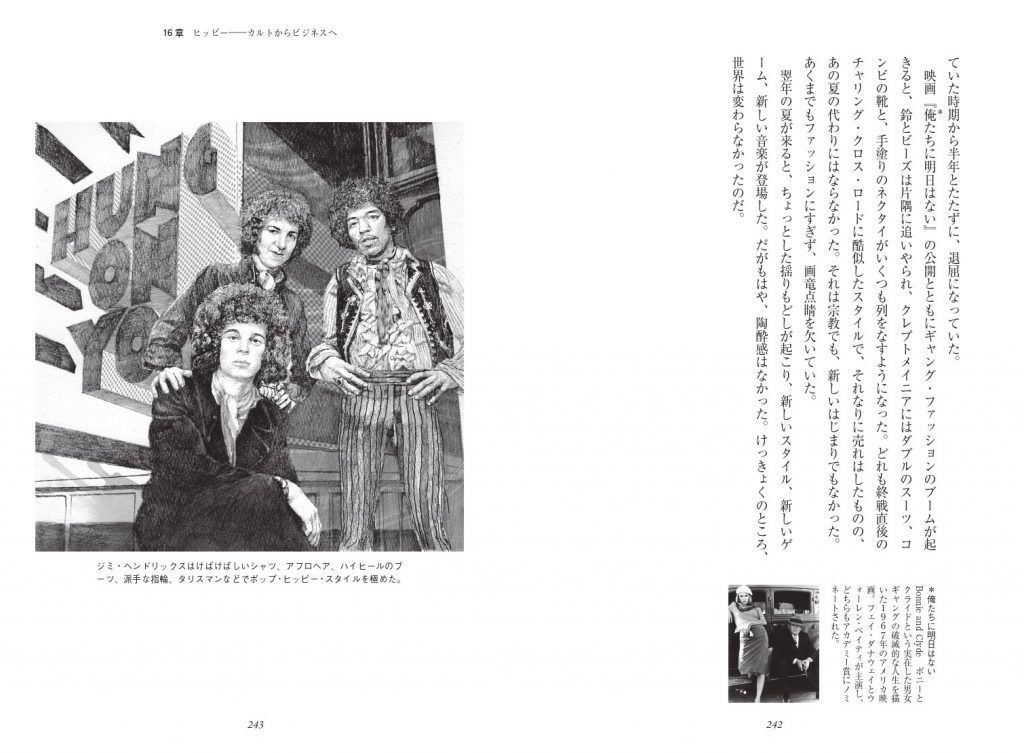今から50年前、1971年のロンドン。ニック・コーンはメンズファッションについての初めての書籍を発表した。靴職人が嘆いた言葉をタイトルにしたという『誰がメンズファッションをつくったのか? 英国男性服飾史(Today There Are No Gentlemen)』(以下、『Gentlemen』)は、第二次世界大戦後のイギリスのメンズファッションシーンの変化を巧みに描いている。執筆時のコーンは25歳という若さだった。1969年初頭に出版した、王道のスタイルに抗うロック文化が芽吹くきっかけを辿りながら、ロック精神の死を訴えた話題作『Awopbopaloobop Alopbamboom』の執筆中に収集した情報を基にしているという。1960年代におけるロンドンの音楽シーンのジャーナリストとして、かけがえのない人生を体験してきた現代におけるストーリーテラーでもあるコーンは、サブカルチャーの勃興や変遷、ブティック経営者達の関わり、労働者階級の若者がなけなしの金をはたいてスーツをあつらえたエピソードなどを鮮明に描き出した。2020年に『Gentlemen』は初版以来はじめて、日本語訳で発表された。
今回は、服飾史本として異例のロングセラー『Ametora: How Japan Saved American Style』(以下、『Ametora』)の著者であるデーヴィッド・マークスがコーンと対談する。『Gentlemen』再来の立役者でもあるマークスとニックの対談から、『Gentlemen』の日本や世界における意味に迫る。
右)デーヴィッド・マークス
右)デーヴィッド・マークス著『Ametora 日本がアメリカンスタイルを救った物語』
『Today There Are No Gentlemen』の制作背景と日本語訳のきっかけ
デーヴィッド・マークス(以下、マークス):2015年に拙著『Ametora』が出版されました。アメリカ版「エスクァイア」のファッションエディターであるニック・サリバンが、インスタグラムに書籍の写真とともに「最初のページしか読んでいないが、メンズファッションについて書いた、『Today There Are No Gentlemen』以来の傑作だ」と投稿してくれたんです。
ニック・コーン(以下、コーン):(笑)。
マークス:それを見て僕は、「おお! ニック・サリバンが僕の本を気に入ってくれている……」と口にした後、「『Today There Are No Gentlemen』って何だ?」と思いました。聞いたことのないタイトルでしたので。すぐにその本を検索したところ、レアな中古本で、しかも900ドルの高値で売られているのを見つけてがっかりしていました。そしたら、ある時、友達が図書館でこの本を見つけて、すべての内容を僕に送ってくれたんです。この本を読み始めた時、『Ametora』のメソドロジー(方法論)とストーリーに、とても近いことに気付いて驚きました。僕が書いたことがそのまま40年前に書かれているように感じたと同時に、この本を参考にしなかった自分が恥ずかしくなりました。
ファッション関連の本でいつも不満に思うのは、トレンドが、魔法のように急に現れるように書かれていること。ある日、モッズが現れて、また別の日にスキンヘッズが現れるというように。あなたの本は、その時どんな人物が集団を作り上げたのか、具体的なブティックやデザイナーが書かれています。サブカルチャーの視点で、モッズと呼ばれるようになる若者に関する話も載っています。『Ametora』でも、カルチャーやムーブメントが突然湧き出るのではなく、特定の人達によって生み出されてきた事実を伝えようと思いました。
『Gentlemen』はファッション史上、最も価値の高い作品の1つと思っていたので、どうにか復刊できないかと考えていましたが、その方法を見つける事ができずにいましたが、ようやくエージェントを見つけることができました。その後、1年かけて『Ametora』を日本で出版してくれた「ディスクユニオン」の出版部門に働きかけて、一緒に翻訳に取りかかりました。日本語版『Gentlemen』には『Ametora』と同じ翻訳家を起用し、1950年代のブリティッシュ英語特有の慣用句(例えば、“Super-mac”はハロルド・マクミラン首相を指す)など、翻訳しづらい部分を特定し、全般にわたって、サポートを続けて、この本の重要性を説明するために序文を執筆しました。何より僕がこの本を復刊させたかったのは、出版された1971年よりも、メンズウェアの勢いが高まっている現在の方が、興味を持つ読者がいると思ったからです。
コーン:それは、素敵な言葉をありがとう。ただ、『Gentlemen』は、「人は洋服の選択で自らを表現する。身に着けるものすべては、適当に選ばれたものではなく、着る人を物語り、自分がどうありたいかを世の中に示す」という、非常にシンプルな考えから生まれたものです。今、この考えはベーシックだと思いますが、出版当時はそうではなかった。「自分はクローゼットにあった洋服をただ適当に着ただけ。ファッションで自分を表現するなんて、気取ってるだけでくだらない」と男性読者の反発を生みました。多くの批判を浴びたために、すぐに打切りになってしまいました……。その他にも、イギリスに特定した内容だったことも追い打ちでしたね。当時はアメリカや諸外国の姉妹編を、少しずつ増やしていく予定だったため、この本は儚いというよりなくなってしまいました……。今まで私が執筆した本で、先ほどマークスが言っていた、この本の日本語版を除いて、唯一重版されなかった作品です。トレンドとは別の視点でファッションを捉えたり、ファッションそのものが“ストーリー”になることに対して、ようやくみんなが話して、注目するようになったのではないでしょうか?
マークス:ニックはそれまでロックンロールについて執筆していましたが、ファッションを書こうと思ったきっかけはなんですか? 出版社からの提案だったのでしょうか? それとも、自らファッションについて書きたいと思ったのでしょうか?
コーン:確か出版社の人とランチをした時に話し合って決めたと思います。彼は『Awopbopaloobop』の時に、お世話になった出版社のトニー・ゴッドウィン。聞き上手だったので「『Awopbopaloobop』のアイデアについてもっと聞かせてくれないか?」と聞かれたんです。
マークス:最近の人は“テディ・ボーイ”“スキンヘッズ”“モッズ”等、サブカルチャーをリスペクトしていますが、当時は明らかに、多くの人々に嫌われていませんでしたか?
コーン:全くその通り。
マークス:あなたのソーシャル・ムーブメントを真摯に受け止める姿勢を見て、当時の読者はどのようなリアクションをされていましたか? 本書はソーシャル・ムーブメントを揶揄したり、批判ではなく、「サブカルチャーに関わる人は洋服を通して正当に自身を表現している」ということが書かれています。
コーン:いつも実践していることを書いていたので、ある意味、自分のトレードマークのような感じでした。例えば、他の作家は社交界には出向くけど、ストリートに注目することはなかった。だから、あえてストリートに出たんです。私はいつも「ストリートにはエネルギーと現実がある」と言ってきましたし、そこから、ロックに関わる本や、『Gentlemen』のアイデアが生まれたんです。その後、映画化されるまで非難を浴び続けた、『Saturday Night Fever』もストリートから生まれた物語です。
マークス:あなたの本には「イギリスにおける洋服は“紳士服”を表す。つまり、ファッションは上流階級が実践してから世に広まったもの」という概念に対する思いがたくさん込められています。「労働者階級の若者が上流階級のファッションのアイデアを見て盗み、自己流に解釈することで新しいファッションを生み出していた」と書かれています。トム・ウルフがアメリカのユース・カルチャーについて書いた内容に似ている箇所がたくさんあるのですが、トム・ウルフの当時の作品についてどう思っていましたか?
コーン:もちろん、トム・ウルフは知っていましたが……ファンになったことはありません。主題から外れて作家が主体になるような内容は書きたくありませんでしたから。ウルフの作品は自らを誇示する内容が多く、本来のストーリーが見えなくなってしまっている。あと『The Noonday Underground』(ブリティッシュ・モッズについてのエッセイ本)を書いていましたが、リアリティーを感じる事ができませんでした。なぜかというと、私はもちろん、その本に登場する人々やクラブをよく知っていましたから。気取った人が、気取った一日を過ごすための休暇でイギリスに観光しに来た印象しか残りませんでした。私にとってこの場所は、人生であり、週末だけでなく毎日の生活の舞台なんです。
マークス:とても興味深いお話ですね。
時代を作るカルチャーは一瞬でなくなってしまうような“エフェメラ性”にこそ魅力がある
コーン:でも、私の人生ではなくなってしまいました。20代の後半に突然ファッションに対する興味を失ってしまったんです。
――1970年代後半でしょうか?
コーン:1970年代半ばでしたね。“スタイル”について書く若い作家が急増して、私を“スタイル”を生み出した人として紹介したんです。何の反応も示しませんでした。だって「ロック評論」を生み出したほど、“スタイル”を作っているわけではなく、ただ興味のあることを書いていただけですから。
マークス:本の終盤に、ファッションへの興味を全くなくすことも“ファッショナブルな選択”と書かれているので伝わりました。ご自身のことを言っていたんですね?
コーン:ある程度はそうですね。当時、ロックやファッションは、その時代だけのもので一瞬でなくなってしまうような“エフェメラ性”に魅力を感じていたんだと思います。だから、誰かがブティックをオープンして素晴らしい洋服を作ったとして、40年後も同じ人達が働き続けてオリジナルのレプリカを作るようなことが、どうしても受け入れられなかったんです。新しい洋服は瞬間的に楽しみ、とことん味わった後は次に進むべきだと考えていました。
――あなたの本に素晴らしい一文があります。“テイスト”についてドノヴァンは「とてもつまらなく、無意味なものだ」と言っています。彼の考えに対して「彼としては、非常に無知な発言。“テイスト”は絶対的なものでなく、常に進化していくもの。また、ある世代にとって良い“テイスト”とされていたものは、次の世代で廃れるかもしれない。われわれの時代では、オーソドックスや礼儀正しさと同等の意味を持つ言葉として使われていたが、それは間違っている。良い“テイスト”の意味を定義するなら、“その時々”に言える感性であるべき。例えば、1960年代に白シャツとグレーのバギーなスーツは全く受け入れられなかったようにね」と。
コーン:(笑)。
マークス:“テイスト”の概念の重要なターニングポイントを年代を追って詳細に説明していると思いました。長年、良い“テイスト”があるという権威的な考え方がありました。確かに、良い“テイスト”はゆっくり変化していきます。「1960年代に“テイスト”は上流階級の特権から離れ、より自由に変化することができ、その瞬間にふさわしいものになった」と書いています。今では当たり前になりましたが、本の中でその変化をリアルタイムで捉えています。
コーン:うーん……。その一文には裏の意味があるんです。当然、出版社はそこを掘り下げてほしくなかったはずですが、1971年に労働者階級の人々がファッションのムーブメントを作っていると思われていましたが、実際には、ゲイカルチャーからアイデアを採用していました。当時のイギリスでの話ですが、それまでのカルチャーに変化を与えたもののほぼすべては、ゲイカルチャーやクラブが源泉で、労働者階級の若者が取り込んだというわけです。当時、彼等の大半はゲイに偏見を持っていましたが、一目で素晴らしさや新しさは理解できたんです。
マークス:ユダヤ人の影響もあります。ラルフ・ローレンやJ.プレス等、アメリカのアパレル業界を代表するパイオニアの多くは、ユダヤ人が立ち上げたブランドであり、アメリカン・スタイルを築き上げてきました。この事について、具体的な見解はありますか?
コーン:実は、当時はそこまで考えていませんでしたね。私自身がユダヤ人ということも特に意識していませんでしたし、身近過ぎて気にしていませんでした。私の両親は2人ともユダヤ人でしたが、ユダヤの文化については教えてくれませんでした。今、考えるとゲイというよりも、ユダヤ系のゲイの人達でしたね。
マークス:ブライアン・エプスタインも含まれるのでしょうか?
コーン:もちろん。ロバート・スティグウッドのような例外もいましたが、基本的にはそうだったと言えます。当時、彼等はアウトサイダーであり、反抗者であったため、労働者階級の反抗に共感し、それをビジネスにすることができました。そして、多くの場合、彼等がアシストして作り出されたすべてのカルチャーを大切にしていましたね。
マークス:モッズムーブメントの章を読んでいた時、パイオニアがゲイだったという印象を受けませんでしたが、彼等に対する当時の偏見によってゲイの影響については控えめに記述する必要があったのだと推測します。
コーン:その通りです。必ずしも全員がゲイである必要はありませんが、振り返ると、私がこの本を書いていた時、「彼はゲイ、彼はそうじゃない」とカテゴライズすることはありませんでした。カーナビ―・ストリートができたり、キングズ・ロードができたり、メンズファッションの変遷を振り返ると、企業家にはユダヤ人でゲイの人が多かったように気付きました。ティーンファッションの中心地である、カーナビ―・ストリートをほぼ1人で築き上げたジョン・スティーヴンは例外でしたが。
*後編へ続く
ニック・コーン
1946年ロンドン生まれ。“ロック・ジャーナリストの父”と称されるジャーナリスト。主な翻訳書に『ブロードウェイ大通り』(河出書房新社)がある。映画『サタデー・ナイト・フィーバー』は、コーンが1976年の「ニューヨーク」誌に寄せた記事が原案になった。2020年、ファッションに革命を起こした、ブティックのオーナーやスタッフ、仕掛け人、デザイナー、ロックスターをテーマに、流行の変遷を詳述した傑作ノンフィクション『誰がメンズファッションをつくったのか? 英国男性服飾史』(DU BOOKS) が初めて邦訳された。
デーヴィッド・マークス
1978年、オクラホマ州生まれ、フロリダ州育ち。2001年にハーバード大学東洋学部卒、2006年に慶應義塾大学大学院修了。日本の音楽やファッション、アートについて「ニューヨーカー」「GQ」などに寄稿。ウェブジャーナルの「ネオジャポニスム」を編集。2017年に刊行された『AMETORA 日本がアメリカンスタイルを救った物語』は服飾史本としては異例の6刷のロングセラーとなる。
Twitter:@wdavidmarx