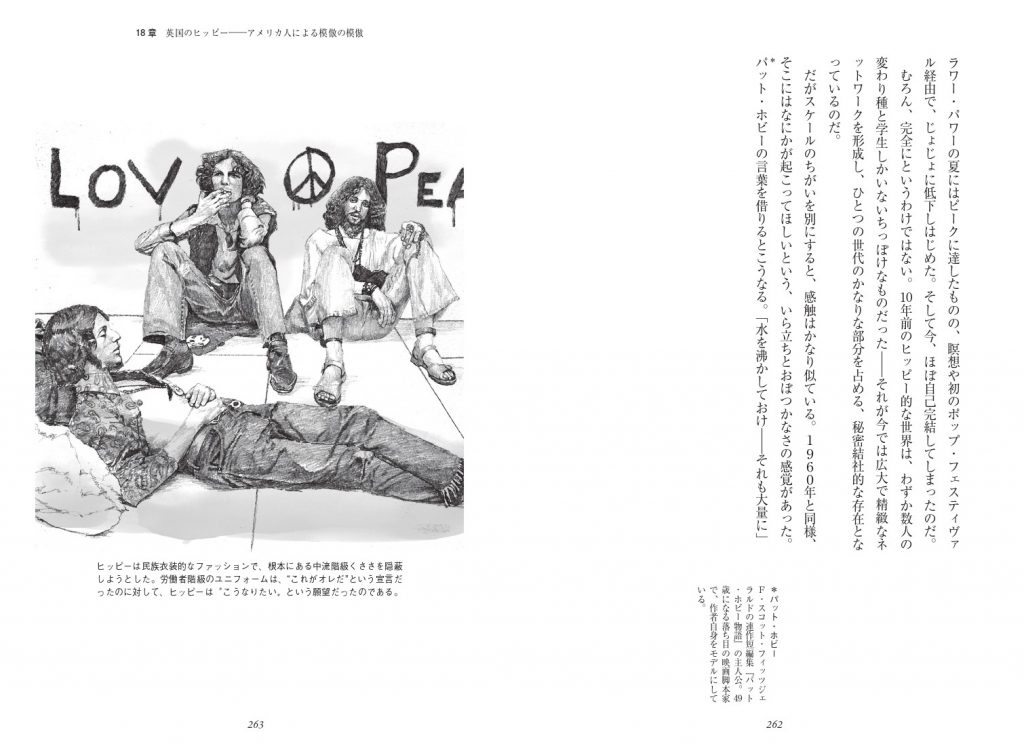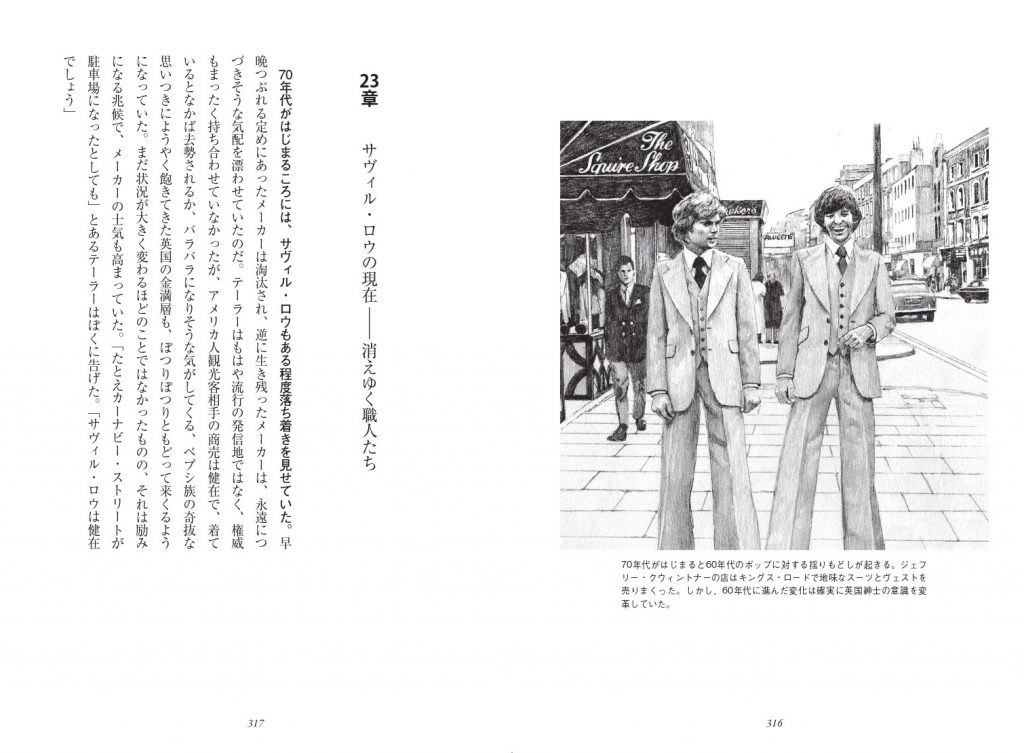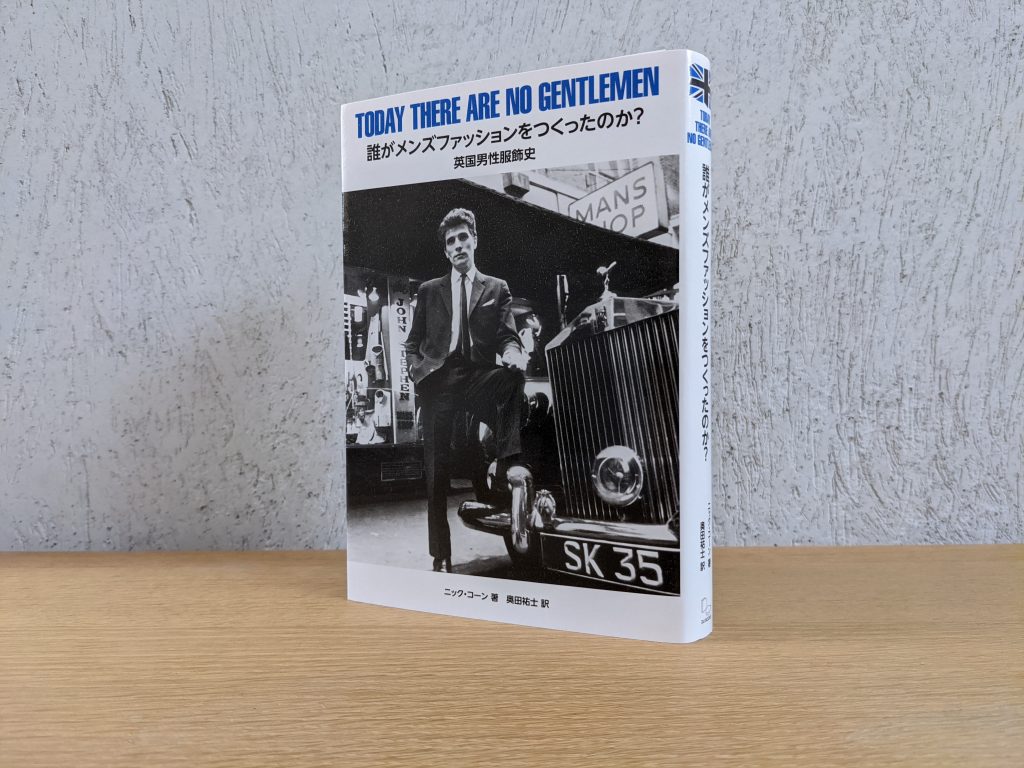1971年のロンドン。ニック・コーンはメンズファッションについての初めての書籍を発表した。靴職人が嘆いた言葉をタイトルにしたという『Today There Are No Gentlemen』(以下、『Gentlemen』)は、第二次世界大戦後のイギリスのメンズファッションシーンの変化を巧みに描いている。昨年の秋に『Gentlemen』は初版以来、初めて邦訳復刊された。今回は、服飾史本として異例のロングセラー『Ametora: How Japan Saved American Style』(以下、『Ametora』)の著者であるデーヴィッド・マークスがコーンと対談する。前編では、『Gentlemen』のコンセプトとその日本語訳、背後にあるサブテキストや歴史について語り合った。後編では、カルチャーとその移り変わりに関する見解とともに、『Gentlemen』以後の数十年間に焦点を当てていく。
右:デーヴィッド・マークス
右)デーヴィッド・マークス著『Ametora 日本がアメリカンスタイルを救った物語』
目まぐるしく変化する音楽とファッション
デーヴィッド・マークス(以下、マークス):『Gentlemen』は、おそらくファッション史本で最も目まぐるしいカルチャーの変遷を記述しています。この10年、大きなカルチャーチェンジは起こっていなくて、ゆっくりとした流れの今だからこそ興味深い。『Gentlemen』を読んで、1960年代は通常ではなく、例外だったという結論に達しました。また、当時のようなカルチャーチェンジをずっと追い続けることはとても難しい。日々変化するカルチャーについて、当時ははっきりとした輪角が見えていたのでしょうか? それとも、振り返ってから気付きましたか?
ニック・コーン(以下、コーン):振り返ってからですね。当時は、自動的に変化しているようでした。潮流はドラッグによって後押しされて、奇妙なことも普通に感じていたかもしれませんが……。しかも、瞬時に切り替わったように感じましたね。
どこかでこの話をした記憶があるのですが、1964年に新鋭のバンドのヴォーカルに「君は真のアーティストだ」と言うと、おちょくっている意味に取られて、殴られることもありました。一方で、1967年に、同じことをすると、彼等はショックを受けつつも、俗物の言葉だと、無視されたでしょうね。たった2、3年のうちに、ポップミュージックはビジネスやアートとして捉えられるようになりました。ファッションに関しても同様です。もちろん、両方ともお金が関係している話です。
マークス:1960年代の映画を観れば、フィルムグレインや色、登場人物が身に着けているものから、何年の作品かを言い当てることができたと思います。でも、現代の映画では難しい。2002年の映画を見ても、製作年を言い当てることはできません。
コーン:その通りですね。1960年代や1970年代は、例えばクラッシュなどのグループもそうですが、「自分はウェスト・ロンドンのバンドで、今は1979年。あのストリートとクラブでつるんでいて、こんなファッションをして、ファンも真似している」というように、特定的であることが重要でした。しかし、現代では時代性とのリンクはさほど重要とされずに、カルチャーが均一化されてしまっています。どこかのストリートや場所から生み出されたものは、すぐ世に広まり大衆化されてしまう。もはや、最初に場所や時間を特定するものを取り除くことから始まります。1960年代には、そんなことはあり得ませんでした。出身地や人が育ってきた環境が無視されることはありませんでしたね。
マークス:イギリスでテディ・ボーイがリバイバルした直後の1971年に『Gentlemen』が出版されて、まもなく、パンクロックが到来しましたが、この2つに関しては書かれていませんでした。当時はどう考えていましたか?
コーン:テディ・ボーイのリバイバルについてはあまり真剣に捉えていませんでしたし、リアルだとも思っていませんでした。誰かの主義というよりも、ただのマーケティング・コンセプトにしか見えませんでしたね。ただ、パンクはリアルに受け止めていました。個人的に、ヒップホップが到来するまで、パンクはいろいろな意味で最もオーセンティックなストリート・ムーブメントだったと思います。
パンク勃興と1970年代サブカルチャーの変革
マークス:マルコム・マクラーレンも1960年代のアパレル起業家のような人だったのでしょうか? もしくは、新鋭な印象ですか?
コーン:彼は“フェイク”という意味で本物でした。知り合いではありませんでしたが、素晴らしい精神を持った、危険を顧みないリスクテイカー。アンドリュー・オールダムが1960年代のローリング・ストーンズに飛びついたように、新しいものに常に目を向けていました。先見の明があったので、それと引き換えになるリスクも負うことができたんだと思います。彼の全くリスクを恐れない姿勢にリスペクトしています。
――マルコムは、『Gentlemen』がきっかけでショップをキングズ・ロードにオープンしたと、生前話していた記録が残っていると、読みました。とても象徴的な1コマだったと思います。
コーン:(笑)。
――『Gentlemen』が出版されてからすぐに、マルコムは有名な存在となりましたが、『Ametora』に少なくとも2回登場します。まず、原宿の「クリームソーダ」と山崎眞行さんから始まり、その後は、再び1980年代初頭に戻り、藤原ヒロシさんがマルコムに会いに行った話が書かれています。
マークス:そこは地続きになっているからです。マルコムのブティックは一時期、「レット・イット・ロック」という名前だったのですが、ある時から「トゥー・ファスト・トゥ・リヴ、トゥー・ヤング・トゥ・ダイ」に変わったんです。「トゥー・ファスト・トゥ・リヴ、トゥー・ヤング・トゥ・ダイ」は日本初のロックンロール・ストアである「クリームソーダ」のスローガンにもなりました。「クリームソーダ」を立ち上げた山崎眞行さんは、1974年から1975年までをロンドンで過ごし、マルコムのショップにも来ていました。帰国後、彼は原宿に「スーパーセックス」というパンクファッションのショップも立ち上げました。「スーパーセックス」は「セックス」(マルコムが妻ヴィヴィアン・ウェストウッドと立ち上げたブティック)をモデルとしていたので、当時、マルコムは日本のユースカルチャーに絶大な影響を与えていたんです。原宿は、東京のカーナビ―・ストリートのようなイメージで、「クリームソーダ」などのショップをはじめ、ユースカルチャーの源といえる場所。また、1990年代のストリートファッションの隆盛を作り上げた、藤原ヒロシさんは早くにヒップホップに目をつけていました。彼は、セディショナリーズに夢中でロンドンに行きましたが、そこでマルコムに「ヒップホップこそが新しいパンクだ」と言われたそうです。その後、彼はニューヨークに行き、日本とニューヨーク、ロンドンのストリートカルチャーの架け橋のような存在になったのです。
僕が今執筆している本には、彼等の歴史から一歩下がり、どのような “ルール”のもとにカルチャーに変化が生じたのかを追求しています。重力のような法則によってカルチャーのムーブメントが起こっているように感じます。そして、『Gentlemen』からわかることは、一定のリズム(期間)で切り替わっているということ。それぞれが、時代に爪痕を残すために生み出されるものの、次第にアイデアが他で利用され、商業化されてしまうことで、画一化されてしまう。さらに、次のムーブメントが現れて強く反発するわけですが、モッズからスキンヘッズへと時代が変化した時に見られた現象です。重要なのは各々が独立していないということ。以前のムーブメントを誇張したり、否定することから生まれているということです。つまり、カルチャーの変革は単独で起こるのではなく、常に前代のカルチャーと連動しているんです。
コーン:私も同じ考えですが、1つだけ補足したいことがあります。当時の前代のムーブメントへの反発に関しては、極端に別の方向へ向かっているような感じがしていましたが、振り返ってみると、そうではなかったと思います。ただ、次から次へと時代がつながっているだけであって、「自分は唯一無二」と言っているだけなんです。過去を繰り返すことで、自分達を追い詰めている。スローガンは異なりますが、根底にある衝動は変わりません。
数年前、アイルランド北部出身の女性から、私の人生を描いた映画を作りたいとアプローチがありました。きっかけを彼女に聞くと、彼女は日本のモッズに関するドキュメンタリーを制作する時に日本に行ったそうです。その時、日本人になぜ良いモッズの映画がないのか聞いたところ、「あなたは勘違いをしている。素晴らしいモッズ映画が1つあります。『サタデー・ナイト・フィーバー』」と答えたそうです。もちろん、彼等はディスコとモッズの違いも両方の関連性も理解していたんです。
マークス:彼等がファッションで起こそうとしているムーブメントの動機は同じですが、違いを表現するためには、常にその前から存在するカルチャーの文脈を理解しなければいけないということですね。
コーン:その通り。“父殺しの”フロイトの考えに似ていますね。
――マークスさんに聞きます。『Gentlemen』で、セシル・ジーのショップウィンドウに飾られていたミュージシャンのディスプレイに興味を抱き、魅力を感じているシーンがあります。「今まで見たことのない素晴らしい光景。ラメやシルク、サテンのティンセルが全体に施されて、マルーン、ゴールド、パープル、シルバー、真っ青なスカイブルーの色が、キラキラと花火のように光るダンスユニフォームのよう」と。1957年は音楽やファッションなど、ニックさんがロンドンに拠点を置くきっかけとなった重要な年だと解釈しました。『Ametora』は幅広いスタイルについて言及していますが、あなたも同じように衝撃的な瞬間を経験し記録したいと感じたのでしょうか?
マークス:僕はフロリダのペンサコーラという知名度があるほど大きな町でなく、大都市からかなり離れた都市で育ちました。ですので、(セシル・ジーのような)ショップへ出掛ける機会はありませんでした。僕にとってはMTVがすべて。兄と姉がいて2人とも、バンドにはまっていたんです。ほとんどの若者がメタルを聴いていた時に、僕はR.E.M.やU2を聴いて育ちました。ですので、早い段階で音楽の知識に関しては自信を持っていたと思います。
一方、ファッションは遠い存在に感じていました。当時のアメリカで洋服といえばTシャツやスニーカー、ショートパンツ、ジーンズがメインで、すべて20ドルで「GAP」で揃えるのがあたりまえ。そんな僕の人生を変えたのは、1996年、19歳の時に訪れた東京。今まで見たことのない、ファッションに溢れた街に突然出合ったわけです。当時のアメリカの雑誌などでは、「日本のキッズ達はクールじゃない」と書かれていたのですが、実際はTシャツ、ジーンズ、スニーカーだったとしても、スタイルが完璧でした。
例えば、あるブランド限定のTシャツに300ドル相当のセルビッジデニムをロールアップ、しかも、あえてセルビッジ・ラインを見せて、アメリカでは誰も履いていなかった「アディダス」の“スーパースター”を合わせていんです。そこから、ファッションに夢中になりました。Tシャツを買うために3時間も並んだことがありました。毎回この話をするたびに、大げさに聞こえますが、本当にたった1枚のTシャツのために3時間。その後に別のショップで同じTシャツが2倍の価格で売られているのを目にしました。その時に転売が始まっていたんですね。
東京での経験は、ただ服への関心を目覚めさせただけでなく、服を通して社会性を考えるきっかけとなりました。「一体どんな人が、Tシャツを1枚買うためだけに、3時間も並ぶのか?」今では「シュプリーム」のように、世界では当たり前の光景です。でも当時は、日本、東京でしか見られない現象でした。
ニック・コーン
1946年ロンドン生まれ。“ロック・ジャーナリストの父”と称されるジャーナリスト。主な翻訳書に『ブロードウェイ大通り』(河出書房新社)がある。映画『サタデー・ナイト・フィーバー』は、コーンが1976年の「ニューヨーク」誌に寄せた記事が原案になった。2020年、ファッションに革命を起こした、ブティックのオーナーやスタッフ、仕掛け人、デザイナー、ロックスターをテーマに、流行の変遷を詳述した傑作ノンフィクション『誰がメンズファッションをつくったのか? 英国男性服飾史』(DU BOOKS) が初めて邦訳された。
デーヴィッド・マークス
1978年、オクラホマ州生まれ、フロリダ州育ち。2001年にハーバード大学東洋学部卒、2006年に慶應義塾大学大学院修了。日本の音楽やファッション、アートについて「ニューヨーカー」「GQ」などに寄稿。ウェブジャーナルの「ネオジャポニスム」を編集。2017年に刊行された『AMETORA 日本がアメリカンスタイルを救った物語』は服飾史本としては異例の6刷のロングセラーとなる。
Twitter:@wdavidmarx