「ものづくり」の背景には、どのような「ものがたり」があるのだろうか? 本連載では、『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら』(宝島社)、『タイム・スリップ芥川賞』(ダイヤモンド社)の作者である菊池良が、各界のクリエイターをゲストに迎え、そのクリエイションにおける小説やエッセイなど言葉からの影響について、対話から解き明かしていく。第3回のゲストは企画デザイン会社・2時の楢﨑友里さん、田中桃子さんのお2人です。

2時は、フェリシモで7年間にわたりユーモア雑貨の商品企画に携わってきた楢﨑友里さんと田中桃子さんが2020年に設立した企画デザイン会社です。世の中を楽しくするモノやコトを生み出すことを活動の指針として、犬が「勝訴」の判決をくわえて走っている写真がSNSでも大いに話題となった犬用おもちゃ「勝訴マスコット」(2021年、バンダイ)や、ファスナー上を「P」の文字の形をしたスライダーが移動する「動く点Pポーチ」(2021年、Creco)など、時計の2時の方角「ななめ上」の発想からユニークなプロダクトを企画担当として社会に送り出しています。
そんなお2人が挙げたのは次の3冊でした。
・穂村弘『本当はちがうんだ日記』(集英社)
・トーマス・トウェイツ『ゼロからトースターを作ってみた結果』(新潮社)
・バカリズム『架空OL日記』(小学館)
さて、この3冊にはどんな“ものづくりとものがたり”があるのでしょうか?
(『本当はちがうんだ日記』『ゼロからトースターを作ってみた結果』は楢﨑さん、『架空OL日記』は田中さんが挙げました)
「こんな考え方もあるのか」と気付かせてくれる、穂村弘『本当はちがうんだ日記』
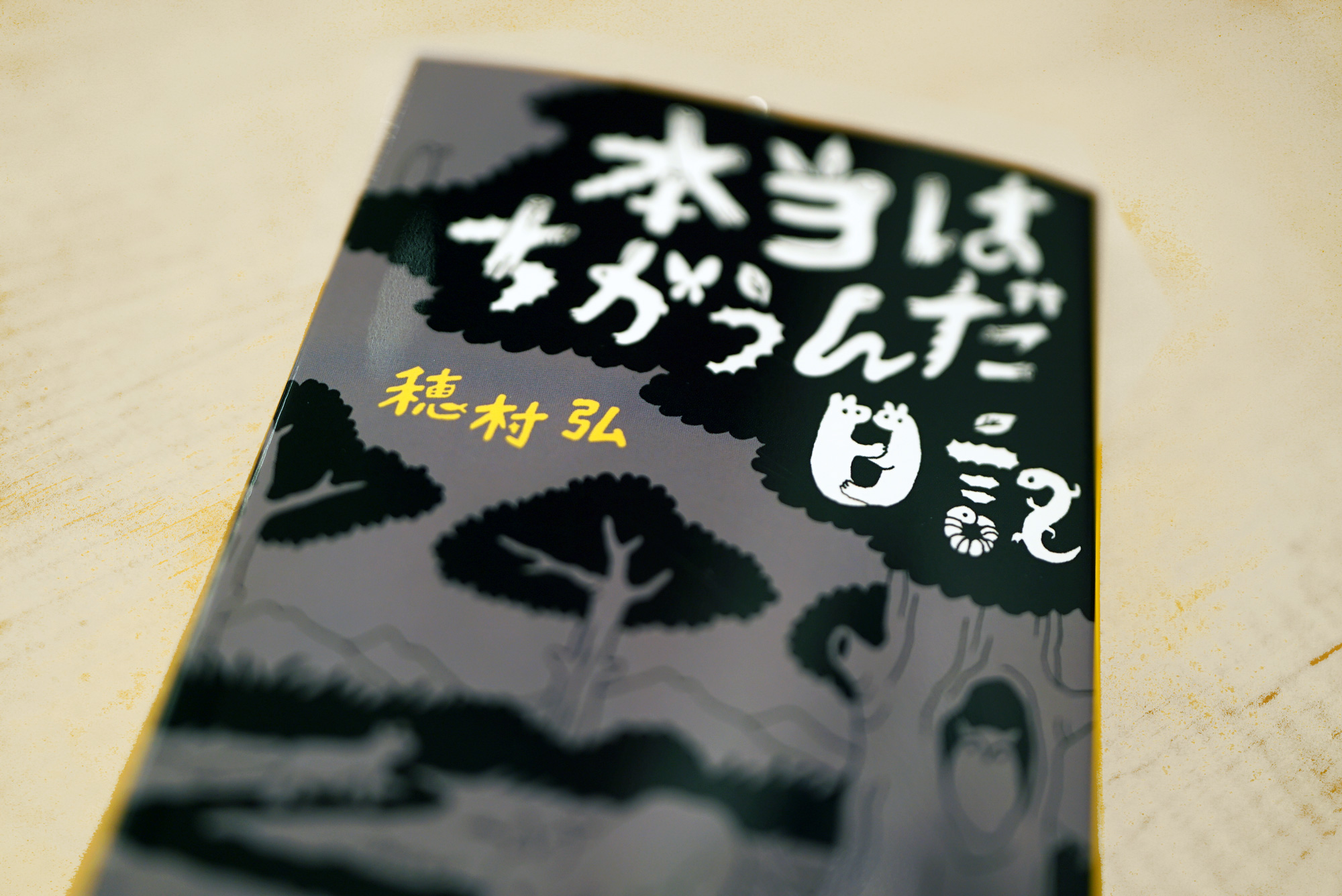
──歌人の穂村弘さんのエッセイ『本当はちがうんだ日記』。こちらはいつ頃読まれたんですか?
楢﨑友里(以下、楢﨑):社会人になってからだと思います。大学の時までは、小説はすごく読んでいたんですけど、エッセイはあまり興味がなくて。ほとんど読んだことがなかったんです。
でも、たしかたまたま人に「穂村さん、おもしろいよ」と教えてもらって、それで1冊読もうかと思ったのが始まりです。
──『本当はちがうんだ日記』がその1冊め?
楢﨑:そうです。
──この本はだいたいどれも4ページほどで終わるエッセイです。基本的に穂村さんの日常を描いていて、どれもくすっと笑えますよね。
楢﨑:すごく読み心地は軽いんですが、それぞれオチもちゃんとあって、切り口がすごくおもしろいと思いました。どのエッセイも短いんですが、どれも味つけが濃いというか。
日常の切り取り方がすごく秀逸で、「ああ、こんな考え方があったんだ」って。
しかも、読者に警戒心を与えない、穂村さんのちょっとダメな部分を出して日常を切り取っている感じが絶妙で。この本を読んでから、穂村さんのエッセイをたくさん読んだほどハマった1冊です。
──オチのつけ方が毎回すごいですよね。ぼくはあだ名のエピソードが好きで。自分は人生で一度もあだ名をつけられたことがない、っていうエッセイなんですけど、急に別の話になってオチがつくっていう。楢﨑さんは特にこのエピソードが印象に残ったっていうのはありますか?
楢﨑:『本当はちがうんだ日記』に載っているものだったら、まず最初に出てくるエスプレッソの話ですね。書き出しからもう心を掴まれちゃって。私はエスプレッソが好きだって言いながら、苦くて飲めたものじゃないっていう始まりで。
穂村さんのエッセイの特徴だと思うんですが、エッセイの中で何も起きていないじゃないですか。スタバに行ってもグランデが頼めないとか、エスプレッソが苦くて飲めないとか。
事件は何も起きていないし、ドラマチックなことはほとんどない日常の出来事なんですよね。例えばネットオークションをしているだけなのに、なんでここまでおもしろく書けるのだろうかって。すごく日常を楽しむ力がある方だなと思いました。
エスプレッソの話も、エスプレッソを飲んだだけなのに、こんな何ページも書けるのかというのがまず衝撃でした。すごくそのくだりは印象に残っています。
──自意識って言っていいのかわからないですけど、内面の逡巡や、ほんとうは背伸びしたいけど恥ずかしいみたいな部分が、すごく共感して読めますよね。こういう本を読むと、文体が頭の中に移っちゃって、日常をそういう目線で過ごすようになりませんか?
楢﨑:めちゃくちゃわかります。そういう意味でクリエイティブな部分でも影響を受けた1冊でもあります。
私達が作るものは日常的に使うものなので、発想において、いかに毎日の生活の中で空想するかというところがあります。「今目の前にあるコップがどんなコップだったらおもしろいだろう」とか。「クッションがどんな形だったらおもしろいだろう」とか。
そういうイマジナリーな部分がかなり必要で、毎日を楽しい目線で見ていくみたいなのは重要なんです。かなり穂村さんの本には影響を受けているんじゃないかなと思います。
──確かにこのエッセイって空想で、日常の中で「こう思われたらどうしよう」と考えをめぐらすだけだったりしますよね。日常をどう見るか、という本ですね。この目線で日々をすごしていると、いろんな発想が出てきそうですね。
ものづくりの過程で起きているさまざまなことを意識できるようになる、トーマス・トウェイツ『ゼロからトースターを作ってみた結果』
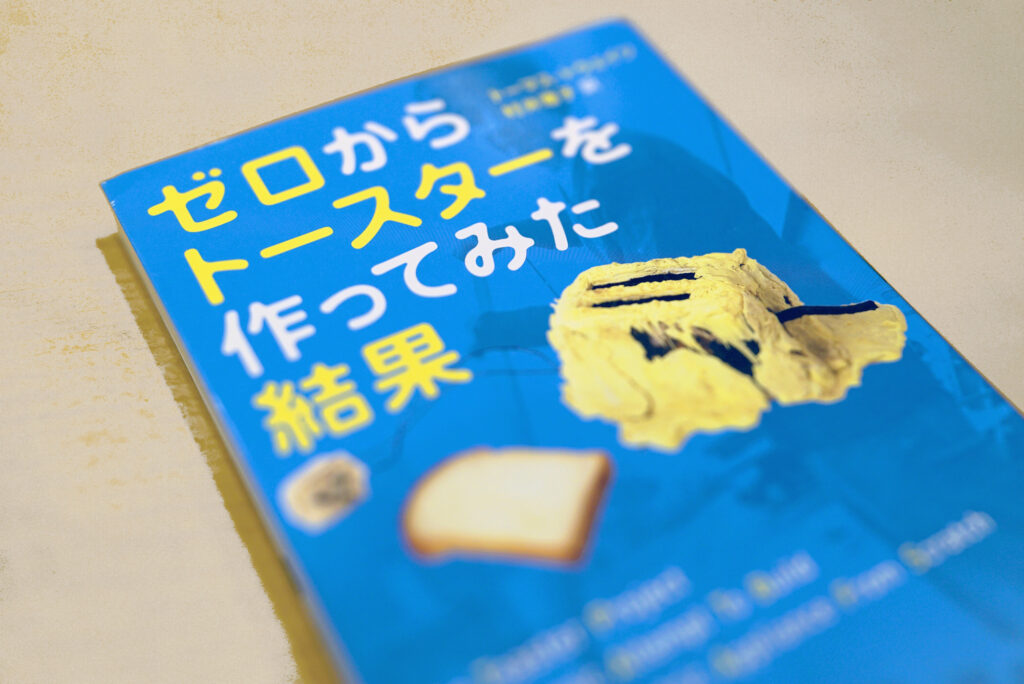
──『本当はちがうんだ日記』が何も起きてないとしたら、2冊目のこの本はすごく行動する本です。
楢﨑:そうですよね、とんでもない行動力です。この本を読んだのも社会人になってからで、何で読んだのかきっかけは思い出せないんですけど、ほんとうに興味を持ってたまたま読んだという感じです。
──2012年に出版されているので、ちょうど10年前ですね。この本はトースターを個人で一から作るっていう。それも本当に一からですよね。
楢﨑:内容的にもすごくワクワクしておもしろいっていうのはもちろんなんですけど、やっぱり私達はものづくりをしている立場で、ぜんぶ自分達の手でつくるのではなくて、かなり分業しているんです。
プランナーが考えたものを、日本のメーカーや海外の工場でたくさんの分業を経て完成させます。ただ、それを意識する機会って少なくて、自分達が考えたものがある日サンプルになって完成した状態で見られるわけです。この本を読むと、その過程で何が起きているのかをすごく意識できるんです。
私達みたいなものづくりをしている人は、絶対に読んだほうがいいんじゃないかなと思います。
──無茶なチャレンジをおもしろおかしく書いてある本ですが、1つの製品が出来上がるまでにどれだけの工程があるかを知ることができる本にもなっています。
楢﨑:途中からずるもし始めるんですよ。最初は産業革命以前の道具を使わないってルールだったのに、鉄鉱石を溶かすために、電子レンジを使い出すとか。そのへんのバランスもシビアじゃなさすぎるのが最後まで読めるポイントかなと思います。
──取りかかってみたはいいけれど、さすがに個人じゃ溶鉱炉を作れないっていう部分ですよね。でも、どうにか達成しようと電子レンジが出てくる。
楢﨑:そうなんです。すごいチャレンジ精神で、思いついたことをちゃんと実行する力というか、それを最後までもっていて発表したり、1冊にまとめる力みたいなものもすごい。「言うは易く行うは難し」を実際にやってみたところがすごいですよね。
──トースターっていうところもいいですよね。日常で使うものってところが。
楢﨑:そうですよね。「パンが飛び出す仕組みってどうなっているんだろう?」「どうやって焼いているんだろう?」と気になる部分ですよね。
──できあがったトースターが表紙になっていて、そのインパクトもすごいです。
楢﨑:この本を読むと、ふと生活の中で身の回りのものを見た時に、ちょっとゾッとするというか。「あれもこれも、こうやってできているのかな?」って。ものすごく分業された世界で住んでいるんだなってことがわかる内容かなと思います。
ものづくりの仕事をしていたら、100均ってすごく怖いんですよ。こんな便利なものが100円で売られているのかって。それもたくさんの分業でできているのかと思うと、もうほんとうに倒れそうになりますね。
──著者のトーマス・トウェイツさんはもう1冊『人間をお休みしてヤギになってみた結果』(新潮社)という本を出しています。こちらもタイトルどおり、人間からヤギになってみようと著者が悪戦苦闘する内容です。
日常を楽しくするための視点を教えてくれる、バカリズム『架空OL日記』

──3冊目はバカリズムさんの『架空OL日記』。1冊目、2冊目はエッセイ、ノンフィクションときましたが、田中さん、これはどう紹介したらいいでしょうか?
田中桃子(以下、田中):なんといったらいいんでしょうね。もともとはブログで書いていたものが書籍化されたみたいです。
7、8年ぐらい前に、そうとは知らずにたまたま本を見かけて、「この“バカリズム“って芸人のバカリズムさんかな」と思って手にとったのがきっかけです。あのバカリズムさんが本を出しているんだって。
──バカリズムさんがOLになりきって日記を書くというすごく不思議な本です。読んでみて、どんな印象でしたか?
田中:ぜんぶ嘘の出来事なんだっていう驚きがやっぱり一番にありました。書いてあることに違和感もあまりなくて、「わかるわかる」みたいな内容がけっこう多くて。
さきほどの穂村さんの本とも通じると思うんですが、ものの見方で日常はいくらでも楽しくできるんだなって思った作品です。こんなふうにものごとを見られたら楽しいよなぁって。
──ほんとうに誰にでも起こり得ることを、ちょっとの言い回しとかで、楽しい出来事にしていますよね。
田中:そうですよね。残業したりとか、帰りに化粧品売り場に行ったりとか、デパ地下に寄るとか、休日はゲームしてとか。そういうほんとうに何気ない日常を切り取っていますよね。
──ストーリーがないのがいいのかもしれないですね。バカリズムさんの書き方も、すごく抑制が効いていて。
田中:日記なので1つの話がすごく短いんですけど、短い中にもちゃんとオチがついていて。最後の一文がすごく秀逸だったりとか。
──妄想なので展開はいくらでもできるはずなのに、日常のちょっとしたおもしろさを膨らませている感じがすごくうまいですよね。特に印象に残っているエピソードはありますか?
田中:日記にタイトルがついていると思うんですけど。そのタイトルだけ聞いたら「どういう話なんだろう?」ってなるのが好きですね。
例えば「グラデーション」。どういう話かというと、同僚達とおしゃべりしていると、いつの間にか上司とかの愚痴になっていくっていう。それがきれいなグラデーションだったという話。
「マウンド」という話も好きです。前歯の差し歯が取れちゃった同僚がいて、それを隠すために手をあてるしぐさが、マウンドにいる高校野球の選手みたいだっていう。
──この本を読んで、何か日常に影響ってありましたか?
田中:私も楢﨑さんも、日常の中での空想や設定をつけるのが好きなんです。例えば楢﨑さんが平安時代からきた人の設定にしたりして、遊んだりしています。それはごっこ遊びみたいなものですね。
──それは穂村さんの話の時にも出てきた「日常を楽しむ視点」に通じそうですね。
田中:そうですね。私達2人で歩いていても道の看板とか、おおしろいお店の名前とか、そういうのをすごく探しちゃうんです。それでそこから空想を広げていくことが多いですね。
根底にあるのは「ふだん使っているものがどうしたら楽しくなるのか」という視点

──そういえば、2時さんのプロダクトはどれも日用品を楽しくするという視点のものが多いですね。けっこう大喜利っぽかったり。
田中:そうですね、ふだん使っているものがどうしたら楽しくなるのかなっていう視点で考えています。
楢﨑:大喜利でいえば、「勝訴」って書かれた犬用のおもちゃ。あれがあるクイズ番組で取り上げられていて、「勝訴」の部分が「?」になっていて、それを当てるという問題になっていたんです。で、いろんな人が答えていたんですが、芸人の方だけ正解できたんですよ。なので、大喜利っぽい発想なんだなって。
──大喜利もそうですし、さきほどのごっこ遊びもそうですが、考えること自体を楽しんでいる感じが伝わってきます。
楢﨑:そうですね。考えること自体がすごく好きですね。さっきも言ったイマジナリーな遊びの中に、「イマジナリー商品」みたいな枠があって、それを取り出してツイッターに投稿したりとか、販売したりしているという感じがあります。
──今後やっていきたいことはありますか?
楢﨑:すごく会社を大きくしたいとか、そういう願望はないんです。楽しくおもしろいプロダクトを作って、それが結果的にたくさんの人を笑わせたり、和ませたりして、口角を上げてもらえたらそれで十分かなと思っています。
田中:「おもしろい会社といったら2時だよね」と言ってもらえるような会社にしていきたいなあって思っています。
──プロダクトに限らず、何かいろいろプロデュースとかで、アイデアを注ぐとか、そういう感じのものも見てみたいです。
楢﨑:やってみたいなと空想したことがあるのは、カフェですね。メニューが普通じゃなかったり、カフェラテのラテアートがすごく変だったりとか。
何かできることがあったら、いろんな分野に挑戦してみたいですね。
株式会社2時
楢﨑友里と田中桃子からなる企画デザイン会社。2人とも株式会社フェリシモで7年間ユーモア雑貨の商品企画に携わり、企画とデザインのスキルを学び、2020年に株式会社2時を設立。バズる商品企画を得意とし、細部までこだわり愛情を持って商品を作り上げている。
オフィシャルwebサイト:https://2-niji.com/
Twitter:@niji_2oclock

