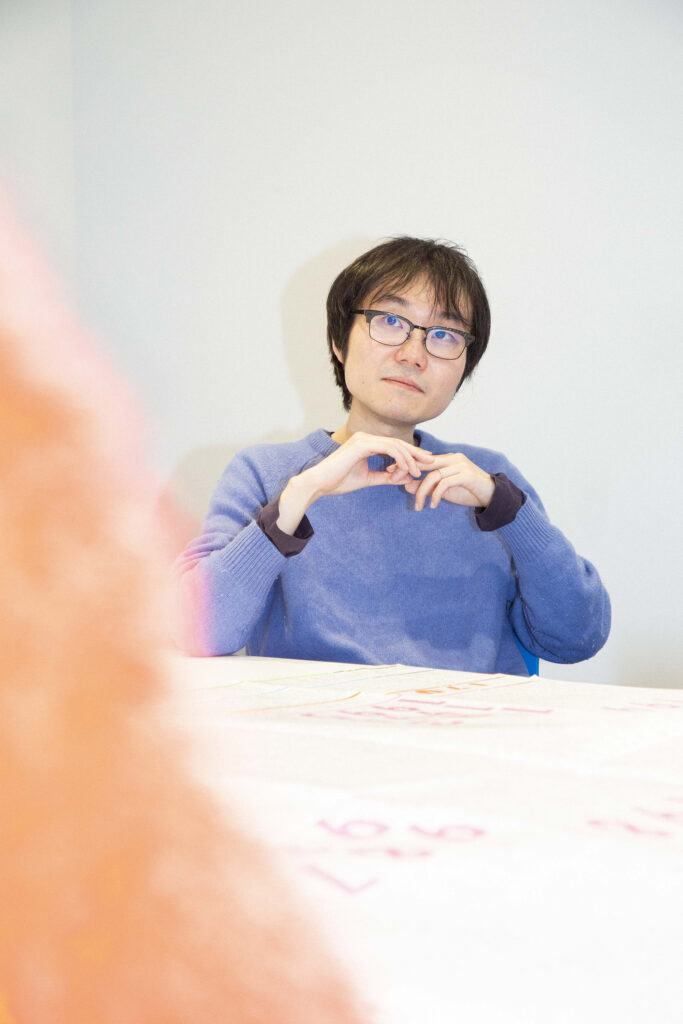1968年1月5日「チェコスロバキア、ドプチェク共産党第一書記就任」で幕を開け、2020年12月28日「劇場版『鬼滅の刃』の興行収入が国内歴代1位に」に至るまで――。「年表・サブカルチャーと社会の50年 1968-2020〈完全版〉」(2021年、百万年書房)は、その50余年間に生起したさまざまな出来事・トピックを、音楽や映画、アニメなどのサブカルチャー、政治経済、社会風俗をまたぎながら、B1サイズ×4枚に隙間なく記した驚異的労作である。目眩を覚えるほどに圧倒的な情報量を誇るこの年表を編纂した、テキストユニット・TVODの片割れとしても活動するライター・批評家のパンス。そして、その版元・百万年書房の代表であり、元『クイック・ジャパン』編集長としてもサブカルチャー隆盛の一翼を担ってきた北尾修一の2人に、年表誕生の背景やサブカルチャーと社会の紐帯、そしてポスト・サブカルチャーの風景などについて、言葉を交わしてもらった。
「年表怪人パンス」が紡ぎあげた驚異の労作
――この1月に刊行された「年表・サブカルチャーと社会の50年 1968-2020〈完全版〉」(以下、「年表〈完全版〉」)の一部は、パンスさんとコメカさんによるテキストユニットTVODの著作『ポスト・サブカル焼け跡派』(2020年、百万年書房)の巻末にも収録されていますよね。その時点ですでに今回の状態までできあがっていたのでしょうか?
パンス:その後に追加や調整を行ったところはありますが、「年表〈完全版〉」に近いものはできていました。ただ、あまりにも膨大で本に入りきらなくて、その時は泣く泣く削って収録したんです。
北尾修一(以下、北尾):オリジナルの1/10とか1/20とかにしてしまったので、「削る」というレベルじゃなかったですけどね(笑)。『ポスト・サブカル焼け跡派』巻末付録のバージョンでも「濃い」と言われましたが、その原型を知っている我々からしたら、あれは上澄みでしかなかったんですよ。

パンス(TVOD) 
北尾修一(百万年書房)
――上澄みですか……。確かにこの膨大な情報量の「年表〈完全版〉」を前にすると、その言葉もごもっともなものと思わざるを得ません。現代史の資料としても非常に価値のある、意義深い労作だと思います。
北尾:この「年表〈完全版〉」にはサブカルチャーの勃興から衰退までが通史として記されていて、100年後でも歴史的資料として残るものだと思います。景気が上昇して日本全体が豊かになるに従って、多くの若者たちが上京して大学に進学するようになり、経済や社会全体が好調に回っている中でサブカルチャーやその土壌ともなる雑誌文化が花開き、やがて衰退していく――。そんなストーリーがこの「年表〈完全版〉」を追うと浮かび上がってくるんです。パンスくんでなければできなかった、本当に素晴らしい仕事だと思っています。
パンス:ありがとうございます。70年代や80年代に青年期を過ごした方からしたら、「あの人が入っていない」「実はこの時にこんなことがあった」とかいろいろと言いたいところはあると思いますが、そのズレも含めて楽しんでほしいですね。それにしても、「年表〈完全版〉」作りは昔からライフワーク的に誰に見せるつもりでもなく取り組んできたことなので、こうして発表する日が来るとは思いませんでした。もし北尾さんと出会っていなかったら、僕のパソコンの中で眠っていたままだったと思います(笑)。
――この「年表〈完全版〉」がライフワークとして制作されていたものだとは驚きます。パンスさんはいつ頃から年表作りに興味を持たれたのでしょうか?
パンス:本やテレビで気になった歴史的な出来事などを大学ノートにメモするようになったのは中学生からで、そのノートを学校に持って行って授業中にニヤニヤしながら1人で見ていました(笑)。そんなことをその後もずっと続けていたんですけど、10年くらい前から、より能動的に細かいことまで書き留めるようになって。本当に年表作成は僕にとって日常的なもので、その積み重ねの果てにこれ(「年表〈完全版〉」)があるんです。サブカルチャーと社会の関連について書くことが今の自分の取り組みの中心にはなっていますが、その前に、とにかく歴史というものが、そしてそれを年表としてまとめるという行為が大好きなんですよ。
北尾:誤解されがちですが、パンスくんにとって「サブカルチャー」と「年表」だと、後者の方が圧倒的にプライオリティーが高いんです。年表の構成要素の1つとしてサブカルチャーがあるだけで、決して逆ではない。言わば、彼は「年表怪人パンス」なんです(笑)。
サブカルチャーと社会の紐帯はいつの時代も失われていなかった
――この「年表〈完全版〉」は、音楽や映画、アニメなどといったサブカルチャー領域と、政治や経済、社会風俗のトピックが横断的、並列的に記されていることが何よりの特徴だと思います。その意図についてお聞かせください。
パンス:当たり前ではあるんですが、サブカルチャーが社会から自由になったことなんて一度もないんですよね。漠然と「1980年代ぐらいからサブカルチャー界隈の人たちが政治に関心を持たなくなった」みたいなことが言われたりもしますが、僕は厳密には異なると思っています。実際に当時の『宝島』を開いてみても、反原発や、総選挙をどう考えるかといった記事が掲載されているんです。この「年表〈完全版〉」を見てもそのことが浮かび上がってくると思います。例えば、反原発のデモは1988年前後が活発で、4月には「一万人行動」があり、7月にはザ・ブルーハーツの「チェルノブイリ」が発表されています。2011年から始まった反原発デモと同じぐらい大規模なことが実はバブルの真っただ中でも起こっていたんですよね。そういった事実を多くの人が忘れているので、思い出してもらいたいという気持ちはあります。
北尾:パンスくんの言うとおりで、僕が単なるリスナーで読者だった80年代を振り返ってみても、雑誌でミュージシャンが政治的な発言をすることは全く珍しいことではなかったですね。
パンス:サブカルチャーの想像力は社会によって規定されます。80年代までは冷戦期の核戦争の恐怖、外国の敵への恐怖が一番にあった。ところが冷戦がなくなったことで、「国の中に敵がいる」と想像力のベクトルが変わっていくんです。例えば米ドラマ作品『X-ファイル』(1993年-2002年)の「実は政府が宇宙人と手を組んでいる」みたいな構図もその表れの1つで。それは今の陰謀論の隆盛にも直接的につながっている気がしますね。
北尾:自分でも実感したことなのですが、この「年表〈完全版〉」があると、昔の作品をより楽しめるようになりますね。「この本が出版された時にはこんなことがあったから、こういう描写があるんだ」みたいに分析的に考えてみると、作品への理解が一層深まります。その時に同時に出ていた本や公開されていた映画を知るだけでも、新しい見方ができると思いますね。
――確かに「年表〈完全版〉」はある種の「ガイド本」としても大いに力を発揮してくれそうですね。「サブカルチャーと社会」というところに戻ると、北尾さんは『クイック・ジャパン』在籍時にさまざまなカルチャーを広い射程の切り口から伝えることを実践されてきたと思うのですが、改めて当時のことをお聞かせください。
北尾:というかそもそも、僕は当時から“カルチャー誌”って言葉が大嫌いだったんです(笑)。未だに“カルチャー誌”なんて言葉、1回も使ったことないし、さらに言えば日本語の“カルチャー”という言葉そのものが嫌い。最近流行っている某映画にあったじゃないですか? 「“カルチャー”と仕事のどっちを取るか」みたいな話が。“カルチャー”が指すものって、例えばカルチャー教室のように、多くの場合は「余裕がある人の手慰み」みたいなニュアンスがついてまわると思うんです。でも、僕が好きだったミュージシャンや漫画家は、1つひとつの作品をもっと切実なものとして考えて作っていたわけで。『クイック・ジャパン』では、そうした現場に立ち会って、なるべくその熱量を下げることなくレポートしたいと思って毎号作っていました。それが成功していたかどうかはともかくとして、当時の自分たちは“カルチャー誌”ではなく“ニュースマガジン”という呼び方をしていましたね。
――社会から遊離した手慰みの“カルチャー”ではなく、あくまで社会の中で生起している“ニュース”を伝えていた、と。
北尾:ええ。なので、この「年表〈完全版〉」で、音楽や漫画などが、政治や経済と等価に扱われているのは、自分としてもすごくしっくりきます。そして何より、終わりゆく「サブカルチャー」の一時代の中で生きて、それに育てられてそれを仕事にしてきた自分なりの「落とし前」として、この時代を歴史に残すことは自分のやる仕事だと思っていたので、パンスくんとコメカくんと出会い『ポスト・サブカル焼け跡派』とこの「年表〈完全版〉」を百万年書房から出すことができて本当によかったです。実は、デザイナーも僕が編集長を務めていた頃の『クイック・ジャパン』を手掛けていたOCTAVEが手掛けていて、それも自分にとっては大きな意味を持っているんです。
これからは「ノーカルチャー」の時代がやってくる?
――この「年表〈完全版〉」は2020年で終わっていますが、それ以降の、これから私たちが生きていく未来には、どのようなことが待ち受けているとお考えでしょうか?
パンス:最近、明治初頭の年表を作っているんですけど、あの頃って「ノーカルチャー」と言えるような時代で。文明開化を機に、江戸的なものに少し西洋文化を取り入れたようなものばかりがあふれていて、まあそれはそれでおもしろいんですが、自国の文化という意味では衰退の時期だったと思います。今の日本を眺めているとなんだか様子が似てきている気がしていて。また、当時は立身出世の時代で意識の高い人しか生き残れず、そこからこぼれ落ちると職を失い大変な生活をしなければいけなかったり、貧困ビジネスが流行っていたりもしていて、社会的な状況でも現在と類似点があるんです。そういった歴史を見ていくと、これからの日本がそういう「ノーカルチャー」みたいな時代に突入することも全然あり得るのではないかと思っています。そんな時代が来たら北尾さんは嫌ですか?
北尾:そうなったら、「ノーカルチャー」の中で、また自分なりに生きてくしかないわけですし、嫌だとかは全く思わないですね。そもそも1968年の50年前なんて誰もロックバンドなんて組んでいないわけですよ。50年単位のスパンで考えると、今自分が親しんでいる文化や娯楽がゆくゆくはなくなるかもしれない。けれど、それは仕方のないことというか、なくなる必然性があるからなくなっていくというだけのことで。でも、結局人間が存在している限り、またおもしろい何かが生まれるはずで、そこは全然悲観していないんです。
パンス:そうですね。北尾さんは常に街というものにフォーカスして雑誌や本を編まれてきていましたよね。街があり、そこに人がいれば、今後も常に何かは生まれ続けていくんだと思います。それが僕たちの知っている「カルチャー」とは違うというだけでの話で。TikTokを見ていても、その踊り自体は何が楽しいのか僕には理解できないのですが、高校単位で表現の独創性を競うようなムーブメントも起こっていて、非常に興味深いんですよ。ただ、そういったものはライヴ配信で記録されていないことも多かったりするので、「年表怪人」としては困るところもあるんですけど(笑)。
――ある時代の終わりは、新しい始まりでもありますね。最後に、今後の取り組みや、今考えていることなどをお聞かせください。
パンス:「サブカル」について言及していると、どうしても日本の現象に特化した話をしてしまいがちですが、“世界の中の日本を見直すこと”が僕にとって大きなテーマです。世界を見渡してみると、各国において極右勢力が躍進する中、それに対抗するリベラルは、果たして次にどのような社会をつくっていけばいいのかということに対して明確な結論を出せず、不安定な状況が続いています。そういった混沌とした世界情勢の中に日本をどう位置付けて、これからどういうことが起こっていくのかを考えていきたいです。また、近隣のアジア諸国で起こっていることもおもしろいので、それも絡めて執筆していければと思っています。もちろん、年表も、分野や時間軸を広げて新しいものを作っていきたいですね。実は、僕のスプレッドシートの中には、この「年表〈完全版〉」よりも前、1848年から始まる年表もあるんですよ。ウォーラーステインに倣って、1848年と1968年に世界史上の画期があったという考え方に基づいて。
北尾:僕の頭の中は、基本的に自社の刊行物にすべて反映されているので、これから出す本にご注目いただければと思います。TVODの2人のことで言うと、今、パンスくんもコメカくんもソロ活動で注目が集まっていますが、各々さらに大きくなってもらって、その後に『ポスト・サブカル焼け跡派』に続く主著をウチから出せればいいなと企んでいます。ソロでさまざまなステージを経験したあとに、2人が久しぶりに組んで伝説のアルバムを残し、そしてレーベルの元には若いTVODチルドレンからのデモテープがたくさん届く――そんなストーリーを思い描いています(笑)。
パンス:いいですね! それが混沌を極めた迷作のラストアルバムにならないよう、頑張ります(笑)。
*
北尾修一
編集者・百万年書房代表。1993年に株式会社太田出版に入社。『クイック・ジャパン』編集長を23号から50号まで務め、2006年には文芸誌『hon-nin』を創刊。2017年に独立し、出版社『百万年書房』を立ち上げる。『ブッダボウルの本』(前田まり子)、『愛情観察』(相澤義和)、『よるくまシュッカ』(エミリー・メルゴー・ヤコブセン)、『ポスト・サブカル焼け跡派』(TVOD)などを刊行。
Twitter:@kitaoshu1
百万年書房: http://millionyearsbookstore.com/
パンス
ライター・批評家。テキストユニット“TVOD”の片割れ。TVODとしての著書に『ポスト・サブカル焼け跡派』。最近の主たる興味対象は、韓国を中心に東アジアの近現代史とポップカルチャー。DJもたしなむ。
Twitter:@panparth
Photography Kentaro Oshio