今や世界中に熱心なリスナーを持つに至った、日本のシティ・ポップ。なぜ、かの音楽は数多の人々をかくも惹きつけるのか。そしてそれは、どこから来て、どこへ行こうとしているのか。その魅力と来し方・行く末を明らかにするべく、クニモンド瀧口を訪ねた。同氏は、自身のソロプロジェクト・流線形として、ゼロ年代以降に生まれた「新しいシティ・ポップ」の金字塔的作品の1 つである『CITY MUSIC』を2003年にリリースしシーンに登場。以降、流線形での楽曲制作の他、プロデュースワークやDJ、著述活動なども行い、現在のシティ・ポップ隆盛の礎を築いてきた人物だ。
前編に続く今回は、アーティストとプロデューサーその双方のキャリアにおける原点となる2枚の名盤と、最新作『Talio』について、そして海外に広がりゆく日本のシティ・ポップに対する想いや見据える未来について、語ってもらった。
現在のブームの起点とも語られる2枚の名盤の誕生背景
――後編では、まず、クニモンドさんのキャリアのスタート地点である流線形の『CITY MUSIC』(2003年)についてお話を伺いたたいと思います。当時、どのような思いを込めてこのアルバムを制作されたのでしょうか?
クニモンド瀧口:2001年に流線形の活動を始めた時、そこで実現したかったのは、山下達郎さんの『IT’S A POPPIN’ TIME』というライヴ・アルバムで感じたような、「都会的で洗練されていて大人なサウンド」だったんです。当時の日本の音楽シーンを振り返ると、90年代から流行が続いているアシッドジャズやディーバ系があったり、はっぴいえんどの系譜を感じさせるものやネオアコ~渋谷系の系譜にあるポップスがあったりして。かっこいい音楽は沢山ありましたが、僕がやろうとしていたようなサウンドを鳴らしているバンドは、あまりいなかったと思います。そんな中で、時代に合わせることなく、自分が好きな音を曲げずに作ったのが『CITY MUSIC』なんです。それと、これは今も心がけていることなんですが、「全てシングルカットできるような曲でアルバムを作る!」という気持ちで制作に臨んでいたのを覚えています。

――流線形は「バンド」ではなく、クニモンドさんが主宰する「プロジェクト」として定義されています。改めてその活動の在り方やこだわりについて教えてください。
クニモンド瀧口:流線形は僕のオウン・プロジェクトなんです。目指しているのが生バンドサウンドのプロダクションなので、バンド風に見せているのですが、実は他はサポートメンバーという(笑)。ただ、最近は固定のメンバーでやることが増えました。楽器にもこだわりがあって、ソフトウェア音源ではなく、極力本物を使いたいと考えています。例えばドラムの北山ゆう子が使うドラムセットは70年代のラディックを、鍵盤の平畑徹也はローズピアノや、クラビネットD6などを使用しています。それらに共通しているのは、単に僕が好きな音であるということ。つまり、流線形は僕の理想のバンドサウンドを追求するプロジェクトなんです。
――そんな流線形として活動する一方、クニモンドさんはプロデューサーとしても活動されています。その最初の代表作となる一十三十一さんの『CITY DIVE』(2012年)はどのような経緯でプロデュースを担当することになったのでしょうか?
クニモンド瀧口:初めて一十三ちゃん(一十三十一)を知ったのは2005年ぐらいかな? NHKの音楽番組で、大貫妙子さんと一緒にシュガーベイブの「いつも通り」を歌っているのを見て、「良い歌声だな〜」と思ったのが第一印象です。その後、実は知り合いとつながっていることが分かって、2006年にリリースした流線形の『TOKYO SNIPER』に、変名(江口ニカ)でヴォーカルとして参加してもらいました。その流れもあって、一十三ちゃんがレーベルを移った際に、(『CITY DIVE』プロデュースの依頼で)声をかけてくれたんです。

――『CITY DIVE』のサウンドは、流線形のバンドサウンドとは異なるところがありますね。
クニモンド瀧口:『CITY DIVE』に参加してくれたDORIANの作品を既に聴いていたこともあって、そこで鳴らされていた音像——「トラックメイカーやDJ視点のプロダクション」でアルバムを作りたいと考えていました。もう1人の参加者であるKASHIFも、ギタリストとしても有名ですが、トラックメイカーとして素晴らしい作り手なので、3人トラックメイカーとして、それぞれアレンジを進めていきました。
この「打ち込みで作る」ことをコンセプトとした『CITY DIVE』には、明確なリファレンス作品がありました。それは、佐藤博さんの『awakening』(1982年)です。
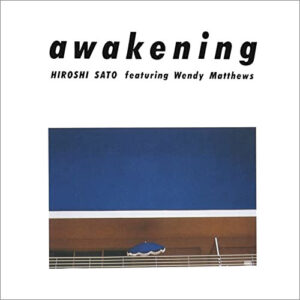
この作品は佐藤さんがほとんど打ち込みで作ったアルバムで。「30年経ってここに帰ってきた」みたいな気持ちで制作を進めていましたね(笑)。実は、『CITY DIVE』制作時よりも前に、『BARFOUT!』誌の企画で佐藤博さんにインタビューしたことがあるんです。『CITY DIVE』が完成したら聴いていただこうと思っていたのですが、本当に残念なことにこの年に佐藤さんがお亡くなりになってしまい、その願いはかないませんでした。
――一十三十一さんのヴォーカルの魅力はどんなところだと思いますか?
クニモンド瀧口:一十三ちゃんの歌声は、聴けばすぐに誰が歌っているかわかるんです。それってなかなかすごいことですよね。スモーキーな感じでちょっと甘ったるい感じの歌い方——“媚薬系”と言われたりもしていますが——に彼女の独特の世界観が込められていて、「何を歌ってもその人の歌になる」というか、唯一無二の存在だと思います。
――両作品は、現在に続くシティ・ポップ・リヴァイバルの嚆矢、起点としても語られる作品となりましたが、改めて思うところをお聞かせください。
クニモンド瀧口:振り返ると、「これがいろいろなことのきっかけになっていたんだな」とは感じるんですけど、当時、何かを変えてやろうとか、リヴァイバルを起こしてやろうとか、そういった気持ちは微塵もありませんでした。ただ自分がやりたいことをやっていただけで、注目されたのは結果論というか、狙ったものではないんです。
流線形と一十三十一がタッグを組んだ『Talio』
――流線形として一十三十一さんとタッグを組み昨年11月にリリースした『Talio』は、ドラマ『タリオ 復讐代行の2人』のサウンドトラックとして制作されていますが、今作が生まれた経緯について教えてください。
クニモンド瀧口:『サイタマノラッパー』や『モテキ』なども手がけてきた岩崎太整さんがドラマの音楽プロデューサーを務めていて、最初に一十三ちゃんに声がかかったんです。その後、「シティ・ポップ」がキーワードに挙がっていたこともあって、一十三ちゃん経由で「流線形として一緒にやりませんか?」と僕に話が来たという経緯になります。ただ、劇伴音楽を作ると聞いた時に、「シティ・ポップ」というよりも、大野雄二さんや井上堯之さん、ミッキー吉野さんたちが作ってきたようなサウンドが思い浮かんでいて。流線形として参加するのであれば、そういったジャズファンク的な音楽をバンドサウンドでやりたいと思ったんです。それで、主題歌はシティ・ポップにするにしても、劇伴はそっち(ジャズファンク)の方向でやらせてもらえませんかと岩崎さんにお話をしたところ、OKをいただいたんです。
とはいえ、劇伴全体がジャズファンクになってしまうのもどうかと思って、一十三ちゃんと共同制作ということもあり、(流線形と一十三十一の両者で)曲を分担することにして。流線形はジャズファンク調の曲を作り、ヒトミちゃんはKASHIFと組んでシティ・ポップ調の曲を作るという役割分担で制作を進めていきました。

――初めての劇伴音楽の制作を進めていくにあたり、参考にした作品などがあれば教えてください。
クニモンド瀧口:作品が「復讐代行人」というテーマ・内容だったので、「刑事モノ」というよりは「探偵モノ」で、しかもアクションがあるドラマをまずはイメージしました。具体的に言うと、小さい時に見ていた「俺たちは天使だ!」「傷だらけの天使」「ザ・ハングマン」「探偵物語」などの作品ですね。
――オリジナルアルバムとは制作プロセスも異なるところがあったと思いますが、実際にはいかがでしたか?
クニモンド瀧口:音楽を制作する段階ではまだ映像ができていないので、「スリル」や「楽しい」、「哀しい」といったお題・キーワードに合わせて楽曲を作っていきました。具体的な制作方法は、メロディーをガッツリ固めるというよりは、アレンジ重視で、コード進行やアレンジのモチーフをメンバーに伝えて、スタジオでセッションして作り上げていくというような流れでした。中にはコード進行がワンフレーズしか決まっていなくて、メンバーが別の曲を録音している時に、別室で次の曲を考えている、という場面も多々ありました(笑)。
――非常にライブ感あふれる制作現場だったのですね。
クニモンド瀧口:その時にみんなで、「ティン・パン・アレーって、こういう感じでレコーディングしていたんだろうね」みたいな話をしていて。彼らは全員スタジオミュージシャンでもありましたし、レコーディングの現場でみんなでアレンジしながら作っていくような感じだったのかな、と。流線形でも最近はアレンジをバンドで行うことも多くて、僕が最初に元ネタというかラフを作って、膨らませていくような感じなんです。この『Talio』でも、例えば「The Sectionの曲『Bad Shoes』のリーランド・スクラーみたいなベースで」と言うと、ベースの松木俊郎はすぐ対応してくれました。ギターの山之内俊夫や、パーカッション&エンジニアの平野栄二も、付き合いが長いので僕が意図していることをすぐに汲んでくれます。人としても気持ちのいい人たちで、本当に一緒にバンドをやることが楽しくて仕方ないですね。僕の未熟な部分をフォローしてくれているメンバーには感謝しかありません。ともあれ、劇伴の制作は初めで大変なところもありましたが、今回でいろいろと学べたので、ぜひまたやってみたいですね。
――今作には元キリンジの堀込泰行さんがゲストで参加されていますが、その経緯について教えてください。
クニモンド瀧口:エンディング曲は一十三ちゃんが歌うと決まっていたのですが、オープニング曲は差別化したいという気持ちがあったんです。それで、岩崎さん、一十三ちゃん、僕の3人が合致して誘いたいヴォーカルとして堀込泰行さんにオファーしたところ、快諾していただきました。そして実は、堀込さんとは、この曲以外にも既に数年前に流線形として一緒にレコーディングをしているんです。アレンジに納得がいかないところがあって直しているんですけど、近いうちに発表できたらいいなと思っています。
――それは楽しみですね。あと、今作については、永井博さんがジャケットを手がけているというのも大きなトピックだと思います。
クニモンド瀧口:中学生の頃に(永井博がジャケットを手がけた)大滝詠一さんの『ロングバケーション』の洗礼を受けた世代なので、永井博さんは僕にとって長く憧れの存在でした。そんな永井さんとまさか知り合いになると思っていなかったんですが、2009年に発売した流線形と比屋定篤子の「ナチュラル・ウーマン」を聴いていただいていて、そのことをTwitterに書いてくださったのをきっかけにDJをご一緒するようになったんです。今回の作品で「メインビジュアルがあったら良い」という話が出たので、僕も一十三ちゃんも知り合いだった永井さんにお願いしてみようということになり、即決でした。狙い通り、番組でも特別な役割を果たした作品を提供していただきました。
永井さんの絵は、海外でも非常に人気が高く、今もどんどん広がっていっています。永井さんの絵を見ると、どこか心地よい場所へ運んでくれるような印象をいつも受けます。「どこの海かプールかわからないけど、なんかいいな」みたいな――。この感覚って、まさしくシティ・ポップの音楽を聴いた時に受けるものと似ていると思うんです。だから、シティ・ポップにおいて永井さんが特別な存在というのは、とても納得のいくところがありますね。
国境を越えるムーブメントへの想いと、今見据える未来
――近年の海外でのシティ・ポップ人気について、どのように考えていますか? 『Pacific Breeze: Japanese City Pop AOR & Boogie 1976-1986』に代表されるようなストレートな再評価から、ヴェイパーウェイヴやフューチャー・ファンク文脈での再評価、アジア圏での独自進化などいろいろな文脈はありますが……。
クニモンド瀧口:「ヴェイパーウェイヴでシティ・ポップが使われている」みたいな流れを意識したのは、2012年にGreeen Linezというユニットが「Hibiscus Pacific」という曲で菊池桃子をサンプリングしているのを聴いた時が最初で。好き嫌いは置いておいて、海外の方たちがいろんな解釈で日本のシティ・ポップを発信するのはおもしろいと思うし、良いことだと思っています。時には日本で聴いていた僕らでも思いもよらないところに目をつけていたりして新鮮ですし、彼らの音楽を通して再発見することがあったりもします。あと、最近になってmacross 82-99を聴いてみたんですが、僕のアレンジがサンプリングされていてビックリしました(笑)。
――シティ・ポップの海外での広がりについて、クニモンドさんご自身で体感していることはありますか?
クニモンド瀧口:最近YouTubeを見て驚いたんですが、流線形の『TOKYO SNIPER』がアップされてから3ヵ月で35万再生になっていたんです。しかもコメントが1000件以上ついていて、そのほとんどが海外の方という状況で(笑)。ここ5年ぐらいは海外の方からの問い合わせも増えていて、最近やたら多いなと思っていたところだったのですが、ここから来ている方も多いのかもしれません。
――日本のシティ・ポップが海外に聴かれる経路として、YouTubeの存在はとても重要なのではないかと思います。
クニモンド瀧口:この数年で、YouTubeでシティ・ポップのミックスやフルアルバムを上げている人が増えましたね。その人たちが、日本人か海外の方かはわかりませんが、僕も聴いたことがない良盤がフルで上がっていたりします。これは、権利的な問題は考えなくてはなりませんが、海外の音楽好きにとっては嬉しいでしょうね。こういったことを含めて5年前とは状況が変わってきていて、さらにシティ・ポップの人気は加速しているようにも思えます。
――最後に、現在のシティ・ポップブームに対する思いと、ご自身の今後の目標について、お聞かせてください。
クニモンド瀧口:「シティ・ポップ」という言葉自体、解釈が曖昧なのでどの辺を切り取るかにもよるんですが、いろんな解釈のシティ・ポップが同時に進行していると思います。日本では、親の影響を受けた若手ミュージシャンやベテランがブームに乗ってシティ・ポップをやりはじめたり、海外では、言葉はわからないけどサンプリングソースとして使ったり、トラックメイカー解釈のシティ・ポップをやったり。その中で、「僕の役割は何だろう?」と考えることがあるんです。最近の音楽を聴いていると「親しみやすいメロディーが減ったな」と感じることが多くて、(自分の役割は)そこにあるのかな、と。シティ・ポップの良さは、アレンジの役割が大きいのですが、やはりメロディーや歌詞も大切で。僕は昭和歌謡の洗礼を受けた世代なので、特にメロディーの良さにはこれからもこだわっていきたいです。あとは、海外のミュージシャンと一緒にやりたいという気持ちはありますね。例えば、ジョーダン・ラカイやカマシ・ワシントンに参加してもらうとか……。海外と日本の境界線なしに音楽を作ることができたらいいなと思っています。
PR、アパレル、レコード屋、ライブハウスを経て’03年に流線形のメンバーとして音楽活動を開始。’03年『シティミュージック』、’06年『TOKYO SNIPER』、’09年 比屋定篤子とのコラボレーションアルバム『NATURAL WOMAN』を発表。プロデュース/楽曲提供/アレンジでは、代表作として一十三十一『CITY DIVE』、ナツ・サマー『HAYAMA NIGHTS』、古内東子「Enough is Enough」などがある。’20年 シティミュージックを選曲/監修したコンピレーションアルバム・シリーズ『City Music Tokyo -invitation-』、NHKドラマ「タリオ -復讐代行人の2人-」のサウンドトラック『Talio』を流線形/一十三十一の名義で発表。音楽を中心に幅広く活動中。文化デリック(故 川勝正幸氏+下井草秀氏)等が選考する『ポップ・カルチャー・アワード2006』の「音楽部門BEST 1」を受賞。
Instagram:@cmd_tgc
Twitter:@cunimondo
■流線形/一十三十一 Guest:堀込泰行/シンリズム/KASHIF
会期:4月16日、5月1日
会場:ビルボードライブ東京
住所:東京都港区赤坂9丁目7番4号 東京ミッドタウン ガーデンテラス4F
時間:1stステージ:開場 14:00/開演 15:00、2ndステージ:開場 17:00/開演 18:00
入場料:サービスエリア:7,300円/カジュアルエリア:6,800円
※本公演は新型コロナウイルス感染症対策用の座席レイアウトを使用し、公演を実施いたします
※ご来場前に必ず〈営業再開時の新型コロナウイルス感染症対策について〉内の〈お客様へご協力のお願い〉をご確認ください
※2021年4月16日の公演の2ndステージではライブ配信が行われます。お客様が映像に映り込む場合もございますので、あらかじめご了承ください
詳細は会場HPより確認のこと。
Photograpy Ryosuke Kikuchi




