その時々だからこそ生まれ、同時に時代を超えて愛される価値観がある。本連載「時の音」では、そんな価値観を発信する人達に今までの活動を振り返りつつ、未来を見据えて話をしてもらう。
今回登場するのは、映画監督の黒沢清。1988年に『スウィートホーム』で一般商業映画を手掛けて以来、ジャパニーズ・サイコ・サスペンスの草分け『CURE キュア』や、オダギリジョー・浅野忠信出演の若者青春映画『アカルイミライ』、オールフランスロケのロマンス・ホラー『ダゲレオタイプの女』など、多彩で豊かなフィルモグラフィーを築き上げてきた。海外からの評価も高く、これまでに数々の映画賞を受賞。この9月にはヴェネチア国際映画祭銀獅子賞(監督賞)獲得という、日本人で17年ぶりとなる快挙を成し遂げることとなった。その受賞作となったのが、現在日本全国の劇場で上映中の『スパイの妻』だ。蒼井優が主演を務める同作は、自身のキャリアにおいて初の「歴史物」作品となる。舞台は1940年、昭和初期の日本。未曽有の大戦を目前に控えた激動の時代を、その中で懸命に生きる夫婦の姿を描くことで、監督が伝えたかったものとは。
「境界」をまたぐ存在は、“幽霊”から“スパイ”へ
1940年の神戸、主人公の福原優作(高橋一生)は貿易会社を営んでいる。真珠湾攻撃は約1年後に迫り、その直前にはソ連のスパイとしてゾルゲが逮捕されることになるだろう。社会の中で相互監視の目がますます厳しくなり、その状況に対してわずかでも客観的な視線を向ける者にとっては、息苦しさが増すばかりという時期だ。
福原の暮らしは西洋化され、仕事柄、外国や外国人との接点も多い。そのうえ、妻の聡子(蒼井優)に女スパイを演じさせる無声映画をお遊びで作るほど、華やかな毎日を送っている。まるで日本全体を覆う空気の重さに気付いていないかのような振る舞いだが、もちろんそのために、憲兵隊からは疑いの目を向けられている。実際、聡子の中にすら不安と疑惑が植え付けられ、彼女なりの捜査が始まる——。
黒沢清の最新作、『スパイの妻』はこんなふうに幕を開く。周知の通り、第77回ヴェネチア国際映画祭において銀獅子賞(監督賞)を受賞した作品である。『スパイの妻』に接して気付くことがあり、改めて黒沢清のフィルモグラフィーを眺めわたしてみた。
哀川翔を主人公に据えたVシネ『勝手にしやがれ!!』シリーズ(1995〜1996年)や特異なノワール/アクション『復讐』2作(1996年)などを通過しながら、シリアル・キラーものの枠を超えて人間の自我のあり方を揺るがす『CURE キュア』(1997年)で1つの頂点を見せた後、“コロナ世界”を予見したかのようなホラー大作『回路』(2000年)にいたる90年代。
ジャンルのフィルターを通すことなく現代社会への違和感を物語と映像に結実させた『アカルイミライ』(2002年)から、『LOFT ロフト』(2005年)や『叫』(2006年)といったひと回りもふた回りもしてからジャンルに向き合ったというおもむきのホラー作品、そしてほぼ文芸ものと受け取れる『トウキョウソナタ』(2008年)までの00年代。
テレビ・シリーズとして作られた『贖罪』(2011年)をはじめとする原作ものを数多く手掛けながら、『Seventh Code セブンス・コード』(2013年)や『ダゲレオタイプの女』(2016年)、『旅のおわり世界の始まり』(2018年)といった海外撮影作品にも取り組み、90年代に続く第二の充実期を迎えたように見える10年代。
『スパイの妻』で気付いたことというのは、他でもなく“スパイ”というモチーフのことだった。

これまで、黒沢作品では“幽霊”が特権的な立場を占めてきた。ストレートに恐怖を起動させることもあれば、『岸辺の旅』(2014年)のようにヒロインを癒やすものとして機能することもあった。だがすべての“幽霊”は、“あの世/この世”の境界線上にいる。“幽霊”の出現によって境界線はあいまいになり、“あちら側”と“こちら側”、“外部”と“内部”、“他者”と“自己”といったものが互いに浸透し始める。それだけでなく、やがては、そうした二項対立そのものが完全に無効化した世界が出現する。それが黒沢映画だった。
ところで“スパイ”もまた、“敵/味方”“向こう/こちら”の境界を踏み越えてくるだけでなく、その際には“真の敵/真の味方”(例えば、“本当に日本/われわれのためを考えている側”はどちらか、など)という仮想の対立軸までをも導入したうえで、境界線の融合する水平線の彼方へと消えていく存在である。
そういう意味で、“スパイ”という存在は、“幽霊”に匹敵するすぐれて黒沢清的なモチーフと言えるのではないだろうか? 『スパイの妻』によって、そんなことを考えさせられたのだ。
「スパイというのは、往年のジャンル映画から最新娯楽映画にいたるまで——日本ではそれほど多くありませんが——特にアメリカなどではよく映画のネタにされます。目に見えているものをどこまで信じるべきなのか。その裏に何があるのか。画面に映っている範囲の外では、何が起こっているのか。実は、観客にとってその点は謎であるわけです。スクリーンに映っているものが映画のすべてであると思い込んでいるけれど、果たしてそれは本当なのだろうか? (画面に映っている)扉一枚を開けたら、その中には予想もしない世界があるのかもしれないし、カメラがちょっとパンして方向を変えると、全然違うものがそこにあるのかもしれない。スパイというのは、そういう映画表現の基本に触れるものの1つなのだろうな、と思います」
さらに言えば、黒沢映画に“幽霊”的な存在が出現し境界がぼやけるとき、当初はその状態が恐怖そのものであるかのように感じられたとしても、最終的には、混乱の中やその向こう側にあるかもしれない救いのようなものの予感が、ある爽やかさをもたらす風景としてわれわれの目の前に立ち現れてくる。今作では、その点が特に鮮明にされていた。
「生と死の境界にいるのが幽霊、モラルとアンモラルの境界にあるのが犯罪——例えば『CURE』に登場したような猟奇殺人のような——だとすると、そういうものを現代劇で扱うと、本当にあいまいになるんですね。つまり、この先どちらに行くべきなのか。そっちに行ったのが正解だったのか、不正解だったのか。あるいは最終的に幸福だったのか、不幸だったのか。そこには希望があったのか、絶望しかなかったのか。それはよくわからないけど、境界線は越えるしかない、というところで映画が終わらざるを得なかったわけです。
しかし今回は時代が少し古い。そのため、物語がある時点で終わったその先で、世界や日本がどうなったのか、僕達は知っている。その結果が現在にまでつながっているために、ざっくりと何が正しくて何が間違っていたのか、どこに未来があってどこに絶望しかなかったのか、ということがあらかじめわかっていた。そのことが、今回の作品では大きかったと思います。だから、いつもに比べて結末はあいまいではなかった。はっきりと境界線を越えて行けた。あるいはとどまることができた。どちらが正しく、どちらがより自由であったか、幸福であったかといったことが、自分の中ではいつもよりはっきりしていました。それは歴史ものだったからだと思います」
さまざまな“外部”を呑み込んできた「映画」のこれから
一方、スクリーンを見つめていると、福原を演じる高橋一生の身体は“軽やかに動きまわる空洞の機械”という印象を与え、内面を感じさせない。それが故に、その行動の背後には信念があるのかないのか、あるとしたらどういう信念なのかといったことが限りなくあいまいになっていく。聡子を演じる蒼井優にしても、そういう夫を前にした妻の内面として観客が期待するものを、身体の表面に貼りつけて行動しているようにも見えてくる。かくして、福原はスパイなのかどうか? 聡子は夫をどのように受けとめ何をするのか? という、境界線上に発生するサスペンスの強度はいやがうえにも高まっていくのである
「高橋さんとは初めてお仕事しましたが、本当におもしろかったですね。こちらからは細かなことをほとんど何も言っていないんですけど、《監督はこんな感じを望んでいるだろう》という狙いを脚本から読み取ってくれました。もちろん、過去の作品も観てくださったうえでのことだと思います。本当は何を考えているのかわからないけれど、口に出す科白は異様に説得力がある、というような芝居を、実に巧みにされていましたね。もちろん、それが真実かどうかはよくわからない。怪しいと思ったらすべてが怪しくなる。でも聡子が、ある瞬間に夫を100パーセント信じるのはわかる、という。でも次の瞬間にはそれを完全に覆され、それでもそのすぐ後にまた信じてしまう、というふうに揺り動かされる対象として、見事に演じていたと思います。自分で言うのもなんですけど、僕の映画に出てきそうな、境界線にいる人物でしたね(笑)」

約10年前に刊行された『ゼロ年代+の映画』(河出書房新社)の中には、黒沢監督のこんな言葉がある。「3Dや偽ドキュメンタリー映画を呑み込むくらい、20世紀の映画は強いんだ、と信じています」また、「『映画』はそう揺るがないのだということを実証する映画を撮ってみたい」とも。“原作”や“海外”といったさまざまな外部を呑み込んでびくともしなかった2010年代の黒沢映画は、確かにこの言葉を実践に移してきた。
「10年前の段階でそんなことを言っていましたか(笑)。でもそうですね。まだしばらく映画は大丈夫だろう、いろんなものを吸収しながらも、映画というものは揺るがないだろう、という確信はより強くなっています。映画は映画館で公開され、暗い中で不特定多数の人と一緒に大きなスクリーンで観るもの、というのが僕にとっての理想であることも変わりません。もちろん、それができない人は自宅でDVDやネット配信で観るというのでも良いのですが、理想としては、映画は映画館で観るというもの、それは譲れないところです。まだ当分の間はこの状態が続くとは思いますが、仮に映画館というものが消滅してしまい、家庭のモニターで一人で観るのが映画である、となってしまうと、僕が思っている映画というものはガラガラと崩れていくかもしれません。
これはかつてあった、《フィルムかデジタルか》という議論とちょっと似ている気がします。今の映画はほぼデジタルで作られていますが、あきらかにフィルムが100年以上かけて作ってきた伝統をそのまま受け継いでいる。ハリウッド映画を観ても、あからさまにフィルムの記憶を引きずっているわけです。場合によっては、まだフィルムで撮っている人もいる。こういう状況が続く限り、デジタルを使うのが主流であっても、そこで作られている一つの理想型は、フィルムが培ってきた何かなわけです。でも、どこかで完全にそういう人たちがいなくなってフィルムの記憶が失われると、映画は完全に変わってしまうかもしれませんね」
1940年代の状況にも通底する、現在時の日本
そして2020年、新型コロナウイルスによって世界の様相は大きく変貌を遂げた。春先には、“かつて黒沢映画で見たような”と思わず口をついて出るような風景が現実のものにもなった。その時期を過ぎて、“それにもかかわらず社会のありようは想像以上に堅固だった”と暫定的に言うしかないのが、この現在時である。日常の景色がみるみるうちに変わっていくことは、ひとまずなくなった。だが、死のきざしはそれほど遠くないところで宙づりになっていて、そのことを常にどこかで意識しながら生きていく毎日。大災厄は、すぐそこまで来ているかもしれないのに、あいかわらずあいまいなままの正解と不正解の境界線。
これはもしかすると、崩壊へと突き進んでいく1940年代の日本の状況に通底しているのではないか。誰もがそう感じざるを得ないだろう。監督自身、作品のオフィシャル・インタヴューではこんな言葉を漏らしている。「表面的には自由と平和が保証されたかに見える現代日本でも、我々は明日にも狂気の沙汰へと転落していく危機と隣り合わせであるように思います」だからこそ、「この映画から、その危機のリアリティを少しでも感じとって」もらいたい、と。
『スパイの妻』はまぎれもなく、すぐれて黒沢清的な映画なのだ。そして(くり返しになるが)黒沢清の作品群はいつでも、境界線そのものをあいまいにし、それを越える/越えないということすらも相対化することで、今まさにわれわれが生きつつあるような状況を幻視してきたと言うことができる。すぐれた作り手の作品とは、すべからくそうなのだ、という紋切り型すら、今さらながら口にしたくなるほどに。
2020年代は、まだ始まったばかりだ。
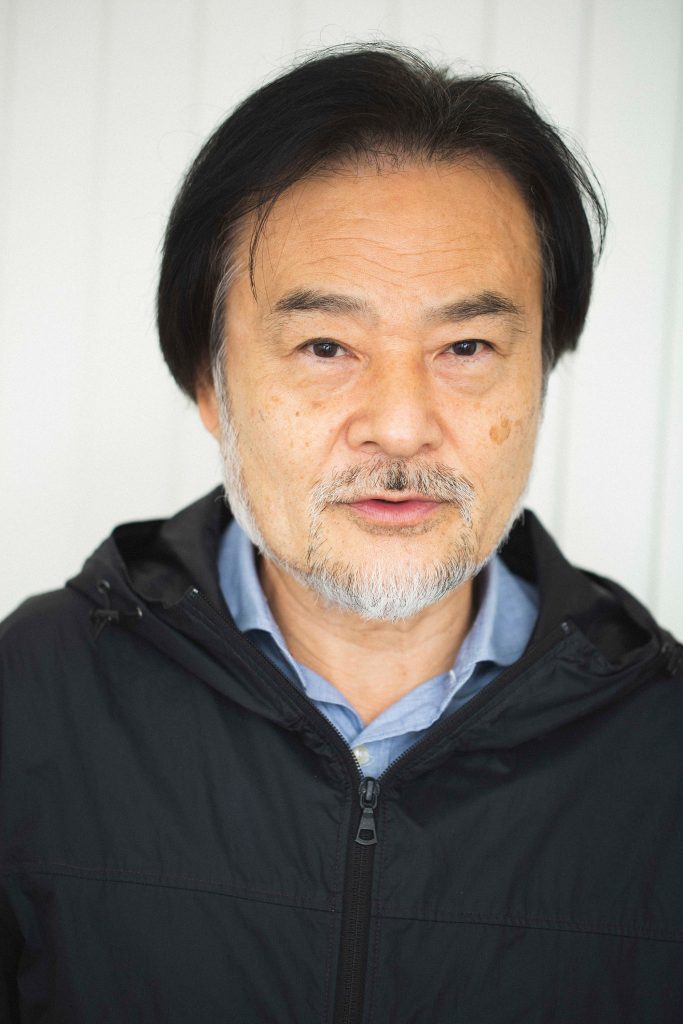
黒沢清
1955年生まれ。大学在学中より8mm 映画を起点にした創作活動を続け、その後ジャンルを問わず精力的に38作品を監督。代表作に『CURE』『カリスマ』『アカルイミライ』など。『回路』は第54回カンヌ国際映画祭で国際映画批評家連盟賞、『トウキョウソナタ』は第61回カンヌ国際映画祭ある視点部門審査員特別賞を受賞。『映画はおそろしい』など映画批評、ノベライズの著書も多数。最新作『スパイの妻』で、第77回ヴェネチア国際映画祭コンペティション部門において銀獅子賞(最優秀監督賞)を受賞した。
Photography Kentaro Oshio


