音楽とファッション。そして、モードトレンドとストリートカルチャー。その2つの交錯点をかけあわせ考えることで、初めて見えてくる時代の相貌がある。本連載では気鋭の文筆家・つやちゃんが、日本のヒップホップを中心としたストリートミュージックを主な対象としながら、今ここに立ち現れるイメージを観察していく。
これまで「ヴェルサーチェ」、「グッチ」、「シャネル」を論じてきたが、第8回から主役となるのはディオール。同ブランドの真なるアイデンティティや歴代デザイナーたちが織りなしてきた“雑多性”、そしてストリートミュージックの表現者たちのリリックにおける現れ方について紐解いていく。
今をときめく「ディオール」、その“異様さ”とは
2021年の今、最も勢いのあるメゾンとは?その質問に対して、ストリートで群れをなす人たちは、バーバリーやルイ・ヴィトンが一瞬脳裏をかすめながらも結局のところこう回答するだろう。――「ディオール」であると。その快進撃は市場において際立っており、競合ブランドに対して相対的に“低迷”というストーリーを付与することにも成功し、ジャーナリストたちは皆「グッチの業績、ついに鈍化か」と書き立て始めている。パーティが次々にキャンセルされ、グラスに注がれた魅力的な泡の輝きがこの世から消え去ったパンデミック禍において、LVMH社の激減したシャンパン売り上げをカバーした筆頭が「ディオール」であるとも報告された。今、このメゾンは、人類の欲望と夢を満たす役割を一身に引き受けているのだ。
ブランドのオーガニックグロースを可能にした要因として真っ先にメンズアーティスティックディレクターであるキム・ジョーンズの手腕が挙げられるだろうが、ウィメンズを手掛けるマリア・グラツィア・キウリによるロマンティックなクリエイションも才気ほとばしっており、21-22AWコレクション――ヴェルサイユ宮殿「鏡の間」を舞台にしたおとぎ話の3D化、そしてスチール/ムービーへの2D化というSNS戦略――が大きな話題をさらったのも記憶に新しい。また、ここに来てコスメ部門も着実に支持を集めている。「ディオール」のこの一見ばらばらに見える価値発信はブランドの顔つきを多彩なものにしており、どこか異様さをまとってもいるだろう。「ディオール」という神秘性に満ちたメゾン、ブランドを考えるとき、それらの雑多性、異様さは重要な違和感として忘れてはならないように思う。
“エレガンス”だけではない、真なるアイデンティティ
「ディオール」のアイデンティティとして、これまで“エレガンス”が挙げられてきた。その時代に合ったエレガンスを追求するメゾン――全くもって間違いのない説明だが、私はそこに“人工的な”という一言を添えたい。クリスチャン・ディオールの生み出した数々のライン、そのシルエットは(女性のリラクシングなスタイルにこだわったココ・シャネルにモード界への復帰を決心させたくらいに)身体を締め付け、その周囲を取り巻くように構築的に形作られるものだった。「ディオールは女性の身体をコルセットでがっちり矯正して美しいシルエットをつくったが、バレンシアガは身体そのものを活かし、さりげないカッティング技術で、その欠点を芸術的にカモフラージュした」(シャルロット・シンクレア著、和田侑子訳『VOGUE ONクリスチャン・ディオール』、ガイアブックス、2013年)とある通り、シャネルやバレンシアガとは相反するスタンス、言うなれば身体を縛りつける形で衣服製作に取り組んできたのがクリスチャン・ディオールである。
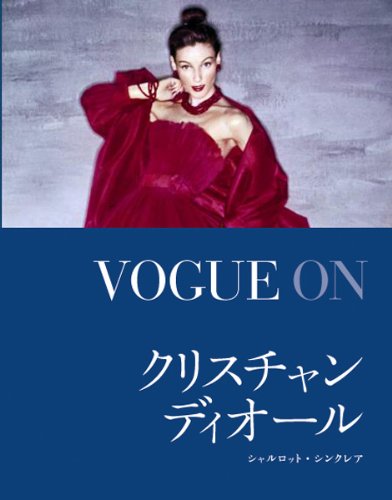
その後も、煌びやかな、豪華絢爛な建築物のごときドレスを仕立てることに邁進したジョン・ガリアーノ、常識を超えたタイトなラインを提唱しメンズウェアのシルエット基準を刷新してしまった「ディオールオム」のエディ・スリマン、そして昨今ストリート色を大胆に導入し「ナイキ」や「ステューシー」とのコラボレーションを敢行しているキム・ジョーンズ――彼の作品もまた、両立しないはずのハイとローの要素が完全に融合し、“高級で上品なストリートグラフィティ”といった語義矛盾を孕むような非現実的な世界を確立している――と続く。偉大なるデザイナー陣が夢想するイメージが人工的かつ繊細な手つきで具現化されたそれらエレガンス作品は、メゾンのアイデンティティとして脈々と息づき、時に退廃的な香りを漂わせてもいる。モード史を彩る、ロマンティックでデカダンスな衣装の数々。それはまさに、アルフレッド・ヒッチコック監督作『舞台恐怖症』でディオールをまといスクリーンに陰翳と官能を充満させ、観る者を痙攣させてきたマレーネ・ディートリッヒのごとく。
「ディオール」を主題としたストリートミュージック史上最も重要な曲
ところで、ポップミュージックのリリックに、「ディオール」はどのように扱われてきたのだろうか?古くは1977年に山口百恵が「ミス・ディオール」(『百恵白書』収録)を、モリッシーが2006年に「Christian Dior」(『In the Future When All’s Well』収録)なる曲をリリースしており、大胆にブランド名をタイトルに据えるところからもこのメゾンに対するアーティストたちからの信頼が垣間見えるが、近年のストリートミュージックの文脈だとまずはPop Smoke「Dior」を避けては通れないだろう。Black Lives Matterにおいてデモ参加者に突如歌われた本曲は、政治的メッセージを直接的には含んでいない“単なる享楽の曲として”多くの人の自由への想いを乗せ世界中に拡散されていった。2010年代後半に吹き荒れたビート革命“ブルックリン・ドリル”の盛り上がりを象徴する曲としても、ストリートミュージック史上最も重要な、「ディオール」をモチーフに作られた曲ではないだろうか。
BAD HOPやWAY WAVEらのリリックに顕在化された、ブランドの“雑多性”という特色
一方で、前述したような「ディオール」のさまざまな喜怒哀楽からなる雑多性を阿修羅像のごとく多面的に表現するブランドの特色もリリックに顕在化している。DJ CHARI & DJ TATSUKIの「GOKU VIBES feat. Tohji,ElleTeresa,UNEDUCATED KID,Futuristic Swaver」(2020年)では「내 눈은 사륜안 /I’m rockin Dior sunglass/지금 내 모습은 스티비 원더」とサングラスへの言及がなされ、BAD HOP「Foreign」(2019年『Lift Off』収録)では「カリフォルニアウィード/DIORのキックス」とスニーカーが引用される。
WAY WAVE「最高の彼氏 -the supreme man-」(2019年)の「シックなスーツでオール/リップはグロスのディオール」やchay「ハートクチュール」(2015年『ハートクチュール』収録)での「Diorのルージュでお出かけ」等、女性アーティスト曲のリリックではコスメが描かれる。
このアイテムの幅広さは、今の「ディオール」の雑多な魅力を象徴しているだろう。ゆえに、つい先日リリースされたBLACKPINK・ジスの「ディオール」グローバルアンバサダー就任のニュースは、“ファッション&ビューティー”の両部門と契約をかわしたという点が非常に興味深い。ファッションと比べるとそのヴィジュアル・アイデンティティをフェミニン~ファンシーなテイストへ寄せすぎているきらいもある「ディオール」のコスメ部門だが、フレグランスなどにも拡大しているその広大なイメージをジスの起用でどのように取りまとめていくのだろうか。
次回は、それら幅広いイメージを人工的なエレガンスで串刺ししてきたメゾンの、その特色が如実に表れている例として、一世を風靡したエディ・スリマンによる「ディオールオム」のクリエイションについて分析していきたい。一体、あの狂騒とは何だったのだろうか?2000年代最初のディケイドにおいてファッション界最大の革命だったであろう「ディオールオム」という事件について、次回no.9ではストリートミュージックとの関係を紐解きながら、改めて見つめ直してみよう。
Illustration AUTO MOAI


